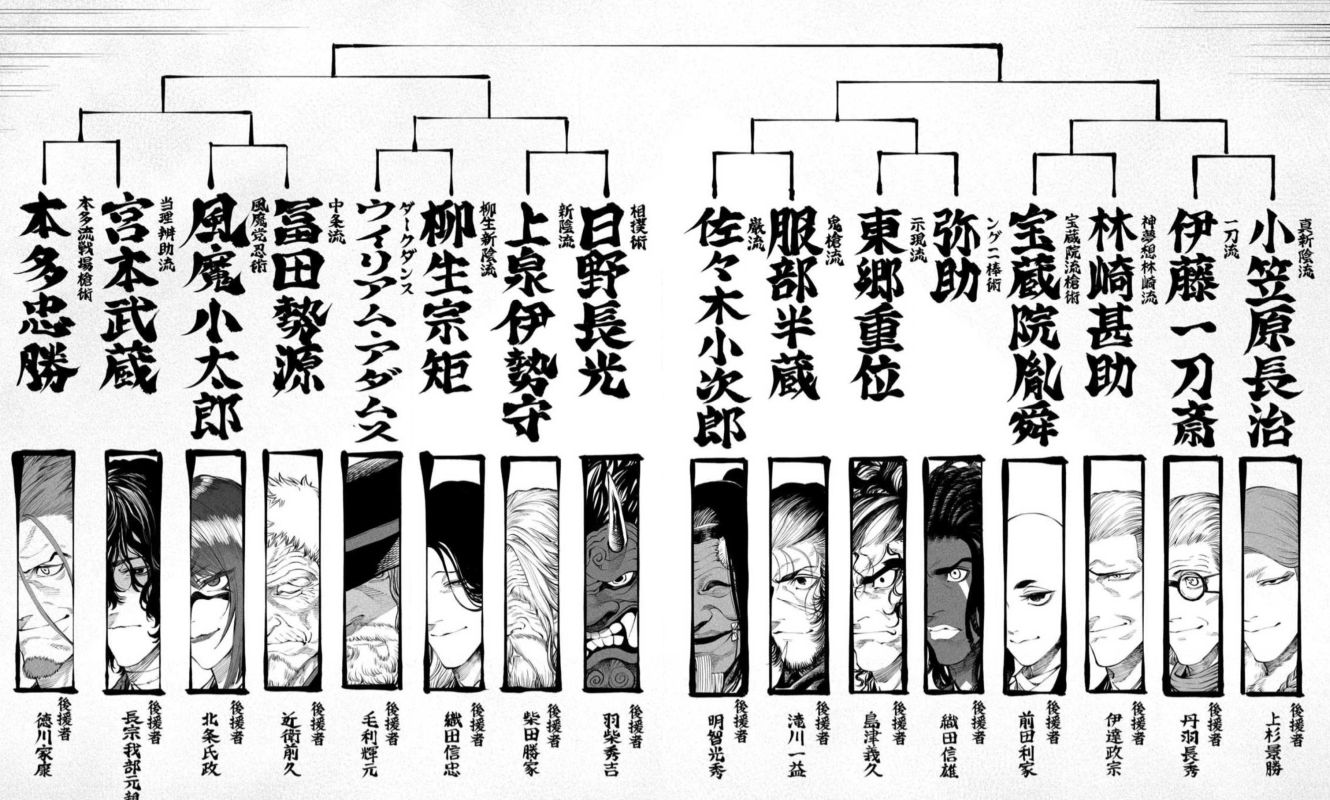2025�N3���`4��
2025-04-19.�E���S�V��TV�A�j���[�V�����w���@���������J���Ȃ̂� EXCEEDS Gun Blaze Vengeance�x�����ɐ�삯�ăR�~�J���C�Y���w���@���������J���Ȃ̂� EXCEEDS�x���n�܂������瑁���ǂ݂ɍs�����ĒÂł��A�����́B
�@�܂��u���@���������J���Ȃ̂͂��ĉ��H�@�^�C�g�����炢�͕��������Ƃ�������ǎ��͑S�R�m��Ȃ���ˁv�Ƃ����l�����ɃV���[�Y�̔��[���������܂��B���ׂĂ̔��[��1998�N�ɔ������ꂽ���N�����Q�[���A������u�G���Q�[�v�́w�Ƃ炢����n�[�g�x�ł���B���̂́u�Ƃ�n�v�B�u�O�p�W���ނɂ����w���t���u�R���v�c�c�ƌ��������ĔE�҂�z���S���o�Ă���Ƃ����A���Ȃ艽�ł�����ȃ\�t�g�ł��B�o�b�h�G���h�������Ȃ����Ƃł��L���B�q�b�g�������߁w�Ƃ炢����n�[�g2�x�A�w�Ƃ炢����n�[�g3�x�Ƒ��҂��������ꂽ���A���ׂē���̊X�i�C�s�j��ɂ��Ă��邾���Ŏ�l����q���C���̖ʎq�͓���ւ���Ă���B2000�N�ɔ������ꂽ�Ƃ�n3�̎�l�����u��������v�B�ŁA2003�N�ɖ{�ҏI������4�N��̖�����`��OVA�V���[�Y�w�Ƃ炢����n�[�g�`Sweet Songs Forever�`�x���n�܂����B�G���Q�[�̌���kOVA�Ȃ���G�b�`�����A�N�V�����v�f�����ɐ����Ă���B���̂Ƃ��ē�S�������̂���Ɂw������x��w���@�����܂ǂ����}�M�J�x����|�����u�V�[���V�v�B���ƂȂ��Ă͊o���Ă���l�����Ȃ��Ȃ������A���̍��̐V�[�́wThe Soul Taker�`����`�x�i2001�N�����j�Ƃ���TV�A�j���Łu5���O�[�i�v�Ȃ�������̃X���X���̓`���I�ȕs�ˎ����N�����A�ƊE���犱����Ă��܂����B���̂��ߕϖ����g����18��OVA�Ƃ�������Ă�����ł��B�Ƃ�n3��OVA��18�ւ���Ȃ�����ϖ��ł͂Ȃ��V�[���V���`�ŃN���W�b�g����Ă���A����OVA���D�]���������ߑ��҂Ȃ����X�s���I�t��TV�V���[�Y�ł�낤�Ƃ����b�ɂȂ��āA���������V�[���V���o�p����邱�ƂɂȂ�܂��B
�@TV�V���[�Y�̎�l���Ƃ��Ĕ��F���ꂽ�̂�����̖��ł���u�����Ȃ̂́v�B�Ȃ̂͂����͂�����u���L�����v�Ȃ̂����A�t�@���f�B�X�N�w�Ƃ炢����n�[�g3�@�����J���������ᔠ�x�Ɂu���@���������J���Ȃ̂́v�Ƃ����ԊO�҃V�i���I�����^����Ă��܂����B�����TV�A�j�������ɍ�蒼�����̂�2004�N�ɕ������ꂽ�w���@���������J���Ȃ̂́x�A�t�@���̊ԂŁu����v��u1���ځv�ƌĂ���i�ł��B�T�u�L�����Ƃ��ċ�����o�ꂷ�邪�A���͂��u�ꕔ�̐ݒ肪���ʂ��Ă��邾���̃p���������[���h�v�ɂȂ��Ă���A�Ƃ�n�Ƃ̒��ړI�Ȍq����͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�w�����J���������ᔠ�x�Ɏ��^���ꂽ���́u���@���������J���Ȃ̂́v���A����Ƃ������̓v���g�^�C�v�݂����Ȉʒu�Â����B�������ăA�j���̃����J���Ȃ̂͂́u�Ƃ�n����n�܂������ł͂��邪�A�p���������[���h�Ȃ̂łƂ�n����͓Ɨ����Ă���v���W�F�N�g�v�ɂȂ��Ă����܂��B�u���@�����A�j�������lj��o�ƃo�g���`�ʂ̓K�`�v�Ƃ������Ƃ������đ�q�b�g�B���N2005�N�ɑ����w���@���������J���Ȃ̂�A's�x����������A�l�C�͂܂��܂����M���Ă������A2007�N�ɕ������ꂽ3����w���@���������J���Ȃ̂�StrikerS�x�����肩��V���[�Y�����G�����n�߂�B
�@����i1���ځj��A's�ł͏��w3�N���������Ȃ̂͂�StrikerS�ł�19�ɐ������Ă���A��������ӎ����Ă���y�L�����������o�ꂷ��悤�ɂȂ��Ă���B�Ȃ̂͂�������i10�`18�j�̏o�������_�ɂ�������Ă��܂������Ƃɂ��A�u�ߒ��������������̂Ɂv�ƒQ���t�@���ň��Ԃ�n���ɁB�u�Ƃ�����19�Ŗ��@�w�����x���āc�c�v�Ƃ����c�b�R�~�������R�قǂ���܂����B�����StrikerS�͍����r��C���������i�A��2�N�[���Ő��삪�����������Ƃ������������j�����Ŏ^�ۂ�����錋�ʂɂȂ��Ă��܂��BStrikerS��2�N��A2009�N�ɂ̓V���[�Y4��ڂƂȂ��w���@��L�����J���Ȃ̂�Force�x�������i�Ƃ��ĘA�ڊJ�n�B�Ȃ̂͂����25�ɂȂ��Ă���A�������ɂ������������炩�^�C�g���Ɂu�����v�̓��͂Ȃ��BForce�͓r���ŋx�ڂ��A����f�ڎ����p���ɂȂ��Ă��܂������ߍĊJ�̖ڏ����������A�u������i�v�Ƃ��������ɂȂ��Ă��ăA�j����������Ă��܂���BForce�Ɠ������ɘA�ڂ��n�܂����V���[�Y5����w���@���������J���Ȃ̂�ViVid�x�͖����Ɋ������Ă���A�S20���Ƃ����Ȃ��Ȃ��̑咷�҂Ŋ֘A����܂߂�2�xTV�A�j�������Ă��邪�A�����A�j���͂��܂�q�b�g���Ȃ������̂ň����������i�ƂȂ��Ă��܂��B5��ڂł��邪���n��I�ɂ�Force��2�N�O�AStrikerS�œo�ꂵ���u���B���B�I�v���Ȃ̂͂��{���Ƃ��Ĉ�������Ă���AViVid�͂��́u�������B���B�I�v�𒆐S�ɐi�s���Ă����B�X�|�[�c���o�ő��ɏo�ꂵ�Đ키���e�ɂȂ��Ă��āA���@�������m�Ƃ������̓X�|���i�����m�ɋ߂��m���ł��B
�@�A�ڊJ�n����6�N�߂��o�߂���2015�N���w���@���������J���Ȃ̂�ViVid�x�Ƃ����^�C�g���ŃA�j�����BTV�V���[�Y�Ƃ��Ă�8�N�Ԃ�A�ʎZ4���ڂɓ�����܂����A�^�C�g���ɂ������Ă���u�Ȃ̂́v���T�u�L�����ł��邱�ƁA�G�s�\�[�h��1�N�[���������Ȃ����[�ȂƂ���ŏI����Ă��܂����Ƃ����ւ��Ă��܂�b��ɂȂ�Ȃ������B�u����2�N�[���̗\�肾�����̂ɁA�������2�N�[���ڂ�����Ȃ������v�Ƃ����\������܂��B�����������������ł��ABD�����܂ł₯�Ɏ��Ԃ��|�������̂���ۂɎc���Ă���B���N2016�N�ɃX�s���I�t�A�j���wViVid Strike�I�x�������BTV�V���[�Y�Ƃ��Ă͒ʎZ5���ڂŁA���Ԏ���ViVid��1�N��ɓ�����B�u�t�[�J�E�����F���g���v�Ɓu�����l�E�x�����l�b�^�v�Ƃ����V�L���������C���ɂ����A�j���ŁA���B���B�I�̓T�u�L�����Ƃ��ēo�ꂷ�邪�A�Ȃ̂͂͑��݂߂��������x�Œ��ڂ͓o�ꂵ�Ȃ������B�Ȃ̂Ō���TV�V���[�Y�̒��ŗB��u�����J���Ȃ̂́v�������Ă��Ȃ���i�ɂȂ�܂��B�{����ViVid�A�j����2�N�[���ڃ��X�g�Ƀt�[�J�ƃ����l��o�ꂳ���āu�wViVid Strike�I�x�ɂÂ��v�݂����Ȍ`�Ńt�b�N����肽�������̂ł͂Ȃ����c�c�ȂǂƊ��J���Ă���B���ƁA�ߋ���z�V�[���ł����߂��Ă��������l��������߂��q�����ɂ��Ԃ��V�[��������̂����A�r���ւ��܂������ʂ��R��������X�g���s���O�Œnj�������Ɨe�͂̂Ȃ��`�ʂŔ��E���ɂ��Ă��Ęb��ɂȂ�܂����B�����܂ł̍쒆�̎��n����܂Ƃ߂܂��Ɓu���i���N��jA's���i10�N��jStrikerS���i4�N��jViVid���i1�N��jViVid Strike���i1�N��jForce�v�Ƃ��������ɂȂ�܂��B
�@�wViVid Strike�I�x�������N��2017�N�ɖ���w���@���������J���Ȃ̂�ViVid�x�̘A�ڂ��I���B�����ŁuStrikerS�ȍ~��`���Ȃ̂͊֘A�^�C�g���v�͒�~���邱�ƂɂȂ�܂��B����2017�N�̉āA����ō�i�w���@���������J���Ȃ̂� Reflection�x�����J���ꂽ�B1���ڂ̑��W�ҁ{���́w���@���������J���Ȃ̂� The MOVIE 1st�x�A2���ڂ̑��W�ҁ{���́w���@���������J���Ȃ̂� The MOVIE 2nd A's�x�ɑ���3�{�ڂ̌����i�ł���A���̊��S�I���W�i���f��ł�����BA's��2�N��A���w5�N���ɂȂ����Ȃ̂͂������������鎖����`���Ă���A�A�j����i�Ƃ��Ă͏��߂āuA's����AStrikerS���O�v�̎��Ԏ��ɐG�ꂽ���e�ƂȂ��Ă���iStrikerS�̉�z�V�[�������j�BReflection�͑O��҂̑O�҂ɓ�����A��҂ɓ������w���@���������J���Ȃ̂� Detonation�x�͗��N2018�N�Ɍ��J����܂����BReflection��Detonation�̓����J���Ȃ̂͂̊i�Q�[�wTHE BATTLE OF ACES�x�iBOA�j��wTHE GEARS OF DESTINY�x�iGOD�j�̐ݒ肪�x�[�X�ɂȂ��Ă���炵�����A���͂����܂ŃJ�o�[���Ă��Ȃ��̂Ő����͊�������BDetonation�̃��X�g�A���w���œG�̎����Z�ɂ���ĉE�肪������ё̂̂����������Y������قǏd�������Ȃ̂͂����̓M���M���̂Ƃ���Ő��҂��A���ꂪ�I���B�w���@���������J���Ȃ̂�EXCEEDS�x�͂���2�N��A���w���ɂȂ����Ȃ̂͂����̊����`���B�v����Ƀt�@���Җ]�́u���w���ҁv���悤�₭�n�܂�͗l���B���������ȁc�cA's����20�N�A�܂�������ȂɊ|����Ƃ͎v��Ȃ������B���Ȃ݂�A's�̍ŏI�b�ɂ����w���ɂȂ����Ȃ̂͂������o�Ă��邪�A����́u6�N��̏t�v�Ȃ̂Œ��w3�N���AEXCEEDS��2�N��ɓ�����B
�@�Ƃ���ŁA�Ȃ̂͂̔N����l���邤���Ŗ��Ȃ̂́u�a�������ׂ����ׂ��Ȃ����ŕς���Ă���v�Ƃ������B�Ƃ�n3���ƂȂ̂͂̒a�����́u3��15���v�ɐݒ肳��Ă���A���̓��ɂ��j������t�@�����������A�����܂ꂾ�Ɩ����A's�̎��_�ł�8�Ƃ������ƂɂȂ�iA's��12���̏o�����ŁA����͂��̔��N�O���j��������́u9�v�Ƃ��������Ƃ͖������Ă��܂��B���̂ւ�A�P���Ɂu�Ȗ��ȓ��t�l�͍s���Ă��Ȃ����疞�N��Ɋւ��Ă͂��B���v�Ǝ�������������ł��傤�B
�@�܂Ƃ߂�ƁA�����̎��n��������T�C�g�̔N�\�ʂ��ł����A�쒆�̎��n��I�ɂ́u���i���N��jA's���i2�N��jReflection�EDetonation���i2�N��jEXCEEDS�v�Ȃ̂ŁA���ꂩ��Ȃ̂̓��[���h�ɓ����Ă���l�́uStrikerS�ȍ~�̂Ȃ̂͊֘A�^�C�g���iStrikerS�AForce�AViVid�AViVid Strike�I�j�v�𗚏C����K�v�͂���܂���B����������Ȃ�ʂɊςĂ��������ǁc�c�Ƃ��������B�ǂ����ݒ���ꕔ�ύX�����݂���������AEXCEEDS��StrikerS�ȍ~�͘b���q����Ȃ��Ƃ������p�������݂����ȊW�ɂȂ肻���Ȃ�ł���ˁBStrikerS�Łu�Ȃ̂͂�11�i���w5�N���j�̂Ƃ��ɑ����������v�Ƃ����G�s�\�[�h���o�Ă���̂ł����A���̏ڍׂ�Detonation�Ƃ͂����ԈقȂ�BEXCEEDS��Detonation�́u���w���ł̗Վ��̌��v�Ƃ����G�s�\�[�h�������p���ȏ�A����StrikerS�Ɍq���邱�Ƃ͂Ȃ��B�Ȃ�ׂ��Z���ԂŁu����܂ł̂��炷���v��m�肽���̂ł���A�uThe MOVIE 1st�v�uThe MOVIE 2nd A's�v�uReflection�v�uDetonation�v�ƌ����i4�{���������邾���ł����B���Ԃɂ���500�����炸�A8���Ԃ�����ƂŒǂ����܂��B�����N���u���r���X�[�c���݂̐퓬���J��L���閂�@���������v�̐��E�ɔ�э������I
�@����V��w���@���������J���Ȃ̂�EXCEEDS�x��13�ɂȂ��������Ȃ̂͂����A�����@�ցu�G�N�V�[�Y�v�̒������Ƃ��ċ@�B�M�Ɓu�_���i���v�ɐ������A15�N�O�܂œ����Ԃ��������̍��ŋN����u���{�b�g�\�������v������\�\�ƁA�Ђƌ��Ђ����@�����v�f�̂Ȃ����炷���ŏ��Ă��܂��B�������ʎZ6���ڂɓ�����V��TV�V���[�Y�̃^�C�g���AEXCEEDS�̌��ɁuGun Blaze Vengeance�v�ƕt���Ă�����Ă��Ƃ́A���炭����̓��e���̂܂܂��A�j���ɂ���킯����Ȃ���ł���ˁB�R�~�J���C�Y�̓A�j���̑O��杂ɓ�����̂��H�@�������������s���Ȃ̂ł܂����Ƃ������Ȃ����c�c�B
�Enonco�u�J�i���l�͂����܂Ń`�������v2026�N��TV�A�j�����A�X�^�W�IKAI������i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@�u�J�i���l�v���Ɓw�J�i���l�͂����܂Ń`�������x�A�j�������I�@�u�k�Ђ̃��u�R������A�ǂ�ǂ�A�j��������Ă����ȁB���͂܂��ɑ僉�u�R������B�J�i���l��2022�N����A�ڂ��J�n������i�ŁA�l�Ԃ̃t�������Ċw�Z�ɒʂ��Ă��鈫���̏����u�J�i���v����y�̏��N�u���V�r�i�i���傤���E�悤���j�v���獰��D�����Ƃ�����ǁA����N���m�̏����ł���ޏ��͂����Ƃ�����ʂŐK���݂��Ă��܂��c�c�Ƃ������q�Ő��~�߃V�`���G�[�V�������������u�R���ł��B��y�N���̓J�i���ւ̍D�ӂ��Y�P�Y�P�ƌ������Ă���A���Ƃ̓J�i���̑Ή�����łǂ��Ƃł��Ȃ�͂��Ȃ̂����A�p���������čŌ�̂ЂƉ������ł��Ȃ��B�����������j���j�����Ȃ���ǂރ^�C�v�̓��₩���u�R���ł���B�L�����������ăh���h�����킢�������Ă����̂����ǁA�����߂��ď����̃L�����͂��܂�o�Ԃ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂����c�O���c�c�u�v�r�j���q�v�Ƃ����w����厸�i�x�́u���q�v�r�j�v���t�ɂ����悤�Ȗ��O�̂��傢���I�ȃT�u�q���C���i�r�i�̗c�Ȃ��݁j������̂ł����A�ŋ߂͑��݂�Y�ꂻ���ȃ��x���Ŗڗ����Ă��Ȃ��B
�@���E�֍s���ăJ�i���̃p�p�i�x���[�u�u�j�Ɖ�悤�ȓW�J������܂����A��v����͂����܂Ŋw�Z�ł���A�W�������I�ɂ́u�w�����u�R���v�Ƒ�����OK�ł��B�A�j�����Ől�C�o�����Ȃ̂͐��k��́u�_�����S�ԁi�����イ���E�Ă����j�v���ȁB�g��190cm��J�J�b�v�Ƃ��������ȈӖ��Łu�f�J���v�l�Ȃ���A�o�ꂷ��̂����ƒx���i�P�s�{����6���j����\����ς��Ȃ��Ƃ���o�ԂȂ������Ȃ�ȁB���Ȃ݂Ɏ��̍D���ȃL�����̓J�i���̂��t���̃��C�h�u�A�~�v�Ɛ��k��L�u�摖�Ҋ��v�A�����Վ��s���ψ����u�e�T�����C�v�ł��B�A�~�͊��F���C�h�M�����Ƃ����V���v���ɃG�����L�����f�U���D���G�B�摖�Ҋ��͖ڕ��n�ނ���h�X�P�x�Ƃ�������������u�b�h�������B�ɂ��ނ炭�̓T�u�L�����䂦�ɒS����ȊO�����Ɖe�������B�e�T�����C�͉A���M�U���n�C���C�g�Ȃ������Ƃ����A���܂舫�������Ȃ����̖���ł͒������������U�镑�������鏗�̎q�B�o�Ԃ͉���������ƒx���A8���ɂȂ��Ă���悤�₭�c�c�Ȃ̂ŋ��炭�A�j���ɂ͓o�ꂵ�Ȃ����낤�B�c�O�B
�@�G�b�`��������̈�����ǁA����Ƃ��̓M���M���o���Ȃ��H���̍�i������w�����搶�x�ɔ�ׂ�A�j�����ɑ���s���͏��Ȃ�������B�J�i���̉Ƒ��Ƃ��F�l�Ƃ��A���͓I�ȃT�u�L���������������܂��J������2����3�������ł͂Ȃ��قǂ̃q�b�g�����҂ł���͂��B����́u�X�^�W�IKAI�v�A�E�}����2����3���A�w�X�[�p�[�J�u�x��w�V���C���|�X�g�x����|�����Ƃ���ł��B�����܂ŗL���ȃX�^�W�I�ł͂Ȃ����A�w��P�⏥�V���t�H�M�A�x�V���[�Y�́u�T�e���C�g�v����V���t�H�M�A�I����ɈڐЂ����X�^�b�t�����j�Ɏ��܂��Ă���炵���A�N�I���e�B�͍��߁B�����_�ł͑f���Ƀ��N���N���ėǂ��������B�������A�J�i���l�܂ŃA�j�����ƂȂ�Ɓu������v�����w���k��ɂ����͂���I�x�i�������ɘA�ڂ��n�܂����}�K�W���̃R���f�B����j�̃A�j�������\�͕b�ǂ݂ɓ������ƌ��Ă������낤�ȁB����̓G�b�`�Ƃ������u���l�^�v�H���̃M���O�Ō��E�܂ōU�߂Ă�Ƃ��낪���邩��Ȃ��Ȃ�������낤���c�c�ŐV���̕\���Ȃ�ăq���C���̕�e������Ȋi�D���Ă���ł����́B����҉�ł́u�@�@�����ȁv�Ƃ������炩�ɃA�����ӎ������l�[�~���O���o�Ă��āA�{�Ƃɔ���������Ƃ���chin���������������悾�B�_�ꍂ���B
�E�w�e���J�C�`�@���{�ŋ����|�Ҍ����x�A�A�j��������I
�@�D���ȍ�i�Ȃ̂ŃA�j�������Ăق����ȁ`�A�Ƃ͎v���Ă������{���ɂ���Ƃ́B�w�e���J�C�`�@���{�ŋ����|�Ҍ����x�́w��ԗ��x�́u���ۗm��v�������S�����Ă��镐�|�Ҍ�������B�D�c�M�������{�ꂵ�āu�D�c���{�v���J����if�̐��E��ɁA�V�����M�����u�D�������҂ɂ��̍�������v�ƌ�O�������J�Â�����B�V����~���镐�������͊e�����҂��ĂъA��O�����ɏo�ꂳ���邪�c�c�Ƃ����b�B�X�g�[���[�͕K�v�Œ�������Ȃ��A��͂Ђ�����E�������������B�l�܂�Ƃ���w�I���̃����L���[���x���q�b�g���Ĉȍ~�J���⡂̔@���������uVS���m�v�̈�ł��Bif���E�Ƃ͂������㌀�Ȃ̂Łw�x�͏��O�����x�i�w�V�O���C�x�̌���j��f�i�Ƃ����邪�A����ƍN�Ⓑ�@�䕔���e�Ƃ������������{��������{�{�����Ƃ��������|�҂��㉇����A�Ƃ����}���́w�P���K���A�V�����x���ۂ��B
�@�w�e���J�C�`�x�̖��͂́u�o�ꂷ�镐�|�҂��S�����L�����Ŏ̂Ď������Ȃ��A��ɂǂ����������킩��Ȃ��v���Ƃł��ˁB�Q�����镐�|�҂�16�l�A�g�[�i�����g�`���ŏ����オ���Ă����̂Ŋ����◼�Ҏ��S�Ƃ��������Ԃ��������Ȃ����15����������s�����ƂɂȂ�i���킪8�����A���킪4�����A�O��킪2�����A�������1�����j�B��ʓI�Șb�����܂��ƁA�g�[�i�����g�o�g�����Đ^�ʖڂɓ����y�[�X�z���ŕ`���Ă����Ǝ��Ԃ��|����߂��邩��A�ǂ����Ă���������V�[���Ƃ��A�u�E�ŏI���ΐ�J�[�h���o�Ă��Ă��܂������ł��B���̎�̖���Ƃ��Ă͒������O�O�ɕ`�����n��̒n�����Z��g�[�i�����g���g���u���Ń}�b�`���C�N���������Ȃ������g�ݍ��킹�����邵�A��u�Ō�����������������B�w�I���̃����L���[���x���̂Ď������Ȃ��^�C�v�̖��悾���ǁA����͒c�̐�݂����Ȃ��̂Ńg�[�i�����g�`�����Ⴀ��܂���B�w���܉ҋƁx�̉A�z�g�[�i�����g�ɂ͊��҂��Ă������ǁA�x�ڂ������5�N�ȏ�o�̂Œ��߃��[�h���Z���Ȃ��Ă����B
�@�u�������Ƃ��āA����C���ɂȂ鎎�����o�Ă���͎̂d���Ȃ��v�Ƃ����펯���u�b�āu�ǂ����������킩��Ȃ��������Ђ����炶������ƕ`���v�o�g���D�������̕��j���т��Ă��ꂽ��Ղ̌������悪�w�e���J�C�`�x�Ȃ̂��B�ΐ�J�[�h�͏���Ŗ�������Ă���̂Ńy�^�b�Ɠ\���Ă������B
�@
�@�@�����ˁA����̒���vs�����̎��_�Ŋ��ɂǂ����������킩��Ȃ��L�l�Ȃ�ł���B�퍑����D�����ϑz�������̂悤�Ȏ����Ɏ����������Ђ����玆�ʂߐs�����Ă����B�o�g������W�����L�[�ɂ͂��܂�Ȃ���삾�B�ŐV���͍����o��11���A�A�ڊJ�n���炻�낻��4�N�o���A�܂����킷��I����Ă��Ȃ��B��7�����ڂ̈��wvs�r��������Ă���Ƃ���ł��B����8�����ځi�ɓ��꓁��vs���}�������j�Ő܂�Ԃ�������A�����y�[�X�Ői�s����Ɖ��肵�Ă������܂ł���5�N�͊|���銨��ɂȂ�B�S�̂̊����͂��Ԃ�20�`30�����炢�ɂȂ�ł��傤�B
�@�����_�ł̌l�I�x�X�g�o�E�g�͑�2�����́u���������Yvs�y�c�����v���B�����Y�́u�Z��ځv�Ƃ����ݒ�ŁA�Ȃ�Ƃ����ς��̑傫�����L���L�ˁ[�����ł���B�w�e���J�C�`�x�B��̏��L�����i���ʕs�ڂ̓z�����邯�ǁj�����֖҂������܂����A�F�C�͂قƂ�ǕY��Ȃ��i������Ƃ��������邱�Ƃ͂���j�B���������Y�ŏ��Ƃ����ƁA�ǂ����Ă��w���b���S�����x�̃A���i�����ڂ͐F���ۂ����m��Ȃ̂ɐ��̓W�W�C�j���v���o���Ă��܂����A�������͐��^���������Ȃ̂ŃA�j�����ŕt�����������Ə������D�ɂȂ�c�c�͂��B���Ƃ��āA�N�����Ă�낤�ȁB����ȂƂ���ő��݂䂫���H�@�����Y�ɑ���y�c�����͏������̒B�l�ł���A�u�ڂ̕s���R�Ȍ����v�Ƃ��Ă��m���Ă���B�u���X�؏����Y�̎t���v�Ƃ����������邪�Aif���E�Ƃ������Ƃ������Ă��w�e���J�C�`�x�ł͍̗p����Ă��Ȃ��B�l�X�ȔE�p����g���鏬���Y�ƒ����o�Ő키�����A���ΐl�O�̗̈�ɑ��ݓ��ꂽ��l�̎E�������͒����͂����ւ��Ĕ��͖��_���B�A�j���͗��N���ė��N�̕����ŁA����̑S�������f�����ł��邩�ǂ����A���Ċ����ł��ˁB1�N�[�����ƌ��������A2�N�[���Ȃ�1����������3�b�g���邩�牽�Ƃ��Ȃ肻���H�@�l�C���o���2���ڂŎc��̎�����S������Ċ����������邩������Ȃ��B�����ɐi��ł�2030�N���炢�̘b�ɂȂ邾�낤���獡����C�ɂ��Ă����傤���Ȃ�����ǁB�Ƃɂ����o�g��������̍�i�Ȃ�ŁA���Ɋւ��Ă͐S�z���炯���B���������߂�3D�A�j���ɂȂ�̂��ȁB3D�A�j�����āu�������₷���v�����Ŕ�p�͂��Ȃ萓�ނ炵������A�����I�ɍl����Ɓu�~�ߊG�̑���2D�A�j���v�ɂȂ肻���ȗ\���B�ł��y���݁B
�E�w�A�g���N���i�N�A�x����k�w�n���@The next series of Atlach=Nacha�x
�@���݂͒m���Ă������ǁA���N���J����Ă����̂��A����B�A���X�\�t�g�����삵��18�փQ�[���i�v����ɃG���Q�[�j�w�A�g���N���i�N�A�x�̌���k�ł��B�w�A�g���N���i�N�A�x�͂��Ƃ���1997�N�ɔ������ꂽ�wALICE�̊�4�E5�E6�x�Ƃ����o���G�e�B�\�t�g�Ɏ��^����Ă����R���e���c�̂ЂƂŁA�D�]����������3�N���2000�N����P�i�̔�����܂����B���������Ă���̂��P�i�ł̕��ł��B�wALICE�̊�4�E5�E6�x�ɂ͓��T�Ƃ��āu�I�t�B�V�����K�C�h�v�Ƃ�����^�{����������Ă���A�����Ɏ��^����Ă�������k���u�n���@The next series of Atlach=Nacha�v�ł���B�Ȃ̂Ő̂���̃t�@���͓��e��m���Ă��邯�ǒP�i�ł���������w�͒m��Ȃ��A�Ƃ��������Ȓm���x�̃G�s�\�[�h�ł��B��2ch�����ŊT�v�����G��Ă����l�������̂ő�܂��ȓ��e�͒m���Ă��܂������A������q�ނ̂͏��߂Ă����狻�����Ă��܂����B
�@�u�w�A�g���N���i�N�A�x������̂͂����Ԑ̂�����A��������ܓ��e�o���ĂȂ��ȁc�c�v�Ƃ����l�����Ɉꉞ������悤�B���_�l�^�o���S�J�Ȃ̂Œ��ӁB����k�̎�l���́u�����v�A�������Q�[���{�҂ɓo�ꂵ���u��Ǎ⏉���v�ł͂Ȃ����̖��ł��B���e�́u��i���낪�ˁj�v�A�ŏI����̂Ƃ��ɔƂ��ꂽ��Ǎ⏉�����s�q�ŁA���̒��O�Ƀq���C���́u�[�R�t�q�v�֗��̏�Ԃő����܂����B�������Ǒِ��Ȃ̂ŏo�Y�����̂͑t�q�ł��ˁB���̍ۂɑt�q�͐l�O�����Ă���A����k�ł�������Ă��炸�Ⴂ�����ڂ̂܂܁B���̌q����͂Ȃ����A��������́u���ꂳ��v�ƌĂ�Ă���B�����������o�܂���A�����̌ːЏ�̖��O�́u�[�R�����v�ł��B�S�̎x���ł������u�o�l�̏����v��r���Ă��炸���Ƒt�q�͐��C�������Ă���A�u���̏����v���o�l�Ɣ��Γ��ꎋ���Ă���B�������}�������Ƃ��L�b�J�P�ɏ����̒w偉����n�܂�A�u�������l�Ԃ���Ȃ���������Ȃ��v�����ɏ����{�l�͏Ռ����܂����A�t�q�͊�т̕\����ׂāu�o�l�I�v���v����Ă���B�����A�{�҂���Ă�Ɓu�����o�l�͑t�q�ɒw偂̎p��������̂����ōŏI����̂��Ȃ��ł����l�Ԍ`�Ԃɖ߂������炢�Ȃ̂ɁA�t�q�͒w偌`�Ԃ��܂߂Ďo�l�������Ă����ȁc�c�v�ƐȂ��Ȃ�܂��B�u�w偂̎e�v�ł���Ȃ��~�ߐ�Ȃ��܂܁A��i�t�q�j�Ɨ���Ƃ�ŕ�炻���ƌ��ӂ��鏉���B�҂�ł�������u������A���̐F�������J�[�f�B�K���v��������߂ď������܂����ڂ��V�[���ŕ���͖����~�낵�܂��B
�@���N�A�A���X�\�t�g�̃\�V���Q�w���V���G�X�J���[�V�����q���C���Y�x�ł��́u�n���@The next series of Atlach=Nacha�v���x�[�X�ɂ����C�x���g�u���₩���ƌĂꂽ�����v���J�Â��ꂽ���߁A����ɔ����Č��J���ꂽ�݂����ł��B�ꖺ�ǂ������u�����v�Ȃ̂ł�₱�������A��̕����u��Ǎ⏉���v�Ŗ��̕����u�[�R�����v�ƈꉞ��ʂ���Ă���͗l�B�������v���C�A�u�������Ă���̂����̏��������ŁA�����������Ǎ�n�c�l�Ƃ����u��Ǎ⏉���Ƃ͎��Ĕ�Ȃ郂�m�v�ɂȂ��Ă���݂����ł��B���̃C�x���g�őt�q�����C�����߂��A�v���C�A�u���L�����Ƃ��Ď������ꂽ�炵���̂����A�Ȃ��w����������́@���X�g�t���O�x���N�[���݂������ȁc�c�i���̃Q�[���ł͗c���ލs�����܂܂����A�\�V���Q�̃C�x���g�Ő��C�����߂��j�B�u�n���@The next series of Atlach=Nacha�v���Ƃǂ����~���Ă��ߎS�Ȗ��������҂��Ă��Ȃ������������[�R��������u�l�O�Ȃ�đ��ɂ��������邵�c�c�v�ȁw���V���x�̐��E�őO�����ɐ����Ă���炵���́A�����z�b�R�������B���Ȃ݂Ɂw�A�g���N���i�N�A�x�͔�Ǎ⏉���Ƌ�̈������@�艺�����ߋ��҂ɓ����鏬���ł����݂��܂����A�d�q������Ă��Ȃ����ߌ��݂ł͓��荢��B�Ƃ������w�A�g���N���i�N�A�x���̂����ݐV�i�ł͔����Ă��Ȃ��i���Âł���⍂���C�����j���A�_�E�����[�h�̔������Ă��Ȃ��݂���������V�K�̐l���v���[���ɂ����Ȃ�ł���ˁB�G���Q�[�͋l�܂�Ƃ���|���m�Ȃ̂ŁA���܂�C�y�ɃA�N�Z�X�ł��Ă�����c�c�Ƃ������������܂����A����������ɐG��ɂ����͎��y�����̂ł��B
�E�t�������w�\��l�̑��R�x�Ǘ��B
�@��N���J���ꂽ�f���w�\��l�̑��R�x�̏����łɓ����鎞�㒷�ҁB��C�푈�̍��A�܂薋��������ł��B�l�X�ȍ߂œ������ꂽ���S�l����10�����A�u�U�ߊ�F���R����Ԃ������܂Ŏ���Ζ��ߕ��ƁA�J������炷�B�f��Ύ�˂�v�Ɣ����A�ۉ��Ȃ��u���R�v�Ɛ키�n���ɂȂ�c�c�Ƃ����a���w�X�[�T�C�h�X�N���b�h�x���B300�y�[�W���炸�Ȃ̂Ƀ��C���L������10�l�ȏ�A�G�T�C�h���܂߂���v��20�l���炢�ɏ��B�������Ɉ�l��l�̈����͔��߂ɂȂ��Ă���A�t����i�Ƃ��Ă͏����ȕ��ނɑ����邾�낤�B�����A���㏬���ŁuL�v��v�Ƃ������ׂ����e�ŁA���X�g50�y�[�W�̏�݊|����悤�ȓW�J�ɂ̓y�[�W���߂���肪�~�܂�Ȃ������B�t�Ɍ����Ƃ����܂ł�������ƃ^���������ł��ˁB���H�z��˓����ɑ����Ă���˂̒��ł��u�O�ꂵ�Ċ��R�ɍR�����I�v�h�Ɓu�������ƐV���{�ɐQ�Ԃ肽�����Ǒ��̔˂̖ڂ����邵�Ȃ��c�c�v�h�����đ����݂������Ă��炸�A�V���{�R���ł��邾�����Ղ������������Q�Ԃ�劽�}�Ȃ̂����A�u�a���Ȃo�J�o�J�����I�@�͂ł˂�������X�����낤�I�v�ƍD��I�ȘA�����摖���Ă��ďՓ˂͔������Ȃ��\�\�Ƃ������G�Ȏ�������āA�v����Ɂu���R�v�݂̂�Ȃ́u���ԉ҂��̎̂Đv�Ƃ��č����o����Ă����Ԃł��B��w�����J��L���镠�̒T�荇���͉\�Ȃ�����ȗ����A�����܂Řb������i�ܓ��R�̈�m��ԁj�ɂ�����ǒn��ɍi���ĒԂ��Ă��邪�A�ʓ|�L���w�i������Ԃ�オ���Ă���܂Ŏ��Ԃ̊|����\���ł��B�f��ł͌��݃l�g�t���œƐ茩����z�M���B
�@�ŁA�����ł�ǂݏI�������ɉf��ł��������܂������A��܂��ȗv�f�͈ꏏ�����Ǎׂ����Ƃ���͂��낢��Ⴄ�B�f��ɂ́u�a�������v�Ƃ����Ɛb�ŃE�B���A���E�e�������������Ă���C�J�ꂽ�Ⴋ�V���c�˂̓a�l���o�Ă��܂����A�����łɂ͂��܂���B���A�f��ł͐������Y����钼�O�Ɂu�҂ā[���I�v�ƒ��~�̖��߂���э��ޓW�J�ɂȂ��Ă��邪�A�����łł͂܂��S���̒��ɂ��āA���Y�̒i��肪�����O�Ɂu���R�v�Ґ��̘b������Ă���`�ƂȂ��Ă��܂��B���S�l����10���̌X�̍ߏ�������ɈقȂ邵�A���ɕ��⎀�ʃ^�C�~���O���ς���Ă���B�Ō�ɐ����c��ʎq�����Ⴄ�B�����������̊��A�w�m�`�Ȃ��킢�x�Ƃ��ŗL���ȋr�{�Ɓu�}���a�v�v��1964�N�ɏ������w�\��l�̑��R�x�Ƃ����r�{�̃v���b�g���匳�ł���B���e�̓y��350�����炢�i�y���Ƃ����̂�200���l���e�p���̂��Ɓj�A��N������Ŏ��M�������\�ȑ��i�f��������ƃy��1���������30�b�ɂȂ�̂ŁA��������175���A3���ԋ߂��̓��e�j�������̂ł����A�u�Ō�͑S���������Ɂv�Ƃ����S�ŃG���h���������ߎB�e���̏����Ɂu����ȕ�����b�Ȃ���Ăǂ�����̂�I�v�ƈ�R����Ă��܂��������Ȃ������B�ǂ₳�ꂽ�}���͓��ɗ��Č��e��j��̂Ă����߁A�������Ă���̂��\���y�[�W�̍[�T�i�V�m�v�V�X�j�̂݁B���̒Z���v���b�g��c��܂����̂��f��ł̋r�{�ł��B�ǂ������o�܂řt�������m�x���C�Y����|���邱�ƂɂȂ����̂��s�������A���炭�f��̋r�{��ǂ܂��Ɋ}���̌��Ăڏ����������̂ł͂Ȃ����낤���B���ꂮ�炢�ו����ʕ��ɂȂ��Ă��܂��B2���Ԕ��ƃ{�����[�����̂͌��\����f��Ȃ̂����A����ς�11�l�͑�����ȁc�c���Ă����̂������Ă��܂����B�����ł��ɓǂ�ł��Ȃ�������N���N������ʂ��t���Ȃ�������������܂���B�����A�f��Ɋւ��Ă̓q�b�g�����ƌ����ɂ����B�����10���~�ɑ��ċ�����4���~���炢�ł��B
�@���ɂ���ȏ��肽�����Ƃ��Ȃ��̂ŁA�ȉ����R�̖ʎq�ɂ��ă������Ă����܂��B�\��l������Ɩ��O���X���X���o�Ă��Ȃ�����ł�����ˁB�����ł��Ɠ��S�l�����͊�{�I�ɓ���ŌĂэ����܂��i�f��ł͂��������Ăэ���Ȃ��j���A�킩���Ă��邩����{�����L���Ă����B
�@���@�c�@�{���̎�l���ɓ����鑶�݁B�u���g�v�Ƃ������_�Ɖ��Ă���������Ă���B��������̂܂܁u���ĉ��v�B�u�������v�Ƃ������̗����Ȃ����[������A�ޏ������\���ꂽ���ƂɌ��V����7�l���̎����u�`�E���Ă��܂��B�����łł͗֊����������A�f��ł́u��ΑP�E�G��v�Ƃ�����l�̎��ɖ������W��A�E�Q�l����������1�l�Ɍ����Ă��܂��B�ߏ�͓��R�u�E�l�v�B�쒆����̃t�B�W�J�������X�^�[�B�f��ł́u�R�c�F�V�v�����������A�u���Ă����Ȃ̂��O�͂����܂����v�Ƃ����ݒ肪�Ȃ��Ȃ��Ă���̂��A�����ł����������i�[�t����Ă����ۂ�����B
�@��������@�c�@�{���s�ڂ̘S����B�Ăі��̒ʂ�V��ŁA���͒��B�˂̎��B�u�֖�̐�v�Œ��G�ƂȂ�A���Q�̐g�ɑ����B��̈������B�l�N���X�Ő��݂����ȉ��͖�Y�������Ƃ����Ԃɔ���グ�Ă��܂��B���ӂƂ��链���͑��B��q����u�ԒO�v�̌v��̕Ж_��S�������Ƃŕߔ����ꂽ�B�f��łł̍ߏ�́u�����E�l�v�ƂȂ��Ă���B�G�X�Ƃ��Ă���悤�ł��Ď��ɏꏊ�����߂Ă���J�b�R�������ǂ���ł���A�o�g���ʂɊւ��Ă͂����Ƃ���ې[���L�����B���ǃN���C�}�b�N�X�̒n�̕��Łu�������́c�c�v�Əo�Ă���̂��Ԕ����Ȃ�ŁA�ł���Ζ{���𖾂����Ăق��������B�}���̃v���b�g�ł́u���ĕF���Y�v���{���Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�f��ʼn������o�D�́u�{�R�́v�A�u�����B�ˑ��p�w��A���ĕF���Y�I�v�Ɩ����������A�u�`�ɂ��Č䍑�ɋt�炢���v��Ⴢ��V����V�[��������܂����A�����łɎ����悤�ȃV�[���͏o�Ă��܂���B���ƍׂ����������łł́u�������v�A�f��łł́u�������v�Ɣ����ɕ\�L���قȂ�B
�@�ԒO�@�c�@�{���s�ڂ̔��k�B�ǂ݂͉f�悾�Ɓu��������v���������łł́u�����Ɂv�ɂȂ��Ă���B�}���̃v���b�g�ɓǂ݂��\�L����Ă��Ȃ��������낤�B��Z�n�������Ȃ������V���������A���b�ɂȂ��Ă����g���J���Ă����q��֔˂̉ƘV�O���ʂ��l�߂Ă������Ƃ��莋����A�u�ƘV�O���ق��킯�ɂ͂����Ȃ��v�Ƃ������R�őg�̓��Ɣz�����S���a��Ă��܂����B���̂��Ƃ�s���Ɏv�����ԒO�͉ƘV�O�̎q��������q��ɗU�����݁A�Ƃ��X���قǂ̑K���C�J�T�}�ŒD������ĖS���Ȃ����g�������̖��S�l��⎙�ɕ����^�����B�ߏ�́u�q���v�B�f��ł́u����E�߁v�������A�����߂����|�W�V�����Ɏ��܂��Ă���B
�@�Ȃ��@�c�@�U�߂��u���ېV���I�@�g�𗧂Ă�`�����X�I�v�ƕ�����ĒE�˂�������Ɏ��S�A�n���̂��ߏ��Y�ɂȂ����B�q�̎q��g�����������߂��炭�x�Ƃ��ē��ӂ̎O���������e���ĉ߂������肾�������A�u���{�e���ƔƂ肽���v�ƌ����o�����Q�l�ɔƂ���ė��Y�B�u�`�M���ĘQ�l���u�b�E�����B�Ȃ̂ŏ����ł̍ߏ�́u�E�l�v�����A�f��ł͒��ڎE�Q����V�[�����Ȃ��j�̉Ƃɕ����Ă��邾���Ȃ̂ōߏu�Εt���v�ɂȂ��Ă��܂��B�g��_�Ȃ��ǂ��F�C�W�J�͓��ɂȂ��B�퓬�v���ł͂Ȃ��т̎ϐ�������炳��Ă���B����́u�O�����v�B�m���̑̂ŎO������e�����X�g�V�[���͊G�ɂȂ�̂ʼnf���Ŋς����Ȃ��A�Ǝv�������f��ł��Ɓu�O���������Ӂv���Đݒ莩�̂Ȃ����A�Ō�܂Ő������т�̂Łu�S�R�Ⴄ�����I�v�Ƌ���ł��܂����B�f��ł̓��[�j���O���B�̌������o�[�u��t���ہv�������܂����B
�@�m���@�c�@�{���s�ځB�ԉŗL���ȁu�ЊL�v�̏o�g�B��b�\�͂ɖR�������ꂵ������Ȃ����A�Ζ����̎�舵���ɒ����Ă���A�ޗ��Ɠ��������Ήԉ┚������o����B�S���Ȃ����Z�Ɏ��Ă���炵���A���̂��Ƃ��u����ɂ�v�ƌĂ�ŕ炤�B�����łł͓����X�ɋ߂Ă���Ȃ̋w��������`�����ߗ��ĉ��ɉԉ���荞�߂ŕ߂܂����B�f��łł́u�n���̉ԉΎt�̑��q�v�ɐݒ�ύX����Ă���A�ߏ���u�Z�Ɏ��Ă��鐭�����Ƃ����v�Ƃ����u�E���v�ɂȂ��Ă���B�f��ł́u���v�{��v���������B�h��Ȕ����V�[���͂��������m���̌��тȂ̂ŁA�L�����Ɋւ��Ă͑��R��MVP�B�����E���߂��������ŏI�Ճ}�Y�����ƂɂȂ��Ă��܂��B���H�z��˓������Ċ��R�ɐQ�Ԃ肽���V���c�˂͐Q�Ԃ�̏����������܂Ŋ��R���Ԃɑ��~�߂��������A�܂�P�Ȃ鎞�ԉ҂��̂��߂ɑ��R��h�������i�������V���c�˂ł��邱�Ƃ��킩��Ȃ��悤�H�삵���j�̂ŁA���R�̋]�����������Ă͍���킯�ł��ˁB�������Ŗ��߂��ʂ��������R�̏�����Q�肷��l�����o�Ă��܂����A�����܂ő厖�ɂȂ�Ɛ������Ă͂����Ȃ��c�c���Ċ����ŁA�Ԃ�����������X�Ȃ���҂��Ă��܂��B
�@�����@�c�@�������̖V��B�{���͂��납�m�����s���B���B���Ƃ��j���̖{���A�Ə����Ēh�Ƃ̖���Ђ��[������Ă߂ɂ������Ƃœ������ꂽ�B�ߏ�́u���Ɓv�B�܂��ɏ��ƖV�B������Ȃ�Ƃ����Ƃ���B���R�̒��ł͒������i��̗]�n���Ȃ������o�[�B�L�����N�^�[�͋����퓬�v���ł͂Ȃ��A���҂��o���Ƃ��ɔO����������̂���ځB�f��ł́u�猴�������v���������B
�@���낵���@�c�@�V���c�˂̌��ˎm�B�{���s�ځB��؈�w���w�сA�u���m�ł͂Ȃ���҂ɂȂ肽���v�Ɗ���đ���E�����A���낢�날���āu���낵��i���V�A�j�v�s���̑D�Ŗ��q���悤�Ƃ������D���Ƀo���ē˂��o���ꂽ�B�{���́u����v�ɍs�������������D�����ꂵ���Ȃ������炵���B�ߏ�͂��̂܂�܁u���q�v�B�q�[���[���ŁA���̃����o�[������������牽�Ƃ����Ă����B�Ƃ͌����Ă��������R��������o���鎡�Âɂ͌��E������A���҂����o����㔼�ɂȂ�ƕa��ł���B���̋C�������A���̒��Łu��Ȃ�ăo�J�o�J�����v�Ƃ����X�^���X������Ȃ������l�B�f��ł́u���R�V���v���������B�����łƈ���ĕ��ʂɐ킨���Ƃ��Ă����ȁB
�@�O�r�@�c�@�H���l�߂��_���B�{���s�ځB��J�ɂ��͐�×��ɂ���ēc�����_���ɂȂ�A�n���̖��ɏ��[�A�q���A��e��S���E���Ď��������ǂ����Ɛ�ɐg�𓊂������A�݂ɑł��グ���Ď��ɑ��Ȃ����B���ɐ��C��r�����Ă���A�قڌ��t���ʂ��Ȃ��B�ߏ�́u��ƐS���v�B�u��v�ɐl�������킳�ꂽ�������A��ɑ��鎷���S�������B�t����i�ł��܂ɏo�Ă���u�܂Ƃ��ȉ�b���������Ȃ��g�v�B�f��ł́u���Y�S��v���������B���ʂɒ����Ă��邩�珬���łɔ�ׂăL���������߁B
�@���@�c�@�C�P�����_���B�{���s�ځB�����̏��[��Q��������A�p�������Ƃ��������������s�`���ʂł͂Ȃ��u�������Ꝅ����Ă��v�Ƃ������R�ői���o���B�f��ł́u���̏��[�Ɨ����ɂȂ����v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���A�ߏ�́u���ʁv�B�����ł��Ɓu���̓X�p�C�v�Ƃ����ݒ�Ȃ��A�f��ł��Ⴛ�̐ݒ肪�Ȃ��Ȃ��Ă���A�₽��q���C�b�N�Ȏ��ɕ�������̂ŏ����ł��C���p�N�g�����邩���B�f��ł́u��m���D�v���������B
�@�ɓ��܉E�q���@�c�@�u�h������v�Ƃ������p����̖�l�B������n�܂��ɔ����Ė�烂̖��S�������q���̋�ʂȂ��a��E���܂����Ă����T�C�R�p�X�B����́u�Ҏa�v�B�ߔ����悤�Ƃ��镺�m�Y�����̂��Ƃ��瓦���o�����A�����킹�����ɒ@���̂߂��ꂨ��ƂȂ����B�ȗ��A���x�ƂȂ����ɏ����ނ������]����Ă���B�ߏ�́u�Ҏa��v�B�����̃V���A���L���[�Ȃ��ǐ퓬�v���Ƃ��Ă͗��������z�B�f��ł́u���������v���������B�����łƈ���đ����i�K�Ŏ��ʂ��A���╺�m�Y�Ƃ̈�������������Ă���̂ł�����ƋL���Ɏc��ɂ����B
�@�h�����m�Y�@�c�@�u�h������v�̓����A�u���S�e���v�̎g����B���S�l�ł͂Ȃ��̂œ���͂Ȃ��B�����h�̔ˎm�ŁA���R�̑��~�߂��I�������́u�˖����Ăł͂Ȃ�����ɍs�������v�Ƃ������ڂŎ�˂���蔤�ƂȂ��Ă���B�������Ƃ��čԂɋl�߂�͂���������l�����𐭂Ƃ̃g���u���őS�����Ȃ��Ă��܂��Ƃ������Ԃɂ��A���S�l�����Ƒg�ނ��ƂɂȂ����B���ɔ�͂Ȃ����Ƃ��킩���Ă���̂ŁA���Ƃ��Ă��ނ����������Ǝv���Ă���B�f��łł͋��m�̑��肩��u���O�͓��S�l����Ȃ���œ��~����ΐ������Ă����Ă��A���̘A���͊F�E�������ǂȁv�Ƃ����b�������|�����u�N�͑���c�c�\��l�ڂ̂ȁv�ƙꂢ�ă^�C�g�����������V�[�����������B�f��ł́u���쑾��v���������B�Ȃ����m�Y�̑��ɓ��S�l�������Ď����킷��u���]���n�i�����j�v�u�r�䖜�V���i�������j�v�u�ؕ鑍���i���l�j�v�Ƃ������ʁX���o�ꂵ�܂����A������͐V���{�ɐQ�Ԃ��Đ������т�\��Ȃ̂ő��R�ɂ̓J�E���g���Ȃ��B����Ɛ��n�̍ȁu���ށv�͔b��O�ɚg������قNĴ�������Ă���A�T�u�L�����̒��ł͂����Ƃ���ۂɎc���Ă���B
�@�ŁA�f��Ə����ǂ������ǂ������́H�@�Ɛu�����ƁA���X�Y�܂����Ƃ��낾�������I�ɔ��f����Ώ����ł̕����Ȃ��B����ȂA�Ҏa������Ɋւ��Ă͉f����������ƃL�����������Ă��܂����A�ו��̍�荞�݂��ǂ��Ƃ������f��͂ǂ����Ă��u�ڂ�����Ȃ��v�Ɗ����镔��������B���ǁA����ʼnf��ł̓��X�Ɩ������グ���������^�C�g����������镺�m�Y���̂Ă������A�u�\�Ȃ痼������������������v���Č��_�ɂȂ�܂��B
2025-04-30.�E�w�A�C�J�c�I�~�v���p�� THE MOVIE �]�o��̃L�Z�L�I�]�x���J�̂��m�点�ɋV���Ă���ĒÂł��A�����́B
�@�܂�Ń{�u�E���[�E�X���K�[�ƃW���b�N�E���[�`���[�̋�������f�悪�B����悤�ȏՌ��ł���c�c�w�A�C�J�c�I�x���w�v���p���x�����������R���e���c�ŁA�n�b�L�������ċ������肾�����̂ł��������R���{�͖ϑz��������u���ۂ̊��v�Ƃ��čl�����l�͂قƂ�ǂ��Ȃ������ł��傤�B���ăZ�K���w�I�V�������� ���uand�x���[�x�Ő�J�����u���������A�[�P�[�h�Q�[���v�Ȃ镪��ɂ����āA�u�|�X�g�E���u�x���v�ƂȂ�ׂ��M����������C�o�����m�����g�ށc�c�������̎��_�Ńh���}�������Ă��܂��܂��B�w�A�C�J�c�I�x�́u�o���_�C�v�̃A�[�P�[�h�Q�[���𒆐S�ɐ������v���W�F�N�g�ŁA2012�N�ɃA�j���������J�n���A���x���^�C�g����ς��Ȃ���ԑg���p�����Ă��܂�����2021�N�́w�A�C�J�c�v���l�b�g�I�x���Ō��TV�A�j���Ƃ��Ă̓W�J���I���B���݂́w�A�C�J�c�A�J�f�~�[�I�x�Ƃ����z�M��̂̃v���W�F�N�g��Youtube�œW�J���Ă��܂��B�����A�w�v���p���x�́u�^�J���g�~�[�v�̃A�[�P�[�h�Q�[������Ƃ���v���W�F�N�g�Ȃ̂ł����A�w�A�C�J�c�I�x���v���W�F�N�g�S�̂��w���p��ł���̂ɑ��w�v���p���x�́u�v���W�F�N�g�̈ꕔ�v���w���p��ŁA��j���A���X�͈قȂ�B
�@�Ȃ�ׂ���Z�ɏ����܂����A�^�J���g�~�[�����������̃R���e���c�Ƃ��ė����グ���v���W�F�N�g���́u�v���e�B�[���Y���v�A�����āu�v���Y���v�A�S�̂�ʂ��Ďw���ꍇ�́u�v���e�B�[�V���[�Y�v�ƌ����邱�Ƃ������B�����l�C�̂������u�������P�v��u��c�^���v���C���[�W���āA���`�[�t�̈�Ɂu�t�B�M���A�X�P�[�g�v����荞��ł���B2010�N�ɃQ�[�����X�^�[�g�����A���N2011�N�ɏ��̃A�j����i�w�v���e�B�[���Y���E�I�[�����h���[���x�iAD�j������J�n�B1�N�i4�N�[���j����������ő��҂ɓ�����w�v���e�B�[���Y���E�f�B�A�}�C�t���[�`���[�x�iDMF�j�փo�g���^�b�`���܂������A����DMF��������Ă��������Ɂw�A�C�J�c�I�x�����1���ڂ��n�܂��ĂԂ��荇���`�ƂȂ�܂����B���ʁA�����l�C�̓A�C�J�c���ɌR�z���オ��A�v���Y���T�C�h�͐헪�̗��蒼���𔗂���BAD��DMF�͓������E��ɂ��Ĉꕔ�̃L�����N�^�[�������p���ł������A���x�͐ݒ��ς��ăL���X�g����V���悤�c�c�ƁA�C�������Ďd�蒼�����̂�3��ځw�v���e�B�[���Y���E���C���{�[���C�u�x�i2013�`2014�N�j�B��i���̂̕]���͍����A�����ɔh���^�C�g���̓W�J�������Ă��邭�炢�ł��邪�A�����̃A�C�J�c�l�C�͂Ƃɂ����������݂Ă����i�s�[�N���̔���͔N��140���A�u�ԓI�ɂ̓v���L���A�������킵���j���ߎ����������A�X�Ȃ�헪�̗��蒼�����K�v�ɂȂ�܂����B
�@�������Č��ꂽ�̂��w�v���p���x�i2014�`2017�N�j�ł��B�u���������w�v���e�B�[���Y���x���ᒷ�����ď��̎q�ɐe���݂������Ă��炦�Ȃ��v�ƁA�^�C�g�����_�Ɏl�����֏ȗ��B�܂��A�V���[�Y�̓����������u�t�B�M���A�X�P�[�g�݂����ȃW�����v�v�Ƃ����v�f���폜�B�u�R�[�f�ƃ_���X�Ɖ̏��v��3����̂ɂ����A�C�h�����ɂȂ��Ă����B�I���ɃA�C�J�c���ӎ������{��ł���B�^�[�Q�b�g�w�����w�Z���w�N���炢�̏��q�����w�N���炢�̏��q�܂ň��������A�u�h���}�e�B�b�N�v�������X�g�[���[���u�R�~�J���v�ȘH���֕ύX�����B���ꂪ�����ɓ������āA�A�C�J�c�ƃv���Y���i�v���p���j�̐l�C�͋t�]���܂��B�����ɏ����ƁA�v���p���ł������u�S�����i2013�N���j�̃A�C�J�c�l�C�v�ɂ͋y�Ȃ��̂����A�v���p������Ă����̃A�C�J�c�͌�q���闝�R�Ől�C���Ȃ肪�o�Ă������ߑ傫���������Ă��܂����B�w�v���p���x�͑��҂́w�A�C�h���^�C���v���p���x���܂߂��2018�N�܂ŕ����𑱂��A�w�L���b�ƃv�����`�����x�փo�g����n���Ď�ȓW�J���I�����܂��B2020�N��ɃX�}�z�A�v���ƘA�����āw�A�C�h�������h�v���p���x�Ƃ���Web�A�j�����z�M���Ă���A������܂߂�ƑS�̂�200�b����B�Ȃ��v���e�B�[�V���[�Y���͍̂����w�Ђ݂̃A�C�v���x�Ƃ�����i�����j�̒��ɕ�������Ă��܂��B�v���p���ɔ�ׂ�ƒn���ɉf�邩������Ȃ����A�A�[�P�[�h�Q�[���̔���́u�v���p���̋L�^��h��ւ��ĉߋ��ō��ɂȂ����v�ƌ������\����Ă��邮�炢�ł��Ȃ�D���A�A�j����2�N�ڂɓ˓������B�A�C�J�c�������A�j�����Q�[��������ĂȂ����珗���l�C����ɏW�������\�\�Ƃ����ʂ����邾�낤���A�A�C�v���̑O�ɂ���Ă����v���}�W�i�w���b�`���v���}�W�I�x�j�̓R���i�Ђ̉e���������Ĕ���s�U�Łu�v���e�B�[�V���[�Y���̂��̂��I����Ȃ����v�ƐS�z���ꂽ���炢�����犄�Ɗ�Ղ̕������������肷��B
�@�v���e�B�[�V���[�Y�����x���ݒ�ύX���Ă���悤�ɁA�A�C�J�c�̃A�j�������x���d�蒼��������Ă��܂��B2016�N�Ɏn�܂����w�A�C�J�c�X�^�[�Y�I�x�͂���܂ł̃A�C�J�c�̓��e�������p�����A��{�I�ɓƗ�������i�Ƃ��Đ������Ă���i�u��{�I�Ɂv�Ə������̂̓R���{�݂����Ȍ`�Łu�ȑO�̃A�C�J�c�v�ƌq���邱�Ƃ����邩��j�B�t�Ɍ����ƁA����̃A�C�J�c��2012�N����2016�N�܂ŁA3�N���ɓn���āu�������E�̘b�v����葱���Ă�����ł��B����TV�A�j���Ƃ��ēW�J���Ă������Ԃ̒����ł����Ɓw�A�C�J�c�I�x�i����j�Ɓw�v���p���x�i�w�A�C�h���^�C���v���p���x�܂ށj�͓������炢�Ȃ̂��B����A�C�J�c�́u���{�������v�Ƃ�����������l���ŁA�ޏ����A�C�h���{�����ł���u�X�^�[���C�g�w���v�̒������ɓ���Ƃ��납�畨�ꂪ�n�܂�B���̌�A���Ԃ�C�o���Ɛ����������Ăǂ�ǂ����i�����A��y�ɓ�����L�������o�ꂷ��悤�ɂȂ�܂��B�����Č�y�L�����̈�l�A�u�����v������́w�A�C�J�c�I�~�v���p�� THE MOVIE�x�Ń��C����B
�@�����肿���͓����u�����������ɓ���鏗�̎q�v�Ƃ������ǂ���ŁA���^�����������������ł����B�������u�����Ȃ�̃A�C�h���v��ڎw���悤�ɂȂ�A�I���W�i���e�B��ł����ĂĂ����A�A�j���͏��X�ɂ����肿�������ɐi�ނ悤�ɂȂ�B3�N�ڂɓ���A����A�C�J�c�͐����Ɏ�l��������������炠���肿���֕ύX�B�A�o���Łu���̔M���A�C�h�������A�w�A�C�J�c�I�x�n�܂�܂��v�Ɛ錾�����������������炠���肿���ɂȂ����B�v���p�����������Ă����̂͂��傤�ǂ��́u�A�C�J�c�̎�����v���s���Ă��������Ȃ�ł��B�u����������������Ȃ��Ȃ����v���ƂŃ��C���̏����w������Ă����A�A�C�J�c�l�C�Ƀu���[�L���|����n�߂��B���̍��Ƀv���p�����傫���L�������킯�ł��B�u�����s��̃V�F�A��D��ꂽ�v�A�C�J�c����T�C�h�ɂ����āu�v���p���v�͋�ƂȂ�A�u�R���{�Ȃǖ��̂܂����v�ȏƂȂ��Ă����܂��B
�@�������A���͂�A�C�J�c���Q�[����A�j���̓W�J���I�����AYoutube�Ƀ`�����l�����c���݂̂ƂȂ����B��������ł������v���e�B�[�V���[�Y��G������K�v���Ȃ��Ȃ�A�������ăR���{���\�ɂȂ����̂ł���B������^���炟��ɍĂщ��I�@�Ƃ������ԂɐS�������l���������낤�B���ǁA����ȑz�����`���b�Ƃ悬�邩������Ȃ��B�u�����ɐ��{������������ȁc�c�v�ƁB��q�����ʂ�A�v���p�����������Ă������Ԃ̎�l���͂����肿���Ȃ̂ŁA�L���X�e�B���O�Ƃ��Ă͎��R�ł��B�����A��x����̃R���{�f��Ƃ����Ȃ�u�炟��ƃK�b�c���������邢��������ς��������ȁc�c�v���Ċ�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ԃ���Ƃ����J���I�o�����x���ŏo�Ă���낤�ȁB�����������͈��N�̉f��w�A�C�J�c�I 10th STORY �`�����ւ�STARWAY�`�x�ő��ƃ��C�u����������A����ȏチ�C���o��������͓̂���̂�������Ȃ��B�Ƃɂ����A���͑����҂����Ȃ����B�A�C�J�c���A�v���e�B�[�V���[�Y���v���p�������Ɍ��肵�Ă������Șb�������邩��R���{�Ŏg����l�^�����������ł���ˁB���������ǂ̂ւ���E���Ă�����B
�E�u���k��ɂ����͂���I�vTV�A�j�����@�ē͗��֒����A����̓p�b�V���[�l�i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@�O��̍X�V�Łu�A�j�������\�͕b�ǂ݂ɓ������ƌ��Ă������낤�ȁv���ď����Ă���{���ɔ��\���ꂽ�ł�����B����A�z���g�������ȁB�����u�}�K�W���ɘA�ڒ��̃��u�R���n����v���āu�A�j��������Ă��Ȃ���i�v������������������Ȃ����H�@�����w�F�߂����m�N���[���x���w��߂˂��˂��Ɓx��2�����c���ĂȂ��ł���B�ǂ��������N�n�܂�������̐V��ł��B�w�F�߂����m�N���[���x�͎�l���̍��ꂽ�������u�V�X�^�[�Ƃ��Đ��U�������т��v�ƍ��ꂷ��h�i�Ȏq�ŁA�ǂ��������̂��Ɠ�������Ă������l�����F�~�̈����u�A�X���f�E�X�v�Ɏ��߂���Ă��܂��A���͂̏������������ȋC���ɂ����Ă��܂��U���̎��Ɂc�c�Ƃ����e���v�e�[�V�����E���u�R���ł��B��l�����F�~�ɕ����Ĉ�����z�����畕��Ă���A�X���f�E�X���������Ă��܂��̂ŁA�Ђ�����䖝���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�^�C�v�Ƃ��Ắu���~�ߌn�v�Ȃ̂����A����ǎ҂��u�A�X���f�E�X�l�A�����Ƃ���Ă��������I�v�Ǝ�l���ł͂Ȃ������̕�������������A�u�{�C�o���Ă���H�@�A�X���f�E�X�A���O�ɂ͎��]������c�c�v�ƃk�����U�f�Ƀc�b�R�~����ꂽ��A�������������ł������Ȃ��ǘa�C�\�X�Ƃ����m���ł��B���Ȃ����u�ł���Ȃ̂��H�v���ăq���b�Ƃ���W�J�����������A�ЂƂ܂��u��ꕔ�E���v�Ƃ��������Ŏ��܂��ĐV�͂ɓ˓����܂����B���̂܂ܑ����̂ł���A�j����������ɓ����Ă��邾�낤���A�������Ɗ낤�����C�����ȁB�G���R�������G�N�\�V�X�g�I�ȃo�g���W�J�����荞�����Ƃ��Ă��āA�H�����m������܂ŘA�ڂ𑱂����邩�ǂ������傢�s���B�q���C���̐�������͎��i�[���^�C�v�ŁA��l�������̏��̎q�ƃC�`���C�`�����Ă���ƈ������|����ŕs�@���ɂȂ���Ă������������L���������牞���������B
�@�w��߂˂��˂��Ɓx�͑O�ɂ����������ǁu�}�K�W���ŁwToLOVE��x�{�w�h��������x�v�B�F���������Ă����|�R�c�����l�́u�i�m�v���A�����ȏ��i����悤�Ƃ�����ǖ���\�����Ă������ȃg���u���������N�����Ă��܂��c�c�Ƃ����h�^�o�^�G���R���B��͂Ɋւ��Ă͂܂�����n�ȂƂ���͂��邯��ǃZ���X���Q�A������ƔZ�����Ȃ��炢�Ǝ��̃I�[�����o���Ă��ēǂގ҂𖣗����܂��B�G���͌��E�M���M�����U�߂Ă邵�A���̎q���������I�ʼn����A��l�����C�J���Ă��Ċy�����B���ɂ������ł����ł��Ȃ��V�[���Ŏ�l�����i�m�̂����ς��𝆂݂������Ă�����A�t�Ƀi�m����l���̃t�j���`���𝆂݂܂����ėV��ł�����ƁA���Ӗ���ࣂꂽ�W�ɂȂ��Ă�̂��D���B���l�^����������A�Ƃ�����_�͂��邪�u������v���A�j�������邭�炢�����A��߂˂���������A�j���������Ȃ����ȁB
�@���āA�̐S�̐�����̘b�����Ă��Ȃ������B�w���k��ɂ����͂���I�x�i���́u������v�j�́w���k��������x�̈ߔ����p�����l�^�R���f�B�ł���A���ړI�ȃG���͏��Ȃ������w���k��������x�ƈ���Ē����̃G�����|���|�����荞��ł���댯�Ȉ�i�ł��B���x�ȃG���ƍ��x�ȃM���O�𗼗��������܂Ɋ����I�ȃG�s�\�[�h�����荞��ŁY��Ƃ����A���܂�Ɍ��̂Ȃ��\���́B�����ċ����Ő��~�̌����Ƃ����p�[�t�F�N�g�����鐶�k��́u�Ós�����q�v�A�ꌩ���i�₩�Ȕ��l�����\�͂̉��g�Ƃ��ċ�������v�́u�ƈ�L���v�A���z�ʼn��������́u�������܂�v�A�u�j������v�Ƃ������R�œ��`����邱�Ƃ�������Ă���L��́u��������v�ƁA���k����o�[�����ł����Ȃ���I�����A����ɃA�N�̋����T�u�L����������������ė��܂邱�Ƃ�m��ʃJ�I�X�Ȑ��E���W�J����܂��B�{�싳�@�́u�ϒˈ��v�i31�j�݂����ɁA�قƂ�ǖ{�҂ɏo�Ă��Ȃ��̂ɖ��ɍ������l�C���ւ�L����������B���Ȃ݂ɍ�҂̑O���w������Ȃ�I�x�Ƃ���i���E�����ʂ��Ă���A�O��L������������Ƃ����o�Ă���������܂��B�w������Ȃ�I�x�͍ŏI���̂��炷�����u�Ȃ�₩��₠���āA�ޏ������̓��N�U��������ƈꏏ�Ɏ��̈����Ƃ����邱�ƂɁI�H�v�Ƃ����u�b��㕨�Ȃ̂ʼn���s�v���낤�B�����s�ސT�Ƃ��������x����ʂ�z���Ă���B
�@�A�j���[�V��������́u�p�b�V���[�l�v�Ŋḗu���֒����v�A�w�ِ��E���{�Ńn�[�������x�̑g�ݍ��킹�ł��B�K���܂݂�ɂ͊���Ă���A���Ă��Ƃ��c�c�p�b�V���[�l�͍ŋ߂��Ɓw�ُC���x��w�T�ƍ��h���x�̃����C�N�ł�����Ă܂��ˁB���������͕s�������A�w�ʂ������x�̃A�j���ł����삵�Ă���B�ʂ������ɔ�ׂ�ΐ�����͉��Ƃ��Ȃ邩�A�Ǝv���Ă��܂�����|�����B
�E�����т̐V���w�L�}�C�����b�ρx�A5��20�������\��B�V���[�Y�̐�s�����ҁB
�@�O���w�L�}�C�����{�ρx����5�N�A�v�X�̐V���ɂ��Đ�s�����҂ł��B���������u��s�����ҁv�Ƃ͉����H�@�g�L�}�C���E��h�V���[�Y���J�n���瑁40�N�ȏ�A��҂ł���u�����сv��70���A�w�L�}�C�����{�ρx���s��Ɉ��������p��̐f�f�������ē��a�����ɓ��������߁A�u�����Ă��邤���Ɋ����������邩�ǂ����킩��Ȃ��v�Ƃ���10�N�ȏ�O����{�l�����ɂ��Ă������O�����悢��؉H�l�܂������̂ɂȂ��Ă��܂����B�u�ŏI���̍\�z�͂��邩��A�ߒ�����������Ċ����҂�����ɏ����Ă��܂����v�Ƃ������ƂŘA�ڂ��J�n�����̂����������\��́w�L�}�C�����b�ρx�Ȃ�ł��B�����V���o�ł��o���Ă��錎�����g����̖{�h��2022�N����f�ڂ���Ă��܂����B�w�L�}�C�����{�ρx���I�������Ɂw�L�}�C����E�ρx�Ƃ����V���A�ڂ��Ă����̂ł����A�a�C�̔��o�ɂ��2021�N�ɋx�ځB���b�ς̘A�ڂ��I������̂ŁA���͎�E�ς̕����ĊJ���Ă��܂��B�u��Ɋ����҂��o���v�Ƃ����͙̂t�����́w�J�I�X ���M�I���@���햂�R�сx�݂����ȑO������邪�A����́u�m�x���C�Y��1�������o���Ȃ��̂ʼnߒ�����������čŏI���킾���������Ƃ���A����ς���đ����ł���悤�ɂȂ�w�ŏI����Ɏ���܂ł̌o�܁x�߂Ă����`�ɂȂ����v�Ƃ������̂����玖��͂����ԈقȂ�܂��B
�@�L�}�C���V���[�Y�͕��ɔłƐV���łŃi���o�����O���Ⴄ�i�V���ł�1�`8���ڂ͕���2�����̍��{�Ȃ̂ŁA�u�V���ł�9���ڈȍ~�v�́u���ɔł�17���ڈȍ~�v�ɑ�������B���Ƃ��Ζ��{�ς̃i���o�����O�͐V���ł���15�����A���ɔł���23�ɂȂ�j�̂ł�₱�������A�w�L�}�C�����b�ρx�͊��s���Ō����ƃV���[�Y24��ڂɂȂ�܂��B�u�ʊ��v�Ƃ��������ɂȂ��Ă���w�L�}�C�����ρx���܂߂��25��ځB�ł���s�����҂Ȃ̂ŁA�쒆�̎��n��ɂ������̓I�ȃi���o�����O����܂��Ă��Ȃ���ł���ˁB�w�L�}�C����E�ρx�͐V������16���ځA���ɂ���24���ڂɂȂ�܂����ǁA���Ɖ��������ΐ��b�ςɒH�蒅����̂��悭�킩��܂���B�ǂl�̊��z���Ɛ��b�ς́u���܂芮���҂��ۂ��Ȃ����e�v�炵������A�����т̌��N����ł́u�^�̊����ҁv�݂����Ȃ̂����߂ďo�Ă���\�����[������Ȃ���ȁc�c�g�L�}�C���E��h�V���[�Y�͐l�Ԃ��l�O�̉����u�L�}�C���v�ɕς���Ă��܂��A�Ƃ�������Ȍ��ۂ̃��[�c��H��Ȃ���u��P��v�Ɓu�v�S���v�A�ӂ���̏��N���u�L�}�C�����v�ɖ|�M�����l�q��`���Ă����`��҂ł��B����������̓r�������Ɨ��̑��݊��͔��܂�A�s��ȌQ�����̗l����悵�n�߂�B�n�܂������_�ł͊w�����m��������ł����A���̕��e�u�v�S�����v��������z�b���n�߁A�X�ɉ�z�̒��ɏo�Ă����������{���֑}����������q�\���ƂȂ�A���͂�V���[�Y�ǎ҂̂قƂ�ǂ͉����{�Ȃ̂��悭�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�@�����̍\�z�ł́u�q�}�����̉��n�Ɂw���n�x�������āA�L�}�C�����̏h�����瓦����Ȃ���Ɨ��͑����𗣂�Ă����ɒH�蒅���v�݂����ȓW�J���v���`���Ă����炵�����A�₪�āu����ȓs���̗ǂ����n�Ȃ�đ��݂��Ȃ��v�Ǝv���悤�ɂȂ��č\�z�͗��������ɂȂ����B�����܂ő����̒��Ő������~�������Ȃ��A�ƁB���܂�ɒ����ɋy�����ō쒆�̎�����c��ł��Ă���A�ŋ߂̊��i�Ƃ����Ă�10�N�ȏ�O�����j���Ɓu�g�ѓd�b���g�������v�Ȃ�ĕ��͂��o�Ă���B�g�L�}�C���E��h�̐��E�Ɍg�ѓd�b�I�H�@�Ă�����쒆�̎��Ԃ�80�N��̂܂~�܂��Ă���ƐM������ł����̂ŏՌ����Ă��܂����B���̓T�u�L�����́u�F�����T�P�v�Ɓu�����@�O�v���D���Ȃ̂Őh�����ĕt���čs���Ă͂��邯�ǁA����𗝉��ł��Ă��鎩�M�͂Ȃ��ł��B���Ƀ`���N���]�X�̐ݒ�͗�̂������L�����蒅�����A���x���ǂݕԂ��n���Ɋׂ��Ă���B���̍ۂ����烁�������˂ď����U��Ԃ��Ă݂悤�B�ꉞ�l�^�o���Ȃ̂Ŗ��ǂ̕��͒��ӂ��Ă��������B
�@��i���[�K�j�̎v�z�ɂ����āA�l�̂ɂ͎ԗցi�`���N���j�ƌĂ��튯�����݂��Ă���B��U�w�I�ɂ͑��݂��Ȃ��B�ʏ�A�`���N����7����Ƃ���Ă���B�����̃`���N���u�T�n�X���[���v�͐哹�ɂ�����u�D�ہv�B���Ԃ̃`���N���u�A�W�i�[�v�͐哹�ɂ�����u�v�B�A�̃`���N���u���B�V���b�_�v�͐哹�ɂ�����u�ʒ��v�B�S���̃`���N���u�A�i�n�^�v�͐哹�ɂ�����u���v�A�`�̃`���N���u�}�j�v�[���v�͐哹�ɂ�����u��ҁv�B�B���̃`���N���u�X���f�B�X�^�[�i�v�͐哹�ɂ�����u�O�c�v�B���i��A�j�̃`���N���u���[���_�[���v�́u��胁v�B��ʓI�ɂ���ȊO�̃`���N���͑��݂��Ȃ����ƂɂȂ��Ă��邪�A�g�L�}�C���E��h�̐��E�ł͍X�Ɂu3�̃`���N���v�����݂��Ă���A����炪�u�L�}�C�����v�Ƃ������ۂɊւ���Ă���B8�ڂ̃`���N�����u�S���v�́u�A�O�j�`���N���v�A���[���_�[���������ɂ����āA���̃`���N�����Ɓu�l���i���̉ߒ��̒��Ŏ̂ĂĂ����A������`���v���u�������v���u�����I�v�ɐ����Ă��܂����߁A�����݂����Ȍ`��ɂȂ�B���̋S���̓����𐧌䂷�邽�߂ɑ��݂���̂�9�ڂ́u�\�[�}�`���N���v�A�ʏ́u���̃`���N���v�B�u�V�̃`���N���v�Ə�����邱�Ƃ�����B��������Ȍ`�ɂ��ē��̏�ɗ��Ă邱�ƂŁu�T�n�X���[��������Ɉʒu����`���N���v�Ƃ��ċ@�\���A����Łu�S���̖\�����L�}�C�����v�����������ނ��Ƃ��ł���B�����čŌ�A�u�S����������ɉ����v�ɂ���Ƃ���10�Ԗڂ̃`���N�����u�A�C���b�p���`���N���v�B�A�C���b�p���`���N���̍����̓\�[�}�`���N���̋t�ŁA�L���̂悤�Ȏp���������̗������킹�邱�ƂŁu�S���������v�̃`���N���𐬗�������B���̃A�C���b�p���`���N�����g���ċS���i�A�O�j�`���N���j�E���������邱�Ƃŗ͂��g�̂��ēV�ɏ����Ă����u�}�n�[�|���v�Ƃ������ۂ��N����B���i�\�[�}�`���N���j�ł��̃|���𐧌䂵�A���������ɂȂ�͂�g�̂̓��ɗ��߂邱�ƂŔ]�̕�������āu�V�̊ØI�i�A�����^�j�v��������B�܂�A�u�V�̊ØI�i�A�����^�j������Ȕ]�������H�v�邱�Ƃ��L�}�C�����̌��Ȃ̂ł���B
�@�w�L�}�C�������ρx������܂ł͒P�������ɖʔ������A�����̃��`��������z���n�܂�w�L�}�C�����V�ρx�����肩�班������ǂ��Ȃ��Ă��܂��B���A���^�C�����Ə����ς��猺�ەς܂�8�N�ȏ�|�������̂ŁA������ւ�ŒE������ǎ҂����Ȃ��Ȃ������B���̖{�͊p�앶�ɔł���r�I���肵�₷�����ȁB�d�q�ł����ƈ������A�����Ƃ����炩�������������葁����������܂���B�V���łƕ��ɔł͏o�ŎЂ��Ⴄ�̂œd�q�ł��ʁX�ɔ̔�����Ă���A��{�I�ɕ��ɔł̕�����������ǐV���ł�6���i���ɔł�12���j�܂�Kindle Unlimited�œǂ߂܂��B���Ȃ݂Ɂg�L�}�C���E��h�V���[�Y�́g�Ŏ��t�h�V���[�Y�Ƃ������N���Ă����ŋɂ߂����l�͂��������������Ă������B�m��Kindle Unlimited�őS���ǂ߂��͂��B���Ɂw���āi�����j�̉��x��ǂ܂Ȃ��Ɨ����@�O�������������̂��悭�킩��Ȃ��Ȃ�܂��B���ƁA�L�}�C���Ƃ͊W�Ȃ������w�V�E��T�`�x��7���ɖ�5�N�Ԃ�̐V�����o�܂��B�u���悢��ŏI�͂ɓ˓��I�v�Ƃ̂��ƂŁA��������I��肪�����Ă����悤�����ǁc�c�B
�E�V���[�x���u�L�}�C�����Ɂv�n���A���}�̂Ȃ��̓d�q�������[�x��
�@�L�}�C���q����Ƃ����킯�ł��Ȃ����c�c���N�i2025�N�j��1��������e�B�U�[�T�C�g�𗧂��グ�A�����i4���j���烍�[���`�J�n�A�Ƃ��������炵���B�w�ِ��E�������u�̂ԁv�x�́u���čƁv�܂�4�l�̍�Ƃ��W�܂��č�������[�x���ŁA�u���ׂĂ̍�i�����f�B�A�~�b�N�X�O��œW�J����v�Ƃ����̂��R���Z�v�g�̖͗l�B�A�j�����͂������ɓ���݂��������A�R�~�J���C�Y�ƃQ�[�����Ɋւ��Ă�100�p�[�Z���g��ڎw���Ă���炵���B����5�̍�i�����J���ŁA���͑��݂����m�����邽�߂��A��̓I�Ȕ̔����͂Ȃ��f�ڕ����ׂĂ������œǂ߂�B�����A�����_�ŗB��R�~�b�N������Ă���w�G�g�����W�� �I�[���@�[���[�h�x�́u�����ƂɂȂ낤�v��u�J�N�����v�ł��ǂ߂�̂ŁA�u�L�}�C�����ɂȂ�ł́v�̓��F�̍��̂Ƃ��날�܂�Ȃ��B�u�����������[�x�����o�����v�Ƃ������Ƃ������ɓ���Ă��炭�͗l�q�����銴�����ȁB
�@���������d�q���[�x�����āu�����I�ȑ��݊��v���Ȃ��Ԃ�A���Ԃ�c�����Â炢�̂���_�B�u�_���K�����Ɂv�Ƃ����V���[�x�����A�n�������̂͋��N�i2024�N�j�Ȃ̂ɑ��݂�m�����̂͂�����������B���uBOOK WALKER�v�ŃZ�[�����݂��������ǁA�����Ƃ��Ă�����������Ɗ��������܂��Ă��炩�ȁc�c�ƃ`�F�b�N�����ɗ��߂Ă��܂��B�w�����K���N�^�X�N���b�v�}�[�`�x�Ƃ������������ɂ����X�`�[���p���N������������ƋC�ɂȂ��Ă���B
�E�̖쏻�߂��w�قƂ������̊y���Łx�ǂB
�@������20�N�ȏ�O�ɔ��s���ꂽ�A�u�ō��ł��傤��400�~�v������́u400�~���Ɂv�ɑ��������B����ł�5�p�[�Z���g�̎��ゾ��������A�{�̉��i��381�~�c�c���ł͂��������s�\�Ȋ�悾�낤�B�����ƈ����̂��ƃ_�C�\�[�Ŕ����Ă����u100�~���Ɂv�Ƃ����̂�������A��舵���X�܂����Ȃ������̂������������������ƂȂ���ȁB���Ă����A�w�قƂ������̊y���Łx�B�^�C�g���ʂ�u�ك��m�v�ɓ�����m���E�V���[�Y�̃~�X�e����i�ł��B���݂͐�ł��Ă���A�w�����Ė��T��͐��܂ꂽ�x�Ƃ������ҏW�Ɏ��^����Ă���\�\���āA����w�����ҁA�ꖼ�x�̊��z�̂Ƃ��ɂ��������ȁB�����Ńf�W������Ǝv�����B
�@�悤�����A�䂪��A�O���قց\�\�T�㏬���D�����V���Ď��O�́u�فv�܂Ō��ĂĂ��܂����j�A�u�~�ؓ���Y�v�B�ނ͑�w����ɓ����T�㏬��������őʕق��Ă���4�l�̗F�l��������B�o�}���ɂ���Ă��郊���W���A�q�l�����ĂȂ������ƃ��C�h�A�����Ė{���̊فB�u�~�͑�������Ƃ����킯�ł��Ȃ����낤�ɁA���������ǂ�����Ă��ꂾ���̎�����P�o�����H�v�@����X�����s��m���Ă��m�炸���A�~�͕s�G�ȏ݂��ׂāu�E�l�Q�[���v�̊J�Â�錾����c�c�B
�@���Ƃ��Ƃ̓C�M���X�Ɍ��Ă�ꂽ�A�x���c�̃}�[�N�݂����Ȍ`�������O�c���̊فu�X���[�X�^�[�E�n�E�X�v�A�������{�Ɉڒz�������̂��u�O���فv�ł���c�c�Ƃ����ݒ���x�[�X�ɁA�u�b�h��Z�����S�삪舕�����v�݂����ȉ��k��s�����Ă����~����B�Q���҂����݂͂��50�߂��Ȃ̂Łu�Ⴂ���Ȃ�Ƃ������A���������ă~�X�e���[�E�c�A�[�̐^�����Ȃ�āv�ƕ���Ȃ�����t�C���鎎�݂Ɏd���Ȃ��t�������Ă����܂��B�v�͊w�����m�ł悭����u�������V�сv�i���̏ꂩ����̐ݒ������ĉ��炩�̖���������A������Ƃ����G�`���[�h�݂����ȃm���j���g�債���悤�ȃX�g�[���[�ŁA�^�ʖڂɓǂނƃo�J�o�J�������Ĉ�ۂ������Ȃ���ǁA�u�ł��~�X�e���̍���ɂ���͎̂q���������ɂȂ��Ă�荞�ށw�������V�сx�I�Ȓt�C����ȁv�ƍl�������a�������X�ɔ��炢�ł����B���͋C�Ƃ��Ă͋��c�ꏭ�N�▼�T��R�i���ł͂Ȃ��wQ.E.D.�ؖ��I���x�̂��ꂾ�B
�@���^�I�Ȏ��_�Œ��߂�ƁA�u���������g���b�N���v���������ǁA���s����̂͂��܂�ɂ����������Ȃ��ȁc�c�w�������V�сx�I�Ȑ������Ƃ����`���ɂ���ΐh�����ăC�P�邩�H�v�Ƃ������G�̂����҂ŁA�����ȓ�����Ƃ��ēǂނƁu����������v���Ă̂��U�炴�銴�z�ł��B�Ȃ̂Ŗ{�҂����܂�ܑ̂Ԃ炸�ɃT�N�T�N�i��ł����B��������������Ƃ͂����T�v���C�Y���d���܂�Ă���̂ŁA�u�ك��m�v���D���Ȑl�Ȃ�������Ȃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����B�̖쏻�߂��w�t���̋G�߂ɌN��z���Ƃ������Ɓx���u���C�N�������ƂŁu���������H���̍�Ɓv�Ƃ����C���[�W�������Ȃ��Ă��܂������A�����́g�Ɓh�O����݂����ɃN���V�J���ȁu�ك��m�v��������^�C�v�̏����Ƃł�����B���̍�i�͓��Ɏ��̑�\��Ƃ��u�K�ǂ̈���I�v�݂����Ȉʒu�Â��̖{�ł͂Ȃ����A�Z�����Ɂu�炵���v������������e�ŁA���ԂɃX�b�ƓǂނԂ�ɂ̓I�X�X���ł��B
�@�����A����o������͂���Ă��Ȃ��̂Łw�����Ė��T��͐��܂ꂽ�x���ۂ��ƈ������Ȃ��Ɠǂ߂Ȃ��̂���_�Ȃ�ł���ˁc�c�d�q���Ђ��ăG�s�\�[�h�P�ʂ̃o��������s������A�P�s�{�����^�̍�i�����肷�邱�Ƃ��ł���_�͉���I�Ȃ�ł����A���ۖ��Ƃ��Ă��̂ւ�ɍׂ����Ή����Ă����i�����Ȃ��āu���̒Z�҂������������̂Ɂc�c�v�Ǝ��y���v�������邱�Ƃ������ł��B���������̂̍�i�͓d�q�����ĂȂ����̂���ʂɂ����āA�v�X�ɓǂݕԂ������Ȃ��Ă��u�d�q�ł��Ȃ��I�v�Ɣߖ��������Ⴄ���Ƃ������B�Ï�����Ƃ��A�d�q�����Ă��钘�삪10�����Ȃ��ăr�b�N�����܂����B3�炢���؏܌��ɂ��I�ꂽ��ƂȂ̂ɁA�܂�������ȏ������Ƃ́c�c�{�l���d�q���ɑ��Ă��܂�ϋɓI�ł͂Ȃ��̂�����H
�E���背�X�B
�@�邪����������C�N���܂������A�A�g���N�i�N�A���ǂ����ȁc�v���Ƃ���ł���
�@�邪����I�̃����C�N�����V���Ƃ̃R���{���L�b�J�P�������炵�����A�Ȃ����Ȃ��b�ł��ˁB���ʓI�ɂ̓A�j�����������Ă�Ǝv�����ǁA18�֗v�f���������Ă�����Ɓc�c�Ƃ����B
�@�u5���O�[�i�v���B����Ȃ��Ƃ�������ł��˂��B�l�ɗ��j����Ƃ����܂����ǁA���݂͂�Ȓm���Ă�L���ēV�[������̂͑�ς�������ł���
�@�V�[�ḗu5���O�[�i�v������`���́u�[�i���ہv���炢�ł��傤�ˁc�c�m���Ă���Ƃ���ł͉���ē����ē������Ă��܂��B����ē̃P�[�X�ł͍�蒼���ɂȂ������ǁA����ē̃P�[�X�ł́u�����ɊԂɍ���Ȃ��v�Ƃ������R�Ō��ǂ��̂܂ܗ����������ȁB
2025-04-13.�E�t�A�j���A�wLAZARUS ���U���x���u�}�W�ł���TV�A�j������c�c�v���ďo�����Ӗڂ��Ă���ĒÂł��A�����́B
�@�ẪA�j�I�^�͌����y�[�W�̃g�b�v�����āu�Ȃr�o�b�v���ۂ��ȁv�Ǝv������������܂��A��������̂͂��w�J�E�{�[�C�r�o�b�v�x�́u�n�ӐM��Y�v���ē��Ă���V��ł��B�u���ēv�߂��w�L���������`���[�Y�f�C�x�����6�N�Ԃ�A�u�ēv�Ƃ��Ắw�c���̃e�����x�ȗ��Ȃ̂�10�N�Ԃ肭�炢�ɂȂ�܂��B����́uMAPPA�v�B�C���^�r���[�Ō���Ă��܂������A�A�����J�̃J�[�g�D�[���l�b�g���[�N���u�S�z�o�����邩��v�ƈ˗����Ă�����i�Ƃ̂��ƁB�uSF�A�N�V�����v�Ƃ����W�������̎w�肾�����āA��͎��R�ɂ���Ă����Ƃ����A�n�ӐM��Y���x���ł��Ȃ���Ε������܂Ȃ��悤�Ȉ˗����B�u���Ⴀ�w�X�y�[�X���_���f�B�x�݂����Ȃ̂ł����H�v�Ɛu�˂���u�m�[�I�@�����ƃV���A�X�Ȃ́I�v�ƌ���ꂿ����������ł����B
�@����2052�N�B�ˑ����F���Ō����ڔ��Q�Ƃ������̂悤�Ȓ��ɍ܁u�n�v�i�v���J������A�����Ƃ����Ԃɐ��E���֍L�����Ă������B�������A����́u�X�L�i�[���m�v�̎d�|����㩂������B�n�v�i���J�������X�L�i�[���m�͂Ђ��������j���̐������E���u�l�ށv���n����I�ފQ�b�Ƃ����v�����A�n�v�i�̒��Ɂu���p�J�n����3�N��Ɏ��ʁv���J�j�Y�����d����ł����Ɛ錾����B���R�A���E�̓p�j�b�N�Ɋׂ����B���̍��A888�N���̌Y���ƂƂ��Ɋč��֕����߂��Ă������l�u�A�N�Z���v���x���̌������ĒE���B�V���o�̋�C�����\���Ă����Ƃ���A��̏��ɋC�₳�����A�u���U���v�Ȃ��̃`�[���Ɋ��U�����c�c�B
�@�n�v�i������̃��V�s�������Ă���̂̓X�L�i�[���m�̂݁B���Ɣ��N�ȓ��ɔ��m�������o���ă��V�s��f�����Ȃ���A��ʂ̎��҂��o��B�^�C�����~�b�g�I�ȏ��ݒ肳��Ă��邪�A���̂ւ�͕��䑕�u�݂����Ȃ��̂Łu����ȃL�b�J��3�N��Ɏ��ʎd�g�݂Ȃ�Ė�������v�Ƃ����Ȃ��Ƃ��l���Ă��d���Ȃ��̂��낤�B�����͎�l���E�A�N�Z�����J��L����p���N�[���B�p���N�[���Ƃ����̂̓t�����X���˂̃X�g���[�g�E�X�|�[�c�ŁA�X�̂���Ƃ�����Ƃ�����u�ʘH�v�ƌ��A�I�u�W�F�N�g����Q���Ƃ��Ĉ����Ĕ�蒵�˂��葖����B�w�A���e�B���b�g�x�Ƃ����f��̖`�����ς���u�����A����Ȋ������v�Ƃ����ɂ킩��܂��B�w�o�u���x�Ƃ����A�j���f����p���N�[���v�f�����C���ł����B���Ȃ�p���N�[�����o�Ă���G���Q�[���炠��܂��B�w�邢�͒q���Ăԁx�Ƃ����\�t�g�ŁA�p���N�[���V�[���͑̌��ł͈͓̔��Ɏ��^����Ă��܂����狻���̂�����̓v���[���Ă݂Ă��������B
�@�Ƃɂ����A�u�[��A�j���ŃR���Ƃ����[�˂��ȁv�Ɩڂ��^���N�I���e�B�ł��B�n�ӐM��Y�ē�i�Ō����ƃr�o�b�v�̌���Łw�V���̔��x�̕��͋C�ɋ߂����ȁB�^�C�g���́u���U���v�͍쒆�ɏo�Ă���`�[�����ŁA�A�N�Z���܂�5�l�̃G�[�W�F���g�����ݕs���̃X�L�i�[���m��{������B���U�����w������A007�ł����Ƃ���́uM�v�ɑ�������u�n�[�V���v�Ƃ�����N���������������o�ꂷ��̂ł����A�S�����D�́u�ь��߂��݁v�B�ь��߂��݂��Ă����V�K�̎d���͂��܂�Ȃ��悤�ɂ��Ă�����ĕ������ǁA����ς�n�ӐM��Y��i�͕ʊi�Ȃ̂��ȁB�L���X�g�͂��Ȃ荋�ł��ˁB���D�ɂ��܂�ڂ����Ȃ����ł��u�������v���ĂȂ�ʎq�B�u�����܂Ŏ�`���������v�Ƃ�������������K���ł��B
�@�Ō�ɁA�u���U���v�̌��l�^�ɂ��āB�����i���n�l�̕������j�ɏo�Ă��鐹�l�ŁA�ڂ������Ƃ�Wikipedia�Ƃ��ɏ����Ă���̂ŏȂ��܂����A���̐l�́u����ɕ��������v�Ƃ�����b�ŗL���ł��B�}�q�d���w���U���E���U���x�Ƃ������������́u�h���v�̈�b���x�[�X�ɂ��Ă����̂ň�ۂɎc���Ă���B�I���Ȃقǁu���ƍĐ��v���e�[�}�ɐ����Ă���ƌ������Ă���킯�ŁA����̓W�J����]�O�]���������B���Ȃ݂Ƀ��U�����]���r�Ɖ��߂��� "Fist of Jesus" �Ƃ����X�y�C���̒Z�҉f�悪����A������Youtube�ɑS�҃A�b�v���[�h���Ă���̂ʼnɂȐl�͎������Ă݂�̂��ꋻ�ł��B���Ɨ����ɂ��w�ʍ�ele-king�@�wLAZARUS ���U���x�Ɠn�ӐM��Y�̐��E�x�Ƃ������b�N���A�ė����ɂ��w�n�ӐM��Y�̐��E �w�J�E�{�[�C�r�o�b�v�x����wLAZARUS ���U���x�܂Łx�Ƃ����P�s�{�������\��Ȃ̂œn�ӐM��Y�D���̐l�͗v�`�F�b�N���B
�E�ق��A�t�A�j�������w�A�|�J���v�X�z�e���x���ǂ������ł��B
�@����Ɓu�|�{��v���L�����N�^�[���Ă�S�����Ă���I���W�i���A�j���B�|�{��̓f�r���[����40�N�����x�e�����ł����A�s�v�c�ƃA�j����i�Ƃ̊ւ�肪���Ȃ��A�g�������悪���x���|�V�����Ă����ߋ��������܂��B���A���́w�A�|�J���v�X�z�e���x�͊�ՓI�ɕ����܂ő������܂����B�l�ނ��ŖS���A����������2157�N�̒n���B�����̋���Ɍ��z�e���u��͘O�v�͍����������Ƃė���͂����Ȃ����q�l��҂������Ă����B�]�ƈ��ł��郍�{�b�g�������ϗp�N���̌��E���}���Ď��X�Ɖ��Ă������A�u�����͒N��������v�Ƃ����\���ƂƂ��ɓ��������Ă���z�e���G���{�́u���`���v�B�ʂ����Ă��q�l�͖K���̂��H�@�Ƃ����|�X�g�A�|�J�v���XSF�ł��B����݂肵�����͋C�����Ǖ��ޏ�̓R���f�B�ɂȂ邩�ȁB�Ƃɂ������͋C���ǂ��āA�u����^���ÂȂ̂ɖ��邢�v�Ƃ����ςȃA�j���Ɏd�オ���Ă��܂��B���ł͏o���Ȃ���������̂ő������������y���݁B�|�{��ɂ��X�s���I�t�E�R�~�J���C�Y�w�A�|�J���v�X�z�e���Ղ��Ղ��x������̂ŕ����ēǂނ��g�B
�E�ʼn��ނ̏����u�t�ďH�~��s�� �t�̕��vTV�A�j�����A�����WIT STUDIO�i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@�u�ʼn��ށv���w���@�C�I���b�g�E�G���@�[�K�[�f���x�̌���҂ł��B�w�t�ďH�~��s�ҁx���V���[�Y���ŁA�w�t�̕��x��1��ڂɓ�����G�s�\�[�h�B�܂�V���[�Y��1��ڂ�����1�N�[���|���Ă�������A�j�������Ă����݂����ł��ˁB���\�������āA�w�t�̕��i��E���j�x�����ł�900�y�[�W���炢���邩��u���ʂ̃��C�g�m�x��3�����v���čl����Ɓu����A��������Ƃ����قǂł��Ȃ����c�c�H�v���ċC�����Ă��܂����B�V���[�Y�͂��̌�w�Ă̕��i��E���j�x�w�ł̎ˎ�x�w�H�̕��i��E���j�x�w�����̎ˎ�x�Ƒ����A����8���ł��B�w�~�̕��x�Ŋ�������̂�����B�����Ă邯�ǂ�����Ɠǂ����Őς�ł�̂ł悭�m��܂��ʁB�W�������Ƃ��Ă͘a���`����ۂ���ł���ˁB�u�t�v��u�āv�Ƃ������G�߂��ӎu�������݁A�v����ɐ_�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Đݒ肳��Ă���A�_�Ƃ��Ă̖����ŖZ�����ăv���C�x�[�g���Ȃ��e�G�߂���d�����ς˂�ꂽ�̂��u�l�G�̑�s�ҁv�ł��B�u�G�ߐ_�̈Ђ���ҁv�ł���A�����������Ύl�G�̉��g�A���X���炷��Ό��l�_���R�ł���B���傷���邹���ŗ��p���悤�Ƃ���A�������₽���A�t�̑�s�҂������u�ԗt���e�v�͗U�������10�N�������s���ɂȂ��Ă��܂����B���̐��e���A�҂��A�����Ă����u�t�v�����߂����Ƃ���\�\�Ƃ����Ƃ��납�畨�ꂪ�n�܂�܂��B�s��ȃX�P�[���̍�i�ł���A�Œ�ł�4�N�[���͂Ȃ��Ɗ����o���Ȃ��킯�ł����A�A�j���͉ʂ����Ăǂ��܂ł���̂��B����́uWIT STUDIO�v�A�w�i���̋��l�x��wSPY�~FAMILY�x�Ȃǂ���|�����Ƃ���ł��B�ŋ߂��Ɓw�^�E���` YAIBA�x������Ă��܂��ˁB�w�^�E���` YAIBA�x���ǂ��������A�ЂƂ܂����҂��Ă������B
�E�u�U�k�@�����v�V��TV�A�j���́uTHE GHOST IN THE SHELL�v�r�W���A����������J�i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@�L�[�r�W���A�����炵�āu������v�Ǝv����w�U�k�@�����x�����ɗ���̂��B�w�U�k�@�����x�́u�m�Y���@�v�̖��������Ƃ��Ă���A�e����T�C�o�[�ƍߎ����܂��ړI�Ƃ������ꕔ���u����9�ہv�A�ʏ́u�U�k�@�����v�̖ʁX���l�X�Ȋ댯�l�������ɗ����������Ă����l�q��`����SF�A�N�V�����ł��B���얟���1989�N�ɘA�ڂ��J�n���ė��N�ɏI���A1991�N�ɑS1���̒P�s�{���o���Ă���B��������ɂ����ŏ��̃A�j���������̌����i�wGHOST IN THE SHELL�^�U�k�@�����x�i1995�N�j�ŁA�L������ݒ�͌���Ɋ�Â��Ă��邪�����̃J���[��O�ʂɉ����o�����앗�ƂȂ��Ă���A���͋C�������ԈقȂ�܂��B����͌��\�G���O���v�f�������āA��l���́u����f�q�v�����ڂ��C�̂��鏗���Ƃ��ĕ`����Ă���A�ӊO�ƃR�~�J���Ȗ���ł���B����������ł��S���E�K�͂Ńq�b�g�������߁A�㑱�̃A�j����i���m�Y���@�ł����wGHOST IN THE SHELL�^�U�k�@�����x���ӎ������V���A�X���̍앗�ƂȂ��Ă������B�Ȃ̂Łu�m�Y���@���ۂ������������w�U�k�@�����x�A�j���v�͖����ɑ��݂����i�����ɏ�����1997�N�ɔ������ꂽPlayStation�p�Q�[���\�t�g�w�U�k�@���� GHOST IN THE SHELL�x��������ŁA�쒆�ŗ����A�j�����[�r�[���u�S�U�k�A�j���������Ƃ��m�Y���@���ۂ��v�ƌ����Ă���j�A����t�@�������N���]���Ă����H���Ȃ�ł��B������N���炢�O�ɓ���͏o�Ă�����ł����ǁA�T�b�p���L���Ɏc���Ă��Ȃ������B
�@���͉���ł��L�b�J�P�ōU�k�ɓ������N�`�����A���쎊���`�����������͂Ȃ����A����͂���Ƃ��Ďm�Y���@�F�S�J�̍U�k�A�j�����ς����ȁc�c�Ƃ����C�����͂����Ƃ������̂ō���̃j���[�X�͘N��ł��B�����̃A�j���V���[�Y�̑����őf�q�̐��������Ă����u�c���֎q�v�͊��Ɍ̐l�ł�����L���X�g���ς�邱�Ƃ́u�߂ނȂ��v�Ǝ���Ă��܂��BARISE�őf�q����Ă��u��{�^���v�������_�ł̗L�͌�₩�B���m���̕��ނ����A�wGHOST IN THE SHELL�^�U�k�@�����x�̃��X�g�őf�q�̈ӎ������ڂ��������^�`�̂�CV���G�X�J�t���[�l�ŗL���ɂȂ�O�̍�{�^���ł���B����́w�_���_�_���x�Œ��ڂ𗁂тĂ���u�T�C�G���XSARU�v�B�ḗu���R�����v�A�A�j���[�^�[�o�g�Łw�_���_�_���x�̕��ē�����Ă邪�A���ꂪ���ēA�j���ƂȂ�B�V���[�Y�\���E�r�{�́u�~�铃�v�A�n���J���i���쏑�[�j�o�g�̊H��܍�Ƃ��B�H��܍�Ƃ��A�j���̋r�{�������ĂȂ��Ȃ��X�S�����Ƃ����ǁA�~�邳��͉ߋ��ɃS�W��������Ă邵�A���Ȃ�w�X�y�[�X���_���f�B�x�̋r�{�������Ă邩�炻��ɔ�ׂ�����x�͒Ⴂ�B�n���J���o�g���Ĕ�r�I�����A�j���ɋ߂���ۂł����B�Â��Ƃ��낾�Ɓw�G�C�g�}���x��w�������x�́u����a���v���n���J���o�g�̍�Ƃ��B�u�n���J���̌��e���͐��C����Ȃ��قLj����ĐH���Ă����Ȃ������v�Ƃ������R��SF������f�O�����Ƃ����߂����w�i�����邪�c�c�b��߂��ĉ~�铃�AAI�������J���Ď���u�u�b�_�v�Ɩ����n�߂��w�R�[�h�E�u�b�_ �@�B�����j���N�x�Ƃ����ASF�Ƃ������u�s��ȃz���b�v�̍˔\������^�C�v�̍�ƂȂ�ł��Ȃ�l��I�Ԃ��A�u�悭�킩��Ȃ����Ȃǂ�łĖʔ����v�ƂȂ邩������Ȃ��̂ŋ@������1���`�������W���Ă݂Ă��������܂��B
�E�u�W���W���v��7���u�X�e�B�[���E�{�[���E�����v�A�j�����A�a�J�ŃA�j�����L�O�����i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@JOJO7���w�X�e�B�[���E�{�[���E�����x�A����ƃA�j�������肩�B�u�n�ɏ���đ嗤���f���[�X���J��L����v�Ƃ����ݒ�䂦�u�n�̍�悪����ǂ����ăA�j�����͍���v�ƌ����Ă��܂������A���̂ւ�̖�肪�N���A�ł����݂����ł��ˁB�n����CG�ɂ��č�������̂��ȁH�@CG�ł��������̂͂��Ȃ��ςȋC�����邯�ǁA�ŋ߂�AI�����Z�p���i�����Ă���Ƃ������A����������悤�͂���̂��낤�B
�@�w�X�e�B�[���E�{�[���E�����x�͍r�ؔ�C�F�̖���w�W���W���̊�Ȗ`���x�̑�7���ɓ������i�ł��B�w�W���W���̊�Ȗ`���x�́u�W���[�X�^�[�Ɓv�̌����ƍ�������ƍ����z���Ďp����Ă����c�c�Ƃ������}����`������̓R�~�b�N�ŁA��1�������6���܂ł͍쒆�̎��Ԃ����X�ɐi�s���Ă����i1888�N��1938�N��1988�N��1999�N��2001�N��2011�N�j�`���ł������ASBR��1890�N�Ƒ�1���ɋ߂�����܂Ŗ߂��Ă���B����͒P���Ɏ���k�����ߋ��҂Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A��l�^�o���ɂȂ�܂�����6���̃��X�{�X�������������\�́i�X�^���h�j�ɂ���ĉF�����č\�z����A��܂��ȗ��j�͈ȑO�ƈꏏ�����Ǎׂ������������낢��ƈقȂ��Ă���p�������Ȑ��E�ɕϖe���Ă��܂��B�u����l���ł͂Ȃ����悭�����L�����N�^�[�v�����݂��Ă���A���[��JOJO�̒m���������Ԃ��Ƌp���č�����˂Ȃ��BJOJO�́u6���ȑO�v�Ɓu6������v�ŕʐ��E�ɂȂ��Ă���i�ł��悭�����L�����N�^�[�͏o�Ă���j�Ƃ������Ƃ�O���ɂ����Ċy���݂܂��傤�B
�@���͂������m�̎���������uJOJO7���v�Ɩ������Ă��܂����A�A�ڊJ�n������JOJO�V���[�Y�Ƃ̌q�����B���ɂ��Ă��āA�u�X�^���h�v�Ƃ���JOJO���L�̗v�f���o�Ă���܂ł̎��Ԃ����߂ƂȂ��Ă��܂����B�Ȃ̂ŏ��Ղ�JOJO�m�����Ȃ��Ă����ɖ�肠��܂��A�X�^���h�o�g�����{�i�����邠���肩��u�����A������Ă��������b�Ȃ́H�v�ƐV�K�̕��͌˘f����������܂���BJOJO�͑�5�������肩��X�^���h�o�g�������G�����Ă����Ă�����������e�ƂȂ��Ă������߁A�X�e�B�[���E�{�[���E�������A�j�����ςĂ��邾���ł͏��X���ݍ��݂Â炢���낤�B�������A����ł����I�ȃL�����N�^�[�����Ƃ̑��l�܂�o�g���͎������邾���̉��l������͂����B�����D���Ȃ̂͂���ς�}���_����B�u�����v���̂��̂Ɖ������G�Ƃ̎�����`���Ă���A�Ԃ����Ⴏ���X�{�X�������ۂɎc���Ă���B
�E�I�U�R���wDV8�@��k�v���C�x�[�g�A�C2�x�Ǘ��B
�@����͐l�ނ�ł��邪�A�l�Ԃ�K�v�Ƃ��Ă���B
�@��p�̏����Ɓu�I�U�R�i���E������j�v�ɂ��n�[�h�{�C���h�����w��k�v���C�x�[�g�A�C�x�̑��ҁB�O��ł͑�k�s�ɏZ��ł�����l�����V�k�s�Ɉ����z���Ă���̂Ō����Ɍ����u�V�k�v���C�x�[�g�A�C�v�Ȃ̂����A�V�k�s���n�於�Ƃ��Ắu��k�v�ɊY������i���ہA�V�k�s�̋��̂́u��k���v�ł���j����ʂɖ��͂Ȃ��炵���B�^�C�g���́uDV8�v�͍쒆�ɏo�Ă���X�̖��O�ŁA�udeviate�i�f�B���B�G�C�g�A��E����j�v�̂�����B��w�����Ƃ������肵���d�������߂Ď����T��ɂȂ����A�Ƃ����ِF�̌o���������A�C���e���Ńi�C�[�u�Ń������R���b�N�ȋC��������l�����܂����Ă������Ɋ������܂�Ă����B���ς�炸�㉺��i�g�Ńr�b�V���������l�܂��Ă���A�ǂ݉����͏[���Ȉ�����B
�@�V�k�s�̒W���i�^���X�C�j�\�\�R����͂���Łu��p�̃x�j�X�v�Ƃ��Ă��`�����A�u����v���Ɓu�����i�E�[�E�`�F���j�v�̐V���ȏZ���ƂȂ����B���l�X��u�G�}�v���o�c����o�[�uDV8�v�ɓ���Z��A���̋q�����Ƃ��ʎ����ł��Ď����T��Ƃ��Ă̎d�������������������A����s�Ȃ�������肵�����X�������B������A�u���Ԉ��i�z�[�E�����A���j�v�Ɩ���鏗������u�c�����ɉ�������O���킩��Ȃ��j�̎q�i���݂͐��l���Ă���j��T���o���Ăق����v�Ɖ_��͂ނ悤�Ȉ˗�������A���Γr���ɕ��Ȃ�����������B��|����͂���B���̒j�̎q�̉Ƃɋ������������N�����A�j�̎q�̕�e���E���Ă������̂��Ƃ����B20�N�߂��O�ɔ��������A1992�N�̎����B���ׂ�͖̂ʓ|�����s�\���Ăقǂł��Ȃ��B�l�b�g�Ō������Ă��T�v����q�b�g�����A�d���Ȃ����n�Ɍ�����������́A���͎҂̎����Ȃ���u�j�̎q�v�̖��O���u�Γc�C�i�V�[�E�e�B�G���V�E�j�v�ł��邱�Ƃ�˂��~�߂�B���Ƃ͖{�l��{�������Ȃ̂����A�Ώ��N�̕�e�u���G�p�i�`�����E�V�E�C���j�v�i��p�͕v�w�ʐ��ŁA�q���͕��e�̐��𖼏�邱�Ƃ������j���E���ꂽ�����͂����̋����E�l�ł͂Ȃ��A�A���E�l�̈�ł��邱�Ƃ��������c�c�B
�@�������ߋ��̎E�l�����ɂ��Ē����������ADV8�ł��ʂ̃g���u�����������Ă���A���C���G�s�\�[�h�̗��ŃT�u�G�s�\�[�h���i�s����\���ƂȂ��Ă��܂��B�˗����ꂽ�u�l�T���v�͊��ƃg���g�����q�Ői��Ŋ̐S�́u�Γc�C�v�Ƃ��R���^�N�g���邱�Ƃ��ł���̂ł����A�̐S�̐Γc�C�́u�����i�Ԉ��̈��́j�̂��Ƃ͊o���Ă���A�ł����X������Ƃ͎v��Ȃ��v�Ɗ獇�킹�����ۂ��Ă��܂��B�T���o�������_�Łu���Ɉ˗��͒B�������v�ƌ��Ă��ǂ������Ȃ��̂����A�����ŕ���o���̂������������Ȃ��A�ƌ����͂��߉���Ă��ėԈ��Ɛ���킹�悤�Ƃ���B���ԓx�������A�u�ĉ�v�͖�����������̂ł����A���̍ۂ�1992�N�̎����̘b��ɂȂ��ėԈ����C�ɂȂ锭�������܂��B�u�\�����͉����������ƂɂȂ��Ă��鎖�������ǁA�܂��\���ꂴ�鉽��������̂ł́H�v�Ƌ^���������͒N�ɗ��܂��ł��Ȃ�����ɒ����s����B
�@��k�𑛂�����A���E�l�S�ƑΌ�����n���ɂȂ����O��Ɣ�ׂ���n���ȓ��e�ł��B1992�N9���ɋN�����E�l�����ŁA���݂�2012�N7���B��p�ł͎��Y�△�������ɑ�������d�厖���̑i�NJ��Ԃ�20�N�i2006�N��30�N�։������ꂽ���A�ߋ��̎����ɂ͑k�y���Ȃ��j������������������ɂȂ��Ă��܂��B�u�ق��ꂴ��E�l�ҁv�����݂���̂ł���A����2�������炸�̊Ԃɓ��肵�đi�ǂɂ܂Ŏ������܂˂Ȃ�Ȃ��B���̃^�C�����~�b�g�E�T�X�y���X�ɂȂ��Ă���킯�ł����A�u�l���̖�����Ȃ��v�Ƃ��u�����܂łɖ������ؖ����Ȃ��Ǝ��Y���m�肵�Ă��܂��v�Ƃ����V�`���G�[�V�����ɔ�ׂ�ْ����͔����ł��B���̎�̃^�C�����~�b�g���ň�ۂɎc���Ă���̂̓����L���E�f�C���B�X���w�f�b�h���~�b�g�x�ł��ˁB�ו��͂���o���ł����ǁA�C�M���X�̌Z���U������āA�U���Ƃ���u�E�l�����̐^�Ɛl��T���o���āA������Ă�l�ߍٔ��̔퍐�߂ɂ���v�Ɨv�������B�ٔ��͑�l�߂��}���Ă��āA���R���̕]�c�i�w�\��l�̓{���j�x�ł���Ă�A���j���n�܂낤�Ƃ��Ă���Ƃ��낾�����c�c�Ƃ����T�X�y���X�ł��B
�@�����͉ߋ������Ǖ���͌��݂Ȃ̂ŁA�wONE PIECE�x��u���R�G�v�v��u���c���i�v�Ƃ��������{�̃G���^���֘A�̃��[�h�����傱���傱�o�Ă���̂��ʔ����B�������D�ރ~�X�e�����u�w�j���O�E�}���P���v��u�}�C�N���E�R�i���[�v���Ɣ������A�������̂ւ�̍�Ƃ��D���Ȃ�Łu������ǂ�ł��ē���ނ��̂��������ȁc�c�v�Ɣ[�����܂����B���̂Ƃ���u�����̐^���v�͑����i�K�Ŕ������A���Ƃ͗e�^�҂�ǂ��l�߂邾���c�c�Ƃ����W�J�ɂȂ�̂ł����A���̎��_�ł����ԃy�[�W�����c���Ă����ł��B�u�����������ƁZ�y�[�W���������H�v�ƌ˘f���Ă����Ƃ���A�`���ŐG����Ă����u�Ƃ��鎖���v���ӂ����ї�������ė���B�Ӗ����肰�������̂ŃT�u�G�s�\�[�h�Ƃ��ĉ��炩�̖������ʂ����낤�ȁA�Ƃ͎v���܂������A�����܂ŃK�b�c���Ɩ{�ɗ���ł���Ƃ͎v��Ȃ������̂ŋ����܂����B�ꉞ�A���C���G�s�\�[�h�ƃT�u�G�s�\�[�h�̐ړ_�͗p�ӂ���Ă����ł����ǁA�n�b�L�������āu�ʁX�̎����v�Ȃ̂ő��݂Ƀ����N���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�~�X�e���I�Ȏd�|���Ƃ������u��ȉ^���v����������`�ɂȂ��Ă��܂��B�֑��ł͂Ȃ����ǐ����A���C���G�s�\�[�h�قǔM�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������ȁc�c�B
�@�܂Ƃ߁B�E�l�S�Ƃ̑Η���`�����O��Ɣ�ׂĔh�肳�Ɍ�������e�����A�t�Ɍ����u�O���藎�����������e�v�Ƃ�������̂ŁA�O���ǂ�Ŏ�l���u�����v���D���ɂȂ����l�Ȃ炶������Ɗy���߂�o���ł���B���X�g100�y�[�W���炢�̓W�J�͍D�݂��������Ƃ��납������Ȃ��B��҂��Ƃ����ɂ��ΎO��ڂ����M���炵���A�I�U�R�H���u�������_�[�N�T�C�h�ɗ��Ƃ��v�Ƃ̂��ƁB�C�ɂȂ邯�ǁA������|��͂����Ԑ�ɂȂ肻���Ȃ̂ŋC���ɑ҂����Ȃ��B�|�Ɓw��k�v���C�x�[�g�A�C�x��2021�N���s�ŁwDV8�x��2024�N���s������3�N���炢�����Ԃ��Ă܂��A�������Ƃ��ꂼ��2011�N��2021�N�̊��s�ŁA10�N�|�����Ă��ł���ˁc�c�����_�Ŋ������ĂȂ��̂ł���A�|��̎�Ԃ��l�����čŒ�5�N�͑҂��ƂɂȂ肻�����B
2025-04-08.�E�t�A�j���A�n�܂�܂����ˁB�������������w���b�N�͏i���i���f�B�j�̚n�݂ł��āx���w�E�}�� �V���f�����O���C�x���w�v�����Z�b�V�����E�I�[�P�X�g���x�ɒ��ڂ��Ă���ĒÂł��A�����́B
�@�w���b�N�͏i���i���f�B�j�̚n�݂ł��āx�A�����āu���b�N���f�B�v�́g�����O�A�j�}���h�A�ڂ̖�����A�j�����������́B����҂́u���c�G�v�A�u���V�u�M���[�`�����l�v�Ɛ�������̂���Ԓʂ肪�����݂������B�f�ڎ����ς���������������ăA�j�����n�܂�܂ŐV�A�ڂ���Ă��Ȃ�Ēm��Ȃ������A�Ƌ����l�����\�����͗l�B���ہA�����V���R�[�i�[��2���������āu�����A���V�u�M���[�̐l���I�H�v�ƋV�����N�`�ł���B�W�������Ƃ��Ă͌��ݗ��s���H�@�̃K�[���Y�o���h���ł��B�ƒ�̎���i�o���h����Ă����e���Ȏq���̂āA��e�͕s���Y���ƍč��j�����D���������M�^�[��������A�u�G�ɕ`�����悤�Ȃ���l�v�ɂȂ�o������߂��u��m�{��肳�v�B�������ޏ��͖��受�q�Z�u���S���w���v�ŁA�u�G�ɕ`�����悤�Ȃ���l�v�ł���Ȃ��猃�����h������@����̏����u���S���H�v�Əo��A�������b�N�Ɉ����߂���Ă��܂��c�c�B
�@�u����l�v��u���b�N�v���킩��₷���Y��I�ɕ`���Ă��镔��������A�c�b�R�~�ǂ���������̂ł����u�M�^�[�e�������I�v�u�h�����@�������I�v�Ƃ������̎q�������Ȃ̎咣���Ԃ������čō��ɃA�K��o���h��ڎw���A�܂������ȃX�g�[���[�ŏ��N���悶�݂��M�������\���邱�Ƃ��ł��܂��B���t�V�[���ȊO��2D�ł����A���t�V�[����3D�ɍ���D������Đ��삵�Ă���B�uBAND-MAID�v�ɂ�郂�[�V�����L���v�`���[���g�p�������t�V�[��������ŁA���C�u�V�[�����ǂꂾ���X�S�����ƂɂȂ邩������y���݂��B�������������炢�H�����|���Ă����K���N����A�T���W�Q���Ǝ��̋Z�p�ɗ��ł����ꂽ�}�C���W�Ɣ�ׂ�͍̂����낤���B�X�g�[���[�̑�g�Ƃ��Ắu���ԏW�߁v�A�o���h��g�ނ��߂ɑ��p�[�g�S���̃����o�[��T���W�J�ɓ���B���̂ւ�łЂƖ㒅��������A���C�u�n�E�X�őo�����邱�ƂɁc�c�Ƃ����̂���܂��ȗ���ł��B���b�N���f�B�́u�N�������J�����������遨��肳�≹�H���L���遨���y�̗͂ŃM���t���ƌ��킹�Ă��I�v���Ђ�����J��Ԃ��b�Ȃ̂ŁA���̂Ƃ��날�܂蕡�G�ȕ����͂���܂���B�o���h���C���������肳���u�m�[�u�����C�f���v�i���ƃ{�N�́u�G���_�[�V�X�^�[�v�݂����Ȃ́j��ڎw���A�Ƃ����v�f�����܂�i�W���Ȃ��B����̍ŐV����7���ŁA�X�g�[���[�̐菊���l����ƃA�j����5���̓r��������ŏI���Ǝv���B�����ł悤�₭��肳�����̃o���h�������܂�܂�����B
�@���H�͑�l�������Ă���Ƃ��͂�����Ɓw�q�P�O���C�x�́u�q�v���ۂ����A�{���o���Ă���Ƃ��͂��Ȃ�S�����Ȃ̂ł��q���ۂ��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B��肳���A���Ō��\�t�B�W�J���S�����Ȃ̂ł����������B���b�N���f�B�̓����͎�l�������̑g�ރo���h���u�C���X�g�o���h�v�ł��邱�ƁB�{�[�J�������Ȃ��A�y��̉��t�����ɓ��������o���h�ł��B�o���h�A�j���́u���t�Ɖ̏��v�̂ӂ������ɓW�J����̂����ʂȂ�ŁA�u�C���X�g���b�N�v���S�ł���Ă�����i�Ȃ�Ă��ꂪ���������炭����������悤�ȃA�j���͏o�Ă��Ȃ����낤�B���Ғʂ�̏o���ɂȂ肻���Ō���D���Ƃ��Ă͊������B����̕��ł����C�o���ƂȂ�ʂ̃C���X�g�o���h���o�Ă��Đ���オ���Ă��Ă��܂��B���͌���X�g�b�N�����܂�Ȃ��̂ŁA���ɑ�q�b�g����2�������肵���Ƃ��Ă������Ԑ�ɂȂ肻���Ȃ��Ƃł��ˁB����܂ł̊ԂɁw�L�����L���x�Ƃ��wMUSICUS!�x���A�j���������肵�Ȃ����Ȃ��c�c�B
�@�w�E�}�� �V���f�����O���C�x�́g�E�}���h�v���W�F�N�g�̈�ŁA���������Ƃ��Ă���BTV�V���[�Y�Ƃ��Ă�4��ځB���n�D������Ȃ��Ă����̖��O��m���Ă���u���т̉����v�I�O���L���b�v����l���ɐ��������ꂾ�B�n�����n���璆�����n�Ɉڂ��đ劈���I�O���̈��сi�D�F�A�O���C�j���V���O�����i�D���Ԃ�P�j�ƌ��ѕt�����S�����^�C�g�������A�u�������@��������v�Ƃ����c���ȈÎ����s��ł��܂��B�E�}���̃A�j���͂��Ƃ��ƃX�|���F���������ǁA�V���f�����O���C�͂Ђƍہu���荇���v���d���������e�Łu�A�c���v�̊ϓ_�ɂ����Ă͑S��i����A��𑈂���ɒB���Ă���B�u�E�}�����ă^�C�g���͒m���Ă邯�ǁA��x���ς����Ƃ��Ȃ���ȁ`�v�Ƃ����l�����S���Ăق����B����܂ŃE�}����TV�A�j����3���܂ł���Ă��āA���ɁwROAD TO THE TOP�x�i�����z�M����Ă���Web�A�j���A��������ɐV�K�J�b�g��lj����čĕҏW�����o�[�W����������j��w�V����̔��x�i����A�j���j�����邪�A��i���ƂɎ�v�����o�[�����V�����̂Łu����܂ł̃E�}���v��m��Ȃ��Ă��S�R���v�ł��B���n�m�������ă[���ł����C�Ƃ������A�ނ���j���x�[�X�ŃX�g�[���[�W�J����Ԃn�ɏڂ����Ȃ��l�̕����u���̐�ǂ��Ȃ邩�v�킩��Ȃ��ăn���n���ł���B
�@�A�j���͒��J�Ȃ���ŁA���̒��q���ێ��ł���Ȃ���Ȃ�����オ�ꂻ���B�����t�������ƂŃL�^�n���W���[���Y���Ɓu�k�����v�̃q���C���x���オ���Ă���̂͏����B����܂ł̃E�}���͒������n�����C���ŁA�n�����n�ɂ��Ă͂قڐG����Ă��Ȃ��������猴��ǂƂ��͌��\�V�N�������ȁB�I�O������������Z��4�������肩�炪�{�ԂȂ�ł����A�A�j���͂ǂ��܂ł��̂�����c�c�����Ƃ͂���2�N�[����邩�炻��Ȃ�̃G�s�\�[�h�������ł���͂��B����2���܂ł��J�T�}�c�҂ŁA1�N�[���ڂōŒ�������܂ł͂�邾�낤�B�����ɈڐЂ���̂�1�N�[���ڂ̓r���Ȃ̂��A2�N�[���ڂɂȂ��Ă���Ȃ̂��B��������1�N�[���S���g���ăJ�T�}�c�҂����̂͊ԉ��т������Ȋ��������邯�ǁc�c����͂���Ƃ��ăx���m���C�g���������B
�@�w�v�����Z�b�V�����E�I�[�P�X�g���x�͓��j�̒�9���A������u�L�`�̃j�`�A�T�v�ɕ�������Ă���A�j���B�u���`�̃j�`�A�T�v�̓e���r�����n��ŕ�������Ă���v���L���A�≼�ʃ��C�_�[�A����V���[�Y���w���̂Ńe���r�����n��̃v���I�P�͊Y�����Ȃ��B�w�L�~�ƃA�C�h���v���L���A�x��8�����A�v���I�P��9���A�w�Ђ݂̃A�C�v���x��9���������ƁA�ǂ͈Ⴄ���Ǎ��̓��j���́u�v���v�O�A�łƂ����ُ펖�ԂɊׂ��Ă���B����ς����c�Łu�^�C�g���Ɂw�v���x��t���Ȃ��Ə������H�����܂���I�v���đ�l�������^�ʖڂȊ�Ŏ咣�����肵�Ă�̂��ȁc�c���Ă����A�v���I�P�́u�L���O���R�[�h�v�ɂ��V�KIP�ŁA��������V���[�Y�����邩�ǂ����͕s�����������_�Łu�֘A��v�ƌĂׂ��i�͑��݂��Ă��܂���B��挴�Ắu���q���j�v�A���쑍�w���́u�㏼�͍N�v�\�\�w��P�⏥�V���t�H�M�A�x�̃R���r�Ȃ�ŁA�����u���������V���t�H�M�A�v�Ɛ\���グ�Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�i���Ȃ݂ɓ������q�E�㏼�R���r���w�N���V�b�N���X�^�[�Y�x�Ƃ����V�������Ă邪�A������͂܂��ςĂȂ��j�B�ḗw�v���Y�}���C�����x�́u����S�v�A�A�j���[�V��������́uSILVER LINK.�v�A�V���[�Y�\���E�r�{�́w�������I�j�����q����x�́u�����v�\�\�{���ɏ��������ł���Ă����ʎq�Ȃ̂��A����H�@�s���ɂȂ�Ȃ���{�������}�������A�z���ȏ�ɃV���t�H�M�A�ŏ��Ă��܂����B
�@���̎q�������s���������̐��E�A�u�A���X�s�A�v�B�����ł͗���鎞�Ԃ̑�������Ⴄ�B���̎q�����̓A���X�s�A�ŋC�܂܂ɉ̂��A�x��A���R��搉̂��Ă����B�������A�j�q���̉����̉��ɔE�ъ��������e���c�c�Ƃ��������ŁA��l�C�A�C�h���̃��C�u������Ă���Œ��Ƀm�C�Y�I�ȃG�l�~�[����ʂɗN���Ă��ĉ����P�������B�b�̗��ꂪ�قڃV���t�H�M�A1���Ȃ�ł���ˁB���m�Ȏ����҂��o���A�V���t�H�M�A�قǐ[���Ȏ��Ԃɂׂ͊�Ȃ����A��g���̂��̂́u�����܂ŊĂ����H�v�ƐS�z�ɂȂ�قNj��ʂ��Ă���B�F�l����@�Ɋׂ�A��l���ɂ����̎肪����c�c�Ƃ�����ʂŔ�߂��͂��o�����A�u�v�����Z�X�v�ɕϐg����Ƃ����1�b�ڂ͏I���B�v���L���A�ƃV���t�H�M�A���������킹���悤�Ȉ�i�ŁA�a�V���͂Ȃ������ʂ��u�ʔN�A�j���ɂ��Ă͊撣���Ă�����v�Ƃ��������ŁA�����܂ŃX�S���͂Ȃ����ǍŒ�ł�4�N�[����邱�Ƃ͊m�肵�Ă��邩�璷���y���߂������B���䂪�u�A���X�s�A�v�ŁA�G�l�~�[���u�W���}�E�H�b�N�v�A�G�g�D�̖��O���u�o���h�E�X�i�b�`�v�ƃ��C�X�E�L�������R�������炿����ƁwForest�x���v���o���Ă��܂�����B���ł���q�b�g����V���[�Y���������߂邾�낤�B�Ƃ肠�������j�̊y���݂�������܂����B
�E�u���i�͂��j�������ɕ�܂�Ă���v�ƚ����ꂽ�ǐؖ���u���@�����C�i�o�v��5��20������A�ڍ�i�Ƃ��ĐV�������ƕ����āu�����̔g�����Ă���v���Ď������܂����B
�@���炩���w�������ʁx�̉e�����Ă��閟��Ȃ̂ł����A��搶�i�R���M�R�j�̔������R���Ȃ̂Ŏ����ٔF��Ԃł���B�ʔ��������ǐ��A�ڂɌq����̂͑f���Ɋ��������ƂȂ̂ŁA������Ɛ�̘b�����ǘA�ڊJ�n���y���݂ɂ��Ă��܂��B
�E�u�c����Ƃ̓��u�R���ɂȂ�Ȃ��vTV�A�j�����A������2026�N�i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@�u�k�Ђ̖���z�M�A�v���u�}�K�|�P�v�ŘA�ڂ���Ă��郉�u�R������ł��B2022�N�ɘA�ڊJ�n���āA���Ƃ����l�C���o������u�v������蔭�\���x�������ȁv�Ƃ������z�B�ŐV����15���ł��B�q���C�����S���c����ŁA�u������ȁv�u�ΈГ��v�u���G���v�u�ؕ鏽�v�u�I���A�i�E�}���[�S�[���h�v�u�����t�v�Ǝ��j�Ɉ��l�[�~���O�ƂȂ��Ă��܂��B�u�y�v�g�̎q���܂��o�Ă��ĂȂ����ǁA���㌻���̂��ǂ����͓�B�c����ŋ������߂�����䂦�A�Ȃ��Ȃ��Â����͋C�ɂȂ�Ȃ��c�c�Ƃ������ǂ������V�`���G�[�V�����ʼn��X�ƈ�������ł�������n���u�R���Ȃ�ŁA��������I�ȁu�����Ɨ����W���i�W����^�C�v�̃��u�R���v�����҂���ƃC���C�����邩������܂���B�u�����������́v�Ɗ�����Ċy���ނ��Ƃɂ��܂��傤�B�q���C�������̉��������\���邱�ƂɑS�_�o���X����B���Ԃ�1�N�[�����낤����A�\����ς����肵�Ȃ������肱���ˁ[�Ƃ��I���A�i�Ƃ��o�Ԃ̒x���q���C���͊�������Ȃ��ŏI��邾�낤�B���Ȃ݂Ɏ��̍D���ȃq���C���́u��Ȃ��v���ƌ�����ȁA����ŗB��̔N���c����ł��B��ԎႢ�̂Ɉ�Ԍv�Z�����ăC�C��ȁB
�@����̕��͌��\�b���i��ł��āA���Ɏ�l���́u���[��[�v���Ɓu�E���V��v���u�I���A�Z�Z�̂��Ƃ��D���Ȃc�c�v�Ɨ�����������o����Ƃ���܂ōs���Ă��܂��B������u�q���C�����[�X�v�͌���������Ԃł��B�������A��l���͑��̗c�������������D�ӂ����Ă��邱�ƂɋC�Â��Ă���A�u�Z�Z�ɍ������ĕt���������ƂɂȂ�����A���̎q�ƊW���M�N�V���N���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����v�Ƌ���ē��ݏo���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����������y���f�B���O���Ă����ԂŁA���̗c������O�C�O�C�����Ă��Ĕނ̐S�͌������h�ꓮ���\�\�Ƃ����u�������l�ŗD�_�s�f�v�Ȏ�l���ɂȂ�������Ă���A�c�O�Ȃ��炦�[��[�ɑ���ǎҐl�C�͂ǂ�ǂ����Ă���B�����q���C�����o���Ȃ����߂̈����L�������X�Ƒ����Ă����ł���ˁB��������100�J�m�݂����ȃn�[�����W�J�ɓ˓������炠��Ӗ��`���ɂȂ邾�낤���ǁA���X�H���ύX�������Ƃ��v���Ȃ����u�ǂ�������c�c�v�Ɠr���ɕ��Ȃ���A�ڂ�ǂ��Ă���Ƃ���ł��B�c������m�Ńq���C�������̒����ǂ��A�������ǂ݂ǂ���̈�ɂȂ��Ă��邩��A�C����W�J�ɂ����Ⴄ�Ɠǎ҂̃n�[�g�����X�ɍӂ����Ⴄ�B�l�I�ɂ͑S�R�A�������ǂȁA�u�c����ƏC����ɂȂ����v���B
�@����������2026�N�A���N�ł��ˁB����́u��˃v���_�N�V�����v�A������u���v���v���O�g�̃X�^�W�I�ł��B�w�ܓ����̉ԉŁx��1���ڂ�w�J�m�W�����ޏ��x��1���ځA�ŋ߂��Ɓw���_�̃J�t�F�e���X�x����|���Ă���A�u���挴��̃��u�R���A�j���v�Ɋւ�����т͐ς�ł���B���Ԃ�u���`���N�`���������A�j���v�ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤���ǁA����Ȃ�̃N�I���e�B�[�̃A�j���ɂ͂Ȃ��Ȃ�������B
�E�A�j���u�����q���C������������I�v2���̐��삪����A�{�����{�̃C�x���g�Ŕ��\�i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@�ߔN�̃��m�x�A�j���ł����M�ɒl���锽���������炵�����ł���A2������͑f���Ɋ������B���\���J�ɂ�����̂ŃX�g�b�N���[������܂��i�ŐV���͗����o��8���A1���ŏ��������̂�3���܂łł��j����ˁB����3���͂�����ƌ��������ȁc�c�Ƃ������Ƃ���ł����B�w�����q���C������������I�x�̓K�K�K���ɂ̐V�l�܁u���w�ك��C�g�m�x����܁v�́u�K�K�K�܁v�i��܂̈���A�d��������܂ł����Ƃ���́u���܁v�ɑ�������j���l����2021�N����X�^�[�g�������C�g�m�x���̃V���[�Y�ł��B���厞�̃^�C�g���́w���͂Ђ���Ƃ��āA�ŏI�b�ŕ����q���C���̉��ɂ���|�b�Əo�̃��u�L�����Ȃ̂��낤���x�������̂ŁA�ύX���đ吳���������Ǝv����B�h�肳�͂Ȃ����G��ȃM���O�Z���X�Ɓu���݂��ނ�v�i�w���R���X�E���R�C���x�̃L�����f�U������l�j�̃C���X�g�����ݍ����A�y�����ǂ߂郉�u�R���Ɏd�オ���Ă��܂��B���u�R���ł���Ȃ��炿���Ɓu�����v�Ɍ��������Ă���A�Ƃ���������ɓƎ��̐F������B
�@�l�C���o�ăA�j�����������Ƃɂ͋����Ȃ��������A�A�j���̏o�����̂ɂ̓r�b�N�������B�K�A�K�K�K����̃A�j���Ƃ͎v���Ȃ����炢�N�I���e�B�������I�@�n�b�L�������āu�K�K�K���ɂ���o�Ă��郉�C�g�m�x��������ɂ����A�j���v���āu�ʔ������ǂ����͂Ƃ��������ʂ̃N�I���e�B�͒Ⴂ�v�Ƃ����̂����ʔF���ł�������ˁc�c�q�b�g����3���܂ł�������K�C���i��͂艴�̐t���u�R���͂܂������Ă���B�j��1���ڂ̍��͂��@�����x���ł����B���Ƀq�h�������̂́w���A�c�C���e�[���ɂȂ�܂��B�x�A1�b�ڂ����\�ǂ������̂Ŋ��҂��Ă�����ǂ�ǂ�N�I���e�B���������Ă����A���ɂ͕�����Ȃ��u������v���N�����ĕ����I������C�����i�ɂȂ��Ă��܂����B���Z�J�i���l�^�Ƃ����T�O�����݂��Ȃ��ދ��Ȑ��E�j�͓��ɕs���������Ȃ��������ǁA�w��L�����F�肭��x�͊��҂��傫�������Ԃ�s���̎c��o���������B
�@�Ȃ̂Łw�����q���C������������I�x�������O�̓C�}�C�`���҂ł��Ȃ��������A�����������n�܂�Ɓu�ȂA����́c�c�v���Ėڂ��^�����炢���Ɖ��o�̃N�I���e�B�������ăr�b�N�����܂����ˁB����A�j���Ȃ�Ƃ������A�[��A�j���ł����܂Ń��C�e�B���O�ɂ������̂��I�H�@���ēx�̔�����܂�����B�u�����̃V�[���ł�����߂̂Ƃ���ƈÂ߂̂Ƃ���Ń��C�e�B���O�̃p�^�[����ς��Ă���v�ƃC���^�r���[�ł�����Ă���A�O�ꂵ�āu�f���̋�C���v�ɗ͂����Ă��܂��B�~�[���������u���J��J���J���J��J�I�v�����삾�ƃT���b�Ɨ����Ă���Ƃ���ł��܂��ۂɎc��Ȃ��̂ł����A�A�j�����ʂŃC���p�N�g���X�S�����ƂɂȂ�܂����B�ꎞ���́u�K�K�K���ɑS�̂̔����8�����߂�v���炢���ꂽ�̂�����A�u�A�j����������ƃf�J���v���Ƃ��Ċm�F��������B�Ƃ肠�����A�ē���Ђ��ς��Ȃ�������2�������҂��č\��Ȃ��ł��傤�B�C�ɂȂ�͕̂����������B�������ɍ��N���͖������낤���瑁���ė��N�̏t�����肩�ȁB
�E�u�������̌� �������[�X�^�@���C�g�v�������G�s�\�[�h�S3�b�AYouTube�Ŋ��Ԍ�����J�i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@�������G�s�\�[�h�Ȃ�Ă��̂����������Ǝ��̒m��Ȃ������c�c�������i���W�҉f��j�ƌ���ł�BD�͔��������ǁATV�V���[�Y��BD�́u�����ł�S���^�悵�Ă��邩��ʂɂ�����v���ăX���[�����������ł���ˁBTV�A�j����BD���ăf�B�X�N�̓���ւ����ʓ|�ōw�����Ă��Đ������Ɏd�������ރR���N�^�[�A�C�e���ɂȂ��Ă��܂�����������A���鎞������قƂ�ǎ���o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�@�������G�s�\�[�h��Blu-ray BOX��1�Ɏ��^���ꂽ�u99.419 �̐��v��2�Ɏ��^���ꂽ�u99.419 ���_�v�A3�Ɏ��^���ꂽ�u99.419 �J���v�ŁA���ׂ�8�����x�̃{�����[���B�S�����킹��TV�A�j��1�b���Ƃ������Ƃ���ł��B���e�Ƃ��Ắu���䏭�������̓���v�Ƃ����������ŁA���ԂŐ키�u�������[�v�v�f�͈����܂���B���n��I�ɂ�TV�V���[�Y�̍ŏI��ȍ~�A��100���čՁi�N�x���ɊJ�Â����s���j�܂łɈʒu����B�ȒP�Ɍ����Ɓu2�N���̓~�v�ł��ˁB�������[�X�^�@���C�g�̃A�j���́u2�N���̏t�v�Ɏn�܂��āA�ĂƏH���قƂ�ǔ���u�~�̂͂��܂�v���}����������ŏI���\���ƂȂ��Ă��܂��B����G�s�\�[�h�ł͂��邪����k�̈��Ȃ�ŁATV�V���[�Y��S�b�ϏI����Ă��王�����邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B
�@�u99.419 �̐��v�͑�100���čՂŏ㉉���錀�u�X�^�@���C�g�v�̈ߑ����̂��߁A���ȂȂƘI��܂Ђ�ƐΓ��o�t�Ɛ_�y�Ђ����4�l��B�g�i����n���ȁj�̍̐��ɕt�������G�s�\�[�h�B�����傫���Ȃ��Ă��邱�Ƃ��C�ɂ���܂Ђ�̕`�ʂ��₽�玷�X�Ȃ́A�u�������[�X�^�@���C�g���ď����͒j���l�C�č���ł����߂������Ȃ��v���Ďv���Ԃ��ĉ��������Ȃ����B���ɃT�I�����A�v���Q�[���u�X�^�����v�ɂ̓z�[����ʂŕ��䏭���̋��̂�������^�b�`����ƒp����������A������u�p�C�^�b�`�v�@�\���t���Ă������Ǖs������v���[���[�����o���������Ŕp�~�ɂȂ�܂����B���͂�����������ȋ@�\�����邱�ƒm��Ȃ��āA�p�~�̕ŏ��߂đ��݂�F�����A�c�O�Ȃ悤�ȁA�����Ȃ��čς�ŗǂ������悤�ȁA���G�ȋC�����Ɋׂ�܂����B�u99.419 ���_�v�͊K�i�œˑR�����������n�߂��V���^��Ɛ_�y�Ђ���̊Ԃɋ��܂ꂽ�������߂����f����G�s�\�[�h�B�u���čՂ܂ł���29���v�Ƃ������莆���o�Ă���̂ŁA2���ł��ˁB����̍����ˎ~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��ĉ�������A�������^���ڂɂ��邱�Ƃ��ł���̂Ő^��t�@���͕K���B���̐^��́u�܂����C�����ŃL���L����ɂ��Ă��鈤�邳��ɂ͂킩��Ȃ��ł��傤�ˁv���Ă�����ƌ��������B�u99.419 �J���v�͂��悢�搹�čՓ����A�Y�ȁu�X�^�@���C�g�v�̊J�����Ԃ����钆�A����̈���ؗ��͍T���ł͂Ȃ��o�b�e�B���O�Z���^�[�ɂ����c�c�Ƃ����킯�ŁA�u�̐��v��u���_�v�őf�U�肵�Ă����ؗ��̕�������������G�s�\�[�h�B�N�������ƍ��q�����C�����V�[���Ƀj���j�����悤�B
�@�Ō�܂Ŏ������āu�ŁA99.419���Č��lj��������́H�v�Ƃ����^�₪�c��킯�ł����A�����99.419�}�C������160�L�����[�g���A�܂�ؗ����o�b�e�B���O�Z���^�[�őł������̋����ł��B�Ȃ�Ƒ�J�ĕ��⍲�X�ؘN��̓������݂��B���₻��Ȃ�������Ȃ��Ƃ킩��Ȃ���I�@����̖������G�s�\�[�h�����o���̓������[�X�^�@���C�g�̃p�`���R���ɍ��킹�Ă̎{��ł���A�������̒��q�Ńp�`������q�b�g������A�j���̐V�������̂��ȁB���ɗ���Ƃ��āA�������̂����Ęb�ł����B�A�j���ł���ĂȂ��͉̂ؗ�������1�N�����������ƁA2�N���łЂ��肪���Ȃ��Ȃ����ĂƏH�A3�N�̏H����~�ɂ����Ăł��ˁB1�N���オ�����Ƃ����傫�����ǁA���̍��̓I�[�f�B�V�����J�n�O�ł���n��������ł̃������[�͂܂��n�܂��Ă��Ȃ��͂�������p�������W�J�ɂł����Ȃ����������G�s�\�[�h�������Ȃ��B�u�Ђ��肪���Ȃ��Ȃ����ĂƏH�v�͂Ђ��肪�o���Ȃ����A�ؗ��̐��_��Ԃ����o������P�����߂�G�s�\�[�h���Ȃ������Ȃ�ȁB�ƂȂ�ƁA3�N�̏H�Ƃ��~���炢�������Ԃ��c���Ă��Ȃ��B����ł�3�N�̏t�A5�����̃G�s�\�[�h�ŁA�wꡂ��Ȃ�G���h���h�x���u�Ă̌����v������7���O��̃G�s�\�[�h�B�T�I�����A�v���u�X�^�����v�ŕ`���ꂽ���t�F�X�i�S���w�������t�F�X�e�B�o���j�̊J�Î������s���i�Ƃ������B���j������u�H�̏o�����v�Ƃ��ĔP�����߂Ȃ����Ȃ����A�X�^�����́u�A�j���{�҂ɂ͓o�ꂵ�Ȃ��I���W�i���̑��Z�L�����v���R�قǏo�Ă��邩�獡�X�V��A�j���Ƃ��ēW�J�����]�݂͋ɔ��ƌ����悤�B�X�^�����̃A�j��PV�Ƃ������ꂽ���ǁA�G�������\�Ⴄ��ł���ˁB��ɍ��ꂽ�ʂ̃A�j��PV�̕����{�҂ɋ߂��Ƃ����B�p�`����O��ɂ��ăX�^�������A�j�������関�������邩������Ȃ��A�ƙR����]�����ɋ�����グ�ăX�^�@���C�g�T���Ƃ��邩�B
�E�A�j���uBanG Dream! Morfonication�v��TV�A�j���uBanG Dream!�i�o���h���I�j�v�̒n��g�ĕ���������I
�@Ave Mujica���I��������AMyGO�̍ĕ��������邩�ȁ`�Ǝv������܂�����1���ڍĕ������B�Ђ���Ƃ��ĐV��܂ʼn��X�Ɖߋ��̃V���[�Y���ĕ����������H�@���t�F1���ځA���āF2���ځA���H�F3���ځA���~�FMyGO�A���t�FMujica�ő�����Η��āi2026�N7���j����V�������������Ȃ��B�o���h���̃A�j����TV�V���[�Y�ȊO�Ɍ���ł́wEpisode of Roselia�x��w�ۂ��҂�'�ǂ�[�ށI�x�A���C�u�V�[���݂̂ō\�����ꂽ�wFILM LIVE�x�A�K���p5���N���L�O���Đ��삳�ꂽ�wCiRCLE THANKS PARTY�I�x�A�����ăV���[�g�A�j���V���[�Y�́w�K���p�s�R�x������̂ł�����������X��2�N�[�����炢�͎��Ԃ��҂��������B�قƂ�ǂ͔z�M�Ŋς��邩��ʂɂ��Ȃ��Ă��������ǁA���J����3�N�ȏ�o�̂ɖ����ɔz�M�����Ȃ��ۂ҂ǂ肾���͍ĕҏW�łł�������ł���Ăق����ȁBMyGO�͋��N�ɑ��W�҉f�����f�������A������͔z�M�ǂ��납�~�Ղɂ���Ȃ��Ă��Ȃ��BTV��MyGO��BD�������I�����甼�N�o���Ă悤�₭���������悤�ȗL�l���������A�o���h���͉~�Ք���̂ɂ��܂�M�S����Ȃ���ł���ˁc�c�B
�@���Ă����A4��17������ĕ���������wBanG Dream!�i�o���h���I�j�x��2017�N��1������4���ɂ����ĕ������ꂽ��i�ł��B�ʏ́u1���ځv�B������u�~�A�j���v�������̂ł����A�����J�n���x�������i�ŒZ�̋ǂł�1��21���j���ߍŏI��4�����{�܂ŃY������ł���B�����g���u���������Ēx�ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�u�N�n�̍Q�������������ɕ������Ă����܂蒍�ڂ���Ȃ����炠���Ēx�߂ɊJ�n���悤�v�Ƃ����_�����������������B�o���h���̓��f�B�A�~�b�N�X�E�v���W�F�N�g�Ƃ���2015�N�ɃX�^�[�g�������A�����̐ݒ�ł͎�l���́u�ˎR�����v���u�C��Ȃڂ����v��������x�[�X�́u������݁v���u�E�҂ɓ����ς��ҁv��������Ƃ��Ȃ�Ȃ������������߁A2016�N���ɂ��낢��Ɛݒ�ύX���āu�A�j����\�V���Q�����̘b�v�ɍ�蒼���Ă��܂��B�u�L���L���h�L�h�L�v�������t�ɁA�]�V�C�Ȃ��炢���邭�đO�����ȍ�������M�^�[�Əo����ăo���h�����ɂ̂߂荞��ł����l�q��`���Ă���B
�@�o���h�v�f�ƖG���v�f���ǂ̒��x���荞�ނ��A�܂�����w�����������͂߂Ă��Ȃ����������̍�i�Ȃ̂ł��Ȃ��T�芴�������ł��B���݂́u3DCG�A�j���v�Ƃ��ĔF������Ă���o���h���V���[�Y�����A����1���ڂ͎�`����悪��{�ŁA3DCG�͕����I�ɂ����g�p����Ă��Ȃ��B�A�j������͍��͂Ȃ��uXEBEC�i�W�[�x�b�N�j�v���B�ḗu��Γ֎j�v�A�ŋ߂��Ɓu�܂ق����v���Ɓw���@�����ɂ�������āx����|�����l�B��������XEBEC���O���ɉ�������u�O���X��v�������A��悪�s����őf���ɃI�X�X���͂��Â炢���ǁA�����ƗL��̊|�������Ƃ��͂���ς荡�ł��D���ł��ˁB3�b�ł�����u���炫�琯�̃A���v���s�]���������Ƃ������ăA�j���́u�����v�ƌ����ɂ������ʂɂȂ������̂́A�������ɔz�M���n�܂����A�v���u�K���p�v���Ɓw�o���h���I �K�[���Y�o���h�p�[�e�B�I�x�̓q�b�g�������߁A�A�j����2���A3���Ƒ������ƂɂȂ�܂��B���͂��������Ԑl�C�����������Ă���K���p�����ǁA�S�����̐����͖{���ɐ��܂��������B�A�N�e�B�u����100���l���Ă������A�u�V���[�h�̌��Z�Łu�o���h���̔��㍂��100���~��˔j�����v�Ɣ��\����邭�炢�ł����B
�@�o���h���̃A�j���Ȃ�č��Ȃ�z�M�ł܂Ƃ߂Ċς�邩��ĕ����̎��v������̂��ǂ������M���^�����A�Ƃ肠�������͐̂���������Ř^�悵�悤���ȁB�����̘^��͂܂��c���Ă��ł����ǁA�^��@�킪�Â�����������SD�掿�Ȃ�ł���ˁc�c���L�̟��݂��u���v�ɂȂ��Ă��邩�炠��͂���Ŏ�[����ł����ǂ��B���ƕs�]�����ďC�����ꂽ3�b�̂��炫�琯�p�[�g�A���C���ł��ς��̂������̘^�悵���Ȃ��i�ȑO�̓A�}�v���Ŗ��C���ł��z�M����Ă����炵�����A��U���C���i�b�v��������āA���������Ƃ��ɂ͏C���łɂȂ��Ă����Ƃ����j���猋�\�M�d�Ȃ�ł��B
�E�A�}�v�����w���^�C���X���b�p�[�x�������B
�@2024�N8���Ɍ��J���ꂽ�M��i�f��Ղł̏�f��2023�N�ɉ��x������Ă���j�ł����A�C���f�B�[�Y��i�Ƃ������Ƃ������ē����͌��J�K�͂������������c�c�Ƃ�����1�ق݂̂̏�f�������B���ꂪ���J��ɘb��ƂȂ��Ăǂ�ǂ��f�K�͂��g�債�Ă����A�X�Ƀu���[���{���܂���{�A�J�f�~�[�܂��l�������Ƃ��b��ɂȂ��č��N�ɂȂ��Ă��܂���f�ق����������Ă���B�܂�w�J�������~�߂�ȁI�x�݂����Ȋ����Ő���オ���Ă�������i�ł��B�������̎��㌀�Ȃ̂Ő����̓J���~�߂��������Ɗ|�����Ă���A���̊z�A��2500���~�i�J���~�߂͖�300���~�j�B�ḗu���c�~��v�͎��g�̗a��1500���~�ƕ������̕⏕��600���~�ɉ����A���L���Ă����X�|�[�c�J�[�iNSX�j��400���~�Ŕ����Ăǂ��ɂ��H�ʂ����Ƃ̂��ƁB��攭�������傤�ǃR���i�Ђ̍��ł��낢���V�������������A���f���s�B�e���̑S�ʋ��͂������ĉ��Ƃ��Ȃ����炵���B�ʏ�łƁA5�����炢�̒lj��V�[��������i�Ƃ������J�b�g�����V�[�����������j�u�f���b�N�X�Łv�����݂��Ă��āA�A�}�v���Ŕz�M���Ă�̂͒ʏ�ł̕��ł��B
�@���͖����B��A��Ôˎm�́u����V���q��v�͓��u�ƂƂ��ɕ��A�ɐ��݁A���B�ˎm�̑҂����������Ă����B����͂Ȃ��Ȃ��̎����ŁA��u�̊Ԃɓ��u�͓|��A��Έ�̂��Ȃ��猈�����݂��ɁB�˔@�~��o������J�ɔG��Ȃ��炢������������Ɠ���U�肩�Ԃ����Ƃ���A�����ƂƂ��Ɏ��E���^�����ɂȂ����B�ǂ������������������炵���B�C���t���ƐV���q��́u�]�ˁv�ɂ������A���������ȕ��͋C���Y���Ă���B�����̖��A�ނ͂����������̐����������140�N��ɂ��関���ł��邱�Ƃ�m���āc�c�Ƃ����A�����̍������m������̎B�e���Ƀ^�C���X���b�v���Ă��܂��f��ł��B�R���f�B�v�f�͑������ǁA�V���A�X�v�f���������Ă���̂Łu�R���f�B��i�v�ƌ������Ă������ǂ����͖����Ƃ���B
�@��������^�C���X���b�v�������Ƃ�������V���q��͂ǂ��ɂ����Č��̎���ɖ߂낤�Ƃ��邪�肾�Ă��Ȃ��A�r���ɕ���B���̘a���ɏE���āu�L���r���̒j�v�Ƃ��ďZ�ݍ��݂œ������ƂɂȂ邪�A����s���Ŏ��㌀�́u�a�����v�������邱�ƂɁc�c�Ƃ�����ɔo�D�ւ̓�����ݏo���܂��B�ēH���A���z�̃x�[�X�ɂ������̂́u����Ƀ^�C���X���b�v���Ă������i�����L�i�j���o�Ă������CM�v�ŁA�����Ɂu5����a��ꂽ�j�v�ٖ̈������u���{���O�v�̃C���[�W���d�˂��A�Ƃ̂��ƁB���̕��{���剉�����i�Ƃ����w���`���C�����C�g�x�Ƃ����f�悪����A�X�g�[���[��̌q����͂Ȃ����u���_�I�ȈӖ������ł́w���`���C�����C�g�x�̑��ҁv�ƌ����邩������܂���B�쒆�Ɂu�֖{�v�Ƃ����E�w�t���o�Ă����ł����ǁA��������{������C���[�W�����L�����N�^�[�ŁA�\�Ȃ畟�{����ɉ����Ăق����������������r�{���M���ɕ��{���S���Ȃ������ߎ������Ȃ������B
�@�N���C�}�b�N�X�̓W�J��������Ƌ����Ńm���Ȃ������͂��������A�ɗ͖��ʂȕ`�ʂ�r���ĕK�v�ȃp�[�c�����ʼnf���g�ݗ��ĂĂ���A�u��\�Z�f��v�̃��[�h�����Y���Ă�����̂̃A�C�f�A�Ə�M�Ɖ��o�ŏ[���ɃJ�o�[�ł��Ă���B�Ō�ɃN�X�b�Ƃ���悤�ȃl�^���d�|���Ă����̂��S�����B�\�Z�J�c�J�c�Łu�n���������v�Ɗē͌���Ă��邪�A���������o�^���߂�����J�͖{�҂ɏo�Ă��Ȃ��̂ŋC�y�Ɋς��Ǝv���܂��B���Ȃ݂ɋ�����10����˔j���������ŁA�Ĕ_�Ƃ����Ƃ��Ă���ē͌o�ϓI�ɂ��~�ς��ꂽ�͗l�B
�@�܂Ƃ߁B�u�^�C���X���b�v���Ă��������w�a�����x�̔o�D�Ƃ��ĐV���Ȑl��������o���v�Ƃ����V���v���ȓ��e�G�ɂȂ�߂��Ȃ����x�Ƀq�l���Ċ����������A�����X�g���[�g�ȃG���^����i�B�u�ŋ߂̉f��͂ǂ������������ĕt���Ă����Ȃ��v�Ƃ����A�u�͉̂f�悪�D�����������Njߍ��͂��܂�ςĂ��Ȃ��v�^�C�v�̐l�ɓ��ɃI�X�X����������{���B���Ȃ݂Ƀq���C���́u�R�{�D�q�v�̕����̖{�I�A�i�n�ɑ��Y�̕��ɖ{������ł���̂͂킩��Ƃ��Ă��������s���̓V���[�Y������͉̂��Ȃc�c�쒆�̐ݒ�N���2007�N�ō�����18�N���炢�O�����A����ł����s�̖{������̂͂����Ԉ�a���������B
�E�����_���w���e�x�Ǘ��B
�@��Җ��́u���E���Ђ�v�Ɠǂ܂���B�u�]�ː에���܁v����܂��ăf�r���[���������ƂŁA����܂łɁu���M�t�F�܁v�u�g��p�����w�V�l�܁v�u���{������Ƌ���܁v�Ȃǂ���܂��Ă���^�C�g���E�z���_�[�ł��B���؏܂̌��ɂ��O�x�Ȃ��Ă��邪�A���̂Ƃ����܂ɂ͎����Ă��܂���B���́w���e�x�����؏܌���ŁA�u���̃~�X�e���[���������I�v��u�~�X�e�����ǂ݂����I�v��1�ʂ��l������i�����Ɋ��҂��ꂽ���A���ʂ͂������q�ׂ��ʂ�B�u�O�Y������v�Ɓu�p�c����v����͕]�����ꂽ���A����ȊO�̑I�l�ψ�����͂��܂�F�悢�R�����g�����Ă��܂���B���Ȃ݂ɂ��̂Ƃ��̎�܍���w��ɐ�����x�ł��B
�@�����̊e�n�ɔ��e���d�|����ꂽ�\�\�O�㖢���ƕ\�����Ă����K�͂̃e���v��ɓ��h����x�@�B�K���ɂ��čŏd�v�e�^�҂͊��Ɋm�ۂ���Ă���B�����Ď��̋@��j���A�Ƃ����߂ŘA�s���ꂽ�A���炵�Ȃ����̂̒j�B�ނ́u�X�Y�L�E�^�S�T�N�v�Ɩ��炩�ȋU�������ɂ��āA�u�슴�v�Ə̂����j�̎����Əꏊ��\�����Ă����B�������̂Ȃlj����Ȃ��u���G�̐l�v���A�����ɂ��Ċח������邩�B�e����H���~�߂����x�@�������݂͒͂ǂ���̂Ȃ����ӂ��T���U�炷�X�Y�L�ɗ����������Ă������c�c�B
�@�ւ�ւ���Ȃ���u������݂��Ă��������v�Ɩ��S���Ă���G�ɕ`�����悤�ȃ_���������A�}�ɑ�K�̓e���̎�Ɗi�Ƃ��Ĉ����鑶�݂ɂȂ�A�`�����\�y�[�W�̈Ó]�����N�₩�Ȉ��B�G�k�ƃN�C�Y��D������Ĕ��j�ꏊ�ɂ��Ẵq���g���o���Ă��������Ƃ̓G���^���f��ɂ��悭�o�Ă��邪�A���������^�C�v�͂ǂ��炩�ƌ����Βm�\�ȍ������ȁu�C���e���v�̃C���[�W�������A�X�Y�L�E�^�S�T�N�̂悤�ȁu�U�E�l���̗��ގҁv�Ƃ��������͋C�̃I�b�T�����̂�肭���ƒNjy�̎���]���Ȃ��猭���肷��͎̂a�V�łȂ��Ȃ��ǂ݉���������܂��B
�@�����A�ǂ��ɂ������̂ŋْ������������Ȃ��A�Ƃ�����_������܂��B���ɔł�500�y�[�W�A��C�ɓǂݒʂ����Ƃ���ƃ_���镔��������͎̂d���Ȃ��ł����A�撲���̒��ŌJ��L������X�Y�L�ƌY���̋삯�����A�撲���̊O���삯������{���������A�����ăe���v�悪�I�����ăp�j�b�N�Ɋׂ��ʖ��O�ƁA�����Ȏ��_�荞�����ŏ����璷�ɂȂ��Ă��܂�����ۂ͂���܂����B�Ɍ��ɒǂ����܂�Č������������A�u�ʂɒN�������Ă�������Ȃ��ł����A�����ƊW�̂Ȃ��l�Ȃ�v�Ƃ����X�Y�L�̌��t�ɔ[���������ɂȂ�x�@�������̎p�������̈�Ȃ�ł��傤���A�u���j�Ɋ������܂ꂽ��Q�҂����v�̕`�ʂ��T���ڂɂ��邱�ƂŐ��S�ȃ��[�h�����炵�Ă���A�u���̎��ゾ�����猻��̏������Ƃ����ԂɊg�U����邾�낤����w���������Ȃ��x�ʼn�����̂͂�����Ɩ���������̂ł́H�v�Ǝv���܂����B������撲���ɌŒ肵�������ǂ������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������؏ܑI�l�ψ��̃R�����g����������Ɨ�����e�ł��B
�@�����_����Ƃ��낪����ɂ����C�ɓǂ߂邵�A�h���f���Ԃ��������āA�Ō�̈�s���L�}���Ă���\�\�u����v�̏����͖������Ă���̂Ɂu���荞�݉߂��v�Ȃ����������Ă��܂ЂƂn�}��ꂸ�A�l�I�ɂ́u�ɂ����v����ł����B���҂Ƃ����w�@��苒�@���e2�x����������Ă���A�Ƃ����������ǂ݂����ĕ�������ł���ˁB���́w�@��苒�x�����ɓǂݏI����Ă��邪�A�O���́w���e�x�������킷�鐨���Ń��N���N�����Ă��ꂽ���nj㔼�͐K���ڂ݂ŏ����K�b�J�������B���������ȏI��������������w���e3�x�Ɋ��ҁB���ƍ��N���ʉf�悪���J�����\���Ȃ̂ŁA�u500�y�[�W�����鏬����ǂނ̂̓_�����ȁv���Đl�͂��������ӏ܂���̂���ł��B
2025-03-30.�E�}���K���2025�A��܍�i�͔���@�q�u���肷�A�F���܂ł��v�i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@�����A�m���Ă閟�悾�B�w���肷�A�F���i�ǂ��j�܂ł��x�͉F����s�m��ڎw����������l���̐t����ł��B��l���u�����c���肷�v�͗��e���p��Ɠ��{��A���������o�C�����K���̎q�Ƃ��Ĉ�Ă悤�Ƃ������ʁA�p������{������r���[�Ŏ���Ƃ̉�b������ȁu�Z�~�����K���v�ɂȂ��Ă��܂����B��b�ɓ�V���邾���ŁA�n���͈����Ȃ��A�����牽�ɂ����ĂȂ��B�����w�E���ꂽ���肷�́A�����������āu�F����s�m�ɂȂ閲�v��ڎw�����ƌ��ӂ���\�\�Ƃ����A�u���Ɍ������ēw�͂���v�撣�艮�ȏ�����`���V���v���ȕ��ꂾ�B�u�}���K�����v�Ƃ����A�v���Ŕz�M����Ă��āA�u�����1�b�ڂ�ǂ�SP���C�t�i�����ǂނ��߂̃A�C�e���j�������v�Ƃ����~�b�V����������������SP���C�t�~�����Łu���Ⴀ1�b�����v�Ɠǂݏo�����Ƃ���A�~�܂�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B����@�q��i�͂ǂ��ƂȂ��u�ʌ����v�Ƃ�����ۂ����������ǁA����͌����o���G���^���v�f���������艟�����Ă��ēǂ݂₷���B���͎҂ƂȂ鏭�N�u��������v�Ƃ̋��������▭�ŁA���u�R���ɗ��炸�b���܂������ɐ���グ�Ă����B�Ƃɂ������肷�̒��������������ăI�X�X���ł��B�܂�3�����o������ł��܂�X�g�b�N�����܂��ĂȂ����A�����������A�j���������Ȃ����ȁB
�ELeaf�AKey�ݗ������o�[�ƐU��Ԃ�u90�N��������Q�[���E�v�őO�������w�Ƃ������x�ɒ��wToHeart�x�A�`���̖��ȁw���̎��x�����b�A�����ς���Key�́u�����Q�[�vetc�c�c���̎���́g�M���h�ɔ����i�d�t�@�~�j�R�Q�[�}�[�j
�@�u���쒼�Ɓv�Ɓu�܌ːL���v�̑Βk�Ƃ������ɋM�d�ȋL���ł��B���́uKey�v�̕��ŗL�������ǐ܌˂͂��Ƃ��ƁuLeaf�v�ɏ������Ă�����ł���ˁB�܌˂�Leaf����͎����悭�m��Ȃ��̂ŋ����[���ǂ܂��Ă�������B���삪�uTYPE-MOON�̓ސ{�����j�g���v���X�̋�������v�Ƌ�̓I�Ȗ��O�������Ă��邪�A���̂ӂ��肪Leaf�́w���i�������Ɓj�x���v���[���āu�A�_���g�Q�[�����Ă��������̂��A���ȂI�v�ƏՌ������b�͂��܂�ɂ��L���ł��B�������Ɏ��Ԃ��o���Ă��邩�炩��l�Ƃ����\�Ԃ����Ⴏ�Ă���A���삪�u���̎��v�ɑ��āu������`�v�u��������o�čs�������Ƃɓ��ĂƂ�ȁ`�v�u�����Ȃ����ĉ����������ł��ˁv�ƃR�����g���Ă���͔̂��܂����BLeaf�𗧂��グ��3��ڂ́w���x��������܂ł́u�����I�ɂ��Ȃ�ꂵ�������v�ƃR�����g���Ă���̂͂܂��������낤�ȁA�ƁB�wDR2�i�C�g���S�x��wFilsnown�x�̍�����Leaf�ɒ��ڂ��Ă����؋�����̃I�^�N�͗t���D���̒��ł����Ȃ菭���h�ł����B�Βk�̒��ł�����Ă��邪�A�wDR2�i�C�g���S�x�Ȃ��2500�{�o�ׂ���700�{��������Ȃ������������B������Windows95���㗤����O�ŁA�G���Q�[�̔��オ���~�C���ɂȂ��Ă����u�J�Ԃ̎����v������Ƃ����̂�����̂�������Ȃ��B
�@�u�w�������x��w�Ƃ������x�̂悤�ȁA�t���ۂ����́v�Ƃ����R���Z�v�g�Ő��삳�ꂽ�̂��wToHeart�x���Ƃ������A�������ƂɊJ�����M���M���Łu�Г��Ńe�X�g�v���C���Ĉӌ������킵����v����悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ������Ƃ����B�o�N�`�݂����Ȑ���̐��ň��R�Ƃ���B���������Ή���̓z�����o2���یˎj���ɂ����ԍD���ɂ�点�Ă������ǁA�������犄�Ƃ����������C��`�������ȁB�܌˂͑�\�Ȃł���u���̎��v�ɂ��Č���Ă��邪�A�����\�肵�Ă����̎�́uLia�v����Ȃ��A�ʂ̐l���̂��͂����������Nj}篃L�����Z���ɂȂ��āA�u���T���[���X�̃X�^�W�I�Ń��R�[�f�B���O�����邱�Ƃ͌��܂��Ă����v���炽�܂��܃X�^�W�I�ɂ���Lia���̂����ƂɂȂ����Ƃ����c�c�G���Q�[�̃V�i���I�ł��u��s����`�v�ƌ���ꂻ���ȓW�J���B���Ȃ݂Ɂu���̎��v�̓t������6�����炢�����ł����A�Q�[����OP�ł�3�����x�ɏk�߂�ꂽ�V���[�g�ł��g�p����Ă���A�X��TV�A�j���ł�1�����ɕҏW���ꂽ�o�[�W�������̗p����Ă���̂ŁA�l�ɂ���āu���̎��v�̂������藈�钷���̓o���o���������肷��B���͂���ς�Q�[���Ŏg��ꂽ�V���[�g�ł���ԓ���݂܂��ˁc�c�B
�@�ق��A�ʔ����g�s�b�N�́u����͎Ⴂ���Ɍ�������Ńo�C�g���āA���̐i�s�ɍ��킹�ďƖ��ς����艹�y�������肵�Ă��������Łw�ǂ������Ȃ��ǂ������Ƃ��ɗ����ΐl�͋������x�̊��o���͂߂��v�Ƃ��uSteam�͐R�����������v�u�R����S������l�ɂ���Ă�����ς���Ă���v�Ƃ��u�w3D�L�����̗x��V�[���ŋ����h��Ă���x�Ǝw�E����ă{�[���i���g�݁j���O���čĐR���̈˗���������w�܂��h��Ă���x�ƕԂ��Ă����i�ڂ̍��o�H�j�v�Ƃ��A���낢�날��̂Ő���ڂ�ʂ��Ă݂Ăق����B
�E�wBanG Dream! Ave Mujica�x�A�ŏI��ɓ������13�b�uPer aspera ad astra.�v����������܂����B
�@�}�C�S�ƃ��W�J�̃��C�u��ł��邱�Ƃ͎���\���̎��_�Ŕ������Ă��܂������A�{���ɍŏ�����Ō�܂ł����ƃ��C�u�I�@�J�n�O�̊|�������Ƃ�MC�Ƃ����W�J���L�̐���������܂����ǁA����ȊO�͂Ђ����炸�[���ƃ��C�u�V�[���ł��B�Ȃ�Ɠr��CM����i�V�A�Ԃ������ł���Ă��܂��B�{���Ȃ�CM�����g�ɂ܂Ŗ{�҂���������ł邩��ŏI�b����27������i������24����j�B�X�S���^������ȁA�{���Ɂc�c���o�Ƃ��Ă͂قƂ��FILM LIVE�i���C�u�V�[�������ō\�����ꂽ�o���h���̌���ō�i�j�ł��B���W�J�͂���܂Ń��C�u�̂��Ƃ𐡌��܂߂āu�}�X�J���[�h�v�ƌĂ�ł��܂������A�������ʊO��������Ă邵�u���ʕ�����v�Ƃ����`���ɂ������Ȃ��Ă��������ȁA�Ƃ������ƂȂ̂�����́u�~�\���M�A�i�_�b�j�v�Ə̂��Ă���B�u���̐_�b�ɂȂ��āi�͂��Ɓj�v���Ȃ����B
�@�ڂ̌��E�܂ŋl�ߍ��Ȃ�5�ȁB�\���Ƃ��Ă̓}�C�S�̋Ȃ�2����āA���ꂩ�烀�W�J�̋Ȃ�3����ďI���B1�Ȃ����݂ɂ��̂��ȁA�Ɨ\�z���Ă������ǁA���܂�p�ɂɕ��䂪��ւ��Ɩv���ł��Ȃ����炩�V���v���Ɂu���C�u��������^���C�u�Ŗ�����v���e�ƂȂ��Ă��܂��B�}�C�S��������Ȃ́u���ⳏH�v�Ɓu�����Łv�B��ȖځA�u���ⳏH�i���������イ�j�v�͏ˎq��z���ĉ̂����Ǝv����V�ȁB�u��v�͕M�A�uⳁv�͎��c�c�ˎq�ɖ����tⳂŃ��b�Z�[�W�𑗂��Ă������X��U��Ԃ�A�킩�ꓹ�̐�ł܂��������邱�Ƃ�����Ă��ꂩ����̂�������ƌ��ӕ\������̂��B�M�^�[���̈����Ɗy�ނ����������ăM�^�[��e������ɔw�����킹�ɂȂ�V�[���������ł��ˁB�����̂��Ă�������g�R�g�R�����Ē�ʒu�ɖ߂�y�ނ��n���ɍD���B�u�����D���v�|�C���g�̓C���g���ʼnf�����uMyGO!!!!!�v�̃��S�ƁA�M�^�[�w�b�h���_���猩�������ł��ˁB�t�@���T���Ă������ŃR�[���X�ɓ���̂��x��čQ�Ăă}�C�N�Ɍ������������W�g�ڂŌ��邻�����ꂽ������闧����X�S���C�C�BMV�����J����Ă������A�u�V�������ɐ�����Ă��v��CRYCHIC���U�̔߂��݂��瑫���݂��Ă������̎�������Ɗy�ނ����������Ă����Ƃ��낪�ō��B��Ȗڂ́u�����Łv�́u���˂сv�Ɠǂ܂���B���\�ς݂̋Ȃł����A�A�j���ł��͎̂n�߂āB������̓}�C�S�̃����o�[�Ɍ����ĉ̂����悤�ȋȂł��ˁB�u�w�����x�����Ȃ��v�u�w����x�v�u�فw�炠�ȁx�v�u�w����x���͂��̂Ȃ����v�u�w�A�x���w�m�x�E�w���x�v�ƃ����o�[�S���̖��O���̎��ɐD�荞��ł���B������Ζڗ��Ƃ��ƃt�@���T�ɗ�ވ����̎p�ɕ���闧���ς�炸�C�C���������Ă��܂��B�V�Ȃ́u���ⳏH�v�̓V���O�������������\���ł����A�J�b�v�����O�Ƃ��āu���S�����i���傤���傤�߂��j�v�Ȃ�V�Ȃ����^�����͗l�B�u�Ȗ��̓ǂ݂��N�C�Y�݂����v�ƌ�����}�C�S�̒��ł����Ƃ��ǂ݂₷���Ȗ��ł͂Ȃ��낤���B
�@���_����ւ��A���x�̓��W�J�̃~�\���M�A�ֈڂ�B�}�C�S�Ƃ͑傫���قȂ�L�X�Ƃ������uG-WAVE�v�BMyGO��13�b�Ń��W�J���uAve Mujica�v�Ƃ����Ȃ�������Ƃ���ł��ˁBAve Mujica�A�A�j���̃^�C�g���ł������ăo���h���ł������ċȖ��ł�����̂ł�₱�����B���͏ڂ����Ȃ��̂ł����̎��肾���A�\���I�ɁuK�A���[�i���l�v�i�L���p2���l�j�����f���ƂȂ��Ă���炵���B4���ɂ����ō������C�u���J�×\�������炻�̌��ˍ���������̂��ȁB���t�����Ȃ́u��䊐��_���X�v�Ɓu��v�Ɓu�V���i����j��Musica�v�A�Ȃ�ƑS���V�Ȃł��B�u��䊐��_���X�v�͌J���̂��Ȃ��Ȃ�������l�`�݂����ȃp�t�H�[�}���X���炢���Ȃ�h���͂̋Ȃ��n�܂�B�u��䊐��v�̓T�[�J�X�̃e���g�́u���ˏ�̓V��v��\���Ă���炵�����A�u�x�c���w���̐��v�̃C���[�W���������Ă���悤���B��r�I�Z���ȂȂ̂ł����ɏI��邪�A����܂Ń��C�u�ł��܂范�����p�t�H�[�}���X�����Ă��Ȃ��������[�e�B�X�i�r�j�����\�ϋɓI�ɓ����Ă��Ė��Ăȁu�ω��v�������܂��B�܂����M�^�[�܂ł���悤�Ȏq�ɂȂ�Ƃ́c�c���Ƃɂ�ނ��L�̃|�[�Y�����Ƃ���A�ꎞ��~���Ă悭����Ɣ���̉e�����Ɋ|�����ĔL�̓��E�݂����ɂȂ��Ă���̂��킩���āu�ׂ����I�v�ƚX�����B�̎����������Â炢�̂ŁA�����\���ł�����̕��͈�x��������Ɏ������Ȃ��畷�������̂��x�^�[�B�u��v�͏��̐�ł�����n�܂钧���I�E�}�M�I�ȃ\���O�B�����u��v�A�V���v���߂��Ă�����ł��Ӗ������ݎ��邪�A�p��́uAlter Ego�v�i�ʐl�i�j�Ƃ��Ȃ�X�g���[�g�ȋȖ��ɂȂ��Ă���B�C��̃v���P�c���₽��ƈ�ۂɎc���Ȃ����A���[�e�B�X�L�b�N���O���̃��[�i�L�b�N�ƏƉ����Ă��鉉�o���S�����B�r�����A�K�����Ńo���G����Ă邨�����������đ̊��͔��Q�Ȃ�ł���ˁB�X�݂Ȃ݂͕�e�Ƃ��Ėr�����������邱�Ƃ͂Ȃ��������ǁA���̍˔\���������āu�������ɗ����Ɓv�͂��������点�Ă����B���낢��ƕ��G�ȋC���ɂȂ鎖�����B
�@���X�g������u�V����Musica�v�c�c�̑O�ɑ}������鐡���B�u�l�ԂɎ̂Ă�ꂽ�l�`�����v���u�\�Ԃɖ������p���f�B�[�X�X�i�y���j�̋R�m�v�ɂȂ��Ă��܂��B�u�Y�p�̏��_�v�Ɖ������I�u���r�I�j�X�Ƃ���ɒ����𐾂�4�l�̋R�m�B�u�َ��^�̎l�R�m�v���C���[�W���Ă���̂�����B���W�J�Č����ɏ��C�ł͂Ȃ������ˎq��S���o������4�l�Ƃ���10�b�̓��e���r�F�����悤�ȋؗ��Ă��B���������Ďn�܂�g���A�u�V����Musica�v�̓��W�J�̑�\�Ȃł���W�听�Ƃ�������uEther�i�G�[�e���j�v���ӎ�������ȂƂ������A�قځuEther�v�̃A�i�U�[�łł��ˁB�u�l�͖Y��Ă��v�u�����͏����Ă��v�Ɖ̎�����������Ȃ�������Ȓ��O��X�����Ȃ̂悤�Ɏv���邪�A�t�ł��鉹�͔������A�u����ł��v�u�����炱���v�Ƃ������ɑO�����Ȉӎu���Y���Ă���B�uEther�v�́u�����ĖY��Ă͂����Ȃ��v�Ƃ����̎��ɑ��Ĕے�I�ȋȂ̂悤�ɂ��������邪�A�쎌����Diggy-MO'�����Ƃ���ɂ��uEther�v�́u���菄��։�ƈ��ʂ��������A����Ɉ�ʂ̃n�C���C�g�ɗn������ŁA�₪�Ă͏����Ă����C���[�W�ł��v�Ȃ̂ŁA�C���[�W�Ƃ��Ắu�i���v�����ǁu�s�Łv�ł͂Ȃ��A�Y�p�Ə��ł̉ʂĂɍ��ꂪ�K���c�c�Ƃ����u�F���K�͂̋����Ō����낷�։�v�ɂȂ��Ă��܂��B����Ƃ������V��̃��m�A�y���ȑ��݂ɔ�ׂ�Βn��̃A���R���͕��ɐ�����ĕ����o�H�̔@�����m�ł����Ȃ����A�����̂悤�ȌȂł����L��������u���̌ۓ��v�����邱�Ƃ��ł���BBanG Dream�i�������������j�Ƃ����v���W�F�N�g���ɑ��������A�����Z�߂����ȂɎd�オ���Ă��ĕ��ʂɊ������Ă��܂����B���ꐰ��Ƃ�����ʼn̂��グ�鏉�ɍ��ꍛ��Ƃ���B�u���_�����R�m�v�����_�̕���������삵�Ă���A�Ƃ����|�����Î�����ƂƂ��ɕ��i�J�[�e���t�H�[���j�B
�@���ߊ���̓}�C�S�̈��A�B���C�u�I����A�Z���^�[��D�悷�ׂ��s�����������̂����œ��Ǝ���q���Ȃ��Ȃ������u���O�Ȃ��c�c�v�Ƃ����������Ƃ�����D���ł��B���������͕��O�҂Ȃ̂Ɋ������܂�܂����ĉ��z����������A���ꂭ�炢�̖͂����Ă�����ˁB��q���o���U�C�̃V�[���Œ[����������ƕЎ肾�������čς܂��Ă��邻������{���B���C�[���ŏ���������B���낢�댃�����܂��������ʁA�u�r�ƃ��[�e�B�X�Ɏڂ�����܂����ĊC��Ƃɂ�ނ�����H������ۂ������ȁc�c���Ƃ܂Ȃ����̈����c�c�v�Ƃ������z�ɗ���������Ave Mujica�ł��邪�A�Ō�ɍō��̃��C�u�������Ė����\�\�Ɨ]�C�ɐZ�肩���Ă����Ƃ�����uIt's MyGO!!!!!�v�uAve Mujica�v�A�j�����҃V���[�Y�̐��삪�����Ƃ����j���[�X�ʼn�������������т܂�����B���Ăق����Ƃ͊���Ă������A�����������Ԃ��|����Ƒz�����Ă��������ɍŏI��̃^�C�~���O�Ŕ��\���Ă��ꂽ�̂͒��������I�@�z���ł����Ȃ����AIt's MyGO!!!!!�������͂܂�Ave Mujica�����\�肪�Ȃ��āA������̎艞������}篑��҂����܂����̂ł͂Ȃ����B�������Ɓu���������v�~�܂�Ȃ���A�����ꌗ�ňٗl�Ȃ��炢�q�b�g�����܂�������ˁB�u�������ł͓n�삪����߂��āA�܂�œ����v���W�F�N�g�݂����ɂȂ��Ă�v���Ęb������܂����B�H�u�ɓ]�Z���Ă�������̈�������b���������N���X���C�g3�l�g�ɂ܂��l�^�܂ł���Ƃ������琦�܂����B
�@�u���҃V���[�Y�v�Ƃ����\������@����ɁA���炭It's MyGO!!!!!��Ave Mujica�Ɠ�����TV�A�j���Ƃ��ĕ�������\�肾�Ǝv���܂��B�K���p����w�v�����Z�X�E�v�����V�p���x�݂����Ȍ���ŘA��̉\�������邪�A����Ȃ�u���Ҍ��ꉻ�v���ď������낤���炽�Ԃ�Ⴄ�ł��傤�B�N�[�����ɂ��ẮA1�N�[����2�N�[���A���Ȃ��Ƃ�����ȏ���Ă��Ƃ͂Ȃ��͂��ł��B����2�N�[�����Ƃ��Ă������ɂȂ�ł��傤�ˁB�o���h����TV�V���[�Y�́uAve Mujica�v��5���ڂɑ�������̂ŁA�ЂƂ܂��ʎZ6���ڂ��m�肵�����ƂɂȂ�܂��B����o���h����1�`3���ځAMyGO��4���ځAMujica��5���ڂƂ�������ŁA6���ڂ��}�C���W�̑��҂Ȃ킯������u�}�C���W�n��̒���������Ƃقڕ��ԁv����ɂȂ�܂��B�u�قځv�Ə������̂́A�o���h����TV�V���[�Y�͊�{�I��1�N�[��13�b�\���Ȃ̂ł�����ǁA�����1���ڂ�OVA�Ƃ��Đ�����ɓ������14�b�����삳��Ă��邽�ߑ����1�b��������ł��B���m���������Ă���������킩��܂����AOVA�u�V������I�v�̓K�[���Y�o���h�v�f���L���C�ɏ��������Ă��āu�o���h���ɂ�����Ȏ��オ�������c�c�v�Ƌ������Ɛ��������BRoselia�̐ݒ肪�ł܂��Ă��Ȃ��������ɍ��ꂽ�̂��A����������Ƃ��Ȃ��a���������ċt�ɖʔ����B�������A����Łu�}�C���W�̑��ҁv��2�N�[���ȏゾ�����ꍇ�͖��m�Ɂu��������}�C���W�n��̕��������Ȃ����v���ƂɂȂ�ȁc�c�u�v���e�B�[���Y�������v���p���̕��������Ȃ����v�݂����Ȍ��ۂ��B
�@�Â�����̃t�@���́u����o���h���̑����v��M�]���A�u���W�J���I�������Ăэ��������������4th Season������Ă���I�v�ƋF���Ă����킯�ŁA���������l�����́u�}�C���W�̑��ҁv�Ɩ�������ĒQ���Ă��邩������܂���B�Ȃ��u����v�u�}�C���W�v�ƌĂѕ����Ă��邪�A�o���h����TV�V���[�Y�͈�т��āu���ꐢ�E�̕���v������Ă��邩�痼�҂ő傫���ݒ肪�قȂ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��i�����̃f�U�C�����}�C�i�[�`�F���W�����蕑��ƂȂ�Z�ɂ̐ݔ���V�����������ȂǁA�ׂ��������Ń��t�@�C�����Ă���Ƃ���͂���j�B�����A����́u�|�s�p�v���ƁuPoppin'Party�v�̃����o�[������݂����ȃ|�W�V�����������̂ɑ��A�}�C���W�̓|�s�p�̃����o�[���J���I�o���I�Ƀ`���b�Əo�Ă���V�[������������̂̊��S�ɘe���ɉ���Ă���A��i�Ƃ��Ẵ��[�h���S�R�Ⴂ�܂��B�u�L���L���h�L�h�L�v�����b�g�[����������ɔ�ׁA�}�C���W�͘I���Ɂu�M�X�M�X�h���h���v���������c�c����A��������\����Ⴂ�ɂ���ăM�N�V���N����V�[���������āu�M�X�M�X�v�ȂƂ���͂��������A�}�C���W�����X�g�͂����Ɓu�L���L���v���Ă����犮�S�ɓh�蕪������Ă���킯���Ⴀ��܂��B
�@�������A��Âɍl����Ɩ���o���h����1���ڂ��������ꂽ�̂���2017�N�ł��������8�N�O�A3rd Season����2020�N��5�N���炢�O�ł��B�}�C���W��������Ă����V�K�w������ɋ���������ăT�u�X�N���Ŏ������闬����������Ă��܂����A�u4th Season�𐧍삷������f���Ɂw�}�C���W�̑��҂ł��x��搂������������͑傫�����낤�v�ƃu�V�������l����͎̂��ɓ��R�̂��Ƃ��B�Ȃ̂Ŋ����t�@����[�������邽�߂Ɂu��Â�|�s�p�v�Ƃ����|�s�p�Ƀt�B�[�`���[�����V���[�g�A�j������邱�ƂŖ��ߍ��킹���Ă�Ǝv���܂��B�u��Â�|�s�p�v�A����ɑS52�b�̃V���[�g�A�j���i�����s�R�V���[�Y�̐V��j�A�g�h���Ɂu�}�C���W�̑��ҁv�ƁA�u�V���͎Љ^��q���ăo���h���I�v���W�F�N�g�𐄂��܂����Ă���B���͂��̂��Ƃ������Ƃ��悤�B�܂��܂���K�[���Y�o���h����͏I���Ȃ��c�c�I
�@���҂�����̂͑����ė��N�̏H���A�����Ȃ�ė��N�̏t��������B���mPV�͓��e�ɂ��čׂ����G��Ă��Ȃ����A�u����ԁc�c�����̂��߂ɁA�����̑z���������Ă������c�c�v�Ƃ������Ƃ��ڂ����Z���t�i���m���[�O�H�j�Ɓu�c�킩���Ă�B���W�J�ɂӂ��킵���̎��A��A��������v���Ă������i�����j���ۂ��Z���t���o�Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�u���Ə��i�����j�v��Δ䂳����_���Ń}�C�S�ƃ��W�J��������������|�W�V�����Ɏ��܂邱�Ƃ��\�z�����B�N�x���ׂ��ƍׂ����ݒ�̎C�荇�킹����ςɂȂ邩�瓕�����͍��Z1�N���̂܂܂���Ȃ��ł��傤���B��q���邪�u���W�J��9���ɉ��U����10���ɍČ��������v�Ƃ��������ȃX�P�W���[���ɂȂ��Ă���̂��A���҂̃X�g�[���[���������ނ��߂Ɂu�{���͔N�������炢�ɍČ������ė���ɂ�����肾�������ǔN���֑O�|���ɂ����v��Ȃ����Ƌ^���Ă���B�V�L������V�o���h�͏o�Ă��邩������܂���B
�@�����ĉ����C�ɂȂ�̂��u�k�����P���s�v�APV�ɉf���Ă���X�̓w���V���L�i�t�B�������h�j�A�I�X���i�m���E�F�[�j�A�X�g�b�N�z�����i�X�E�F�[�f���j�ŁA�u�k���O���̂ǂ����v�ł͂Ȃ��u�k���O���̂��ׂāv������ɂȂ�\�������܂��Ă��܂����B�o���h���͂���܂łۂ҂ǂ�i����Łj�ŃO�A���ɍs���Ă��܂����A�����̓C�M���X���w�̋A��A�ˎq�̓X�C�X�ɍs�����ꂻ���ɂȂ�Ȃǁu�C�O�v���ӎ������W�J�����������ATV�V���[�Y�ł����܂ő�|����ɂ��̂͂�������B���Ȃ݂�8�b������X�ŏo�Ă����o�C�g�X���u��{�C���v�́u��e���t�B�������h�l�v�Ƃ����ݒ�Ȃ̂ʼn��炩�̌`�ŗ���ł��邩���B��Ԉ������C�ɂȂ�L�����́usumimi�v�́u���c�܂ȁv�ł����c�c���̃p�[�g�i�[�Ȃ̂ɂ낭�ȏo�Ԃ��Ȃ��A�u�ڃL�c�������̎q�͑��҂̕��łǂ��ɂ����悤�v���ēr���ŕ���o������Ȃ����Ǝא����Ă��܂��B�������C�u�ɂ��o�����邭�炢�Ȃ�������ƗD�����Ăق������B�u�X�݂Ȃ݁v�Ƃ��u�L�쐴���v�Ƃ��u�L��莡�v�Ƃ��A���̂ւ�͂����������ȁc�c�u�L��̋��낵���v�Ȃ�Ă����t���[�o�[���@�艺���邭�炢�Ȃ瓕�����̗c�Ȃ��݂́u�݂������v�Ƃ����o���Ăق����ł��B���Ƃ���Ave Mujica�݂����ȃ��C�u���d���̓W�J�͍T���Ă��炦��Ƃ��肪�������ȁc�c�b�̑O������x���Ђ�����Ԃ����̂͂������ɂ���ǂ������ł�����B
�@�]�k�BMyGO�̍�����u�쒆�̓��t�ݒ���Ăǂ��Ȃ��Ă�낤�H�v�Ƃ����ƋC�ɂȂ��Ă����̂ŁA���̋@��ɏ����������Ă݂܂��BMyGO��1�b�ځA�������H�u�ɓ]�����Ă����Ƃ��������u���������S�[���f���E�B�[�N�ł����v�ƌ����Ă��邩��4���̏I��荠�Ɛ���ł��܂��B�ŁAMyGO���Ƃ���ȍ~�͓��t�����ł��閾�m�Ȏ�|���肪�قƂ�ǂ���܂���B7�b�̃��C�u�ł��|�X�^�[�ɏ�����Ă���̂͊J�Î��Ԃ����ʼn��������Ȃ̂��͂܂�����������Ă��Ȃ��B��̓I�ȓ��t���������Ⴄ�Ɓu�����A���̂Ƃ��̃|�s�p��A�t�����āZ�Z���Ă���Ȃ��H�v���ăK���p�Ƃ̖����������Ă��܂����˂Ȃ��i�}�C���W�ŕ`����Ă���N�̓A�t���̉��U�b���o�Ă������������炻�̂ւȂ�Z���V�e�B�u���j����A���덇�킹�̘J�͂��Ȃ����߂Ɋ������Ă���낤�B���t�l���Ēn���Ȋ��ɂЂ�����肪�|����܂�����ˁB
�@MyGO��9�b�Ō��m�X���t�y���̒�����t��|�X�^�[�������Ă��āA�悤�₭���t���������B�u6��6���i�y�j�v�Ɓu6��7���i���j�v�B�J�����_�[�I�Ƀ}�C���W��2020�N���x�[�X�Ɣ������܂��B������t��ɍ��킹�ė�����ɉ�ɍs���̂ŁA������͂V�[����6��6����7���ł��ˁB�������u���悳���CRYCHIC���Ȃ�v�ƌ������͍̂ŒZ��6��8���i���j�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����10�b���@�ɃL�������݂�ȉĕ��Ɉߑւ��B�ēɂ��u1�����͌o���Ă��Ȃ��v�Ƃ������ƂȂ̂ŁA7���̓����炢���Ǝv����B�ڂ̓s���ŏȂ��ꂽ���A���̃|�G�g���[���[�f�B���O����Ă����Ԃ����ƒ����āu�����J�v�ɂ��Č����͒Z�����ς����Ă�7�����{���ɂȂ�܂��B�ŏI�b��13�b�AAve Mujica�̃}�X�J���[�h�ɂāu7��25���i�y�j�v�Ƃ܂����t���o�Ă���B�ɂ�ނ��u����I�ڃ��C�u�v�ƌ����Ă���̂ŁA���̓������W�J�̐����ȃf�r���[�ƌ��Ă������낤�B�ˎq���u���v�Ɂu�S���A�Y�ꂳ���āc�c�v�Ɠd�b�����̂�5���̉��{���炢�ŁA6�����Ƀ����o�[�W�߂��I�����A��������1�������炢�|���ăf�r���[�̏��������Ă������ƂɂȂ�BMujica1�b�ڂ͒ʊw�V�[�����Ȃ����Ƃ��l����Ƃ܂��ċx�݊��Ԓ��A8���̏I��肮�炢��������Ȃ��B2�b�ڂ͒ʊw�V�[��������̂�9���ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�ŁAAve Mujica�̉��U��9��20���B�j���͏�����Ă��Ȃ���2020�N�x�[�X�ƍl����Γ��j���ł��ˁB�����čŏI��ŕ`���ꂽMujica�̃~�\���M�A�i���C�u�j��10��18���i���j�B���U����4�T�Ԍ�A�܂�5�b�`13�b�͈ꃖ�����炸�̊ԂɋN�������o�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B5�b�Ń��u���u���W�J���U���Ă���ꃖ�����炢�o��ˁv�ƌ����Ă������Ƃ�6�b�ŊC�邪�u���ꂩ��ꃖ���v�Ɣ������Ă������Ƃ��l����ƒ��낪����Ȃ����A���C�u�̏����i�i���̑ł����킹�E���̎�z�j��`�P�b�g�̔̔����Ԃ��l������ƃ~�\���M�A�̓��t�ݒ�͖{�������ƌ��A12�������N��1�����炢�ɂ�����肾������Ȃ����H�@�ł��}篑��҂����܂��āA�u�r���ŃN���X�}�X�̘b����ꂽ������V��̘b��11���X�^�[�g�AAve Mujica�̃A���R����10���ŏI��������Ƃɂ��悤�v�݂����Ȃ��Ƃ��l�������ʃ^�C���X�P�W���[�������������Ȃ��Ă��܂����c�c�Ƃ����ӂ��ɉ��߂��Ă��܂��B
�@�ǂ���������ł���A���t���������ꂿ������ȏ�}�C���W�̃A�j���́u�������H�u�ɗ��Ă��炴�����蔼�N�ԂɋN�������o������Ԃ��Ă���i���R�Ȃ����z�V�[���͏����j�v���ƂɂȂ�܂��B���e���Z������1�N���炢�͌o�߂��Ă���C���ɂȂ�Ȃ��B�����Ɠ��������m�荇���O�̒��w������ɂ��Ă͓��t�����ł���ޗ����قڂȂ��A��G�c�ɋG�ߒP�ʂő����邵���Ȃ��B�ˎq���o���h���n�߂�L�b�J�P�ɂȂ����u���m�X���y�Ձv�̋�̓I�ȊJ�Î����͕s���ł����A���m�X�ɓ��w�����u�q�c�܂���v���u������ς������v�Ɗ���ăo���h�iMorfonica�j��g�݁A�t�@�[�X�g���C�u���s����ɏI����āu�o���h���Ă����Ɗy�������̂��Ǝv���Ă��̂Ɂc�c�v�ƕs�啅�ꂠ�����U�̊�@�I�ƂȂ���Ȃ�₩���ŏ��z�����J�����ђ������m�X���y�ՂŃ��C�u�A���x�͑听���\�\���ė�����l����Ƃ���Ȃ�ɓ������o�߂��Ă���͂��Ȃ̂ŁA4���̏I��肩5���̂͂��ߍ����Ǝv���܂��B�Ȃ̂Ő���i�ˎq�̕�e�j���S���Ȃ����̂��A�ˎq���������Əo��̂��A�������t���B�����u�t���e�v�Ƃ����Ȃ����邭�炢�����ACRYCHIC�̎�Ȋ��������͏t�B�ŏ��ōŌ�̃��C�u���J�Â��Ă���Ԃ��Ȃ����U���Ă��܂��̂ŁA�Ă�H��~�̎v���o���܂���������܂���B�����̗{�����S���Ȃ��ĒP�g�㋞���A�u���c�܂ȁv�Əo����āu���v���`�Łusumimi�v�Ƃ������j�b�g��g��ŃA�C�h���f�r���[������̂����̏t�B�t�͏o��ƕʂ�̋G�߂Ƃ͂����C�x���g���W�����߂��Ă���c�c�I
�@Morfonica�����C�u�̗\��������ς��l�߂��ċx�݂Ɍ����āu�ă��j�J�v��v��������l�q��`�����wBanG Dream! Morfonication�x�Ƃ����X�s���I�t��i������̂ł����A�uCRYCHIC�����U������̉āv���Ǝv���Ċς�Ɠ����Ƃ͈قȂ銴�G�������Ė��킢�[���B��҂̊J�n1��������A�w�i�ɂ���Ɩr���`���b�Ɖf���Ă���V�[��������܂����ǁA�ǂ�ȉ�b���Ă邩�z������Ə����݂��ɂ��Ȃ�B�ˎq���������𑲋Ƃ���܂ł͌��m�X�ɍݐЂ��Ă������ƂɂȂ邪�A���̊Ԃ���ɕt���܂Ƃ��đ����T�������������낤�ȁc�c�H�u�ɍs�����́A�w��̖������邾�낤������Ɗ�����킹�Ȃ��čςނ���Ƃ����ʂ��������̂ł́H
�@���w�𑲋Ƃ��č��Z�ɐi�w�����Ƃ���ŏˎq�Ɠ��͍ĉ���ʂ������A�b�������悤�Ƃ��铕���ˎq�����₵�Ă��܂��B����ȏ��S�̓��ɘb�������Ă����̂��ςȎ����ɓ]�����Ă��������������\�\�Ƃ����`��MyGO�q�����Ă����B�U��Ԃ��Ă݂��CRYCHIC�����U������̉Ă���~�ɂ����Ă͋��炯�ł��ˁB���U���Ă�����珑�����ƂȂ�����A�ƌ���ꂽ�炻��Ⴛ���ł����ǁB���Əˎq�̃N�\�e����쐶���͒�3�̏t���獂1�̏H�܂ŁA��������1�N�����������ƂɂȂ�܂��B�Ō�̕��͏��i�����j�̕����ɓ]���荞��ŕ��u���Ă���������ۂ͂����ƒZ�����B
�@��������ƁA�uCRYCHIC�͂ЂƏt�����ۂ��Ȃ������i�Œ��ł�1����������ƁA�Z����1�������炸�j�v�uMyGO�͈����������o���Ă���w�Ȃ�ŏt���e������́I�x�܂�1�����|�����Ă��Ȃ����炢�v�u�w���悳���CRYCHIC���Ȃ�x���玍���J�̃��C�u�܂ł�1�����|���邩�|�����ĂȂ������炢�v�u�w�S���A�Y�ꂳ���āc�c�x����Mujica�̃f�r���[�܂ł�2�������炢�A��������1�������x�Ń����o�[���W�߁A�c��1�������������Ԃɔ�₵���v�uMujica�̃f�r���[������U�܂ł�2�������炸�A���U����Č����܂ł�1�������炸�v���Ċ����ɂȂ�B�����ʼn��U������ۂ̂���Ave Mujica����CRYCHIC�̕����Z���������i�������Ԃ��܂߂��Mujica��3�������炢�ۂ����j�ȁA�Ƃ킩�����肵�Ėʔ����B
�@�}�C���W�̃X�g�[���[�̓K���p���甼�ΓƗ����Ă��邽�߃N���X����v�f�͂��܂�Ȃ����A���͍쒆�̎������Č��m�X�Łu���y�Ղ𒆎~�ɂ��悤�v���đ��������������Ȃ�ł���ˁB��N�̉��y�Ղōs��ꂽ���j�J�̃��C�u�i�ˎq���ڂ��P�����Ă�����j��������蔏�q�ő������������A�Ƃ������R�ŗ�����������I�ɒ��~��錾���Ă��܂��B�[���ł��Ȃ����j�J�̖ʁX�͒��~�P��Ɍ����ď����������哱���܂��B�ŏI�I�ɒ��~�͓P��A���m�X���y�Ղ͖����J�Â����̂ł����A���ꂪ�A�j���̉��b�ڂ�����ɓ�����o�����Ȃ̂��A���덇�킹����ς����炩�n�b�L�����Ă��܂���B�J�Î����͏t�̂܂܂݂���������AMyGO��1�b�`9�b�̊Ԃ��Ǝv����B���邢�͈����̓]�����O�ɂ������o������������Ȃ��B�K���p�ł͔N�x���Ƃ̏o�������u�V�[�Y���v�Ƃ����P�ʂŋ���Ă���A�u�ˎR�����v�����|�s�p�̃����o�[�����Z1�N�����������i�A�j����1���ځj���V�[�Y��1�A���Z2�N�����������i�A�j����2���ڂ�3���ځj���V�[�Y��2�A�����ă}�C���W�̏o�������V�[�Y��3�ɊY�����܂��i������CRYCHIC�̌����E���U�̓V�[�Y��2�̎����j�B���m�X���y�Ւ��~�����̓V�[�Y��3�̂͂��߂�����Ɉʒu���Ă���B�Ȃ��A�j����2���ڂ�3���ڂ͐��m�ɂ��u2nd Season�v�u3rd Season�v�ƕ\�L����̂ł����A�o���h���t�@���̊Ԃ��Ɓu3rd Season�v�Ɓu�V�[�Y��3�v�̈Ӗ������m�ɈႤ���߂�₱�����B���܂�����ȊO�ł͂Ȃ�ׂ��u2nd Season�v��u3rd Season�v�Ƃ����\�L���g��Ȃ��悤�ɂ���̂�����ł��B
�@�V�[�Y��3�̑傫�ȏo�����Ƃ��āA�`���ł������G�ꂽ���uAfterglow�̉��U�����v������B�A�t���̖ʁX�����Z3�N���ɂȂ������Ƃ�����A������i�H�̂��Ƃ��������č��Z�݊w���ɗL�I�̔������낤�A�Ƃ����b�ɂȂ�܂��B�A�t���̓v���o���h�ł͂Ȃ��c�Ȃ��݂��W�܂��č�����A�}�`���A�o���h�Ȃ̂ʼn��U���������ĂȂ����̋��ڂ����Ȃ�B���Ȃ�ł����A�ꎞ�قډ��U�X���X���̏�ԂɊׂ��āA��������Č�������\�\�Ƃ����̂��V�[�Y��3�ł̑�܂��ȗ���ł��B�Č������݂̃G�s�\�[�h������Ă����̂��ߑւ��̌ゾ������ŁAMyGO��10�b������ł��ˁBMyGO����ςȎ����Ɏ��̓A�t������ςȂ��ƂɂȂ��Ă����A�Ƃ������������������i�A�t���̉��U������{�i�I�ɒNjy�����̂�MyGO�̕����I���ゾ�����j�B�����A��q�����ʂ�A�t���̓A�}�`���A�o���h�ł�����A�u�Č����v�Ƃ����̂����X�̘b�ł����đΊO�I�ɂ́u�����������U���Ă��Ȃ��v���ƂɂȂ��Ă��܂��B�������̉āA�A�t���������ɉ��U�����m���Ă����痧���̏�͂Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă������낤�ȁc�c�B
�@���Ȃ݂ɃK���p�̓\�V���Q�̏�Ƃ��ăo�����^�C���␅����n���E�B����N���X�}�X�Ƃ��������A���̋G�߂Ɉ��C�x���g�A������u�G�߃C�x���g�v�����傭���傭�J�Â����̂ł����A���̂ւ�̎��n���Ɋւ��Ă͞B���Ƃ������p�������Ƃ������u����͂���I�@����͂���I�v�Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂��B���Ƃ����Ԍ��C�x���g�A�u�����炢�Ă��鎞���͂܂��C�M���X�ɗ��w���������͂��̈��������R�Ɗ���o���Ă���v�Ƃ������m�Ȏ���̔P�ꂪ�����Ă���i�Ă��A�Ăɂ悤�₭�uMyGO!!!!!�v�Ƃ����o���h�������܂����͂��Ȃ̂Ɂu�}�C�S�݂̂�ȁv���Ԍ��ɗ��Ă��邱�Ǝ��̂��������j���A�ׂ������Ƃ��C�ɂ����Ⴂ���Ȃ��B�����āA����Ȃ��ƋC�ɂ��Ă��烀�W�J�i�Č�����j�̐����C�x���g�Ȃ�ăV�[�Y��4�ɂȂ�Ȃ��Ɣq�߂Ȃ����ƂɂȂ邼�B�݂�Ȃ��������ł��傤�A���W�J�̖ʁX�����l���ɕY�����Đ����p�ŃT�o�C�o������g���`�L�C�x���g���c�c�I�@�O�̂��ߏ����Ă����ƁA������K���p�ł��u���l���ɕY�����ăL���X�g�E�A�E�F�C����v�Ȃ�ăs�R�݂����ȃG�s�\�[�h�͂���܂���B�p�X�p���̃����o�[��TV�̊��Ŗ��l���ɍs���ăT�o�C�o�������𑗂�C�x���g��������x�B�����u�V���̃������[�X�^�@���C�g�̃\�V���Q�ɂ̓}�W�ł���܂������ǂˁA�u���䏭���Y���L�v�Ƃ������l���Y���C�x���g���B�g���`�L�ƌ��������ăV���A�X�Ȍ����肪��������A�����ƃI�`����������ƂȂ��Ȃ���ې[���C�x���g�ł����B
�E�A�}�v�����w�\�EX�x�ς܂����B
�@�u�\���b�h�E�V�`���G�[�V�����E�X�����[�v�i�����Ȃǂ́u���肳�ꂽ���v�ɂ�����Ɍ���`���X�����[�j�Ɩ��ł��ꂽ�g�\�E�h�V���[�Y��10��ځB�A�����J�ł�2023�N�Ɍ��J���ꂽ���A���{�ł̌��J��2024�N�B�g�\�E�h�V���[�Y��2004�N�ɃX�^�[�g���Ă���̂ŁA���N�͂��傤��20���N�ł����B�V���[�Y�����J���ɕ��ׂ�Ɓw�\�E�x���w�\�E2�x���w�\�E3�x���w�\�E4�x���w�\�E5�x���w�\�E6�x���w�\�E �U�E�t�@�C�i���x���w�W�O�\�E�F�\�E�E���K�V�[�x���w�X�p�C�����F�\�E �I�[�����Z�b�g�x���w�\�EX�x�ɂȂ�܂��B�u���[�A����Ȃɂ���́H�@���ԂɊς�̃_�����ȁc�c�v�Ɗ�������������邩������܂��A���̂Ƃ���w�\�EX�x���炢���Ȃ莋�����Ă���܂��ȃX�g�[���[�͗����ł��܂��B�u�Ȃw�F�����m�́x�݂����ȕ��͋C�Œm���L�������o�Ă����ȁc�c�V���[�Y�t�@���Ȃ�w�������x���ĂȂ�Ƃ���Ȃ̂��H�v�Ǝ���X���Ă��܂��V�[�������邾�낤���ǁA�ނ���V���[�Y�m���Ȃ�������̓W�J�ǂ߂Ȃ��ċp���Ėʔ����\���������ł��B
�@���a�Ɏ��߂���A�]�����Ȃ��j�u�W�����E�N���C�}�[�v�B��]����ނ́A�����҂̏W���Œm�荇�����u�w�����[�E�P�X���[�v����u���b�N�E�W���b�N���݂��ň�ҁu�Z�V���A�E�y�_�[�\���v���Љ��āu�{���ɂ���ȃE�}���b������̂��낤���H�v�Ɣ��M���^�Ȃ������p���邽�߉��H�y�X���L�V�R�ւƌ������B�������|�����A�ӎ������߂������ɂ͂����u��p�v�͊������Ă����B����Ő����Ȃ��炦�邱�Ƃ��ł���\�\��т��B����Ȃ��W�����͑��z�̎�p����A����Z���V�A�ւ̃v���[���g����Ɏ{�݂��������A�����͂��ʂ��̊k�Ɖ����Ă����B�u��p�̗l�q�v�Ƃ��Č�����ꂽ�f���͊����i��DVD�ɉ߂����A���Ɋ����ꂽ��т������Ă݂�ΊJ���̍��Ղǂ��납�����������`�Ղ���Ȃ������B�S�����\�������I�@�{���V���Ղ������ŃL�����W�����́u���͎ҁv�̎����č��\�ƈ�s�̏��݂�˂��~�߂�B�W�����E�N���C�}�[�A�ނ����̓A�����J�e�n�ŗ�I�ȁu�Q�[���E�l�v���J��Ԃ��C�J�ꂽ�T�C�R�E�L���[�u�W�O�\�E�v�������̂ł���c�c�I
�@�Ƃ����킯�Łw�W�O�\�E�@�{��̍��\�t�F�E���x�ȃG�s�\�[�h�ł��B�V���[�Y�S���ςĂ���l���Ɓu�ߋ��ɂ������悤�Șb�i�d���̋������悤�ȁu�_��ᔽ�v���w�E���ĕی��������Ƃ��Ȃ������ی���Ђ̃N�\�Ј��ǂ��E����G�s�\�[�h�j�������ȁc�c�v���Ďv���o���Ă��܂��Ă��܂�V�N���͊����Ȃ��B��������10�������Ă�ƃ}���l���ȕ������o�Ă���͎̂d���Ȃ��ł��B���ς�炸�W�O�\�E�̎d�|����Q�[���͈���ɂ܂�Ȃ��A�u�ɂ����v�x�͉ߋ��C�`�̃��x���ɒB���Ă��邩������܂���B�ǂ������Ό��_��A�A�������������p�^�[���ȓW�J�B�V���[�Y�̔M�S�ȃt�@���A���ɃW�����E�N���C�}�[�i�g�r���E�x���j���D���Ȑl�A���邢�̓V���[�Y�̒m�����قƂ�ǂȂ��l�͊y���߂邪�A���[�ɃV���[�Y��m���Ă���l���Ɓu�܂����ꂩ�c�c�v���ăm���Ȃ��^�C�v�̉f��ł��B
�@�u�ŁA���������g�\�E�h�V���[�Y���Ăǂ�ȉf��Ȃ́H�v�Ƃ����₢�ɓ����邽�߃V���[�Y�S�̂�U��Ԃ�܂��B�l�^�o���S�J�Ȃ̂ł��ꂩ��ς�\��̐l�͔���Ă��������B���J���ɍs���܂��ƁA�w�\�E�x�i2004�j�\�\�V���[�Y�̎n�܂�Ȃ̂łƂ肠�����������Ă����������C�C�ł��B�E�l�S�u�W�O�\�E�v�ɂ��čׂ����������A���X�g�ł��̐��̂����������҂̃W�����E�N���C�}�[���Ɩ������B�W�O�\�E�͎c���ȃQ�[�����d�|���邪�A��̐▽�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��u�����铹�v�͈ꉞ�p�ӂ��Ă���B�������ꂪ�u�r��藎�Ƃ��v�Ƃ������ߍ��Ȏ�i�ł���Ƃ��������B���̂��N�����W�O�\�E���u�Q�[���I�[�o�[�v�ƍ����ċ����Ă����Ƃ����1��ڂ͏I���B���Ȃ݂Ɂw�\�EX�x�͎��n��I��1��ڂ�2��ڂ̊ԂɈʒu����G�s�\�[�h�Ȃ̂ŁA���e�����Ō����Ȃ�w�\�EX�x�Ƃ��������w�\�E1.5�x���B�w�\�E2�x�i2005�j�̓W�O�\�E���x�@�ɒǂ��l�߂��Ĉꎞ�͍S������邪�A�Ȃ�₩���ő{�����̗���������㩂ɛƂ߂�B�W�O�\�E�̋��͎҂ł���u�A�}���_�E�����O�v�����o�ꂷ��G�s�\�[�h�B�g�\�E�h�V���[�Y�A��Ƃ̓W�O�\�E�i�W�����E�N���C�}�[�j�Ȃ�ł�����Nj��͎҂���p�҂��͕�Ƃ�炪���X�Əo�Ă���̂ł�����E���Ȃ��Ȃ��Ă�����ł���ˁc�c�����������ׂԂ肪�y���߂�l�����̃V���[�Y�ł͂���B
�@�w�\�E3�x�i2006�j�A���̂ւ�b������g��ł���̂łȂ�ׂ��Z���Ԃň�C�Ɋς邩�A�������Ȃ��王�����������g�ł��B�c�s�i�S�A�j�V�[���̃O�������G�X�J���[�g���Ă���B�W�O�\�E�͕a���Ȃ�i�s���A�����܂Ƃ��ɐg���������Ȃ���ԂɊׂ��Ă��܂��B���͎҂̃A�}���_�����s�ƂƂ��ē�����邪�A�ŏI�I�ɓ�l�Ƃ����S����B�A�}���_�Ɋւ��Ă͂������䂪�c��A�����Ԍ�ɂȂ��ĉ������邱�ƂɂȂ�܂��B����ȍ~�́u�W�O�\�E�̎���v�ɓ�����G�s�\�[�h�ŁA�W�����E�N���C�}�[�͉�z�V�[�������n��I�ɉߋ��ɓ�����G�s�\�[�h�ɂ����o�ꂵ�Ȃ��Ȃ�B�w�\�E4�x�i2007�j�̓W�����̈�̂���U����V�[������n�܂�A�݂̒�����ނ́u�⌾�v�����߂��e�[�v�����������B�o��l���̒��ɃW�����̈�u���p���u�W�O�\�E�̌�p�ҁv���������Ă���A�Ƃ����W�J�Ȃ�ł����A4��ڂł����ԓo��l���������Ă������ߏ������Ȃ��ƒN���N�����킩��Ȃ��č������邱�Ɛ��������B�w�\�E5�x�i2008�j�̓Q�[���̐��Ҏ҂ƂȂ����Y�����Ƃ���l�����u�����A�W�O�\�E�̌�p�҂���Ȃ����H�v�Ƌ^���đ{������b�B�W�����̌��Ȃł���u�W���E�^�b�N�v���W�����̈�i�����V�[����������̂́A���g�����Ȃ̂��͌����Ȃ��B3�ȍ~�͂���Ȃӂ��ɖܑ̂Ԃ�`�ʂ������ł��B�u��p�ҋC���̂����v�́w�\�EX�x�ɂ��o�Ă��邪�A�v���Ԃ�߂��Ė��O�o���ĂȂ������B�w�\�E6�x�i2009�j�̓A�}���_�ɂ܂���A�W�����ڂɂ����W�����̈�i�Ƃ������������������Ă����B�w�\�E �U�E�t�@�C�i���x�i2010�j�́u�W�O�\�E�̌�p�ҁv�����鑈���ɋ�肪���G�s�\�[�h�ŁA�u�����Ԙb�����G�ɂȂ��Ă��܂���������ȏ㑱���͍��Ȃ��v�Ƃ����A�����J���̃R�����g��M���ē��{�̔z����Ђ��u�U�E�t�@�C�i���v�Ɩ��ł������ʁu�I���I��鍼�\�v�ɂȂ��Ă��܂����B3D�f��Ƃ��Č��J����邱�Ƃ�O��ɍ������i�Ȃ̂Łu���킪��ʂɌ������Ĕ��ł����若��̐�[����ʂɔ���v�O���V�[���������B�^�̌�p�҂͂��������N�Ȃ̂��\�\�Ȃ���Ȃ�ɂ��u�����ҁv�Ƃ��č��ꂽ��{�Ȃ̂ŁA�V���[�Y�̒��ߊ���ɑ����������X�g���}����B�����Ɂu�W�O�\�E�̌�p�҂��ǂ��̂����̂��Ęb�ɂ����t������Ȃ��Ă����ȁv���ăz�b�Ƃ��܂��B
�@�w�W�O�\�E�F�\�E�E���K�V�[�x�i2017�j��7�N�Ԃ�ɐ��삳�ꂽ�V���[�Y8��ځB�u�l�C������߂��ďI���Ȃ��v�Ƃ����q�b�g�V���[�Y���L�̔߂��݂�w�����n���ɂȂ�܂����B�W�����E�N���C�}�[�̎��ォ��10�N�ȏ�o�����Ƃ����̂ɁA�܂����Ă��u�W�O�\�E�v��f�i�Ƃ������I��������������B���O�̃W�����ƕt����������������p�҂ɂ��ƍs���A����Ƃ��W�����{�l�Ƃ͂܂������ړ_�̂Ȃ��͕�Ƃɂ����̂��H�@�ꉞ�u�d�|���v���p�ӂ���Ă��āg�\�E�h�V���[�Y�炵���o���ɂ͂Ȃ��Ă��邪�A�W�O�\�E�́u���ꂴ���p�ҁv���V���ɐ����Ă���Ƃ����u�������������Ă�I�v�ȓW�J�ɃQ���i�����܂��B�w�X�p�C�����F�\�E �I�[�����Z�b�g�x�i2021�j�͓���2020�N�Ɍ��J�����\�肾�������A�R���i�Ђ̂�����1�N�x���2021�N�Ɍ��J���ꂽ�B�u�I�[�����Z�b�g�v��搂����������Ă���܂ł́g�\�E�h�V���[�Y�̐ݒ�͂قƂ�ǃX�g�[���[�ɗ���ł��Ȃ��B�u�W�O�\�E�̌�p�ҁv�]�X�ɂ��������E���U�����Ă����̂ł����͗ǂ������ł����ǁA�v�́u�W�O�\�E�̎����^�����͕�Ɓv�̃G�s�\�[�h�Ȃ̂œn�슴�������B�g�\�E�h�V���[�Y�͊�{�I�Ɉ��l��W�I�ɂ��āA�������u�K������������E���킯�ł͂Ȃ��v�_�Ŏd�|�l�Ƃ��Ŏ�l�Ƃ��u���b�N�E�G���W�F���Y�Ƃ��Ƃ͕��j���قȂ�i���肪�s��Ȋo��������ΐ������т���I�����͗^����j�̂ł����A�w�X�p�C�����x�́u�Q�[���v�Ƃ������u���Y�v�̃��[�h�������ĒP�Ȃ�u���Ȏd�|�l�v�ɂȂ��Ă����ہB�Ƃ�������p�҂��������Ă���A���́u���₵�ď��Y���邽�߂ɃQ�[��������Ă�v�p�^�[���������A�u������ڑO�ɂ����W�������_�������̂悤�ɐl�X�֎�����^����v�Ƃ��������ȋ��C�ɔ�ׂĘ��������@�ɕt����ȁB
�@�ŁA�b��߂����w�\�EX�x�i2023�j�B�u����ς�g�\�E�h�V���[�Y�Ƃ�������W�����E�N���C�}�[���낤�v�Ɗ�����Č�p�҂��̖͕�Ƃ��̂��o�Ă��Ȃ��ߋ��҂ɂ��Ă���킯�ł��B���͎҂̃A�}���_��A��Ɍ�p�Ҍ��ɖ����o��^�L�������o�����܂����A�w�\�E�E���K�V�[�x�݂����Ɂu�V���Ȍ�p�ҁv�������Ă��邱�Ƃ��Ȃ��t�@���T�[�r�X�ɓ����������e�ɂȂ��Ă���B10������钷���V���[�Y�Ȃ���A���̓W�������Q�[���}�X�^�[�R�Ƃ��ĐU�镑���G�s�\�[�h�̓R�������Ȃ�ł���ˁB����܂ł̃G�s�\�[�h�ł͂ǂ���ϑ��I�Ȗ����������Ă����̂ŁA�ӊO�Ƃ��������R���߂����|�W�V�����ŃX�g���[�g�ɃQ�[�����^�c����l�q�͕`����Ă��Ȃ������B�V���[�Y�̐ݒ���悭�m��Ȃ��V�K�̐l���A�u�w�C�R���C�U�[�x��w�r�[�L�[�p�[�x�݂����ȁw�r�߂Ă����I�b�T�������o���z�������x�n���̉f��Ȃȁv�Ǝv���Ίy���߂邩������Ȃ��B���Ȃ�O�����V�[��������̂ŁA���������̂��t���Ȃ��l�͂�߂����������ł����c�c�B
�@�܂Ƃ߁B�V���[�Y��i�Ȃ̂ŏ����̕��͂ǂ����Ă��u����ɂ����v�������Ă��܂����낤���A�O���ϐ����������Ă���̂ł���Ζ��Ȃ��ς����e�Ȃ̂ŋC�y�Ƀ`�������W���Ă݂Ă��������B�Ƃ���ő��҂́w�\�E11�x�͍��N9���Ɍ��J�\�肾�����̂ł����A�u���C�I���Y�Q�[�g�ƃv���f���[�T�[�w���Η����Ă���v�����Ő��삪�i�܂��A���J�\�肪�L�����Z���ɂȂ��Ă��܂����炵���B�w�\�E11�x�A�ŏ��̌��J�\���2024�N9���ŁA��������2025�N9���։����ƂȂ��Ă����̂ł����A����u����v�Ƃ����L�l�Ɂc�c���e�ǂ������ł͂Ȃ��o�c���x���̝��ߎ��������������ŁA�c�O�Șb���BX�͐����҂����邩��A11�Łu�Z�Z�̋t�P�v�݂����ȃG�s�\�[�h�����̂��ȁA�Ƒz�����Ă����̂ɁB���ƁA�u�W�O�\�E�̌�p�ҁv�͐����s�����܂߂Č���5�l���炢�̌�₪����̂ŁA�S���W�߂ăo�g�����C�������J�Â�����ꕔ�̃t�@���͊�Ԃ�������Ȃ��B����A�ǂ��l���Ă��V�i���I���܂Ƃ܂�Ȃ��Ƃ������ʔ����b�ɂ͂Ȃ肻�����Ȃ��A���Ă����v���I�Ȍ��_������̂ł�����ǂ��B
�E���背�X�B
�@�L���R�m��Ȃ������̂œǂ݂ɍs������ʔ��������B�ǂݐ�Ȃ�Ă͂̐������������ǁA�A�ڂ������������ł��ˁ[
�@������̃z�X�g�����������������Ȋ������o�Ă��ėǂ��������A�����ȘA���Ƃ̃o�g����`���Ăق����Ȃ��A���Ďv���܂��B
2025-03-23.�E�}���K������10���N���Ŕz�M���ꂽ�ǐ��u������ځ@�L���R�v���S���Łw�n�U�炷�x�������̂Ōy���ɃV�F�A�������ĒÂł��A�����́B
�@�i���g��ɔ��������̈����ł�����s�����������A�u�����v�ƌĂ��悤�ɂȂ��������ŁA������̂��߂ɋ���q�����쎎�����J��Ԃ��Ă��鏗�����m�u�L���R�v�A�l�Ă�Łu������ڃL���R�v�B3�̍����瓁��U����Ă����ƍ��ꂷ��ޏ��͂�����A�̕��꒬�Ő��r�̏������m�Əo��\�\���Ă����E�����ȕS���\�[�h�E�A�N�V�����ł��B�u�����v������̌��ꊴ�o�͐X���r���S�̃f�r���[���w�����n���ԁx��A�z������B�ȂɂԂ�ǐȂ̂Ŏ�l���ƃq���C���̈������n�܂����Ƃ���ŏI����Ă��ĕ�����Ȃ����A�A�ڂɌq���邩������Ȃ��̂ňꉞ�������Ă������B
�E�wBanG Dream! Ave Mujica�x��12�b�uFluctuat nec mergitur.�v�A�\���㎟��i�ŏI��j�Ń��W�J�ƃ}�C�S�����̃��C�u���s���K�v������̂ŏ����͍���łقڕЕt���͂��c�c�ƌő������݂Ȃ��猩���܂����B�r�{�̓V���[�Y�\����S�����Ă���u���ނ�ɂ��v�AIt's MyGO!!!!!���Ƃ��́u�Ȃ�ŏt���e������́I�v��7�b����|�����l�ł��B����ȊO����1�b�A3�b�A13�b������Ă���BMujica��1�b�Łu�㓡�݂ǂ�v�Ƌ������ċr�{�������Ă��邪�A�P�Ƃł��̂�12�b�����ł��B
�@�`���A��`�ɏ�����L��Ƃ̎ԁB���Ɨp�@�Œ��̐g���̂܂܃X�C�X���������ƂɂȂ����ˎq�B�^���b�v�ɑ����|���悤�Ƃ����ޏ��̔]���ɂ���܂ł̓��X���悬��B�^���ɍR�����Ƃ��邽�ё����ɓۂݍ��܂�Ă����c�c�������܂��ۂݍ��܂��̂��H�@�Z�������̖��A�X�C�X�s�������ۂ��ĒE���B�������ɐl�ڂ̂���ꏊ�ŏ��q��������艟�����Ė������s�@�ɏ悹��킯�ɂ��������A�_�����Ō�����L��Ƃ̎g�p�l�����B�������ŗ͐s����I��ł�����ʕ�Ė����N�җ���őߕ߂��ꂩ�˂Ȃ�����d���Ȃ��B���ǖL��̗}�����āu�ˎq����l�����]���v���Ƃ��O��Ő��藧���Ă��邩��A�ˎq����e����̂��Ⴖ��n���Ղ��������~�߂��闧��̐l�Ԃ����Ȃ���ł���ˁB������OP�A�Ȃ��uKiLLKiSS�v�ł͂Ȃ��uGeorgette Me, Georgette You�v�I�@���i��ED�ŗ����Ȃł��B�u�����I������̂��A���������ȁc�c�̊�2�����v�ƃ{�P�����Ȃ邪�A�P��OP��ED�����ւ�����ꉉ�o�ł��ˁB�����̃A�j���w�M���h�̎�t��ł����A�c�Ƃ͌��Ȃ̂Ń{�X���\���������悤�Ǝv���܂��x���AED���R�~�J���Ȃ̂ŃV���A�X�Ȉ������ƕ��͋C������Ȃ����炽�܂ɂ���Ă��܂��B
�@A�p�[�g�A�ׂ����o�܂���������ăt�F���[�ɏ���ē��������ˎq�B�Ȃ�Ƃ��t�F���[�̉^�����炢�̎莝���͂������炵�����A�c�����u���̗܁v�ɂȂ��Ă��܂����ޏ������܂��ܒʂ肩�������^�N�V�[���悹�Ă����B�L��ƂƊW�̂���^�]��炵���A�O�p�Ƃ̌���ɂ��Ă����y�B��Ƃ͖{�y�Ɉ����z�����Ă������ɂ͂��Ȃ��炵���B�����A�ŋ߂ɂȂ��Ďo�̕����A���Ă����A�Ɓc�c���ǁu�{���̏��v�Ƃ͍ĉ�Ȃ�����ł����A����ς肱�ꓖ���̃v�������Ɨ{������Ȃ��āu�o�q�̖��̏��v���S���Ȃ��Ă�����Ȃ����ȁB�莡���爴�����ꂽ�Ƃ��ڂ����ʑ��̊Ǘ��ɏ]�����Ă��������ɁA�ǂ������������Őڂ��Ă������킩�炸�u��������v�Ƒ��l�s�V�ȌĂѕ�������ˎq�̎p���Ȃ��B�������g�̌�����u�莡�̉B���q�v�u���̃t�������ċ߂Â����v�u�ˎq�Ƃ̎v���o�͂Ђƈ��肵���Ȃ��v�������m�F���ċ������A�ˎq���~���Ă����̂́u�w���x�������鏉���̉��y�v�Ȃ̂ő�Ƃ��Ă͖��Ȃ��B�S�O�������̎�����������ē����s���̃t�F���[�ɘA��Ă����V�[���A�u�b������I�v�Ƃ������т��܂�ܓ�l�̏����������Ă��ď��Ă��܂����B
�@�ˎq�̓t�F���[�̍b�Łu������������ł���[�I�v�Ƌ��сA�o���h����肽������o���h��g�ނ̂��ƕ������߂�B�ˎq�̓v���C�h����������l�O�ő吺���o���悤�Ȃ͂����Ȃ��^���͕��i���Ȃ��̂ł����A���ƈꏏ�ɕ������ɂ����Ƃ��ƁA�����ƈꏏ�Ƀt�F���[�ɏ�����Ƃ������吺�ŋ���ł��ł���ˁc�c�ˎq�Ə����A�܂��܂������荇���Ă���Ƃ͌����Ȃ���l�ł����A�ˎq���������S����������̂ł͂Ȃ����B�����Đ[��̖L��@�Œ莡�Ɍ������ĖL��Ƃ���o�Ă������Ƃ�錾�A���肰�Ȃ��u�����l�̂��ƁA��낵�����肢���܂��v�ƃN�\�e���������t���Ă����̂ɂ͕������B�����͖��ɗ��炸���͂ŗ����オ���Ă��炤�����Ȃ��̂ŁA�ˎq���ǂ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ���肶��Ȃ��̂͊m���ł��ˁB�߂��Ă��������̃}���V�����̃��t�g�œV������グ�Ȃ��珉���̟����R�[�q�[��҂B�Y�������k���Ȃ���u���̓����c�c�����ł���v�ƙꂭ�ˎq�B�ˎq�����͑�̍g���}�����A����ς�R�[�q�[�͍D������Ȃ������ȁc�c����̐g�����珉���ɑ��āu�R�[�q�[�͌����v�ƌ����Â炩���������ŁBMyGO�ł���z�܂߂ĉ��x���u�H������X�v�ɍs���V�[��������܂����ǁA�R�[�q�[�𗊂��Ƃ͈�x���Ȃ������͂��B�u����Ȃӂ��ɏˎq�����͍��������ɖ{�����B���Ă���Ă�������ł��v�Ǝ����J�b�g�Ȃ̂��낤���A���ݕ��̍D�݂��炢�͑f���ɑł�����������������I�@�܂����������̐��i�I�ɑł�����������u���������Ɍ����ȃR�[�q�[�������ƈ��܂��Ă��Ȃ�āc�c�I�v�ƃV���b�N�ăR�[�q�[���[�J�[���̂Ăčg���Z�b�g�ɍ����ւ������ȕ|�������邩�猾���ɂ����낤���ǁc�c�����u�R�[�q�[�����g�����D���v�Ƃ������t��[���ɂȂ�Ȃ��Ŏ~�߂Ă�����������Ƃ����ȁB
�@B�p�[�g�ARiNG�ɏW�܂��Ă��郁���o�[�̂��Ƃ������V�[���B�r���Łu���ׂĂ̌����v�Ƃ���������郂�j�J�̖ʁX�Ƃ���Ⴂ�܂����A�u��������悤�v�ƈ��A���邾���ŗ����~�܂�������������Ă����B�ˎq�ɂƂ��āu�^�������́v�̃V���{���ł��������j�J���A���͂�u����v�ł͂Ȃ��u�h�ӂ��Ēʂ�߂��邾���̐�y�o���h�v�ɂȂ����B���˓I�Ɂu��������悤�v�ƕԂ��Ă��܂������A�Ȃ�ň��A���ꂽ�̂��킩��Ȃ��Ȣf�����j�J�����܂����B�W���������W�J�̃����o�[�ɑ��u�^�����ÂĎe���K�v�͂Ȃ��v�ƌ�����ˎq�́u�킽�������_�ɂȂ�܂��v�ƍ��ꂷ��B�ςȃN�X���ł�������̂��H�@�Ɩ₢�����Ȃ邪�A�o���h���͂���܂ł��u���̍Ńb���̉��y�ŁA�K�[���Y�o���h������I��点��I�v�Ɛ錾�����悤�Ȏq�����邩��ϐl�x�͂����܂ō����Ȃ���ł���ˁB�u�_�v�Ƃ������z�͓��˂ɏo�Ă����킯�ł͂Ȃ��A10�b�́u���鎄�̐_�b�ɂȂ��āv�ւ̃A���T�[�ł����邾�낤���B�ˎq���e���������j�J�́u�q�c�܂���v���A�s�R�̃l�^�ł����Ǎ����j�m�[�g���u�喂�P�����v���Ɓu�F�c�삠���v�ɏE�����i�ӂ��[�[�I�̑�10�b�u�����̃����B�A���m�[�g�v�j�������āA�m�[�g��ǂ�������������āu�䂱�����_�I�v�Ƌ���ł��܂����B���̉摜����ƂȂ��ˎq�����͂܂��낿���ƍ��������镔������ȁc�c�Ɗ����Ă��܂��B���W�J�s�R�ł̃S�b�h�E�E�H�[�Y�J���S�҂��ɂ��Ă��܂��B
�@���p�ł�����͉̂��ł����p���ăo���h�𑶑������悤�Ƃ���A�u�������v�����}�C�S�́u��u��u��ςݏd�˂Ĉꐶ�v�Ƃ͈Ⴄ�`�́A�ǂ����ŕǂɃu�`�������Ĕj�ł������Ȋ낤���������o�����u�l�דI�ȉi���v�Ɍ������đD�o���郀�W�J�B���x���ǂ������͂�����Ȃ�A�����ǂ��u�`�����B�����������̂悤�ɃI�u���r�I�j�X�̊፷���͗h�邬�Ȃ��B����ƖL��ˎq���u���ƈł��������Ȃ��ŋ��Ɍ�����v���ߏ�ɂȂ��Ă��ꂽ�B���C�i�X�̖ѕz�݂����Ɏ������Ă�����e�̌`���i���l�`�j��L��@�ɒu������ɂ��Ă����J�b�g�͏ے��I�B�ł��������̕tⳂ��W�߂��m�[�g�͎����čs�����̂ŁA�ߋ��ւ̖������肠��Ȃ̂��킩���ĉ����B�����̓o���h�����o�[��������������͂Ȃ����ǐS�̖{���͓��̂܂܁B�Y�p�����̂ł͂Ȃ��A�Y�ꂽ�t�������Ă��邾���B�ł��撣��Ώ������������̂��Ƃ�Y�ꂳ���邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B����ɂ��Ă��u�l�ԂɂȂ肽�����āA�����������Ƃł��̂ˁv�Ƌ������q���u�_�ɂȂ�܂��v�ƌ��ӂ���́A�قځu���т��]�ނȂ�A�l�͐l����߂āA�_�ɂł��Ȃ�ł��Ȃ낤�v�́wCARNIVAL�x���ȁc�c����̓Q�[�����ƌ��ӂ���Ƃ���ŏI����Ă��āA���҂ƂȂ鏬���łŁu���̖��H�v�ɂ��ĐG�����̂ł����A�����ł͓d�q������Ă��炸�v���~�A���t���Ă��ăX�S�����i�ɂȂ��Ă�����Ă����B������݂��ׂĂ�Y�p���A���͖����̍r��𐪂��ƙႦ���Ƃ����OP�́uKiLLKiSS�v�������́A�Ȃ̃C���[�W�����]���銴���ōD���ł��B
�@�u�L��̋��낵���v�Ƃ�炪���Ȃ̂��͂킩��Ȃ��i�����Ƃƈꏏ�ōׂ����Ƃ���܂Őݒ肵�Ă��Ȃ��Ǝv���j���A�v�_�Ƃ��ĉ�������ׂ��Ȃ̂́u�e���ꓯ�ɏ����Ƃ����B���q�̑��݂��m��n������莡�����r���遨�A���I�ɏˎq���������낤���Ȃ邩������Ȃ��v�Ƃ������������B������ˎq����ȏ����͐g���������Ȃ��Ȃ����킯�ł����A�u�킽�����̐������낤���Ȃ낤�ƈ���ɍ\���܂����I�v���Ċo������߂��ˎq���u�����̌����o�����܂����v�Ƃ���l�������Έ��͂Ȃ�ě��ł��Ȃ��Ȃ��ł���ˁB�S�g�Ƀ_�C�i�}�C�g�������āu�������邼�I�v�Ƌ��Ԃ悤�Ȍ���i�ł����ǁA�v���I�Ȏ�݂������Ă���ȏ�A�莡�͔j�ꂩ�Ԃ�̑����ɏ������邵���Ȃ��B�������L�삩��ǂ��o���ꂽ���_�Ō��ޗ��ƂȂ鏉���̑��݂�m�炸�A���ɒm���Ă����Ƃ��Ă������̏ˎq�ł͎����㓙�̃l�S�V�G�[�V����������o�傪�Ȃ������B�ł������{���̓��X���o�āA�{��ƐM�O�����ɗ��s�s�֗����������Ă����u�d�v���B�����l����ƃ}�C�S�������q���܂��������W�J�̂��ꂱ��͖��ʂ���Ȃ������c�c�̂�������Ȃ����A����ς葊���ςȃA�j���ł���A�wBanG Dream! Ave Mujica�x�B�u���납��o���Ȃ��̂Ȃ甠�M�ɂ�������v���炢�̔��ŕЕt���ɂ��Ă���B�u���_�͍ŏ����猈�߂Ă������ǁA�����Ɏ���܂ł̉ߒ��̓��C�u���d���ŋl�߂Ă������v�����ʼn��Ƃ��`�e�����������킢�Ɏd�オ�����B�ē̃C���^�r���[��ǂނ�����u�_�̔@�����\�ɐU�镑������l�v�������{���̏ˎq���ł���A�ޏ��������ɊJ������܂ł����]�Ȑ܂�`�����̂��wIt's MyGO!!!!!�x�ƁwAve Mujica�x�A�ӂ��̃A�j����i���������Ă��ƂɂȂ�B
�@���̂قƂ�ǂ��������Ȃ��܂܁u�ꉞ�̌����v�ɂ���čĊJ��ڎw���A�]�т��炯�̃o���h�uAve Mujica�v�ɂ܂�镨��͍���łقڌ����Ƒ����Ă����̂��ȁB�ŏI��͗\���Łu���W�J�ƃ}�C�S�̐V�Ȃ���v�ƃA�s�[�����Ă���̂ŁA�X�g�[���[�����͐���10�����x�����Ȃ����낤�B�����̐��������Ɋւ��Ă͖{�l�Əˎq�݂̂��m��A�r�ƃ��[�e�B�X�̌����L�떳��i�𗣐����ꐫ��Q�ɂ����x�����낢�날���āA���K�v�ȃP�[�X������Βn���ȃJ�E���Z�����O�ʼn��Ƃ��Ȃ�P�[�X������̂����A���������r�͐����Ȑf�f����x���Ă��Ȃ�������x�Ɋւ��Ă͌��悤���Ȃ��j�ɂȂ��āA�C��̃g���E�}�]�X�͂����Č@�艺�����A�ɂ�ނ��r�ɑ��ĕ��G�ȑz��������Ă��邱�Ƃ͑��̃����o�[�ɂƂ��Ă͂ǂ��ł������B�o���h���ɂ�����v���o���h�͂�����x�u�r�W�l�X���C�N�ȊW���e����J����ށv�Ƃ����v�f������̂ł�����ǁA�o���h���[�_�[���u���ׂĂ��x�z����_�ɂȂ��ă����o�[�S���𑩔����A���ʂ܂Ől�`�V�т𑱂���v�Ƃ����ɒ[�Ȍ��_�Ɏ���̂͏��ł����R�Ƃ����B���������ςȕ����ɓ˂��������Ⴄ�́A����Ӗ��u���Ɍ������đS���O�i�I�v�ȑq�c�܂���Ɠ����^�C�v�Ȃ̂�������Ȃ��B
�@���W�J�̍s�����͂��Ă����A�Ƃ肠�����ڐ�̖��Ƃ���sumimi�̉��U�͖h�������ȕ��͋C�ŗǂ������B�����́u���c�܂ȁv�͂����Ɖᒠ�̊O�ɒu����Ă��āA�u�����s���̃A�C�h���ł͂Ȃ�sumimi�Ƃ������j�b�g��g��ł����X�g�[���[��̈Ӗ��͉��������̂��v�͂悭�킩��Ȃ��������c�csumimi�����邱�ƂŃ��W�J���U��Ɂu�A�C�h���w���x�̋A��ꏊ�v��p�ӂł���A�Ƃ����̂͂��邪�A����܂ł̃X�g�[���[��U��Ԃ�Ə��i�����j���s���A�C�h���ł��[���b�͐�������i�ނ��돉�����܂Ȃ̂悤�Ȗ��邢�A�C�h���������邱�ƂŖ{�l�Ƃ̃M���b�v���ۗ��j�C�������ȁB�Ђ���Ƃ�����ŏI��ł����Ȃ�܂Ȃ��������C���ɂ����V�o���h�������Ă���\��������H�@�u���̕��̏��v��e�ɑ[���Ă��A�T�u�L�����~���W�߂����1�o���h���炢�͑g�߂����Ȃ�ł���ˁB���c�܂ȁA�������̗c�Ȃ��݁u�݂��i�r�{�݂��H�j�v�A���ƃA���T���u�������炵���u�͂Ȃ��i���� �͂Ȃ��H�j�v�A������[�̎o�u�Ŗ��^��v�A�ɂ�ނƓ����I�[�f�B�V�����ɎQ�����Ă����n�[�h�����f�B���O�����́u��Ɨт�����v�A����5�l���V�o���h��������I�`�A�m���Ƃ���0.001�����炢�͂���Ǝv���܂��B
�@�ŏI��ɓ������13�b�̃^�C�g���́uPer aspera ad astra.�v�A�u�������z���Đ���ڎw���v�Ƃ�������̗\�z�ʂ�ɂȂ�܂����B�A�j�������������w�ޕ��̃A�X�g���x�ł��g���Ă������e����̐���ŁA���Ƃ������������Ō������錾�t�ł͂���BFGO�̃v���[���[���Ɓu�������X���N�B���k�X�v�̕��u���̘r�͂��ׂĂ�A���ցi�y���E�A�X�y���E�A�h�E�A�X�g���j�v�ň�ۂɎc���Ă��邩������Ȃ��B�n�b�s�[���ǂ����͂Ƃ�������]�̓���������I�����ɂȂ肻���ŗǂ������B�Ō�̍Ō�ő��ޑ�Ԃ��ɂȂ肻���A�Ƃ����s�����[���ł��Ȃ����ǁc�c����\���Ƀ`���b�Ɖf���Ă����m���m���ő̂����E�ɗh����r����Ƃ肠�����y���݁B���Ȃ݂ɑ��̃����o�[�̗l�q���|�c�|�c�Ɖf���Ƃ���Ŗr�����́u���̌�v���`���b�ƕ`����Ă������A�x�[�X�͖r������ǎ����̑��x�������ɗǂ��Ȃ��Ă��āA�u�ǂ����{���������������v�͂Ȃ��Ȃ��Ă���B����͎��������܂肵�Ȃ��Ȃ�̂��ȁB�����l����Ə����₵���B���Ɩ��f������������Ɏӂ낤�Ƙb�������鏉���Ɂu���C�ł����H�@�o��Ƃ��o�܂����v�ƈЊd����C�邪�ʔ��߂����B�u����C�ƌĂԕӂ����ϊC�邿���ɂƂ��Ă��ꋁ���s���������v�Ǝw�E����R�����g�������ăc�{�ɓ������B����Ə����A�N���X���C�g�Ƃ��������œ��ɐړ_���Ȃ��������ǁA���ǂ����悤�Ƃ�����C�邪�ז�����ȁc�c�Ƃ킩���ďC����D���ɂ͊y���������ł��B
�E�u�ӂ��Ȉ����ł͂������܂����v�A�j�����I�ē͎R��݂��A����͓���H�[�i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@����ς�A�j��������̂��B����̐l�C�����邤���ɃR�~�J���C�Y�̕]�����������玞�Ԃ̖��A�Ɗ����Ă����t�@�����������낤�B
�@����́u�����ƂɂȂ낤�v��5�N�قǑO�ɘA�ڂ��J�n����Web���������A���Љ��ɔ����Č��݂͌��J�I���ƂȂ��Ă���B����ߏ샂�m���ۂ��^�C�g���Ȃ���A�]���l�^�ł͂Ȃ�����ւ��l�^�B5�l����܌��̂����A�����Ƃ��]���������u�ǂԃl�Y�~�v�ƕ̂܂�Ă��鏗������p���s���Ĕ܌��̃g�b�v�\�\�u�Ӓ��v��搂����l���ƍ������ւ��Ă��܂��B�������čc���q�̒����������Ƃ�����������l���́A�N������₽���ڂŌ��������u�ǂԃl�Y�~�v�Ƃ��Đ����Ă������ƂɁc�c�ƁA���炷���ł͎�l�����ߌ��̃q���C���݂��������A�����t�@������u�|�l�v�ƌĂꂽ�����^�����҂̎�l���A���̒��x�ł͂ւ�����Ȃ��B��l���̌��͕̑̂a�ɖ`����Ă���A�u����ł��܌��Ƃ��Ă̖��߂��ʂ����˂v�ƌ��̟��ނ悤�ȓw�͂��d�˂Ă����̂ł���B������ւ��̔Ɛl�͂܂��������܂ŕa�ꂪ�������Ƃ͎v�킸���]���|�B����A��l���͌��N�Ȑg�̂���ɓ��ꂽ���ƂŃE�L�E�L�C���B����ɉ��Ǝv���悤���C�ɂ����l����搉̂��܂��B
�@2���łЂƋ�����3������V�W�J���n�܂�̂ŁA1�N�[���Ȃ炽�Ԃ�2���܂ł͈̔͂�����ďI���ł��傤�B����͗����o��ŐV����10���A�X�g�b�N�͏[���Ȃ̂�2���ځA3���ڂ��]�T���B�Ƃɂ�����l�������邭�O�����Ȑ��i�ŁA�C�P�������r�����Ȃ̈ӎu��ʂ��^�C�v������j���ǎ҂��ǂ�ł��C���������B�����̎q������Ȏ�l�����J����Ă�����ŃV�X�^�[�t�b�h�����Ƃ��Ă��[���C�P����e�B�X�^�W�I�́u����H�[�v�����A�f�R���҂��Ă��܂��ȁB����A����H�[�ł��u�A�^���̓���H�[�v�Ɓu�n�Y���̓���H�[�v������̂ŕs�����[���Ƃ����킯���Ⴀ��܂��c�c�n�Y���̕M���i�́w�c�Ȃ��݂���ɕ����Ȃ����u�R���x�A��҂��A�j���̏o���ɐ�]���Ď�Z��ɂȂ����Ƃ����B
�@����H�[�Ƃ����X�^�W�I�A�̂́w���P�����o�x�Ƃ��G���Q�[����A�j������|���Ă����̂ł����A2011�N�́w�����x�����肩��u���탂�m��G���A�j���v�̕���ŕ]������Ă����悤�ɂȂ�܂����B��悪���J�A���R�~�J���ȉ��o�����ӂƂ��Ă���B�ő�̃q�b�g���2023�N�́w�y�����̎q�z�x�B3�������܂��Ă��邪�A���̒��q�Ȃ�t�@�C�i���V�[�Y���ƂȂ�4���܂ł���Ȃ�������B
�E�Ƃ�c�݂̂�u����`���Ď��ˁvTV�A�j�����@�����|�R����`�����e�B�U�[�r�W���A���i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@����͍D�������ǁA�u�Ƃ�c�݂̂�v�̊G���͂��܂�A�j����������Ȃ�������v���ȁc�c�ƐS�z����C�����������B�w����`���Ď��ˁx�͊ȒP�Ɍ����Ɓu�ߘa�Łw�܂��x�v�B����D���̏��̎q���A�u������Ď����ŕ`�����Ƃ��ł���I�v�ƋC�Â��đn��̓��̂����ݎn�߂�B���挤����𗧂��グ�A���������u���W�܂��ė���W�J�́u�t�������m�v�̃e�C�X�g�������B�������A������Ƃł��閟���ږ�̉ߋ���`���V���[�Y�u���X�g���[���h�v���ǂ݉����[���ł���A�u�������m�v�����ł͊���Ȃ��ʔ���������B�u���X�g���[���h�v��1�b�ڂ����l�b�g�Ō��J����Ă����̂ŋ����̂�����͂ǂ����B
�E�V���ɒq���w�A�E�^�[Q�@�㏬Web�}�K�W���̎�����x
�@�f���w����x�̌����w�ڂ���A����x�Ńf�r���[�����u�V���ɒq�v�ɂ��~�X�e���A��W�ł��B�u�A�E�^�[Q�v�Ƃ����}�C�i�[��Web�}�K�W���̎��ӂŊ����N���邢�����̎�����`���Ă���B�I�J���g�Ƃ��������팻�ۂ݂����ȗv�f���ꕔ�����Ă��܂����A�ǂ��炩�ƌ����u�l�Ԃ̈��ӂ��ׁv�����ɐ������Ă��܂��B��ɂ���ă����`����Web�̃`�P�b�g���]���Ă����̂ŏ������邽�߂��R�~�J���C�Y����ǂݎn�߂��Ƃ�����e�Ɉ������܂�A�u�������ǂ݂����I�v�ƂȂ��Č���Ɏ��L����������B�����7�̒Z�҂��琬���Ă���A�R�~�J���C�Y��5�ڂ̃G�s�\�[�h�ɍ����|�������Ƃ���Ȃ̂ŁA����œǂ݂����l�͂���������Ƒ҂��ăR�~�J���C�Y���������Ă���܂Ƃ߂Ėڂ�ʂ����������������ł��B
�@�G�s�\�[�h�ɂ���Ď��_�l���͔����ɕς�邪�A�u��l���v�ƌ����č����x���Ȃ����x���ł悭�o�ꂷ��L�����N�^�[�́u�l�v���Ɓu�p�j�v�BWeb���C�^�[�Ƃ��ăJ�c�J�c�̐����𑗂��Ă���27�A���낻��]���̘H������E���ĐV�@���̊��𗧂Ă˂c�c�Ƃ����Ƃ���ŊX�ɐ��މ������u��v��ǂ����ƂɁc�c�Ƃ�����ɉ��ق̗ނ��u��ށv�̂��߂ɉ����������Ă����`���ł��B�`���ꔭ�ځA�u���I���b�v�͓ǎ҂Ɂu���������H���ł���v�Ɠ`���邽�߂̃E�F���J���E�h�����N�݂����Ȃ��̂ŁA���̓V���v���Ȃ���u��v�̓�����T�蓖�Ă邽�߂ɊX�̂���������������銴�o��ADV�Q�[�����݂Ă��ĂȂ��������Ȃ�܂��B���̓v���[�������ƂȂ����ǁw�s�s�`����̃Z���^�[�x������ȃm���Ȃ̂��ȁA�Ǝv������B�����̓y�ǂɏ������܂ꂽ��̗������A�ʏ́u�I���b�v�̐^���Ƃ́H�@�����̈����I�`�ŁA�u���̖{�͊�{�I�ɃX�J�b�Ƃ���b���Ⴀ��܂����v�ƒ��J�ɋ����Ă���܂��B
�@2�Җڂ��u�̂��n���o�[�K�[�v�B�u�킽���v���Ɓu�牮���v�����_�l���ƂȂ�G�s�\�[�h�ŁA�p��͘e���ɉ���Ă���B���Ắu�V����t�[�h���C�^�[�v�Ǝ��Ě����ꂽ�u�킽���v���������A���݂͋��H�ǂɔY�܂���A�d�����������������B����Ȃ�_�����A�ł�u�킽���v�̓A�E�^�[Q�Łu���邩��ɓ���ɂ������͋C����w�������X�x�̎�ށv�Ƃ������ɏ��o�����c�c�Ƃ�����ŁA�œ_�ƂȂ�u�������X�v�̓X�����u�V���M���E�n���o�[�K�[�v������^�C�g�����u�̂��n���o�[�K�[�v�B�S�̂��猩��Ƃ��ꂪ��ԃ}�V�Ƃ������A��r�I�z�b�R������G�s�\�[�h�Ȃ�ł����u�n�b�s�[�G���h�v�Ƃ͌�����Ȃ������������ă��������������z���c�邱�Ɛ��������B
�@3�ҖځA�u��ԃX�g�[�J�[�Ƌ��ԃA�C�h���v�B���C�^�[�ҋƂ��O���ɏ�����u�l�v���Ƙp�j�́u���邱�Ƃ𑝂₵�����v�Ƃ������R�ŎB�e�̎�`�����n�߁A������n���A�C�h���̃��C�u���B�e���邱�ƂɂȂ����B���đ傫�ȃO���[�v�Ŋ������Ă������̂́A�����ɗ����t�@���ɏP������ĉ�����A�u���Ɓv��]�V�Ȃ����ꂽ�����B���`��ς��Ēn���A�C�h���Ƃ��čďo�����邱�Ƃ����ӂ����ޏ����������A���C�u�̍Œ��ɂ܂����Ă��������N�����āc�c�V�L�����Ƃ��āu�n��A�C�h���v�Ǝ��s����u���n�˂�v���o��A�X�e�[�W��ŗ���������Ă����H�ׂȂ���������ރp�t�H�[�}���X������Ƃ����A��������Ă��悭�킩��Ȃ��q�ł��B�ڂ���Śg����ƁuSICK HACK�v����ǂ��o���ꂽ�u�A�䂫����v�݂����ȁc�c����A�������قǎ�Ȃ͈����Ȃ����ǁc�c����͒T������˂肿����߂�̂ŁA�p��̉e�͔����B�ǂ��炩�ƌ����˂肿���̊猩���Ƃ������i�̋����G�s�\�[�h���ȁB
�@4�ҖځA�u�ڊo�߂鎀�҂����v�B�ԉΑ��̖�A�������ŋN�����������|���̎��́\�\��Q�ɑ�������l�ł���p�j�́A���ꂪ�u���k�̃l�^�v�Ƃ��Č���Ă��邱�Ƃɉ��Ƃ������Ȃ����S�n�̈����������Ă����B���b���k�ł���ȏ�A���ۂɂ��������̂��l�^�ɂ����͓̂��R�ƌ����Γ��R��������Ȃ��B�����c�c��������Ȃ���������������钆�A�������̋ߕӂŊ�ȁu��v���������U����Ă��邱�ƂɋC�Â��c�c���O�̃G�s�\�[�h�ɓo�ꂵ���u�n��A�C�h���v���n�˂肪�ēo��A�u��v���͉̂�����������邪�A��l�����������̎��̂Ŗڌ������u�s�A�X���炯�̐Ԃ����̐N�v�Ɋւ��Ă͓��ɒNjy����ȂȂ��܂I���B�쒆�ɕ`����Ă��鎖�̂́u���Ɍ����Ύs�̕��������́v�����f���ŁA�����u�����̃����L�[���\��Ă����v�Ƃ����\������܂������A���ǃf�}�Ƃ������Ƃŗ��������ɂȂ�܂����B�ނ���l���~���ɖz�����Ă����̂ł́H�@�Ƃ��������������̂ŁA�����������������]����I�`�Ȃ̂��ȁc�c�Ǝv��������ɂ���Ȃ��Ƃ��Ȃ������Ƃ����B
�@5�ҖځA�u���߂郆���G����v�B�p��̐�y�ɓ����郉�C�^�[�u��o�a�^�v���F�l�̈˗����āu�ё���ɕ`���ꂽ�����v�̐g��������o�����Ƃ���G�s�\�[�h�B���_�l���͈�o�̗F�l�A�u�ڂ��v���Ɓu��쏫���v�ł��B���ɉ��x�������������o�Ă���\�\�u�ڂ��v���������������ۂ́A���̏����ɂ�������̊G���Ƃ̒����猩���������Ƃł�����x�͓��������B20�N�قǑO�A�e���a�̎s�Ŕ����āA�����z���̍ۂɕ��u�ɕ��荞�܂�Ă����ё���B�q���̍��́u�ڂ��v�́A�G�ɕ`���ꂽ�����𖧂��ɐS�̒��Łu�����G����v�ƌĂ�ł����c�c�Ƃ��������Łu�����G����v�̃��f���ɂȂ�����������肵�悤�Ƃ���b�ł��B�p����e���Ƃ��ēo�ꂷ��B���_�������Ă��܂��ƃ��f���͖����ɓ��肳��܂��B�����A�߂ł����߂ł����c�c�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�f���ɉ��߂���o�b�h�G���h�Ȃ̂��낤���A�l�ɂ���Ắu��������n�b�s�[�G���h�Ɏ������ނ��Ƃ��\�v�ƑO�����Ɏ��邩������Ȃ��B�ۂǂ����C���Ɉʒu���Ă���G�s�\�[�h���B
�@6�ҖځA�u�f����V�����~�v�B�O��҂̑O�҂ɓ�����G�s�\�[�h�Ȃ̂ŁA���ꂾ���ł̓X�g�[���[���������Ȃ��B�^�P�R�E�C���^�[�i�V���i���Ƃ������������^�����g�i���f�����N���͌����܂ł��Ȃ��j�̔ԑg�ɏo���������ƂŃo�Y��܂����Ďd�������������p�j�A�ނ́u�����s�~�s�Ɋ�ȉƂ�����v�Ƃ������ƂŖZ�����Ȃ���ނɕ������B���E�����̖��ɋL���������A��l�łЂ�����Ɗ���ȃI�u�W�F����葱���Ă���j���u�H�R�����Y�v�B�ϐl�ƌ����Εϐl�����v���������������_�炩���u��������������̂��݂�ȂɌ��Ăق����v�ƌ��p�Ɋ������A�H�R�@���u�V�����~�v�Ɩ��Â��A�t�^�[Q�ő�X�I�Ɏ��グ��p�������c�c�Ƃ��������ŁA����͏I���Ɍ����ĉ������Ă����܂��B�p��Ɉ��ӂ͂܂������Ȃ��A�u�݂�Ȃ��R�������Ċ������Ăق����v�Ɨ����Ɏv���ďЉ���̂ł����A���ꂪ�\�z�����Ȃ������S���������N�����Ă��܂��B�����Ď��̃G�s�\�[�h�֑����܂��B
�@�ŏI�͂��u�܂���n�����~�v�B�^�C�g���Ŏ@���邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂����A�u�f����V�����~�v�Ƒ��ׂ��G�s�\�[�h�Ɛ\���܂����O��҂̌�҂ɓ�����G�s�\�[�h�ł��B��S���ɂ���Ĉ�]�A�u�V�����~�v�́u�n�����~�v�ɕϖe�����B��������ĉc�Ƃ��Ă����킯�ł͂Ȃ��H�R�����ӂ߂Â炩�����̂��A���̖���͏Љ�L�����������p��Ɍ������B�L�����f�ڂ����A�E�^�[Q�ɂ����f���|���Ă��܂����c�c���ӂ̔O�ɋ����p�������A�H�R�@�ŋN�������u�S���v�������̎��̂ł͂Ȃ����҂����Ӑ}�I�ɔ��������������Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�����[�܂�A�^�������������ɂ͂����Ȃ��Ȃ�c�c�Ƃ�����Ɂu�����ҁv�I�ȓ��e��Ԃ��Ă��܂��B�O�҂Œ����Ă��������A�݂̂Ȃ炸����܂ł̃G�s�\�[�h�ɖ��݂���Ă��������܂ʼn������A�{���̑����Z�߂����������}����B�P�Ȃ�L�������ėv�f���Ǝv���Ă����������^���̈ꕔ�������Ɣ�������ȂǁA�����ɖ������l�^�o���V�ł���B����������́A����܂ł̃G�s�\�[�h�́u���̌�v�ɂ��Ă������G��Ă���B���̂܂܌��I�ȓW�J���Ȃ��A����݂�Ƃ������͋C�ŕ��ƂȂ�܂��B
�@�܂Ƃ߁B���^����Ă���Z�҂͎G���Ɍf�ڂ��ꂽ���m�Ə������낵��2��ނ���A�G���f�ڂ��ꂽ���̓G�s�\�[�h�̊������������A�������낵�̕��̓G�s�\�[�h�̘A�����������d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B�u�S�̂̃I�`�v����������w�A�E�^�[Q�x�͂���Ŋ����A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���A���̋C�ɂȂ�Α��҂����Ȃ��ł��Ȃ����͋C���B����Ƃ��V���[�Y�����Ăق����A�Ɗ肤�قǓ��F�̋�����i�ł͂Ȃ����A�����������o���甃�����Ⴄ���낤�ȁc�c�Ɗ�����Ƃ���͂���܂��B�����A�p��Ɋւ��Ă͂�������Ȃɋ������Ȃ����ǁA���n�˂�Ɋւ��Ă͌@�艺�����~�����B�ޏ��͔@���ɂ��Ēn��A�C�h���Ȃ���̂ɐ���ʂĂ��̂��A�I���W����H��̂��������A���̂ւ����č���������Ɋ������܂ꑱ����`���ł������B���҃C���^�r���[�ɂ��Ɓu�؉H�l�܂��Đ��b�Ŏv�������L�����N�^�[�v�炵���A������3�b�܂ʼne���`���Ȃ������ȁc�c�Ɣ[�����܂����B���̌��Ԃ肾�Ƒ��҂̍\�z�Ƃ��͂Ȃ����������ǁA����͂���ŕʂ̐V����y���݂ɂ��悤���ȁB
�E�f���wPearl �p�[���x���ς܂����B
�@�wX �G�b�N�X�x�Ƃ����z���[�f��̑��ҁB�Ƃ����Ă����n��I�ɂ́wPearl �p�[���x�̕����ߋ��Ȃ̂ŁA������O��杁i�v���N�G���j�ɊY�����܂��B�ς鏇�ԂƂ��ẮwX �G�b�N�X�x���wPearl �p�[���x�A�wPearl �p�[���x���wX �G�b�N�X�x�ǂ���ł��\��Ȃ��B�Ԃ����Ⴏ�wX �G�b�N�X�x���ɊςĂ���Ƌt�Z�ŁwPearl �p�[���x�̑�܂��ȓW�J���킩�����Ⴄ���A�wPearl �p�[���x���ɊςĂ���ƁwX �G�b�N�X�x�̊j�S���ŏ�����m���Ă����ԂŗՂނ��ƂɂȂ�̂ŁA�ǂ����̃��[�g��I��ł������b�g�ƃf�����b�g�������ł���ˁB���������V���b�L���O�ȃV�[���������̉f��Ȃ�ŁA�X�g�[���[�����Ɋւ��Ă͂����܂Ńl�^�o���ɑ��Đ_�o���ɂȂ�Ȃ��Ă������̂�������܂��c�c�B
�@1918�N�A��ꎟ���E��풆�̃A�����J�B�e�L�T�X�̔_��şT���������X�𑗂��Ă��鏗���u�p�[���v�́A�����Ɓu�����ł͂Ȃ��ǂ����v�ɓ���Ă����B�~���[�W�J������D���Ȕޏ��́A�_���T�[�ɂȂ��ĉ��B�֓n��A���т𗁂тĉX���������𑗂���X���Ă���B�����������͌������B�h�C�c�n�ږ��̐��܂�Ƃ������Ƃ������Ď��ߕ����ʂ��������A�_��œ����ȊO�Ɏd���̓��Ă͂Ȃ��B�܂��A�a�C�ŎԈ֎q���痣����Ȃ����e����삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����������B�p�[���͊����҂����A�v�͉��B�̐��ɏo�����ŁA�ŋ߂͕ւ���r�₦�Ĉ��ەs���B�Ⴓ�����ė]���Ăǂ��ɂ��s���Ȃ������ɐ�]����p�[���B�ޏ��̟T���͂₪�āA���S�Ȍ`�Ŕ�������c�c�B
�@�l�^�o��������Č��̂��������O��܂߂ăl�^�o���S�J�ŒԂ��Ă����܂����A�wX �G�b�N�X�x�ő�\�ꂵ���E�l�S�̘V�k�u�p�[���v�������ɂ��ăT�C�R�L���[�Ƃ��Ċo����������`���G�s�\�[�h�ł��B�wX �G�b�N�X�x�̃q���C���u�}�L�V�[���v���������̂́u�~�A�E�S�X�v�Ƃ������D�Ȃ�ł����A���͎E�l�S�o�o�A�́u�p�[���v����l����ʼn����Ă����B���ꃁ�C�N���X�S�������������Č����Ȃ��ƋC�Â��Ȃ����x���Ȃ�ł����A������������������āwPearl �p�[���x�̎剉�����������~�A�E�S�X�ł��B���͂�u�~�A�E�S�X�̉����߂邽�߂̃V���[�Y�v�Ɛ\���グ�Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�n�b�L�������Ă��܂��ƃq���C�����Ђ�����T���𗭂ߑ����Ă����O���͑ދ��Ȃ̂����A���ɗՊE�_���ău�`�M���Ă��܂����Ƃ��̕\����܂����āu�����v�ƂȂ�B���̂��o���o���Ɏa�荏�蕅���������v���N������Ƃ������O�����`�ʂ����傱���傱�o�Ă���f��Ȃ���A���������S�A�V�[�������u�q���C���̊�v�̕������{���|���B�q�����ς���g���E�}�ɂȂ肻���B�Ƃɂ����~�A�E�S�X�̉��Z�͂ƕ\���͂��}�����Ă��Ĉ��|����܂��B�O�̐��E�֔�яo�����Ƃ��ăI�[�f�B�V���������ʁA�c�O�Ȃ��玸�i�ƂȂ��Ă��܂��̂ł����A���������Ɗ��^���Ԃɂ��ċ������ёʁX�����˂鉉�Z�����^�����ĎE�l�V�[�������V���b�N����B�wX �G�b�N�X�x�̎E���܂�����Ղ�ɔ�ׂ�ƎE�Q�l�������Ȃ��i�Ў�ő������x���j����X���b�V���[�f��Ƃ��Ă͂�┏�q�����̕��������������A�u�������������v�x�͖{��̕�����ł��B
�@�p�[���͎E�l�S�����A�u��ނɂ�܂�ʎ���ŎE�����v�Ƃ����قǂł��Ȃ��̂Ŗ{���Ȃ瓯��ɒl���Ȃ��l���̂͂��Ȃ̂����A�~�A�E�S�X���S�g�S��ʼn����������ʂ�������u���킢�����v�Ǝv���Ă��܂��u�Ԃ����x������܂��B�}���I�ȑԓx�Őڂ����e�ɂ͓{����o�����Ⴄ���A�u����ȉƒ���ōK���Ȗ������v���`���ƌ����Ă��c�c�v�ȂƂ��낪����B�Ȃ�Ƃ��ޏ����K���ɂȂ铹�͂Ȃ������̂��A�Ƃ�������Ȃ���]��T���o�����Ƃ��Ă��܂��B�ŏI�I�ɂ͕|�������Ȃ������f��B�O����̊����ҁwMaXXXine �}�L�V�[���x�̓A�����J���Ɗ��ɋ��N���J�ς݁A���{�ł͍��N��6��6���Ɍ��J�\��ł��B�wX �G�b�N�X�x��6�N���`���B�����1985�N�̃n���E�b�h�A���݂̎E�l�S�u�i�C�g�E�X�g�[�J�[�v���X�g�[���[�ɗ���ł���炵���B���R�A�剉�̓~�A�E�S�X�ł��B
2025-03-16.�E�A�j������Ă邵���҂��n�܂������c�c�Ƃ������Ƃŋv�X�ɓǂݕԂ��Ă����w���[�x���u���b�g�x���ŏI���i23���j�܂œǂݐ����ĒÂł��A�����́B���[�x���u���b�g��0������X�^�[�g����̂ŁA23�����Ōゾ���Ǎ����Ƃ��Ă�24���ڂɂȂ�܂��B�d�q�ł��w������Ƃ����̂ւ�ō����������Ȃ̂Œ��ӂ��܂��傤�B
�@�u���Ȃ鑄�v����ɗ�������14�l�̗E�҂����\�\3�l�͗��̓r���Ŗ��𗎂Ƃ��A�c��11�l���u�łٖ̈M�i���B�V���e�q�j�v�ɑ��ݓ��ꂽ�B�����ċA���Ă����̂�7�l�B�ނ�͌����A�u4�l�̎�҂��łٖ̈M�Q�Ԃ낤�Ƃ����̂ŁA��ނȂ��n�������̂��v�ƁB�������Đ��҂���7�l�́u���p�Y�v�Ǝ]�����A�A���Ă��Ȃ�����4�l�́u����̑��v�Ƃ��đ�������邱�ƂɂȂ����B�������^���͈قȂ�B�u���p�Y�v�������|�C�Â��ēG�O���S�������a�҂����ł���A�u����̑��v���Ȃ߂�ꂽ�҂����͂�����4�l�ŖړI���ʂ����Ė߂��Ă����ɂ��ւ�炸�A���Ă̒��Ԃ����ɂ���ěj��E���ɂ���蕿��D��ꂽ����ȋ]���҂������̂��B�u����̑��v��1�l�ł���A�鍑�ŋ���搂�ꂽ���m�u�A�V�F���[�g�v�́u�P�C���c�F���v�Ƃ����U���𖼏��A�ς��ʂĂ��p�ƂȂ��āu���p�Y�v�ւ̕��Q�𐋂���ׂ��T�[�����g�鍑�ɕ����߂��Ă����c�c�Ƃ����A��g�Ƃ��Ă͕��Q杂ɓ�����_�[�N�E�t�@���^�W�[�ł��B0���ɂ́u����̑��v�̖����x��4�l�̋U�҂��o�ꂵ�A�U�A�V�F���[�g�ɑ��ăP�C���c�F�����u���������{���̃A�V�F���[�g���v�Ɩ������V�[����������ɂȂ��Ă���̂ł����A�ڂ̓s�����͂��܂��b�����G�ɂȂ邩�炩�A�A�j���łł�0���̓��e���o�b�T���ƃJ�b�g����Ă��܂����B�A�j��������������͐���Ƃ������0���ɖڂ�ʂ��Ăق����Ƃ���ł��B�P�C���c�F�����鍑�ɖ߂��Ă���܂�20�N���|���������R�ɂ��Ă����y����Ă���B
�@���āA���̓��[�x���u���b�g�����A���^�C���œǂ�ł����̂ł����A�r���܂ł͑f���Ɋy����ł����̂ɓr������u���`��c�c�v�Ȋ����ɂȂ��āA�Ō�̕��͔��ΑĐ��ŕt�������Ă��܂����B����ǂݕԂ��Ă킩������ł����ǁA���̖���A�܂Ƃ߂ēǂނƖʔ�����ł���B�ł������܂�14�N���炢�|�����Ă���̂ŁA���A���^�C�������Ɖ��x���ǂݕԂ��悤�ȔM�S�ȃt�@���ȊO�̓_���C���ɂȂ��Ă��܂��B�u���p�Y�v�����Ղ�ɏグ�Ă����y�[�X�A��������3�l�ڂ��炢�܂ł͒��D�����Y���ŃT�N�T�N�i�ނ�ł����A4�l�ڂɓ�����u���x�����g�ҁv���璷���Ȃ��Ă����ł���ˁB���x�����g�ɂ͂�������q�������āA���̂ւ�̃G�s�\�[�h�ɂ����������M��������邵�B�Ȃ��Ȃ����x�����g���|���Ȃ��ȁ[�A�Ǝv���Ȃ��猩����Ă���ƁA�E�����͂���3�l�ځi�O�����j���Ȃ����h���āA�������c��̍���_�����x�����g�Ƒ����n�߂�c�c�Ƃ������p�Y���m�̐푈�A�u�p�Y�푈�ҁv�ւ��ꍞ��ł����B2�l�����5�l�ɂȂ����u���p�Y�v���ӂ��̐w�c�ɕ������̂����A���x�����g���ɕt�����z���N���������v���o���Ȃ������̂ōēǂȂ̂ɐV�N�ȋC���Ŋy���߂܂����B���́u�p�Y�푈�ҁv�ɍ����|�����āA���Q�v�f�������Ԕ��܂��Ă��܂������烊�A���^�C������e���V�����������Ă��܂�����ł���ˁB���ꂶ��P�C���c�F���̕��Q���u�T�[�����g�鍑��L�v�̓Y�����ɂȂ����Ⴄ�ȁA���āB�u���p�Y�v������ɖ���������n�߂����ƂŁu�P�C���c�F���ɂƂ��Ă̐킢�v�ɑ��闎�Ƃ��ǂ���������₷���Ȃ����i�푈�O�̎��_���Ɓu�����玄�������邩����Ē鍑�ɂƂ��ďd���ł��鎵�p�Y���E���܂���Ε��a������Ă��܂��̂ł́H�v�Ƃ�����肪�������j���ǁA���ʂŃP�C���c�F���̑��݊��������Ă��܂������݂�����܂��B
�@�ŏI����ł͂���܂ł̃L�������h���b�Əo�Ă����Ԃ̓W�J�ɓ˓��B���ǎ��ɂ͖Y��Ă����A�����܂Ƃߓǂ݂̂������Łu�����A�������v�Ƃ킩�邩��e���V�������u�`�オ��܂����B�A�j����1�b�ڂɏo�Ă���ɓ������Y���̑m�����i���V�F�u�j�Ƃ��A���\�I���̕��܂Ő����Ă��邩��A�j���ł̍ēo���S�҂��ɂ��Ă���B���Ə��ǎ����Ɗ��Ă�����ۂ̂���}�X�R�b�g���u�s�[�s�v���v�����قǂ͏o�ԂȂ��āu�L������������Ă����c�c�I�v�ƃr�b�N��������B�q���C���H�ƌ����Ă����̂��ǂ����킩��Ȃ����Ǐo�Ԃ͑����u�G���T���A�v���A���̒��ł͂����ƃ��u�R���V�[���̑����C���[�W�������̂Łu���̖���A���̎q�������u���Ă���ȂɃI�b�T�������莟�X�Əo�Ă���b�����������H�v�ƌ˘f���n���Ɋׂ����B�Ԃ����Ⴏ���ǎ��̓I�b�T���ɑ���S�������������炾�������Ȃ��Ȃ��Ă�������ȁc�c�������ɍēǂł͌����������܂����B�T�u�L���������ǃ��x�����g�̑��q�i�l�j�j�u�o�����g�v���C�C���o���Ă���B�Ƒ����E�����P�C���c�F���͑������A����������Ƒ��������̂�����O�b�Ɠۂݍ��ނ����Ȃ��c�c�Ƃ����h���|�W�V�����B�����M�����[�L�������Ɓu���Y���v���������������𐋂��Ă��܂��B���Y����0������o�Ă���L�����Ȃ�ŁA�A�j���h�̓P�C���c�F���Ɍ����镡�G�Ȋ���킩��ɂ����Ǝv���܂����c�c�B
�@���҂ƂȂ��w���[�x���u���b�g�U�@�����鉤�̋R�m�c�x���o�Ă��邩���܂��Ȍ����̓o���o�����낤�������Ă��܂����A�P�C���c�F���i�A�V�F���[�g�j�̕��Q�͖����������āu���p�Y�v�S���𑒂苎�邱�Ƃ��ł��܂����B�u����̑��v�̉�����Ⴎ���Ƃ��ł������A�����S�c��͂Ȃ��\�\�Ǝ��g�܂�14�l�̕�i�u���p�Y�v�͑����w���������ߍ��ȗ����Ƃ��ɂ������Ԃł͂������A�Ƃ������Ƃňꏏ�ɒ����Ă���j���痧������V�[���ŁuEnde�v�B�p�Y�푈�̃S�^�S�^�������Ē鍑�̑̐��͔ՐƂ͌������A�Č���}���Ă��邳�Ȃ��u�����鉤�̋R�m�c�v�Ɩ����V���ȓG������āc�c�Ƃ����̂����A�ڂ��Ă���U�ł��B�A�j�����ɍ��킹�Ă����N�n�܂�������ŁA�܂�2�������炢�����X�g�[���[���i��łȂ�����ǂ������b�ɂȂ邩�����_�ł͂悭�킩��Ȃ��i���C�~����߂Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����ꂽ�̂��u�łٖ̈M�v�֘A�ɂ͂��܂蓥�ݍ��܂Ȃ������̂ŁA���x�������ݍ���ŗ~�����C�����͂���j���A�P�C���c�F�������́u���̌�v��q�߂�Ƃ����ă��N���N���~�܂�Ȃ��B�Ȃ�Ƃ��ł���ꂸ�ɑ����ė~�������̂��B
�E�v�X��Fantia�����c���EG���E�X�P�̃y�[�W���`�F�b�N��������_���́w���ےn������A�[�f�B�e�B���x���~�܂��đ�ܐ_���wDies Entelecheia�x���n�܂��Ă������B
�@�ǂ����A�[�f�B�e�B�����s���l�܂��Ă��܂����̂ň�U�y���f�B���O���āA�̑�����ܐ_�����ɖ��߂邱�Ƃɂ����݂����ł��ˁB��ܐ_���́u�։��]���i�T���T�[���j�v���e�[�}�ŁA�C���h�_�b�����`�[�t�ɂȂ��Ă���_�ő��_���Ƌ��ʂ��Ă��邩����e�I�ɘA��������K�v���������悤���B�_���V���[�Y�̃t�@�����炷��Ɓu���ׂĂ̂͂��܂�v�ł���A�[�f�B�e�B���������[�����A��l�_���iDies irae�j�Ƒ�Z�_���i�_��_�А_�y�j���q���G�s�\�[�h�ł����ܐ_���̕������߂ɖ��߂Ăق����ӏ��������̂ŁA�A���ƌ����A����������܂���B�A�[�f�B�e�B�����́A�匳�́wDies irae PANTHEON�x�ł͉B���G�s�\�[�h�I�Ȉ����������炵�����B�����A��ܐ_���͋������������Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ��c��Ȃ̂ŁA���ߐ��̂��ǂ������S�z�ɂȂ�Ƃ��낾�B�w�����̃A���F�X�^�[�x�͔�r�I�����ɐi���2�N���x�ŘA�ڂ��I��������A�w���ےn������A�[�f�B�e�B���x�͓�q�����݂����ŘA�ڂ���3�N�o�����Ƃ���Œ��f�i�S5���\�z�ŁA��3���̓r���܂Ői��ł����j�B�A���F�X�^�[�̃Q�[�����ȂǑ��̍�Ƃ��d�Ȃ��ĖZ���������낤���ǁA���̒��q����Entelecheia�������ɐi�Ƃ��ĘA�ڊ�����2027�N���A�����|�����2028�N�A��q�����2029�N��2030�N���炢�ɂȂ肻�����B�A�[�f�B�e�B���̕����A�ĊJ�����܂����Ƃ��Ă��������犮���܂�2�A3�N�|���邩������Ȃ��B�������c�M�҂̂قƂ�ǂ͒�������o�債�Ă��邾�낤���A���������đ҂����Ȃ��ł��ˁB
�E�u�E�҂̃N�Y�vTV�A�j�����A�E�҂ƃ}�t�B�A�̌���ٔ\�o�g���@�����OLM�i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@�����A����8�N���炢�O��1�����o�����Ǒł�����2������������Ȃ������w�E�҂̃N�Y�x���A�j�����I�H�@�߂��Ⴍ����r�b�N�����Ē��ׂ����ǁA�ǂ�������t�@���̖���Ƃ��ł���ꂽ��Ɏ����Łi���e�����Ȃ��Łj�h�������R�~�J���C�Y�𑱂������ʁA2022�N�����C�h�Ђŏ��Ɖ����A�l�C�ɉ��_���ăA�j�����܂œ��B�����炵���B���A�������b���ȁB����ɔ����Č���̏����ł��ď��Љ������͗l���B�܂�������ȃ~���N�����N���낤�Ƃ́B����҂́u���P�b�g����v���w�E�ҌY�ɏ����x�Ƃ�����i���������č��N�A�j���������\��Ȃ�ł����ǁA���̐����Ȃ��w�����s�s�x�܂ŃA�j���������˂Ȃ��ȁB��x�ł���ꂽ��i���A�j�������ď��Љ�����́A���������Ă����c�c�����wF�����N�̖\�N�x���w���Ɖ��̃f�B�A�X�t�F���h�x��������ĕ]������đ������o���Ăق������B
�E�wBanG Dream! Ave Mujica�x��11�b�uTe ustus amem.�v�A���Ɂu�O�p���v�Ɩ�����Ă��������̐��̂����炩�ɂȂ��ł����B
�@�{���́u�O�p�����v�A���e�͖L��ˎq�̑c���ł���u�L��莡�v�ŁA��e�͓��ŖL��Ƃ̕ʑ����Ǘ����Ă��������B�܂�u����l�̉B���q�i���O�q�j�v�Ƃ����ꕔ�̃o���h���[�}�[�ɂ��\�z�����������`�ɂȂ�܂��B�����A�u�{���̎O�p���v�͑o�q�ł͂Ȃ����e�̈Ⴄ���A�ٕ����ł����B�u�Ȃ�����l�͏����𖺂Ƃ��ĔF�m���Ȃ������H�v�Ƃ����^��́A�u���������ł͂Ȃ��莡�����{�q�������v�Ƃ��������������������ƂŕX���B����l�������l�ɑ��Đh煂ȑΉ������Ă����͎̂��g�̗��������قǔՐł͂Ȃ��������炾�����̂��c�c�B
�@��ƌ��������{���i���̐l�̐����O�p�j�͈����l����Ȃ������݂��������A�u�����Ƃ͌��̌q���肪�Ȃ��v���Ƃ�崂������Ă��������B����Ȓ��A�L��̕ʑ��֔����ɗ����ˎq�Ɩ��̏������ǂ��ɂȂ�B�����Əˎq�͏f��ƖÂ̊W�ɓ�����iJOJO�̏Ə����Y�̊W�ɋ߂��j���A���͌����I�ɂ͊��S�ɑ��l�Ȃ̂œ��ɖ��͂Ȃ��B�����A�莡�̉B���q�ł��鎩���Əˎq���e���ɂȂ�����v��ʑ������N���邩������Ȃ�����A�Ƃ������R�ŐڐG���S�O�������B�������A�u�{���͎����������Ȃ��Ă�����������Ȃ��L��̎q�v�ւ̋����͉����E�����A�ˎq�����ɍs���āA�炪���Ă��邱�Ƃ��珉�ƌ�F����Ă��܂��B�f����T��ꂽ���Ȃ����������͏��̃t�������ďˎq�ƗV�Ԃ����A�ޏ��ɖ�������Ă����\�\���֗����Ƃ��ɏˎq�������Ă����l�`���������m��Ȃ��������ƁA�u����i�ˎq�̕�e�j�Ɖ�������Ƃ�����v�Ǝw�E����ďł����悤�Ȋ�����Ă������ƁA�v���o�b�������ɐH������Ă������ƁA���߂�ɍs�����Ƃ��Ɛ������Ă����Ƃ��ŕ������Ⴄ���ƁA�ߋ��ɂ���߂Ă�����������C�ɉ������܂����B�����̕��G�Ȑ���������m��Ȃ��ˎq�ƈꏏ�ɂ���Ƃ������A�����́u���킢�����Ȏq�v�ł͂Ȃ��u�l�ԁv�ł�����B�ł����Ԃɍs���Ɩ��̏��ƃJ�`�����\��������̂ŁA��̊Ԃ����������Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ����c�c�u���z�v�̏��Ɓu���v�̏����B���Ԃ�o���h���ɍ�������O�̐ݒ�ł͏��Ə����͑o�q�ŁA�u�S���Ȃ������ɂȂ肷�܂��Ă���v�Ƃ����^���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���邪�A�u���܂�ɏd������v���ė��R�Ńi�[�t����āu�ٕ����ő������v�ɕύX���ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���i���Ƀ\�[�X�Ƃ��͂Ȃ��A�P�Ȃ鎄�̖ϑz�ł��j�B
�@�u�����j�i�莡�j�̌��������ҁv�ł���Ȃ���u�L��̎q�v�Ƃ��Ă��P�l�̂悤�ɉ߂����Ă���ˎq��i�݂䂩��Ă��������̐S��͂��ꂱ���uOdi et amo.�v�ŁA���̃t�������Ȃ���ڂ��Ă��邤���Ɏ����̖{���̋C���������Ȃ̂��O�`���O�`���ɂȂ��Ă��܂��Ė{�l�ł��悭�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��낤�B����ȏ����̐l���͗{���̎����L�b�J�P�ɈÓ]����B�C�̎��̂ŋA��ʐl�ƂȂ�A�u�o������v�Ƃ������R�ŋC��ɐU�镑���Ă��������͖�����u�p�p���Ⴄ����߂����Ȃ��I�v�Ɛӂ߂���B���̌��t�ɏ����Ȃ�����A�u���̂ŋ}�ɖS���Ȃ����Ƃ����̂ɁA���݂����ɓ��h���ēx���������肵�Ȃ��̂́A�{���ɔ߂����Ȃ�����Ȃ̂ł́H�v�Ǝ������g�ɑ��ĉ��^�������Ă��܂��B�u�߂��݁v�Ɏ��M�����ĂȂ��ޏ����u�h�����X�i�߂��݁j�v�Ɩ�����Ă�������ȍ\�}�B���ɋ��ꏊ���Ȃ��Ɗ����������͒��߂Ă����������������đD�ɏ��A���H�y�X�㋞����B���̂ւ�ŋC�ɂȂ�̂́u�����⏉�͊w�Z���ǂ����Ă����̂��v�Ƃ������B�������u���v�Ɩ������TV�ɏo������قNJ��Ă���A���͂������̂��Ə��w�Z�⒆�w�Z�ňꏏ�������q�͓��R�C�Â��đ����ɂȂ�͂��Ȃ̂Ɂc�c�ߑa�n�̓�������w�̂�̂�т��x�̈��u���Z�݂����ɏ��������Ő��k�����l�������Ȃ������̂��ȁH
�@�炪�ǂ����炩�㋞���X�ɃX�J�E�g���ꂽ�����́A���̏����u�����֍s���ăA�C�h���ɂȂ�I�v�Əˎq�ɖ�������Ă������Ƃ̒��덇�킹�Ƃ��āA�u�O�p���v�Ɩ�����ăA�C�h����ڎw���B�܂菉�����g�͕ʂɃA�C�h���ɓ���Ă��炸�A�u�f�r���[������������ƍĉ�ł��邩���v�Ƃ������҂���|�\�E���肵�����ƂɂȂ�Bsumimi�̊����Ŕ�ꂽ�悤�Ȋ�����Ă����̂��A�C�h���ҋƂ��̂��̂ɑ��郂�`�x���Ⴂ���炾�낤�B�Ƃ��������n��I�ɏ������u���v�Ƃ��ăf�r���[����̂�CRYCHIC���U�O�Ȃ̂ŁA�܂����w���������͂��c�c�܂������w�Z�𒆑ނ��ăA�C�h���ɂȂ����̂��H�@�����A�C�h���H�@����A�ԍ�쏗�q�w���ɒʂ��Ă�����炻�̂ւ�͒莡������Č��͂ő��ƈ����ɂ������A���邢�͖{�y�̒��w�Z�ɓ]�Z�����̂��ȁB�o���h���͓��{�Ȃ̂ɔ�ы��̎q�����鐢�E������A�w��ݒ�Ɋւ��Ă͊��ƃ����߂ł��B�ˎq�ɑ��āu�����̖Áv�ƃn�b�L���������Ă���̂ŏ��Ȃ��Ƃ��N��̂͂��Ă��Ȃ��͂��B
�@��������悪��������g��ł��܂��ˁB�X�J�E�g����āA�u���c�܂ȁv�ƃ��j�b�g��g�ނ��ƂɂȂ������A�����N�Ȃ̂ŕی�҂̋����K�v�ɂȂ�B�������̎В��Ɂu�L��莡�̍��O�q�v�ł��邱�Ƃ𖾂����A�莡����������Ƃł܂ȂƂ̃��j�b�g�usumimi�v�͓����ɑ�X�I�Ɏ��グ����B�f�r���[�O�A�傫�ȃr���̗������ŏˎq�̕��e�ł���u�L�쐴���v���������A�ˎq�Ƃ�����x�������S�̏����͐��炢�Ȃ̏o�����������Ă��܂��B�����́u������L��̎q�Ƃ��ĔF�m���ׂ����v�ƒ莡�ɑi���邪�A�L��{���̌��łȂ��莡�̍��O�q���}���邱�ƂȂǑ��̐e���������Ȃ��A����Ȃ��Ƃ�����Β莡�����r���A�����̏ˎq���H���ɖ������ꂪ����c�c�Ɠ˂��ς˂���B���̂ւ�̌�����͐������璼�ڕ������̂��낤���H�@�ŁA����ɐ������ǂ��o�����B
�@�����ȃ^�C���e�[�u���͂킩��Ȃ����A���������̗���Ƃ��Ắu����i�ˎq�̕�j���a�ɂ���������������ˎq�A���m�X�̍u���Ń��j�J�̃��C�u��r�ƈꏏ�Ɋӏ܁��o���h�A�ł���I�����t�y���̂�������U�A�A�蓹�œ����琁��Ŗ��^��i����̎o�j���痧����Љ�Ă��炢�ACRYCHIC�������������ɏ����̗{�������̎��������͒P�g�㋞���A���X�J�E�g����遨�������̎В��ɑf���𖾂����A�܂ȂƂ̃��j�b�g�wsumimi�x�Ńf�r���[���邱�Ƃ����聨�f�r���[�O�̃C�x���g�Ő����Ɖ���Ē莡�̍��O�q�ł��邱�Ƃ�ł������遨�ˎq�Ƀf�r���[�����܂������Ƃ�`����i�A����������������̂��A�ˎq�����̏��ƘA������������Ă��Ȃ��m�M���������̂��A�ȂǍׂ����^��_�͂��邪�ЂƂ܂������j��CRYCHIC�����C�u���J�ÁA�����삯���遨���C�u�I����A��������w�����ꏏ�ɕ�点�Ȃ��x�ƘA�������遨CRYCHIC���U�A�قړ�������sumimi���f�r���[�v�A����Ȋ������낤�B�������͂��Ƃ��ƌ|�\�l�ɋ������Ȃ��A���Ă̂����邾�낤����sumimi���f�r���[���ă��f�B�A�ɑ傫�����グ���Ă�������CRYCHIC����ςȎ������������珉�̊�▼�O���S�R�o���ĂȂ������낤�B�����͖����g��Ave Mujica�Ƃ����o���h�Ɂu���̌����҂�����v���Ƃ�m���Ă������ƂɂȂ邪�A���̌���ɓM�ꂽ���Ƃ������Ăǂ��ł��悭�Ȃ��Ă��܂����̂��낤���B
�@�����̎�ςł́u�����̏����������đΗ������v���Ƃ������Ő����͖L��Ƃ���������ꂽ���ƂɂȂ��Ă��邪�A���䂪�S���Ȃ��Ă������Ƃ��m��Ȃ��������炢�����A168���̍��\�������\������c�����ĂȂ����낤�B�Ȃ̂Ŏ����҂��炷��Ə����̎�ς��������̂��Ԉ���Ă���̂����f���������B�u168�������͌����������v�ƒ莡�{�l���F�߂Ȃ������肱�̌��͌������Ȃ��ł��傤�B�����͂ǂ�����A�������_�ł́u�����̉I舂ȍs�������ƂŐ������L��Ƃ���ǂ��o����A���e�����̂Ă��Ȃ������ˎq���Ƃ��яo���A�v���ߏ삳�Ȃ���̋�J������n���Ɋׂ����v���ƂɂȂ�B����c�c�₯�ɏˎq�̋����ɏڂ������ǁA�����ƊĎ����Ă��̂��c�c�H�@�܂��������|�����ǁBsumimi�Ƃ��ĖZ������������T��A�v���C�x�[�g�̎��Ԃ�Â��q�̃X�g�[�L���O�ɔ�₵�Ă����Ȃ�ăt�@�����m�����玸�_���Ă��܂����낤�B
�@�ˎq�ɑ��Ĉ������荬����C�������������Ƃ͂����A�h���ڂɑ����Ăق��������킯�ł͂Ȃ������͍߈�����������ƂɂȂ�A�߈����䂦�ɖӖړI�Ȉ�������邱�ƂɂȂ�B�Ȃ�Ƃ������A�w�v�����Z�X�E�v�����V�p���x�́u�ψ����v���v���o����������ȁc�c�X�p�C�{�����ɑ����A���їD�G���������̂̍K���Ȏv���o���낭�ɂȂ��A�~�b�V�������T�{���ăh���V�[�ƈꏏ�ɂ������ړ��V���n�̋L���������B��̋��菊�������q�B�u���̂Ƃ����߂ėV���n�ɍs�����̂�B�y���������Ȃ��c�c���ł����Ɍ���̂�A���Ȃ��ƗV���ƁA�������Ɓv�@�ɉՂ܂�u���ȁv��ۂĂ��ł�ł����A�S�カ�ҁB�u�����̏X���v����ڂ�w�������Ă��������͂����Ɉˑ�����悤�Ȓ��q�ŏˎq�Ɉˑ����Ă���̂��낤�B���Ȃ݂ɏ㋞��A�������w�Ƃ��ǂ����Ă����̂�����Ă��Ȃ����疾�Ăł͂Ȃ����A�ԍ��ɓ������Ƃ������Ƃ͍Œ���͂��Ă���͂����B�|���͂܂������ːЂ��C�W���āu�O�p���v�ɂ��Ă��܂��Ɩ{���̏��ɗ݂��y��ł��܂��̂ŁA���炭�w�Џ�͖{���́u�O�p�����v�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���ʂȎ������Βʏ̎g�p��������邾�낤���A�����̎���ł͖������낤�B�������̗����C��́u�O�p����v�Ƃ����Ă�ł��Ȃ����A���̃N���X���C�g���u���v�ł͂Ȃ��usumimi�̏��v�ƌĂ�ł���̂ŁA�u�{���ƌ|�����Ⴄ�v���Ƃ�m��債�ċC�ɂ��Ă��Ȃ��̂��낤�B�o���h���̊����o���h�ł���RAS���ƁuRAISE A SUILEN�v�̃����o�[���{���ƃo���h�l�[���͕ʁi���Ƃ��u�`���`���v�̖{���́u��肿��v�����A�ޏ���{���ŌĂԃL�����͂قƂ�ǂ��Ȃ��j�ł��B
�@�Ƃ͂����A�{���u�O�p�����v�����ł���u�O�p���v���x���āu���v�Ƃ����|���Ńf�r���[���A���W�J�ł́u�h�����X�v�Ƃ����o���h�l�[�����g���Ƃ����o���h���j������Ƃ���₱�����q�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͊m���B�N���X���C�g�̊C�邪��������u�����v�Ƃ����{�����o�����Ă��܂������Ŋ��������˂Ȃ��A���X�̏�Ő������Ă��鉼�ʐ����ł��B20���߂��g���āu�����̈�l�ŋ��v�Ƃ����`���Ő^���𖾂�������A����͒莡���u�����A�A��Ȃ����v�ƌ������|�C���g�֖߂�܂��B����ȏ�ˎq�Ə����̓ƒf�������ł��Ȃ��Ȃ����莡�́u�ˎq���X�C�X�ɗ��w������v�Ƃ������d��i�ɑł��ďo��B�u�Z�������I������v���Ƃ�����������͉ו����܂Ƃ߁A�̋��ł��铇�֖߂�B�ˎq�͓�֏�ԂʼnƂ���o��ꂸ�A�����͊��ɓ������狎�����B������������Ƀ����o�[2�l�������ċ@�\�s�S�Ɋׂ��Ă��܂������W�J�B��@�I�ȏȂ̂Ɂu���������̂�߂Ăق�����ł���A�g���E�}�Ȃ�ł���I�v�Ƌ��ԊC��̖����Ɠ������ăV���A�X�ȃ��[�h���������ł��܂����B�Ƃ������Ȃɂ���sumimi�����U�̊�@����Ȃ����R���B�ŋ߂͂܂Ȃ������\���̎d���������Ă��Ă�݂�����������U���Ă�����Ă����邾�낤���ǁA�����Ȃ莫�߂�ꂽ��˘f���Ȃ�Ă��̂���Ȃ��ł���B�ǂ������������}����ɂ���A�����͂�����L�`���Ƃ܂Ȃ����Ɏӂ������������̂ł͂Ȃ����B
�@���Ă������i�����j�̔閧���������ꂽ���ƂŁA��́u�ˎq���������e��邩�ǂ����v�Ɓu�莡�̖W�Q���ǂ�����ď��z���邩�v�A���͂ӂ��ɍi���܂����B����l���X�C�X���w�Ƃ������d��i�ɏo���́A�u���̖L��Ƃ̘A���̎�O�d���Ȃ��v�Ƃ������ƂȂ낤���A�u�ނ��덡�܂ł̃��W�J�̊����͗e�F���Ă����v���ăr�b�N�����܂���ˁB�L��{���̌����p���ˎq���u�M���Đ��ꗬ���v�Ƃ��ucode 'KiLLKiSS' uh�c�c�v�Ƃ�����Ă�̂�OK�������c�c��K�[���Y�o���h���ゾ���炩�H
�@�c�肠��2�b�A�P�炸�ɍl����u����Ɏ��Ă��Ⴖ��n�v�ȏˎq���L��@��E�����A�P�g�ł����̃����o�[�𗦂��Ă��͂킩��Ȃ������Ɍ������ď������}���ɍs���B�g���������Ƃ��鏉����������ē�����A��o���A�莡����Ƃ�������b�������������Ŏ����̈ӎu�������ʂ��B�X�ꂽ��L��̉Ƃ���o�Ă������ƂɂȂ邩������܂��A����͂���CRYCHIC�̂Ƃ��ɂ���Ă邩��u���܂������ĖL��Ƃɋ��c����W�J�𑱂���v�����Œ�������̂ł͂Ȃ����ȁB�u�q����������l�̌��͂ɗ����������v�Ƃ����̂͐̂̃A�j���ł悭�������W�J�����A�u��l�̌��́v�����܂�ڍׂɕ`���Ă��ʔ����Ȃ�Ȃ��̂ő�G�c�Ɂu���y�̗͂ł˂�������v�����ɂȂ��Ȃ����Ǝv���܂��BCRYCHIC�̑��Ǝ����I�����ˎq�ɂƂ��đ�Ȃ͉̂ߋ��ł͂Ȃ��u���ꂩ��v�Ȃ̂ŁA�������R���܂����Ă������Ƃ������܂Œv���I����Ȃ��B�l�܂�Ƃ���ˎq���u���Ɩ���鏉���v��I�̂́u�����̓���݂�����v�ł͂���܂���BMyGO�̏t���e�ɃV���b�N����RiNG�����яo�����ˎq�����グ���X���r�W�����A�����ɂ������u���v����������������ł��B���Ƃ͂������ǂ������ɔ[�����Ă��炤���ł��ˁB�M���M���ڂɎ��܂肻�������ǁA�܂Ȃ����͍Ō�܂ʼnᒠ�̊O�ɂȂ肻���Ȃ̂��s�����ȁB�u�S���̂ǎ������5�A�e�v�Ƃ����ߋ������炩�ɂȂ����܂Ȃ����A�ˎq�Ɠ����^�C�~���O�œ��ɏ㗤���ď�������荇������C����D���̎��Ƃ��Ă͑勻���Ȃ̂����A�ʂ����Ă���2�b�Ƃ�������ꂽ�ڂ̒��ł܂Ƃ��ȏo�Ԃ��p�ӂ���Ă��邾�낤���B
�@����قڏ����̈�l��肾�����̂Łu�ǂ��܂ł��^���Ȃ̂��v�s���Ăł���A�ɒ[�̏ꍇ���Ɓu�������Ȃ�čŏ����炢�Ȃ���H�v�ȃC�}�W�i���[���̃p�^�[�������肦���ȁc�c�������u���v�Ƃ������������Ă����������Ă����B�r�^���[�e�B�X�Ɣ�邩�炳�����ɂ�������̂̓N�h������A���ʂɁu�{���̏��v���o�ė����Ȃ����A�Ǝv���܂����B�{���̏��́u�����ŃA�C�h���ɂȂ肽���v�Ƃ��������Ƃ����Ɍ��Ȃ��Ȃ��Ă��ĕ��ʂ̒��w���ɂȂ��Ă���̂�������܂���B�����̖��O���x���Ă���o���ǂ�ȋC�����Ō��Ă���̂����C�ɂȂ�Ƃ��낾�B
�@�����12�b�̃^�C�g���́uFluctuat nec mergitur.�v�A�p���̕W��Ƃ��ėL���ȁu���䂽���ǂ����܂��v�Ƃ����Ӗ��̌��t���B������������g�������肵�ėh��邱�Ƃ͂��邯�ǁA�����Ē��܂Ȃ��B�v���Ԃ�Ɋ�]�̌�����薼�ł��B���c�}�n�̏����ɂ��̌��t�����ɂ����w���䂽���ǂ����܂��x�Ƃ����{�����邵�A�����Ⴄ�����쓹�̏����ɂ��w�Y���ǒ��܂��x�Ƃ����{������B�w�a�t����āx�Ƃ����V���[�Y��6���ڂ��BAve Mujica�Ƃ����a�t�͂��������ǂ��֗��ꒅ���̂��B
�E�O�}�����w���������̐��T���@�\���y�Z�v�e���f�L���z�x�ǂB
�@2001�N�Ɏn�܂���2023�N�Ɋ��������i����k�܂ޒZ�ҏW���܂߂��2024�N�Ɋ��������j�w�E�B�U�[�Y�E�u���C���x�̍�ҁu�O�}���v������24�N�Ԃ�̐V�V���[�Y���e�ł���B�w���������̐��T���x�����C���^�C�g���Łw�\���y�Z�v�e���f�L���z�x��1���̃T�u�^�C�g���A��l���u���b�g�v���������閂���̖��ł��B���̒��q����2����3���������̖��O���T�u�^�C�g���ɂȂ�̂�����BSF�F�̋��������O��ɑ��A����̓t�@���^�W�[�F�����߂ŁA���SF���ۂ����͋C���c���Ă��銴���B�u�����v���n�߂Ƃ���I�[�p�[�c���݂��Z�p�����݂��鐢�E�Ŏ�l�������u���������v���s��ȃ\�[�h�E�A�N�V�������J��L����B
�@2000�N�ȏ㑱�����u�����푈�v���A���ɏI���\�\�����O�܂ʼnp�Y�Ɛ��߂�ꂽ�u�����g���v�́A���△�p�̒����Ɖ����Ă����B�ށE�ޏ���́u�p���߁v�ɂ���ċ��ꏊ�������A�卑�̈Ќ����͂��Ȃ����n�u�Z���g�����v�ł̂ݑ��݂�������Ă���B��̍��u�I�[�X�g�v�������Ă��������u���b�g�E�O�����g�v�́A�S����Ƃ̐������ʂ����u�V����̖����g���v�ƂȂ��ČȂ����𐢊E���ɍ������悤�ƁA�ӋC���V�Z���g�����̖��������B�������A�����͂����錻���͌����������B���͂▂���g�����m���n�������ċ����������ȂǁA���������r�������B�Ђ��[���猈����\������ł��f���A���������ǂ��납�}�b�`���C�N����ł��Ȃ��B�d���Ȃ��u�M���h�ɏ������Ĕƍߎҕߔ��▂�b�ގ��̈˗��ł����Ȃ����v�ƍl���邪�A�푈�I�����炱�����A�H���l�ߎ҂ƂȂ��������g�����e�n���牟���Ă���Z���g�����ł́u�r�������ǂ����v�ł͂Ȃ��u�M���ł��邩�ǂ����v���d�v������Ă���A�Љ��̈�������ʏ����Ȃ�Ăǂ�����O�����B���Ɍ�`�F�X�g���Ă��܂����ꍇ�u�N�����Q��⏞������I�v�Ƃ������ɔ��W���邽�߁A�Љ��Ȃǂ����ȒP�ɂ͏����Ă��炦�Ȃ��B�V����ɂȂ�ǂ��납�����̐���������Ԃ܂�鋇�n�ɗ������ꂽ���b�g�B�r���ɕ�ꂩ���Ă����Ƃ���A���̍��u�G�C�V�A�v�̂��̂������ɏP���Ă����ʂɑ������A����K���ƌ��ނ����Ƃ��날��₱���̖��u�_�O�����ٔ��v�ɏo�ꂷ��^�тƂȂ��āc�c�B
�@�V����̖����g���ƂȂ�ׂ����������̂Ɋ̐S�̐푈���I����Ă��܂����I�@�Ƃ����g�z�z�ȏ�Ԃ���n�܂�\�[�h�E�A�N�V�����E�t�@���^�W�[�ł��B��l���̃��b�g�����͍D��I�ŁA���������ޑ���Ɂu�Ք��荇�������I�@�Ք��荇�������ł���������I�v�ƍ��肷�邨���ڂȂƂ���������ĉ����ł��B�����������ɂ��ւ�炸���̈ꖡ�ƊԈ��ꂨ�̂�����̌�q�ƌ���������n���ɂȂ�A�������ő���̘r���ւ��܂��Ă��܂��āA�ނ��o�ꂷ��\�肾���������ٔ��ɑ㗝�ŎQ�����邱�ƂɂȂ������b�g�����B��������͋������ƕ����Ă����̂ɂȂ����אg�̔��������o�Ă��č�������n���ɁB�Ȃ�Ă������Ȃ��A���̎q���o�ꂷ��\�肾�����j���u�`�̂߂��Ă��܂��������ő㗝�Q������^�тƂȂ��Ă����̂ł���B�h�L�b�I�㗝���炯�̐_�O�����ٔ��A�|���������邩����I�i���ɍ�������ւ̉Ԃ��|�����ƎU��Ό����Ƃ������[���j
�@���āA�{���̓ǂ݂ǂ���͉��ƌ����Ă������g�������ɂ�錕���V�[���B���Ƀ��b�g�����̎E�w�͂��Ȃ�f�������Ȃ̂Łu�͂₭�A�j�������˂����ȁv�Ɠǂ�łċC���}���Ă��܂��B���b�g������閂���u�\���i�Z�v�e���f�L���j�v�͂��̖��̒ʂ�17���̐n���d�˂č\�z���ꂽ�匕�ł���A���܂�̃f�J���ɏ�ɔ[�߂邱�ƂȂǂł��Ȃ��B���ɒ邱�Ƃ��w�������Ƃ��s�\�B���Ⴀ�ǂ�����̂��Ɛ\���܂��ƁA�d�͐���̂悤�Ȗ��@���g���ăZ�v�e���f�L���𒈂ɕ������Ă����ł��B�����g�̂܂܁A�ӂ�ӂ��STG�̃I�v�V�����݂����Ƀ��b�g�����ɒǐ�����Z�v�e���f�L������A�z������Ɣ��܂����悤�Ȃ�����ƕ|���悤�ȁB�����Ƃ����ʂ�Ƃ��ɂ�����ƌX����`�ʂ��o�Ă���̂��ׂ����ł��B���b�g�����͂��̃Z�v�e���f�L����������u���삵�Đ키�킯�ł����A�{�̂������l�ʂ��Ă����˂������Ă���킯����Ȃ��A�b���グ���̏p����g���ēG���u�`�̂߂���Ƃ���B�܂�R�����艣�����肵�Ȃ��疂����ア����a�艺�낵����A�Ƃ��������^�b�O�}�b�`�̂悤�ȉ��~�ɂȂ��Ă���̂��B���̟��ނ悤�ȓw�͂ɂ���ăZ�v�e���f�L������̐���͊����ɂȂ��Ă��邩��A���̐n�𑫏�ɂ��Ē�����A�������g��싅�̃{�[���݂����ɑł��o���ē��U�i�u�b�R�~�j���������肷�邱�Ƃ��ł���B�A�N���o�e�B�b�N�����āu�����l�̐킢������Ȃ��c�c�v���ĂȂ邯�ǁA���b�g�����̓T�����C����Ȃ�����ʂɂ������B���o�I�ɂ́u�t�@���l���g���Ȃ���ڋߐ�ރ��r�[���X�[�c�v�ł���A�܂�Ń��{�b�g�A�j���ł��ςĂ�C���ɂȂ�܂��B���̒��ŋ����Ă���BGM�́w���b���S�����x�́uBLADE ARTS �V�v���B
�@���b�g�����ȊO�ɂ��A�u������苭�����Ƃ��t�������������v�Ɗ���Ėk�̍��u���`�A�v�������Ă������C�s�A���u�R��i�����X�g�D�����j�v�i�d����C�ӂŕύX���邱�Ƃɂ��u�M�|�̃��[�r�B�E�f�B�b�N�݂����ɓ��������Ƃ��̈З͂𑀍�ł���j�̎g����u�N�����E�N���E�N�����v��A���ĂƂ���u���Ёv�ɏ������Ă��������͓Ǝ��̖ړI���ʂ������߂ɒZ���^�����u�S�m�i�I���j�V�A�j�v�i���l�̖����̐����D�����A�������ŗL�̌��\�܂ł͒D���Ȃ��j����g���ĈÖ�u�\�t�B�A�v�Ƃ��������������������o�ꂵ�܂��B�`��120�y�[�W���炢��3�l�̖������������X�ɏЉ��`���ƂȂ��Ă���A���͋C��������ƌQ�������ۂ��B�\�t�B�A�����H���A�����푈�����O�i�܂�2000�N�ȏ�O�j�Ɂu�ŏ��̖����g���B�v���u���̖�ЂƖ����̌R���v�Ɛ_�b�I�ȑ������J��L���A�����̗͂ł������u���Ȃ��v�ɕ������߂��Ƃ����B�u���Ёv�ƌĂ��W�c�́u���Ȃ��v�̕���������āu���̖�ЂƖ����̌R���v�𐢊E�ɌĂі߂����Ƃ����B���Ɂu���Ёv�͕������A���̎c�}�ǂ������߈����v��s���悤�Ƃ��Ă���B���܂�ɂ��X�P�[�����傫���ĉ₩�ɂ͐M�����������b�g�����ł��������A�ⓚ���p�Œǂ��闧��ɂȂ��Ă��܂��A�ۉ��Ȃ��N������\�t�B�A�ƃ`�[����g��Ő키���ƂɂȂ�܂��B
�@��l���̖ڕW�́u�ŋ��̍��v�ɓ��B���邱�ƂŁA���̓_�Ɋւ��Ă͒P�������Ȃ�ł����A����s���Łu���E�ŖS�v��h���킢�Ɋ������܂�A�u�Ȃ炸�ҁv�Ƃ��Ēǂ���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��ȂǁA�v���`���Ă����p�Y杂Ƃ͑S�R�Ⴄ�����ɓ˂��i�ށB�����Ƃ����u���Ёv�̋K�͂͑z�����Ă���A2000�N�����������푈����u���Ȃ��邽�߂Ɏg�p����Ă��閂�����e���������悤�d������v���߂Ɂu���Ёv�������N�������s��ȉA�d���������\�\�Ƃ������܂����B�l�����ꂽ�R�̉��ň�Ă�ꂽ���b�g�����ɂ͙��邱�Ƃ������B���b�g�����́u�O�����g�Ɓv�͏\���i�Z�v�e���f�L���j�Ƃ����K�i�O�̖������p�����Ȃ�����A�K�i�O�����邪�䂦�ɊJ�c�ȊO�N���g�����Ȃ��Ȃ��Ƃ�������ɒ��ʂ��A�v���̖��Ƀ��b�g�����̕�̑�Ŕp�����Ă��܂����Ƃ����߂����o�܂����B�p��������Ƀ��b�g�����Ƃ�������ȗ��̎g���肪����A�Ȃ̂ɖ����푈����I����Ă��܂����Ƃ����̂��������Șb���B���������������u���b�g�E�O�����g�v�̓��b�g�������ɖ�����Ă��邾���ł���A�O�����g�ƂȂ���̂͌������Ă��Ȃ��B��ʓI�ɃC���[�W�����u�Ɓv�̃C���[�W���Ȃ����̏C�s�ɖ�����ꑱ�������̐l����z���āu���߂�Ȃ����v�Ǝӂ��ƁA�u�����A���Ȃ��̖��Ƃ��Đ��܂�čK���������I�@���Ȃ��̖��Ɗ肢�͕K���ʂ����܂��I�v�Ɛ������b�g�����̌��͉��x�ǂ�ł�������B�₪�āu���Ёv�̎c�}�ɂ���āu���Ȃ��v�̕���͉�����A���̌���������u�Ђ��v������Ă���B�H���l�ߎ҂Ƃ͂��������g�����W�܂�X�Ȃ̂ňՁX�Ɓu�Ђ��v�ɋ����邱�ƂȂ������Ȃ����u�������R���W�J�̓A�c�����A�_�b���̎��Ԃɂ����Ă͏Ă��ɐ��B���E�̖��^�͎O�l�̖��������ɑ�����邱�ƂƂȂ�܂��B
�@��L�薂�������̃X�N���b�h������s���Ő��E���~���I�@�Ƃ����A�E�B�Y�u���Ɣ�r���Ċ��ƃX�g���[�g�Ƃ������ɉ���y�����ȃm���Łu�O�}���炵���v�͂��ł�����ǁA�`���ɏo�������`���C���̖����g�����ӊO�Ȋ������������A���߂����ɂȂ�����l�����݂肵���̕�̌��t�����N�����ė����オ�点����ȂǁA���J�ɐ���オ��v�f��ςݏd�˂Ă����ăh�J�[���ƌ���������o���Ă���܂��B�܂��܂��s��ȕ���͎n�܂���������ă��[�h�Ȃ̂ő������y���݂��B��҂̙ꂫ���炷���2���ڂ̌��e�����M���݂����ŁA3���ւ̕z�𒅁X�Ƒł��Ă���݂��������甄��ʂŌ��������ƂɂȂ�Ȃ���܂��܂��u��v������͂��B�����A���Ƃ����ő��̏��������������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���̂�10���ȏ㑱�������V���[�Y�ɂ͂Ȃ�Ȃ���������܂���B���z�Ƃ��Ă�3���炢�V���[�Y����s���ēW�J���Ă��炢�����Ƃ��낾���ǁA�O�}���ɂ����܂ŋ��߂�̂͂������ɖ����Ɛ\���܂����c�c�Ƃɂ������́w���������̐��T���x���~����������Ƃ���܂Ŏ����čs���Ăق������̂ł��B
�E�f����w�r�[�L�[�p�[�x���ς܂����B
�@�u�W�F�C�\���E�X�e�C�T���v�剉��i�B���̂����z�M����邾�낤�ȁA�Ƃ͎v���Ă��܂���������Ȃɑ����z�M������Ƃ͗\�z���Ă��Ȃ��ăr�b�N�����܂����B�A�����J�Ō��J���ꂽ�̂�2024�N1�����������1�N�ȏ���O�Ȃ�ł����ǁA���{���J�͂��Ȃ�x���2025�N1���A�ق��2�����O�ł��B�ḗu�f���B�b�h�E�G�A�[�v�A�u���b�h�E�s�b�h����Ԃɏ��f���w�t���[���[�x�Ƃ����B�����l�B���w�X�[�T�C�h�E�X�N���b�h�x�̊ēł�����̂ŃA���R�~�t�@������̕]���͋X�����Ȃ����A����Ɋւ��Ắu�����̃R���g���[���̌����Ȃ��Ƃ���őS�R�Ⴄ���̂ɂ���Ă��܂����v�ƌ���Ă��邩��ē��g�ɂƂ��Ă��s�{�ӂȏo���������悤���B�r�{�́u�J�[�g�E�E�B�}�[�v�A�����w���x���I���x�̊ēƋr�{�߂��l�ŁA�ꕔ�̃}�j�A�̊Ԃł͗L���B���̉f��̓J�[�g�E�E�B�}�[�̃h�C�c�ɏZ��ł��锌�ꂪ���ꍼ�\�̔�Q�ɑ��������Ƃ����̔��[�Ƃ������ƂŁA���\�Ƃǂ��ɑ���{�肪�����Ă���B�u���}�͎��ˁI�v�@����ȊO�̃��b�Z�[�W���͂قڂȂ��A�X�J�b�ƒP�������Ɋy���߂�A�N�V�����f��Ɏd�オ���Ă��܂��B
�@���Ắu�{�I�Ɓi�r�[�L�[�p�[�j�v�ƌĂ�钴�@�K�I�ȔC���ɏ]������閧�H������������A���ތ�̍��͓c�ɂŕ��ʂ̗{�I�ƂƂ��ĕ�炵�Ă���j�u�A�_���E�N���C�v�i�U���A�o���͖�������Ă���{���s�ځj�B�������A�[����݂��Ă����אl�u�G���C�[�Y�E�p�[�J�[�v�����ꍼ�\�̔�Q�ɑ����A���g�̎��Y�݂̂Ȃ炸�Ǘ����Ă������P�c�̗̂a���܂ŒD��ꂽ���ƂɐӔC�������Ď��E�������Ƃ��L�b�J�P�ɁA�u���ʉ���v�̉��g�Ƃ��čőO���ɕ����߂��Ă���B���̓r�[�L�[�p�[���A�Q�����邽�߂Ɏז��ȃ��m�͂��ׂĔr������\�\�Ƃ����T�^�I�ȁu�b�������ł͂Ȃ��\�͂ʼn�������v�^�C�v�̘b�ł��B�v���w�W�����E�E�B�b�N�x���w�C�R���C�U�[�x���������悤�ȉf��B�p�[�J�[������n�������s�Ƃ͌Ñ��ɘA�����đ����ɓ���A�������R�[���Z���^�[�ɃK�\�������T���ďĂ����������Ԃ肪�C���������B30�������Ȃ������ɋ��_�̈���o�[�j���O���Ă������Ă��܂��B�z���g�A�r�{����`����Ă���J�[�g�E�E�B�}�[�̓{�肪���܂����B��͌����߂̘A�����E���ɍs���W�J�֓˓�����̂ł����A�����郉�C�u���̓n�b�L�������Ė���́w�^�t�x���Ȃ̂ōׂ����c�b�R�~�ǂ���͖������ăG���W���C���܂��傤�B�u�Ȃ�ň��ނ����̂Ɍ����������Ă���́H�v�ȂǁA�{�I�Ɓi�r�[�L�[�p�[�j�Ȃ�g�D�̎��Ԃ��ӂ�ӂ킵�߂��Ȃقǂӂ�ӂ킵�Ă���B�u�A�_���E�N���C�͂����g�D�����g�����������Ⴈ���v�ƈ��Ղɒǂ�������������ĕԂ蓢���ɂ���A�r�r���ĐÊς̍\���ɓO����r���̓W�J�Ƃ����A�g�D�Ƃ��Ă��܂�ɂ��O�_�O�_���B���ׂĂ̓X�e�C�T�������o���邽�߂̕��䑕�u�Ɗ���낤�B���ƁA�Ƃ���ǂ���ŖI�]�~���}�������m���͑��c�^�ƌ��얟����ۂ��ȁA�Ǝv���܂����B
�@����4000���h���قǂƔ�r�I��\�Z�ō��ꂽ�f�悾���ɑ�슴�͂Ȃ��A�u������Ƃ����̊G�̓V���{���ȁv�Ɗ�����ӏ����������������������Q�Ȃ������������đދ������ɍŌ�܂Ŋς邱�Ƃ��ł����B���̃n���E�b�h�f��A�R���i�Ђ̂Ƃ��ɗ��ꂽ�ϋq�����܂�߂��ĂȂ��āA�X�g���[�~���O�z�M�ɂ�鎩��ł̎����փV�t�g����������l�������A���s������DVD�EBD�̔��オ���~�C���炵���āu���f��v���̂��̂������Ă���炵����ł���ˁB���{�̉f��قł��C�O���ʉf��̑��݊����キ�Ȃ�A�����L���O�̏�ʂ̓A�j����M�悪��߂�X���ɂȂ��Ă��Ă���B�قږ����̂悤�ɊC�O���ʉf��𗁂тĂ����g���炷��Ǝ₵�����B�b��߂��ăr�[�L�[�p�[�A���E�I�ɃX�}�b�V���q�b�g���������Ƃ������đ��������Ҋ�悪�����Ă���͗l�ł��B�ē̃f���B�b�h�E�G�A�[�͍��u���s�剉�̉f�� "Heart of the Beast" �i�����ꕔ�������̃u���s����s�@���̂ŃA���X�J�̍r��ɕ���o����A���ނ����R�p���ƈꏏ�ɃT�o�C�o������b�炵���j�̎B�e�ŖZ�����炵���A�u�v���f���[�T�[�v�Ƃ����|�W�V�����Łw�r�[�L�[�p�[2�i���j�x�Ɋւ��炵���B�V���Ȋḗu�e�B���E�W�������g�v�A�C���h�l�V�A�o�g�̎��Ńz���[���ʂ����ӁA�S�A�\���ɒ�]�����邻�������瑱�҂̓O�����`�ʑ����邩���B�w�r�[�L�[�p�[�x�Ǝ����H���̃A�N�V�����f���wMr.�m�[�o�f�B�x�̑��ҁwMr.�m�[�o�f�B2�x�i���N8���ɃA�����J�Ō��J�\��j����|���Ă���A���܂��������̂܂ܑ��Ґ����l�Ƃ��ďd��邩�H�@�r�{�̓J�[�g�E�E�B�}�[�����̂܂ܑ����ł��B�Ȃ̂őg�D�̃O�_�O�_�Ԃ�����炭���̂܂܂ł��傤�B�B�e�J�n�͍��N�̏H����Ƃ������ƂŁA������Η��N�̏t���炢�ɂ͌��J����邩����B
�@�܂Ƃ߁B�X�g�[���[�ʂ͂��Ȃ�e�����ǁu�X�e�C�T�������o���邾���ŃX�J�b�Ƃ���v�w�ɂ͂����Ă���1�{�B���Ȃ݂ɃG�A�[�ƃX�e�C�T���̃R���r�� "A Working Man" �Ƃ����V��ɂ��g����Ă���A��������u���ނ���������H������U�����ꂽ�Ƒ����R�̏��������߂����ߋ���Ȑl�g�����g�D�Ɛ키�v�Ƃ����w�r�[�L�[�p�[�x�n�̉f��ł��B�A�����J�ł͍���28�����J�\��Ȃ�ł����A�M�肪�Ȃ����Ƃ���킩��悤�ɓ��{�ł̌��J�\��͕s���B���肷��ƌ�����J�i�V�Ŕz�M��~�Ղ݂̂�������Ȃ��ȁA����B
2025-03-09.�E�����Y�̍ŐV��w���ɂ�����x�A�����W�����I�A�v���Ȃ�S�b�����L�����y�[���J�Ò��A3��19���܂�
�@�w���ɂ�����x�A�ǂ�Ȗ��悩�ƌ����Ɓw�R�x�̍�҂ɂ��{�N�V���O���ł��B����ȏ�̗\���m�������Ȃ���1�b�ڂ���ǂ�ŗ~�����B�u�S�b�����������āA�܂�5�b�����v�Ǝv����������܂��A1�b������̃y�[�W���������̂�5�b�S�����킹���200�y�[�W�ȏ�A�P�s�{1�������炢�̃{�����[��������܂��B��ǂ�����l�����4�b�ڂ�1�����I��点�āA2����5�b�ڂ�����č\���ɂȂ邩�ȁB�ǂނȂ�܂��ɍ����ă^�C�~���O���B���Ɠ���l���Ȃ̂��X�^�[�V�X�e���Ȃ̂��悭�킩��Ȃ����I�b�V�[���Ɓu�����P�����v��������̃L������2�b�ڂɏo�Ă��܂��B�w�R�x�t�@���͗v�`�F�b�N�B
�EInterview: Director Kodai Kakimoto on Ave Mujica and Its Unique Direction�iAnime Corner�j
�@�uAnime Corner�v�Ƃ����C�O�̃A�j���T�C�g�Ɍf�ڂ��ꂽ�A�wBanG Dream! Ave Mujica�x�̊ēu�`�{�L��v�̃C���^�r���[�L���ł��B�ǂ݉����̂���{�����[���ł����A��r�I���Ղȉp��ŒԂ��Ă��邽�ߋ@�B�|��Ɋ|������������̓��e�͂킩��܂��B���̌o�܂Ȃǂɂ��Č��y����Ă���A�����[���B�����̃C���^�r���[�i�����Ƃ��w���K�~�}�K�W���x�Ƃ��j�ł�����Ă��܂����A���Ƃ���MyGO��Mujica�́u�V���A�X�ȃo���h������肽���v�Ƃ����v������o�������v���W�F�N�g�ł���A�����̒i�K�ł̓o���h�����犮�S�ɓƗ��������[���h�ƂȂ�\�肾���������ł��B�r���Ńo���h���ɍ������邱�Ƃ����肵�A�L�����f�U�܂߈ꕔ�̐ݒ�͍�蒼�����ƂɂȂ����B�����O�̐ݒ肾�Ɓu�����Ɛh煂ȃL�����N�^�[��W�J�v�����������ŁA����ł������ԃM�X�M�X���y������Ă���c�c�ƏՌ����܂��B���ɏ����Ă̏ˎq�́u���Ȃ茙�Ȏq�v�������炵���A�ǂ�����Ă��o���h���̃L�����ɂȂ�Ȃ��̂ő�����蒼�����͗l�B
�@�܂������̃v�����ł�MyGO��Mujica�ɕ�����Ă��炸�A�S26�b�̈�т���2�N�[���A�j���Ƃ��č\�z����Ă��āA4�b�ڂ܂ŋr�{��Ƃ��I����Ă����Ƃ̂��ƁB10�l�̏��������̎v�f���������Ăӂ��̃o���h�����܂�Ă����ߒ������s�ŕ`���Q�����݂����ȍ��ɂ�����肾�����炵���B����́u�S13�b��1�N�[���A�j�����ӂ����v���j�Ɍ��܂������MyGO���ɂ�邩Mujica���ɂ�邩�͂��炭���������A���A���o���h�̃����o�[�̏W�܂���X�P�W���[���̓s����������MyGO���s�����邱�ƂɂȂ����B�ߋ��́wBanG Dream!�x�́u�S�����D���C���[�W�����L�����N�^�[�f�U�C���ɂ��邱�Ƃʼn����₷������v�H�v�����Ă������ǁA�}�C���W�Ɋւ��Ă͐�ɃL�����N�^�[�f�U�C�����ł߂āA���ꂩ��L���X�e�B���O��Ƃ��n�߂��Ƃ����̂ŃA�v���[�`�̎d���������ԈقȂ�݂����ł��ˁB����ƃN�[���������ꂽ���Ƃ�MyGO�̖�肪��ɉ������AMujica�̖���MyGO�����o�[�����͂���W�J�ɂȂ������A�����̍\�z�ł�CRYCHIC��Y�ꋎ�肽���ˎq�����̖ʉe�̎c��MyGO�����X�����v���A�����ƌ�����MyGO�����o�[��G������W�J�ɂȂ�͂��������炵���B���̃��[�g���ƃ��C���{�[���C�u�́u�����q���v�݂����ȃ|�W�V�����̃L�����ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B
�@MyGO��5�l�Ɋւ��Ắu���̍˔\�̓X�S�����ǃR�~���j�P�[�V�����\�͂ɓ����v���𒆐S�ɋl�߂Ă������ƌ���Ă��܂��B���̍˔\�����o���ĕ���Ɉ�������グ��u��������v�̎�����ł���ˎq�A���̍˔\�ɍ��ꍞ��Ń��������ɂȂ��Ă��܂�����i����ɂ����������̕\���̓��������̓x���߂��邾��I�j�A���̍˔\�ɋC�Â��Ȃ��i����������ڂ���炵�Ă��܂��j����A�ǂ���ɂ��]�т���r�c�c�Ƃ����z�u�B���������Ə����i�K�ł͗���Ƃ��悪�����ƑΗ�����悤�ȊW�Ƃ��čl����ꂽ�̂��ȁB���ۂɃL�����N�^�[�����i�K�ɓ����Ċ���̌@�艺�����s��ꂽ���A�݂�Ȏv�����悤�ɍs�����Ă���Ȃ������ŋ�J���������ł���B�v���b�g�i�K�ł͏����ɐi�ނ̂ɁA�V�i���I�N�����̒i�K�ɓ����āu���܂����A�����͂��̏��Ⴑ�������Ȃ��I�@�������ɍs���Ă��܂��I�v�Ɣ��o����̂͊��Ƃ��邠�邾�B�u�������v�������悤�Ȍ��ۂɔY�܂��ꂽ���Ƃ��ߋ��̃C���^�r���[�Ō���Ă���B������A�ɒ[�ȃN���G�C�^�[���ƃv���b�g����ؑg�܂Ȃ����Ƃ�����܂��B��\�i�́u�e�n�G�s�v�A�����̓L�`���ƃv���b�g�g��ł��炵�����r������u��҂���̓W�J��m��Ȃ������ʔ���������v�Ƃ������R�ōr���˂���悤�ȃX�^�C���ɂȂ��Ă������BMyGO��Mujica�������ԃ��C�u���̂���X�g�[���[�Ȃ̂Łu�����̃v���b�g�ʂ�ɂ͐i�܂Ȃ�������Ȃ����v�Ƌ^���Ă������A����ς肻����������ł��ˁBMyGO�̃C���^�r���[�ł��r�{�̐l���u9�b�̎��_�Łw�{���ɂ��̎q�����o���h���g�߂�̂��H�x�Ɛ���w���S�z�ɂȂ����v���Ė������Ă�����ȁB
�@�uAve Mujica�v�Ƃ����o���h�̃R���Z�v�g�͊����̃S�V�b�N���^���o���h�ł����uRoselia�v�Ƃ̍��ʉ���}��_�����������ƌ���Ă��܂��B�u���ʂ�t���遁�{�����B���v�Ƃ����̂��u���͊J���Ă�������v�iNeo-Aspect�j�ȃ��[���A�ƑΔ䂷��Ӗ������������ł��傤�B����܂ł̃o���h���́u�M���ɂ�����J��F����܂��v�Ƃ����O���������Ƃ��ł����A�ǂ����Ă��b�������p�^�[���ɂȂ��Ă��܂��E�B�[�N�|�C���g������܂������ǁA�u���������ł��Ȃ��܂܁A�S�Ɉł�������܂܌q����o���h�������Ă����̂ł͂Ȃ����v�ƃA���`�����X�g�[���[��搂����Ƃŕ����L���悤�Ƃ��Ă���B�Ƃɂ����e�L�������D������ɓ����������A�u���H�̏o����T���Ă���悤�Ȋ����v�ƃR�����g����ēɏ��Ă��܂����B
�@�����Ƃ������ɋ�J�����̂́H�@�Ɛu����āu��t�r�ł��ˁv�Ƒ������Ă���̂ɂ����B�����i�K�ł́u���[�e�B�X�v�Ƃ����l�i�����݂��Ă��炸�A�u�����ЂƂ�̓o��l���v�Ƃ��Čォ��V�i���I�ɒlj��������Ƃ��q�ׂĂ���B���̂����Ŋ��ɏ����オ���Ă���4�b�܂ł̋r�{�������������ƂɂȂ����݂���������A���[�e�B�X�̓��W�J�̃��C�u�����ے�����L�����ƌ��Ă����̂�������܂���B�܂��o���h���̐V��A�j������|����@��������牽����肽�����A�Ƃ�������ɑ��Ă�RAS�iRAISE A SUILEN�j�ƕԓ����Ă���B�[������o���h�̗����グ�Ɋւ�����̂ň���������炵���B���̌��Ƃ��Ă̓��[���A�̐V��������Ă���B���[���A�̌���ŃA�j���̓K���p�̃V�i���I���x�[�X�ɂ��Ă���̂ŁA�I���W�i��������Ă݂����A�ƁB�ŏI�I�ɂ́u�S���̃o���h��肽���v�ƌ���Ă��܂����B
�@�������p��̃C���^�r���[�L�����o�Ă���̂̓r�b�N�������ȁB���W�J�͉p�ꌗ�ł��W���W���l�C���L�����Ă���炵���A���낢��Ƃӂ����|���Ă����p�ꌗ�̌����A�J�E���g���������B�O�A�������䂾�����ۂ҂ǂ�i�o���h���̌���Łj�݂����ɁA����͊C�O�œW�J����b���������肷��̂��ȁB�����������A���Ă��������Łu�����v�����ɂȂ��Ă���C�M���X��ɂ����V��X�g�[���[�Ƃ��ςĂ݂��������B
�E�u�����Ȃ��ŏ���w����v2025�NTV�A�j�����A�X�|�[�c�����Z�́g�}�b�T�[�W���u�R���h�i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@�Ȃɂ��A�ŏ��̓X�|�[�c�h�N�^�[��ڎw���Ă����̂ɍŐV�G�s�\�[�h�ł͂Ȃ����G���o�y���̍��l�j���Ƀ����Y�G�X�e�̎w�������Ă��鏬��w���A�j�������ƁI�H�@�����̍��͂悭���邿�傢�G���n�̂��F�C����ŁA���̂Ɋւ��鉽�炩�̔Y�݂������Ă���A�X���[�g���q���������փ}�b�T�[�W���{���Ė��������Ă����c�c�Ƃ����y�߂̃��u�R���������̂����A��l���̃}�b�T�[�W�Z�p���u�l���E���Ȃ��k�l�_���v�݂����ɂȂ��Ă����Ăǂ�ǂ��O���킵�Ă������߁A���u�R���Ƃ�������w���ݕ����t�x�I�Ȃ��F�C�M���O�ɂȂ��Ă��܂�����삾�B�L���Z�̈�Ɂu���イ�v�Ƃ������̒��S�ɂ���c�{��˂��̂������ł����A�u�h�D���������@�s���b�I�v�ƍŌ�ɓ����e���ăt�B�j�b�V������B����e���K�v�Ȃ�����I�@�Ƒ��c�b�R�~������V�[���ł��B�r�����猩����ŋ}�ɃJ���[�y�[�W�ɂȂ鉉�o�����荞�܂�Ă���A���̉��o���h��Ȃ��Ƃ���u�p�`���R�J���[�v�Ƃ��`�e����Ă���B
�@�L�[�r�W���A���ł�5�l�̏��̎q���f���Ă��邪�A�i�ނɂ�Ăǂ�ǂ̎q�������Ă����̂�����w����̓����ŁA�����������l�̎q�Ɏ{�p�����̂��v���o���Ȃ����炢���B�u����Ȃɏ��̎q�̔��ɐG��āA�N���Ȃ̂ɏ���w����̓����������Ȃ��̂��H�v�Ƃ����^����@�艺����G�s�\�[�h������̂ł����A���Ȃ��Ƃ��A�j����1���ڂł͂����܂Ői�܂Ȃ����낤�B�u����w����̌����i���~���Ӗ�����B��j���v�͌��\�d�v�ŁA���ɂ͌ҊԂ�G���Ȃ���u�{�p���ɖu�N���Ȃ����ǂ����v�m�F������ʂ��炠��B�����܂ł��Ƌt�ɏ���w����ւ̃Z�N�n���ɂȂ��Ă��܂�����c�c�Ƃ����ʂ̖����������A���낢��ƃZ���V�e�B�u�Ȗ���ł���B�䂦�ɃA�j�����͍���Ǝv���Ă��܂������A�u�k�Ђ�����ۂǃ^�}���Ȃ��낤�ȁB�ŋߎn�܂����u�k�Ќn�̂��傢�G�����u�R���̒��ł��w���ꂪ���C�h�̃J���i�ł��x���Ă��˃V���^������D���Ȃ̂ł䂭�䂭�̓A�j�������Ăق����B
�E�wBanG Dream! Ave Mujica�x�͑�10�b�uOdi et amo.�v�ł悤�₭�o���h�Č����c�c����̂����A����ȂɘA�ъ����������܂ܕ�������o���h�������Ă����̂��I�H�@�ƃu�b��������e�ł����B
�@����̓��C�u�V�[�������邽�ߎڂ��L�c�L�c��OP��ED�̓J�b�g����Ă��܂��BA�p�[�g�̏o�����͂ɂ�ނɃI�[�f�B�V�����Q���̃I�t�@�[���������ǒf�������߁A�ŏI�I��sumimi�́u���c�܂ȁv���̗p���ꂽ���̏㉉�B�܂Ȃ���f����̘I�Ə�����A�������ɂ��Ă��Ȃ��Ȃ��U�߂����e�̓������BCM������A�ɂ�ނ�RiNG�Łu�L�v�Ɣ��������V�[������ĊJ�B�y�ޓ��l�u���[�e�B�X���r�������Ă���v���Ƃ��Ɍ��������ɂ�ށA�ޏ��͐X�݂Ȃ݂���u�r�͉��Z�̉����v�ƕ����Ă���̂Łu��d�l�i�҂ł͂Ȃ��w��������d�l�i���Ǝv������ł���q�x�v���Ǝ���Ă���A�u���ʂ����Ă���v�_���܂߂āu��t�r�v�Ȃ̂��Ƒ����Ă���B������r�̏�Ԃ�a�C�Ƃ��v���Ă��Ȃ����A���Â��K�v�Ƃ��l���Ă��Ȃ��̂őԓx���h���C�ɂȂ��ł��ˁB����ɑ��Ă���̓��[�e�B�X�����낢��ƌ��E�Ȃ̂����A�^�I���𓊂����ނ悤�Ȑ����Ŕޏ���X�̊O�֘A��o���B���[�e�B�X�͖r�����ɂ��āu����ɗ������I�v�Ƌ���ł��܂����A�ē̃C���^�r���[��v��Ɓu�{���ɏ�������肪����Ȃ�ޗ��Ɉ��ݍ��܂�Ȃ��悤�h���藧�Ă͂�����ł��������̂ɁA��������Ȃ��������_�Ń��[�e�B�X�Ɂw���̂܂ܖr��������Ă��ꂽ�����s�����ǂ��x�Ɗ���č�������C���������������Ƃ͊m���v�Ȃ킯�ŁA���݂����ȁu���m�ȎE�Ӂv���������Ă��Ȃ����̂́A�u���K�̌̈Ӂv���炢�͑��݂��Ă������ƂɂȂ�܂��B�r������S�z���Č��ǂ��������A�������̌��ǂ��i�O�ɂ����Ɗy�ނ����ɂ��m�F�����قǔ�����Ȃ��j���������A�u���O���ǂ��������I�v�Ƃ���ɊC���A��o�������ƁA�o���o���ɓ����Ă���悤�ł��ĘA�ъ��̂���MyGO�����o�[�ɃW�[���Ƌ����������Ȃ�B����Ɉ����ւ�Mujica�����o�[�̊��X������c�c�N���I�@���[�e�B�X��S�z���Ă��Ȃ��̂ł���I
�@�ˎq�ɁuAve Mujica��낤�I�v�ƗU���đ��ɂ��ꂽ�i�ˎq���炷��Ɓu����ǂ��낶��˂��ł���v�Ƃ����������낤�j���A����̐^���Âȕ��C��ŃV�����[�𗁂т�V�[���̓V���v���Ɂu�a�݁v��\�����Ă���B�^���Âȕ��C��ŃV�����[�𗁂т�l�ԂȂ�āA����ۂǓd�C���ߖ����l�Ԃ������^���������Ă�l���̓�ґ���ł���B���t�g�ɏオ��A���������}�l�L�����킩��Ȃ����u�����v�ɔp���\�肾�����I�u���r�I�j�X�̈ߑ��𒅂��ē�����V�[���A�a��ł�q���D���Ȏ��ł��f���ɋC���������Ǝv���܂����B����X�����[�f��ŃT�C�R�L���[���s������̏����E���Ď��̂ɕ�e�̈₵�����𒅂���V�[���̉��o����I�@�ˎq�������قNJ����������̉̎��ɑł��̂߂���A�u���̂܂܂��ᓕ�����Ɏ��ꂿ�Ⴄ�v�Ɗ�@�����点�鏉�͐V���ȉ̎��Ƃ��������d���u���^�[������I�ɖa���n�߂�B�N���ǂ����Ă����u���^�[�Ȃ̂ł������ɓ��e���S�O�����A�ǂ�����Ƃ��Ȃ����ꂽ�ɂ�ނ��X�}�z�����グ����ɃA�b�v���[�h�B��́u�X�}�z�̉�ʂ��������Đ�]�̐F����ɕ����ׂ鏉�v�͂��̃V�[���������̂��c�c�C��̍s���͂ɓ��Ă�ꂽ�̂��u�F�̏ꏊ�v�֖߂邽��Mujica�����̈ӎu���ł߂��ɂ�ނ͏����畷���o�����L��@�ֈꏏ�ɏ�荞�ށB���A����ς�L��@�̏Z����c�����Ă������ǂ����ċߊ��Ȃ������ȁB�C���^�[�z���z���ɂ���`�������̊�����āu�����肭�������v�ƍ��������Ƃ���L��Ƃ̊W�҂ł���\�������܂����B�w�b�Z�́w�f�~�A���x��ǂ�ł����ˎq�̂Ƃ���֓˓�������l�A�����k���܂��ċ��S�n�������ɂ��钆�A�ɂ�ނ́u�l���悱�����Č������ӔC�����v�Ɣ���܂��B�ˎq�́u�m��܂����v�Ɨ�ɂ���ē���Ȃ������悤�Ƃ�����̂́A��Ɉ�l�A���̕tⳂɒԂ�ꂽ���͂ƌ��������āu��͂莩���Ŏ�������Ȃ��牽�Ƃ����˂v�ƌ��ӂ���B�ŏI�I�ɏˎq�̐S�����̂�Mujica�����o�[�ł͂Ȃ��u�̂̏��v�ł��铕�̌��t���Ƃ����̂��z���g�ɂ����c�c�B
�@�O�x�����܂������ƂŁu�����������ł͂Ȃ��v�ƒm��Ȃ�����`��������ˎq��Mujica�Č������������A�u�a�߂�Ƃ������₩�Ȃ�Ƃ����v���ɍ݂邱�Ƃ𐾂��悤������B���́u�͂��c�c�v�͐��̎��x�����܂����A�u�A��Ƀ[�N�V�B�����i�͂��Ɓj�v���炢�̂��Ƃ͍l���Ă������B��������g���g�����q�ŕ������C�u�ւƘb���i��ł����BTGW�R�l�N�V�������g���Ȃ�����傫�ȃn�R�͉�������ꂸ�ARiNG�Ń��C�u���s�����Ƃɂ����ʁX�B�u�V�����f���A�A�撣���Ă݂����ǂ�����Ɠ���āv�ƙz�X�q���`����悤�ɁA�ő��ŕ����ق܂ōs�������ƃo���h�������̘T�����グ��ɂ͂�����܂�Ƃ����K�͂ɗ��܂��Ă��܂��BMyGO��13�b��Mujica��1�b�ɔ�ׂ�Ƃǂ����Ă��u�n�R�̏������v���ӎ������ɂ͂���ꂸ�A�����ۂ����o������ɂ͂���ς肠����x�̋�Ԃ��v��ȁA�Ǝ������܂����B�n�b�L�������Ă���܂ł�Mujica�̃��C�u�ɔ�ׂăX�P�[���̓V���{���̂ł����A�t�����g�}���ł��鏉���̂��o������ȍ����͐�����ԁB�ǂꂾ���n�R���������Ă��A���i����Ȃɏ�Ȃ���X�Ȏp����N���Ă���q�ł��A�p�t�H�[�}���X�̗͂ŕ����Ă݂��邱�Ƃ��\�Ȃ̂��B�����o�[���ꂼ��l�ԓI�Ƀ_���ȕ��������������āA�s�a���炯�ł܂Ƃ܂�̂Ȃ��o���h�ł����Ă��A���t���f���炵����Ε����B�����Ƃ��ł��Ă��܂��B�u���y�̗́v��I���I�ɏؖ����鉉�o�ł���A��������MyGO��10�b�u�����Ɩ��q�v�Ƃ͐������B�q�Ȃɔw�������Ă܂Ń����o�[���m���ߍ����ċC������ʂ����킹��MyGO�ɑ��AMujica�݂̂�Ȃ̓o���o���ŒN�����N�������Ă��ڂƖڂ��������Ƃ͂Ȃ��B�u����������Ɛ肵�����I�@�����オ��Ȃ�����������艺�낵�����I�v�Ɨ~�]�����o���̃h���h���\���O�����|�I�ȉ̏��͂ʼn̂��グ�鏉�͏ˎq�ɔM�����������܂����A�������悤�ɖ��\��ȏˎq�́u���y�֕�d����}�V�[���v�ɓO���ď��̌��d������̂�肭�����]���B���������𑗂��Ă���Ƃ��͘낢�Č����Ėڂ����킹�悤�Ƃ����A����������O�Ɍ����Ă���悤�₭����グ�ĕ��G�����Ȗʎ����ŕ\����M���B�u�Ȃ��킩��Ȃ����Ǐ���{�C�ɂ����Ă��܂��܂�����c�c���ʉ���Ȃ̂Œ��߂܂����ǁA�ł���Γ����o�������ł���c�c�v�Ƃ����ˎq�̐S�̐����������Ă��邩�̂悤���B
�@���̎��i�����j���S�̋��тł���悤�ɁA����̏��̎��i�����j���S�̋��тł͂����ł���ˁB���ꂪ�����Ƃ�P����Ƃ��������ŁB�u�l�ԂɂȂ肽���v�Ɛ؎��Ɋ�������ɑ��u���鎄�̐_�b�ɂȂ��āv�Ƃ˂��Ƃ藍�݂����A�Δ�ɂ��Ă���������߂��ăG�O���B�uCRYCHIC��̂̏��i�������j�Ȃ�ĖY��Ď������āI�v�Ƌ��萺�ői����悤�ȉ̎��Ȃ̂ɁA�����f�B��CRYCHIC��f�i�Ƃ������Y��ʼn����݂̂��镵�͋C�c�c�u�Y�ꂽ���Ă��Y����܂����v�Ƃ����̂��ˎq�́u�����v�ł��傤�B���܂�ɂ����x�Ȃ���Ⴂ�ň��R�Ƃ���B����ł�����ł�����欂��Ȃ��B�����uImprisoned XII�v��PV�ł��ˎq�͊��Y�����ɋC�����������邱�Ƃ͂Ȃ��i�K�i���瑫�݊O�������ɂȂ����Ƃ������~�߂����炢�j�A�߂������炢�Ɉ���ʍs���B�����Ă�̂����ăn���J�`�����o�����ɖڂ����ꂸ�o�����������Ƌ삯�o���ˎq�̎��싷��Ԃ�ɂ͂�����Ə����B�^�C�g���́uXII�v�͐������`�[�t�Łu�\��g�k�v���ȁH�@�Ǝv�������^���b�g��12�A�u�݂��ꂽ�j�i�n���O�h�}���j�v���w���Ă����Ȃ����Ƃ�����������͗l�BOP�A�j���ɂ��n���O�h�}�����ۂ��J�b�g������܂�����ˁB
�@�����C�����������������Ă���Œ��A�u�A�e�t���ł����A�ł������ɂ��v�ƌ����Ă������[�e�B�X�̓��ʂɂ��ω����K��Ă����B�u�r�����Ȃ�Ă��Ȃ����������v�Ǝv���ēޗ��֒Ă��Ă����̂��������Ă��܂������ǁA����ς�u�M�^�[�͖r������̕��v�Ȃc�c�ƌȂ̒��ɂ������Ȃ�������Ċm�F���u��A���������܂�v�Ƃ���Ɏ���ޗ��g�𓊂���B�����ēޗ��̒�̒�A�[�C�̂悤�ȏꏊ�ŏ����������Ă����r�����֕������A�����܂ܗ܂��U�炵�ċ��ɏ��ł��܂��B���[�e�B�X���{���ɗ~���������̂̓M�^�[�i�u�����v�̏ے��j�ł͂Ȃ������B�r�����ɋC�������~�߂Ăق��������B�������݂�F�߂Ăق��������B�ꌾ�ł܂Ƃ߂�Ɓu�ق߂�ꂽ����v���낤�B�c���ꂽ��{�̃M�^�[�͟���̈ÈłÂ��ɒ���ł����B�u�ӂ��肪������Ĉ�ɂȂ�v�̂ł͂Ȃ��u���ɏ�����v���o�Ȃ̂́A�M�^�[��e���n�߂��u��t�r�v�͖r�����ł����[�e�B�X�ł��Ȃ��A�ӂ���̗v�f���p�����u�V���ȑ��݁v�Ȃ\�\�ƍ����Ă��邩�̂悤�ŐȂ��Ȃ����B�^�C�g���́uOdi et amo.�v�i���͂��Ȃ��݂Ȃ��爤����j�́u��t�r�v�ɑ��ăA���r�o�����g�Ȋ��������u�S�V���ɂ�ށv���w�����̂ł���Ɠ����Ɂu�˂��D���v�Ȗr�����Ɓu�ˎq������v�ȃ��[�e�B�X���R�C���̗��\�ł��邱�Ƃ������A�����Ď��Ȍ����Ǝ��Ȉ��̋��Ԃŗh�ꓮ����t�r���g�����\���Ă���낤�B�ēC���^�r���[��8�b�́u�������˂�CRYCHIC��肽���v�Ɣ������Ă������̖r�́u�����Q�Ă���悤�ȏ�ԁv������ӎ��N�O�Ƃ��Ă��ė��������܂蓭���Ă��Ȃ��A�ƌ���Ă��܂������ǁA����������ɂ�ނ̌��t���u�S�͂��������������ȃ}�[�u���͗l�ł����Ă������v�Ɣ[�����Ėڂ��o�܂����̂ł͂Ȃ����B�܂�10�b�̃��C�u�ȍ~�̖r�́u������������߂��r�v�Ƃ����Ӗ��Łu�o���r�v�ƌĂ�ł����̂�������܂���B���ꂩ��ޏ��͈�l�ōႦ�Ⴆ�Ƃ����������Ă����B�g����ɂȂ��Ă���郂�[�e�B�X�͂��炸�A�u�����������Ȃ��v�B�܂����Ƀ��[�e�B�X�����S���ł��Ă����Ƃ��Ă����W�J�s�R�ł͉������Ȃ������悤�ɕ�������낤���ǁB
�@����[�A�������u�����Ƃ��G���[�V���������܂�|�C���g�Ń��C�u�ɐ���ꍞ�ށv�Ƃ����̂��o���h���̓S�����Ƃ����̂ɁA����I�Ȑ���オ������ė~�]�Ɩ�S�ƐӔC�������ōČ��������o���h���l�X�ƃ��C�u�ɗՂނ́A���܂�ɖ����ꒃ������B����Ȃ́w�M���O������a�x�̃l�^�������Ƃ����v���Ȃ��B����Ȑ��}�����闬��Ŗ��̏オ�������C�u�ɏ���킯���c�c�Ǝv���Ă����̂ɂ����n�܂�ƃp�t�H�[�}���X�̗͂ʼn����āu���̉̂��������v�ƂȂ邩��ςĂ��邱����̏�̓O�`���O�`���B�݂�ȐS�̓o���o���Ȃ̂ɉ��t�����͑f���炵���A�u�˔\�̃S�������v�����������Ă���C���B�ł��ˎq�ɂƂ��Ă͂��̉������܂荇��Ȃ��ē��̉̐����O�Y�O�Y������CRYCHIC���U���C�u�̕����܂𗬂��قǍK����������ȁc�c���đz���ĐS���������B����͂���Ƃ��āuCrucifix X�v�̂��邭����C��Ɩr���D���BCrucifix���Ēm��Ȃ��P�ꂾ���璲�ׂĂ݂����ǁu�C�G�X�E�L���X�g�����ɂ���Ă���\���ˁv�A�悭����ɂ���A�����w���Ă���݂����ł��B�uX�v�́u�ߏ\���ˁv���C���[�W���Ă���낤���B�u���ԁv�Ƃ����̎����炷��ƃ^���b�g��10�A�u�^���̗ցi�z�C�[���E�I�u�E�t�H�[�`�����j�v���w���Ă���\�������邪�B�Ȃ��q�����̃K�[���Y�o���h�A�j���Ȃ̂Ɍt�������ď\���˔w�����ė����œ��W���i�S���S�^�j�̋u��ڎw���悤�Șb�ɂȂ��Ă��Ă�ȁB���̐l������i�G�b�P�E�z���j����B�ł����Y�ɂȂ�̂͏ˎq�����ŁA���̃����o�[�́u���Ȃ��͂����ő҂��Ă��Ȃ����v�Ɩ��߂��ꂽ�C���݂����ɓ{��̓��܂ŕ��u�v���C��炢�����B
�@�^���͂��Ă����B�n�R�͏������Ȃ������ǁA�������Ȃ����������ŋp���Ē��D���������ɂȂ�uAve Mujica�͂��ꂮ�炢�̋����ł���Ă����̂����傤�ǂ�����Ȃ����ȁv���ċC�����܂����B�z���g�l�ԓI�ɂ̓A�������ǃt�����g�}���Ƃ��Ă̍˔\�͔��Q�Ȃ̂ŁA�n�R���������낤�Ƒ傫���낤�Ə����A��U��i�邾���ŗe�Ղɗ̈�W�J�ł��Ă��܂��B����͉ߋ��C�`����U�߂ĉ̂��Ă��邩��F��Ǝ��f�����ݍ������悤�ȃX�S���ȂɂȂ��Ă��ł���B�u���������قǁv���ĘR�炵�Ă���l���{���ɋ����������炽�܂�Ȃ��B�����������Nj�����Ȃ��i�r�ւ̊Q�ӂ����I���������݂Ƃǂ܂����j��Ȃ��B�������A�ォ��̈��͂ŕ�����j�~����Ă��郀�W�J����r�I���K�͂Ƃ͂�������Ƀ��C�u�Ȃ���Ă����̂��H�@�Ƌ^��Ɋ����Ă�����X�[�b�ƖL��莡�i�ˎq�̂���l�j�̎Ԃ��C���T�[�g���āu�����A����ς���v����Ȃ������v�Ƃ�����ʁA�莡�����ɑ��u�����i�͂ˁj�A�A��Ȃ����v�ƌĂт��������Ƃ�TL�͍��ׂ̉Q�֒@�����܂�܂����B�ǂ������ɕ���āu�O�p������Ǎ⏉���v���������Ă���l�܂ł���͕̂������B���̐F���炷��Ɓu���؏����v�̕����Ó�����B
�@�悤�₭���̕����Ă���u�閧�v�̈�[����������܂������A�܂菉�̖{���́u�����v���Ă��ƁH�@�m���Ɋw�Z�̃V�[���ł��u�O�p����v���usumimi�̏��v�Ƃ����Ă�Ă��Ȃ��̂ŁA�u���v���|���Ƃ����\���͂���܂������c�c����AMyGO�̃L�����Љ��Łu�{���͎O�p���v�ƃn�b�L�������Ă��邵�A�̂���̒m�荇���ł���ˎq���u���v�ƌĂ�ł���̂ŁA�u�����v���{���Łu���v���P�Ȃ�|���Ƃ����̂͂���������ł���ˁB����l�̔����Ƃ����A�ޏ����u�X�L�����_���X�ȏo���̔閧��������L��Ƃ̊W�ҁv�ł��邱�Ƃ͂قƂ�NJm��I���낤�B�����̂Ƃ����l�����Ȃ��Ă����u���ؑo�q���v�_�҂����𐁂��Ԃ��Ă���A�l�@���͍��ׂ��ɂ߂Ă���B�o�q�Њ��ꎀ�S���̏ꍇ�A�O�p���ƎO�p�����̑o�q�o���ŁA�ˎq�ƈꏏ�ɗV�������ɖS���Ȃ��Ă��ď������u���v�Ƃ����|�����g���Ă���ƍl����AMyGO�̃L�����Љ�ȊO�͕����������B����A�o�q�����������̘_�҂��u10�b�ŃI�u���r�I�j�X�̈ߑ����c���ł����̂͋l�ߕ�����Ȃ��đo�q�̂�����l�i�{�����j�����Ă����v�Ǝ咣���Ă���A�������P���킩��Ȃ��B�Ƃ������A�����������Ȃ��قǂ�������ȑo�q��������莡���u���Ɂu�����̕��v�ƌ������͕̂ρi�ԓ��ɏ�������Ƃ��Ȃ�Ƃ������j�Ȃ̂ŁA�����ꗑ���o�������Ƃ��Ă����̕��͖S���Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B
�@�����11�b�̃^�C�g���́uTe ustus amem.�v�A�u�i���̖S�[���j�Ă���Ă����Ȃ������������v�B���[�}�̎��l�u�v���y���e�B�E�X�v�̎��ɏo�Ă��錾�t�ł��B�u�����ӂ�����܂Łv�ł͂Ȃ��u�����ӂ�����Ƃ��v�ł���A�u���㋭�܂�O�v�߂����s���ȃj���A���X��������B�`���Œf����̘I�Ə��������_�̂܂Ȃ���l�A���`�̒��i�{���E�h�E�W���X�e�B�X�j�̐n�������Ă���̂�҂g�ɂȂ������i�����j�B�\���J�b�g�������G������ŐV�K�J�b�g���ꖇ���Ȃ��́A�u�����Ɋւ���閧���ׂĖ������܂��v�Ɛ錾���Ă��邩�̂悤�B����𖾂������莡���u���������킯�Ń��W�J�̕����͔F�߂�v�Ɨ����͂�����ǂɂȂ�낤���A���y�ւ̏�M�����������������܂܂ɂȂ��Ă���ˎq���L�`���ƌȂ̗~�]�Ɍ��������Ȃ̈ӎu�ŗ����������āA���߂Đg�����������ɂȂ��Ă��鏉���̎��͂݁u�M���������ƒ�R���Ă��A�����K���M����D���čs���܂���I�v�Ɩ{���̈Ӗ��ŏ������u�I�ԁv�G�s�\�[�h�ɂȂ��Ăق����B�ˎq�����͋l�܂�Ƃ���u��̉��������t�B�X�g�t�F���X�v�ł�����ˁB
2025-03-03.�E�[��A�j���Ȃ̂ɒ��h���x���������Ă����wBanG Dream! Ave Mujica�x�̑�9�b�uNe vivam si abis.�v�A�z���ȏ�ɍ������ɂ߂��ɂȂ��Ĉ�x�ς������ł͗������ꂸ�����ēx�������܂����B
�@�ȒP�Ɍ����ƁA�������b�����Ɖe�̔��������u�O�p���v�����ɍs�������ł��B�A�o���͈ړ����̎ԂŊy�������ɘb��������u���c�܂ȁv�̌��t����؎��ɓ���Ȃ��l�q��MyGO�̃A�J�E���g���`�F�b�N����l�q���`����Ă���B��������Y���Ă����uSNS�Ď��K�[���v�̃C���[�W������Ŋm��I�ɂȂ��Ă��܂����B�Ƃ��������_�̏�������܂ŋ��킹�Ă���L��ˎq�ɑ��Ă܂Ȃ����͓{�錠��������Ǝv����c�cOP��������A�p�[�g�A�ߋ��̃��C�u�f�����ςȂ���r�̃M�^�[���t���R�s�[���悤�Ɨ��ł��郂�[�e�B�X�B�M�^�[�Ƃ����A�C�f���e�B�e�B��D��ꂻ���ɂȂ��Ă���r�̓��[�e�B�X�ɂ�߂�悤�i�������邪�A���݂��������Ă��郂�[�e�B�X�͊�Ƃ��Ē�R����B�����̉�b�Ŗr���Ȃ����W�J�ł͂Ȃ�CRYCHIC����蒼�������̂����������܂��BCRYCHIC����Ă����̏ˎq�i������u���̏ˎq�v�j�͊y���������������ACRYCHIC��Y��邽�߂Ƀ��W�J�ɑł�����ł��������̔ޏ��i�u�ł̏ˎq�v�j�͋ꂵ�����������B�ˎq�ɋꂵ��łق����Ȃ�����CRYCHIC������Ăق����c�c�܂�A�r����{���ɗ~�������̂�CRYCHIC�ł͂Ȃ��u���̏ˎq�v�BCRYCHIC�͂����܂ł��̂��߂̎�i�ɉ߂��Ȃ��B���{�I�ȗv���𗝉����Ȃ��܂܋v�X�ɉH�u�֓o�Z�����ˎq�͓��ƈ����ɓ��������A�u�r�̂��߂�CRYCHIC�������Ă���Ȃ����v�Ɨ��ݍ��ށBMyGO�ɖ��f�����������͂Ȃ��ƌ����邪�A�������͊|�������Ȃ�Ċ�p�Ȑ^���ł���Ǝv���Ȃ��������Ȃ�Ȃ����ȁA�Ƃ����̂������Ȋ��z�B
�@�������̎��_�ł������Ă���̂��h������ȁc�c�r�����́u���̏ˎq�v�ƃL���b�L���E�t�t�����������Ȃ̂ɁA�����CRYCHIC���Č��������悤�Ƃ������قǏˎq�͓܂����ɂȂ��Ă��܂��B�u�r�̂��߂Ȃ�ǂ�ȋ�J���w��������ł�낤�v�ƌ��ӂ������Ƃŏˎq�����͂ǂ�ǂ�u���̏ˎq�v���牓�������Ă����B����Ƃ��������悤���Ȃ��B���[�e�B�X�����W�J�Č����̂��߂ɃA�e�t���i�y������t���Ă���t���j�ғ��P���Ă�̂��u�r��CRYCHIC��蒼�����߂ɃM�^�[�̗��K���Ă�v�Ɗ��Ⴂ���āu�ז������ራ���ł���v�Ƃ���Ɋ����킹���ɋ������Ⴄ�́A�������ɋr�{�̈��ӂ���������B�ˎq�������߂邱�Ƃɗ]�O���Ȃ��B
�@�ˎq��CRYCHIC�����v�]�ɐ�^�˘f�����̈����͏n������Ԃ��Ȃ�SNS��ʂ��ď����烁�b�Z�[�W�����B�Ăяo����Č���������͉H������X�B������[�̍D���ȃo���h�uAfterglow�v�̃����o�[�u�H����݁v�̉ƂŁAMyGO�̂Ƃ������x���o�Ă����ꏊ�ł��B���X�Ɠ����ɏo�}���Ĉ��������������┯�̎q�́u��{�C���v�A��T�r���J���I�P�ʼn̂��Ă����p�X�p���̃����o�[�̈�l�ł��B�t�B�������h�������ė������{�����D���̏��̎q�ŁA�u�u�V�h�[�v�������邠�܂�K���p�s�R�ł́u�u�V�h�[�I�v�������ɂȂ��Ă��܂����B���Ȃ݂ɏˎq���D���ȃo���h�uMorfonica�v�̃����o�[�u��t�����v�������Ńo�C�g���Ă��܂��B���Ƃ̖���Ƀh�L�h�L�C���Ȉ����ł��邪�A�ςĂ邱����͈Ⴄ�Ӗ��Ńh�L�h�L��������BCRYCHIC�̌������o�[��������������MyGO�̌������o�[������AMyGO�̈���ł��鈤���͉����m���Ă���̂ł͂Ȃ����c�c�Ƙm�ɂ��v��z���ŘA�����������������A�K���s�K����r���S�ň����̌�����u�ˎq�����CRYCHIC�����������ā`�v�ƍ������܂��B�ׂ����������ɂ��ē`���������ŏˎq�����b�`�����C��CRYCHIC�������悤�Ƃ��Ă���悤�ȃj���A���X�ɂȂ��Ă��܂��A�V���b�N�������̓A�C�h���������Ⴂ���Ȃ��\��Ŝ��R�Ƃ���B�Ƃɂ�������͏��́u��v�����낢��ƈ�ۓI�ȃG�s�\�[�h���B
�@����A�ɂ�ނ͖{���u���Ă������Z�̓��֓��ݍ������ƃI�[�f�B�V�����ɗՂނ��A�t���b�V���o�b�N����r�̎p�ɈϏk���Ă낭�ɉ��Z���ł��Ȃ��B���鉤���Y�̒Z�ҁu�F�̏ꏊ�v���ӂƔ]�����悬��܂����ˁB�u�F�v�i�T�O�I�Ȃ��̂ŁA���̉����ɒu�������\�j�ɑ��������҂́A��l�ɓ����o���Ă��\��Ȃ����Ԑ��𗧂Ē����Ă����Ɂu�F�̏ꏊ�v�֖߂�Ȃ��ƁA���̌�ꐶ�u�F�v�̋��|���瓦�������邱�ƂɂȂ�B�ɂ�ނɂƂ��Ắu�F�v���r�ł���A�u�F�̏ꏊ�v�����W�J�Ȃ̂��낤�B�����CRYCHIC�������悤�Ƃ��Ă���ˎq�ƃ��W�J�������悤�Ƃ��Ă���C��̊Ԃɋ��܂�Ăǂ��U�镑�������̂��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�C��Ƃ̉�b�����ݍ��킸���ǂ��������A�����ɂ���Ă��������u���AAve Mujica��邩��I�v�Ɛ錾���������ł܂��܂����P���킩��Ȃ����ԂɁBCRYCHIC�̌������o�[�ł��闧��Ɂu���������͓n���Ȃ�����I�v�ƈЊd����Ӑ}�������̂ł��낤���A�������킩��Ȃ�����ƊC��͂��������˘f������B�܂Ƃ��ȁc�c�܂Ƃ��ȃR�~���j�P�[�V��������؍s���Ă��Ȃ��I
�@���W�J��h�点�邱�Ƃŏˎq�Ƃ̉������߂��������͎������̈̂��l�ɓ��������čČ��������肷�邪�A�u�������̈ꑶ���ገ�߂��Ȃ��v�u�ォ��~�߂��Ă���v�ƁA���炩�́iTGW�O���[�v�́H�j���͂��|�����Ă��邱�Ƃ߂����B�u���ꂶ�ᎄ�́c�c�v�Ɖ������������Ă����Ƃ��납��@����ɁA�����L��Ƃ̊W�҂Ȃ̂��H�@�L��ƂƂ͕ʂɎO�p�Ƃ������̌��͎҂ň��͂��|���Ă����\�������邪�A���X�O�p�Ɖ]�X�荞�ޗ]�n���Ȃ����낤���f���Ɂu�L��Ƃ̊W�ҁv�ƍl���������ǂ������B����i�ˎq�̕�j�̑��V�ɎQ�Ă��Ȃ������i����ǂ��납�S���Ȃ������Ƃ��m��Ȃ������j���ƁA�ˎq���琐��̘b�������o����ăh�L�b�Ƃ��Ă������Ƃ��l����ƁA�X�L�����_���X�ȁu�o���̔閧�v������ł���悤�ȋC�����邪�c�c5�b�ŏˎq�̑c�����u����i�ˎq�j�͐���Ɏ��ĈӊO�Ƃ��Ⴖ��n������ȁv�ƌ��y����Z���t�����������Ƃ��l����ƁA���䂪�����ȊO�̒j�Ƌ삯�������ĎY��ŁA���̎O�p�Ƃ֗a����ꂽ�q�H�@���čl�������ǁA�ˎq�̒a������2��14���ł��邱�Ƃ��l������ƁA���ɏ����v���t�B�[�����U���Ă���Ƃ��Ă��N�q�ݒ�ɂ���͖̂���������B���Ɂu�����̉B���q�v�Ƃ��u�ˎq�̂���l�����̈��l�ɎY�܂����������v�Ƃ����낢��l�������A������ɂ���o���h���ł����܂ł͂��Ȃ��c�c�Ǝv�������B���ƍl������̂͐����̋������u�O�p�v�ŁA���͕����̏]�o�����m�Ƃ��A���邢�͏����̗��ꂽ�����̖��i�܂�ˎq�ɂƂ��Ă͓����N�̏f��j���ăp�^�[�����B��q�́u���Ⴖ��n�v�����Ƃ����A����͎��͂̔����������Đ����ƌ��������߂�����B����Ō��X����l�͎O�p�Ƃ������v���Ă��Ȃ��������ǁA168���̎������N�����������Ŗ{�i�I�ɉ���낤�Ƃ����̂ł͂Ȃ����B�ˎq�ƘA�������Ȃ����������A�^����Ɍ��Ƃ��ċ�����͂��̖L��@�������K�₷��C�z�܂������Ȃ������́A�u�O�p�Ƃ̐l�Ԃ͖L��@�̕~�����ׂ��Ȃ��v����Ȃ�c�c�����̖ϑz�ɉ߂��Ȃ����A���̃����o�[�͑�Ȃ菬�Ȃ�e��Z��ɂ��ĐG���V�[�N�G���X������̂ɏ������͉Ƒ��Ɋւ���b�肪�܂������Ȃ��A��Ώo���ɉ�������Ǝv����ł���ˁB���Ȃ݂ɏ��̌̋��Ƃ���Ă��铇�͍��쌧�́u�������v�����f���Ƃ�������������Ă���B���Ă����A���ߐ�Ȃ����̓��W�J����̈ߑ��ɂ��Ė₢�����A�u���̈ߑ��͔p���\��v�Ɩ���ȓ�����B�q�ɂ������Č����o�����I�u���r�I�j�X�̈ߑ��܂ɂ́u�p���v�̔��q���傫��������Ă���A���͐O������ŗ��܂��Ȃ���܂�������߂�c�c�G�ʂ����S�Ɂu�̂Ă�ꂽ���v�̂���ŋ����ꂵ���Ȃ����B
�@B�p�[�g�A�ɂ�ނ͖{�Ƃł���z�M�������x�݂����ɂȂ�A�ڂ�C�ȑ�O�́u�ɂ�ނ��v���������������B���������W�J�����ɓq�����M���Ȃ��A�������U���Ă���C���ǂ��o���Ă��܂��B�����A�M�^�[���P�̂��߂ɊC��̃A�p�[�g�֒ʂ��Ă��郂�[�e�B�X�B��B�������Ă�����̂̋Z�p�ʂ͖r�ɋy���_���o������ĕs�啅���B���̋A�蓹�A�C���ɂ̂��x�z�͂���܂��Ă���̂��A�r���ӎ������߂��B�r�͓��̉ƂɌ������A�������邽�ߘA�ꗧ���Ĉړ������l�̓v���l�^���E���̋߂��ŏ��Ƒ����B�˂����D���D���g���I�����������ďW�܂�`�ɂȂ�A�C����D���̎��͑勻���ł��B���ɍ쎌�m�[�g���������A�����쎌�S���̃{�[�J���X�g�ł��鏉�͂����ɘU�߂�ꂽ���b�Z�[�W�𐳊m�ɓǂݎ���ē��h����B�r����u���W�J��CRYCHIC��Y��邽�߂ɍ������p�i�������v�Ƃ����c���Ȏ������������A�����������̃����^���̓{���{���B�u���̎��͈Ⴄ�ˁACRYCHIC����Ȃ��B���̓������́AMyGO�̎�����v�ƌ���������CRYCHIC������j�����Ƃ���́A���܂�Ɏ�X������R�ł��킢���B���ς�炸�����Ȃ̔����Ȃ��r�����́u���ؖق��ĂāI�v�̈ꌾ�ʼn�b��ł����ĉᒠ�̊O�ɒu���A�������V������B�u�����炳�������Ȃ��ŁI�v�Ƌ��ԃV�[���̏��A�܂����o���h���ł���Ȍ`�����q�߂�Ƃ͎v��Ȃ������ł���B��������ꂽ�r���Q�[���݂����Ȑ�����ѕ�����̂͏��Ă��܂����B�n�b�Ɛ��C�ɖ߂�V�[���ł������̌��V��˂�����͏��̓��Ȃ�C���[�W�ł���A���ۂ͂����ł܂��Ă����������Ɣ������邪�A�r�ւ̎��i���قƂ�ǎE�ӂɋ߂���܂ō��܂��Ă��邱�Ƃɜɂ��܂��B�R�~�b�N�ł̕��ł͊����n�b�L���`���Ă��邪�A���͏ˎq�Ƃ̋������߂��r�ɑ���т��Ď��i�̔O������Ă����ł���ˁB���ꃀ�W�J�Č������Ă����X�ƒs�b���܂����������ł́c�c�H
�@�r�̓��ʂł̓��[�e�B�X�Ƃ̎哱���������ˑR�Ƃ��đ����B�\�͂ɖƉu���Ȃ������Ȗr������[�e�B�X�ƃL���b�g�t�@�C�g�ł���́A�u���������������v�Ȃ낤�ȁc�c�r�����͎��������������瓯���ł��郂�[�e�B�X����������B�����ĝ��ݍ����Œ��ɖr���肷���j�A�[�����̒��֓]�����Ă��܂��B���[�e�B�X�����܂ŃM�^�[��e���Ȃ������i�e���Ȃ������j�͖̂r�����̃A�C�f���e�B�e�B��N�Ƃ��Ȃ����߂ŁA�u�N�Ƃ���Ƃǂ��Ȃ邩�v�̓������R���ł���B�u����D����v�͎̂��ɓ������B�ϋq�̖r�i�����k�j�����́u�r�����̎��v�����т���B���Ȍ����̔O���������炱���u�����̎��v���q�ώ����Ċ��ł��܂��ȁc�c���ă]�b�Ƃ��܂����B���_���E�Ȃ̂Łu�m���Ɏ��v�Ƃ͌�����Ȃ��i�Ƃ������M�^�[�����Ȃ��痎���Ă�̂łقڊm���ɐ����Ă���`�ʁj�����A���[�e�B�X�͂���Ŗr�Ƃ̌�M���s�\�ɂȂ�A�u�r�����������I�v�Ɠ��h����BMyGO�����o�[���W�܂��ďˎq�Ɖ�b���Ă���Ƃ���ɊC��A���A���[�e�B�X�́u���W�J���������������v������Ă��đΖʁB�킩��ɂ������ǁA�R�[�q�[��u����̃J�b�g�Łu�l�q��������Ă���l�Ԃ�����v���Ƃ������Ă��܂��ˁB�����āu�|���������Ă����o���h�A���ׂĎ��߂Ă��܂����v�u����ł��M�p�ł��܂��I�H�v�Ɨ܂Ȃ���ɊC�邪�����Ă���D�Q��ɓ˓��B����|���������߂Ĉ�̃o���h�ɐ�O���Ă���Ȃ�ĒN������łȂ��ł���c�c���������Ƃ�����B�u���ׂ��r�����v�����������Ƃő��݈Ӌ`�������郂�[�e�B�X�́u�����g���r�����ɂȂ�����v�Ǝ����O�̉��Z�͂Ŗr�̃t�������ďˎq�����W�J�����֗U�����悤�Ƃ��܂��B���̗l�q�߂Ċy�ނ��u��������[���̎q�v�ƙꂢ�Ă���Ƃ��납�炷��ƁA�r�����̏�Ԃ̓��[�e�B�X�����O����قNJ�@�I�ł͂Ȃ��̂�����B�����O�`���O�`���Ŏ��E�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă����ʂ��D�u�ƌ��ꂽ�ɂ�ނ����t�𓊂�������B�u������c�c�L�v�@�e�������D�̒����̂��������悤�Șb�ł����B���������X������ʼn���������Ă��Ȃ��c�c�I�@����Ŗ{�����J�i�o���h�j��a��������̂��H�@MyGO��Mujica�̓o���h�݂̍���Ƃ��đΔ䂵�����悤�ȊW�Ƃ��Đv����Ă���炵������A�u���ꂼ�ꂪ���ꂼ��̒n���������v�G���h�ɂȂ�͉̂�����������Ȃ����A����u�ォ��̈��́v�i�ˎq�̂���l�H�j�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Ɍ����_�ň�v�c������o���ĂȂ��̂��܂�ɓ��̂肪��������B����v���Ă邯�ǂ��̃A�j���A�z���g�ɑS13�b�ł܂Ƃ܂�̂��H
�@����10�b�̃^�C�g���́uOdi et amo.�v�A�u���͂��Ȃ��݂Ȃ��爤����v�B�����Ɋւ��鎍�ŗL���ȃ��[�}�̎��l�u�K�C�E�X�E�E�@�����E�X�E�J�g�D���X�v�����l�Ɉ��Ă����̒��ɏo�Ă��錾�t�������ł���B�������銴���������A���r�o�����g�ȐS����[�I�ɕ\�������̂ŁA������U��s���ȗ��l��ӂ߂�j���A���X���U�߂��Ă���B�u���v�ƌ����A���[���X�Ȃ̂ŁA���낻��{�i�I�ɂɂ�ނ��@�艺�����Ȃ̂�����B���̕����Ă���u�閧�v�����낻�떾�炩�ɂȂ�̂ł́c�c�Ƃ����\�z�����邪�A���āB
�E�o���h���I�V��~�j�A�j���S52�b���쌈��I
�@�������A�K���p�s�R�̐V��c�c�I�@�^�C�g���͕ς�邩������Ȃ����A�u�s�R�X�^�b�t�ďW���v�Ȃ̂Ŏ����I�ɂ̓K���p�s�R�̑��҂��낤�B�u�K���p�s�R�v�Ƃ̓o���h���̃A�v���w�o���h���I �K�[���Y�o���h�p�[�e�B�I�x���p���f�B�����V���[�g�A�j���E�V���[�Y�ŁA�ߋ��Ɂu����v�u�吷�v�u�ӂ��[�[�I�v��3�V�[�Y�������J����Ă��܂��B�u�A�j���̃X�s���I�t�v�ł͂Ȃ��u�A�v���Q�[���̃p���A�j���v�Ȃ̂ŋ}�ɃK�`�����o�̍Č����n�܂�����ȂǃQ�[������ĂȂ��Ƃ悭�킩��Ȃ��l�^����������Ă���B�u�S52�b�v�ƕ����ƕ����������悤�Ȉ�ۂ��邪�A1�b������3���i����30�b��ED�j�Ȃ̂�156���AED������130���Ƃ���Ȃɑ����́c�c����A���\�����ȁH�@�ߋ��̃V�[�Y���͂�������S26�b�Ȃ̂ŁA52�b�Ƃ����̂�2�V�[�Y�����ɑ������܂��B�}�C�S�s�R���ƃ��W�J�s�R�������킹��52�b�A�Ƃ�������Ȃ̂��낤�B�s�R�D���Ƃ��Ă͏���肹���ɂ����Ȃ��B
�@�^�C�~���O�I�Ƀ}�C�S�⃀�W�J�̃l�^�������Ȃ邩������Ȃ����A���Ԃ̃o���h�̃G�s�\�[�h���ӂ�ɐ��荞�܂��͂��B����Ȃ���52�b���l�^��P�o�ł��Ȃ����낤�B�T�[�r�X�J�n���_�ł�5�����v���C�A�u���E�o���h���Ȃ������K���p���A����8�A���W�J��������9�ɂȂ�B���Ɓu������݂�[�����Ձv�Ƃ���Vtuber�o���h�����邩�炻����܂߂��10�ɂȂ邪�A��߂݂��̈������ǂ��Ȃ�̂������_�ł͂悭�킩��Ȃ��B�s�R�V���[�Y�͂ق̂ڂ̃l�^���������ŃJ�I�X�ȃl�^�������A���n����̘b���n�܂�����A�o��l�������ەs���̂܂I���z���[��܂ł�������ƁA�����鎖�ۂ��u�{�҂Ƃ͕ʎ���̏o�����v�Ƃ��ď�������܂��B�u����1�N�[������܂���I�v�u5�T��������Ă��I�v�Ƃ��������^�l�^�������邱�Ƃ������B��肽������Ȏ��R�ɂ܂�Ȃ��m���������䂦�A�����ƃ}�C�S�����W�J���{�҂̖ʉe���c��Ȃ����炢�M��|���Ă����͂����B�r�ƃ��[�e�B�X�̌�փl�^�͐�u�`����ł��邾�낤���A����E�U�E�f���W�����Xvs�}�X�N�h�E�I�u���r�I�j�X�̃v�����X��Ƃ������R�Ƃ��ɈႢ�Ȃ��B�u���̐��̂����́Z�Z�v�l�^����肻���B�n�N��́w�}�O���x�p���f�B�Ȃ�ăl�^�܂ł���Ă邮�炢�Ȃ̂Łw���ʃ��C�_�[�x�p���f�B��w�X�p�C�_�[�}���x�p���f�B���炢�͕��C�ł��܂���B�u�Ȃ�ŏt���e������́I�v�M��͖��_�̂��ƁA����́u������I�v��������M���Ă������B�y�ނ̖����l�^�͎U�X����Ă邩��u�������[�����v���炢�M�A���グ�Ă��邾�낤�B�X�݂Ȃݎ剉�̒��h���l�^����肩�˂Ȃ��B���Ƃ̓��j�J�t�@���̏ˎq�ƃ��j�J�����o�[�Ƃ̗��݂����҂������Ƃ��납�B�������Ɂu�w���ׂĂ̌����x�w�����̍����x�w�����x�q�c�܂���v�l�^�͂��Ȃ��Ǝv���܂����c�c�s�R�������Ƃ܂ł͌�����Ȃ��ȁB�ߋ��Ɂu�퍐�l�@�q�c�܂���v�ȁw�t�]�ٔ��x�p���f�B���������Ƃ����B
�@�u�q�c�܂���v�Ƃ����̂͌��m�X�̍������ɒʂ����k�ŁA���j�J���ƁuMorfonica�v�̃{�[�J���B�}�C���W�̎��_����2�N���ŁA�����r��1��ł��B�ޏ��́u�ˎR�����v�ɓ���ăo���h���n�߂悤�Ǝv���A�o���h�������Ȃ����m�X�ŏ��̃o���h�ł���Morfonica�������B����l�w�Z�䂦�o���h�ɂ܂������Ɖu�̂Ȃ��������m�X�ɏՌ��������炵�܂��B���j�J�̉��t�����ˎq�i�������w�O�N���j�͐[���������āu�������o���h��肽���I�v�ƌ��������̂�CRYCHIC�ł���A���������̒i�K�ł̓��j�J�̋Ȃ����t����R�s�[�o���h�ł����B���Ȃ݂ɒ��肻��̓��j�J�̉��t���̂��̂Ɋ��������킯�ł͂Ȃ����u�o���h�v�Ƃ����J�݂̍���ɓ���ďˎq�̗U���ɏ��������A�ޏ����܂��u���j�J�̉e�������v���k�̈�l�ł���B�䑶�m�̒ʂ�CRYCHIC�͉��U���܂������A�uCRYCHIC�Ƃ������i�悷���j��Y�ꂽ���v�ˎq�͐V����Ave Mujica����������BMyGO��CRYCHIC���Ȃ���Βa�����Ȃ��������낤���A�}�C���W��10�l�S�������ڂɂ���Ԑڂɂ���q�c�܂��낪�ׂ����s���̉e�����Ă����ł���ˁB�������̂Ƃ��܂��낿����m�X���y�ՂŃ��C�u����Ă��Ȃ���ACRYCHIC��MyGO��Ave Mujica�����݂��Ȃ������B�}�C���W�ɂ����āu���j�J�̍u�����C�u�v�͕������^�[�j���O�|�C���g�ɂȂ�������Ă�킯�ł��B���j�J�����ă|�s�p���Ȃ���Α��݂��Ȃ��������A�|�s�p�����ăO���O�������������猋�����ꂽ�킯�����c�c���Ȃ��Ƃ��ϑ��ł���͈͂Łu�e����^�����o���h��2���ߎS�Ȍ`�ʼn��U���Ă���i���Ȃ�MyGO���قډ��U���Ă��������������j�v�̂̓��j�J�����B
�@�������Ń}�C���W�̃����o�[���q�h���ڂɑ������сu�q�c�܂��낪�o���h���Ȃ������Ȃ��Ƃɂ́c�c�v�u���������q�c�������c�c�v�u���炽�܂̂�������c�c���̎����A�����v�Ɩ��悪�܂��낿���Ɍ������A�Ƃ������Ԃ��l�b�g�̈ꕔ�ŌJ��L������B�v�́u�V���~�q��������v��u�����������A���v�n�̃l�b�g�~�[���ł���B������̗����s�����郂�j�J�t�@����܂���t�@�������܂����A���̑q�c�܂��낪�������Ȑ��i�����Ă��Ĕ�Q�ϑz�̋����q�����Ɂu�t���݂ŋ��e�����q�c�v���l�^�Ƃ��ăn�}��₷���Ȃ��Ȃ��p��Ȃ��B���ꂱ���ߋ��̃K���p�s�R�ɂ��u�S�z���̂܂��낿���v�Ƃ����ߏ�ɕs��������G�s�\�[�h������܂��B���C�u��A���͂̔�����������������u���������č���̃��C�u�A�ǂ������Ǝv���Ă���͎̂������ŁA���݂̂�Ȃ́w�V�����{�[�J���̎q�����悤�x�ƍl���Ă��c�c�����Ďז��ɂȂ������͒n���J���{�݂ɑ����āA�Ȃ�₩��₠���čŌ�͖ҏb�Ɛ�킳���I�v�Ǝv���l�߂�B������CRYCHIC���U�̕��āu���̂����v�Ǝv���悤�ȃl�^���c�c���₳�����ɃZ���V�e�B�u�߂��邩����Ȃ����B�������Ƃ�����r�Ƃ̗̈�W�J�o�g�����ȁB�܂��낿���͋�z�Ȃ������A���������Ă��邾���ŋ���j������~���������郌�x���ɒB���Ă���A���W�J�̃��[�e�B�X����̕`�ʂŁu�܂��낿���̋�z�v��A�z�����o���h���t�@���͏��Ȃ��Ȃ����낤�B�o���h���L�����̒��Ń��[�e�B�X����ɖ�������ł����������Ȃ������Ȏq�̕M�����܂��낿�������҂��Ă��܂��B���Ƃ͉����A�֒f�̃n���n�s�R���{���c�c�n���n�s���Ɓu�n���[�A�n�b�s�[���[���h�I�v�Ƃ����o���h�͐ݒ肪�u�b���ł���i�����������o�Ńv���[���g����鍋�؋q�D�A�A�C�Z���}���̂悤�Ȕ�s�\�͂�L����������݁A�^���̉����l�ƉZ��ȗe�e�����������o�[���j�����ŁA�u���������ɑ��݂��邾���Ń��A���e�B���C���������v���߃}�C���W�ł͏o�ւɋ߂��������Ă���B���̃o���h�̃����o�[�͑�Ȃ菬�Ȃ�Q�X�g�o�����Ă���̂ɁA�n���n�s�̃����o�[�̓}�W�Ŗ��O����o�Ă��܂���B�������Ƀs�R�ł͏o�֑[�u��������邾�낤����A�������s�ȏ����ԉ���MyGO�Ƃ̏o��Ƃ�������Ă����͂��B�u�Ί�̔g��U���v����������ƊC��̏Ί�Ό����ς����B
�@�Ō�Ɏ��̍D���ȃs�R�̃G�s�\�[�h���������I��ŏЉ�܂��B�܂������11�b�A�u�n���n�s�X�J�C���C�u�v�B������̔��ĂŃX�J�C�_�C�r���O���Ȃ���Ń��C�u���邱�ƂɂȂ����n���n�s��s�c�c�ƁA�J�n���_�Ŋ��ɋ����Ă���B�������炷���́u�̂ɍ���Ȃ��������n�̐��v�Ƃ����ꕶ�����ʂɃX�g�[���[�̍L��������������܂��B���͑吷��8�b�A�u�J�[�h�t�@�C�g!! ���o�����I�v�B���L�����̂ӂ��肪�J�[�h�Q�[�������ŃV�X�R���o�g���i���o������j����b�ŁA�w�J�[�h�t�@�C�g!! ���@���K�[�h�x�p���f�B�ł�����B��������ɂ������ʔŁi�G�C�v�����t�[���l�^�j������A�u�`���`���ƃJ���y���Ȃ���Z���t��ǂݏグ�鏬�V�����v�Ƃ����M�d�ȉf�����q�߂邼�B���ꂩ��吷��12�b�A�u�K�[���Y�o���h�V���v�B�������K���X��˂��j���Ĕz�B�����K�[���Y�o���h�V���c�c���āA�K���p�̃��C���t�@���w�Ɂw���|�V���x�l�^���ʂ���킯�Ȃ�����I�@�s�R�̓z���[���傭���傭����A�����吷��19�b�u�܂���X�e�[�V�����v���s�s�`���u�����炬�w�v�̃p���f�B�ł��B�ӂ��[�[��20�b�A�u�Q�[���Z���^�[�Ƃ����v�B�^�C�g���́w�Q�[���Z���^�[���炵�x�̃p���f�B�����K�E�Z�́w�L���v�e�����x��w�L�����}���x�p���f�B�Ƃ����J�I�X��B�Ȃ�ƂȂ��킩���Ă����l�������Ǝv���̂ł����A�s�R�̃p���f�B�͑S�̓I�Ƀl�^���Â߂Ȃ�ł���B�����狰�炭�V����S�łƂ������̎q�Ƃ��t���[�����Ƃ������ŋ߂̃p���l�^�͂��Ȃ��͂��B�ǂ����Ă��M���O���J�I�X��̕�����ۂɎc�肪�������A�����ɗǂ��b�Ƃ��ċ��������̂͂ӂ��[�[24�b���u���肪�Ƃ��v�B���ׂŔ���������ɂȂ��Ă��܂����u���F��߁v�̃T�|�[�g������u���䃊�T�v�A�ӂ���̈ȐS�`�S�ȊW��`���ق�����G�s�\�[�h���B���������̂����邩��u�{�҂̊������u�`�ɂȂ肻���ł�����Ɓc�c�v�Ƌ���ł���l������E���ۂ��ă`�������W���Ăق����B
�@�T�[�r�X�I�������}�M���R�̃C�x���g�X�g�[���[��������Youtube�Ŕz�M����A�Ƃ������ł��B�v���R�l�i����j�������悤�Ȃ��Ƃ��Ă܂����ˁB�}�M���R�͊�{�I�ɖ{�҈ȊO�{�C�X���t�����A�e�L�X�g��ǂݐi�߂邾���Ȃ̂�������ł����\�����āA�ЂƂ̃C�x���g�X�g�[���[��1���Ԃ�2���Ԃ͊|����܂��B�Ȃ��Ȃ��C�������Ȃ��ƒʓǂ͓���B�u�ʓǂ͖����ł�1��2�͎����ɓǂ�ł݂����ȁv�Ƃ������ɃI�X�X���������̂�������́u�`�x�b�g�̃��N�V���[�V�[�ҁv�B�C�x���g�����ǏI����ɖ{�҂֑g�ݍ��܂ꂽ�AFGO�̃��C���E�C���^�[���[�h�Ƃ�����1.5���iEpic of Remnant�j�ɋ߂��ʒu�Â��̃X�g�[���[���B����̖��@�����������ߋ��̎���ɑk���ė��j�Ɋ����A�l�X�Ȗ��@���������̊���Ɩ��H�����͂���V���[�Y�u�s���G���E�q�X�g���A�v�̈�҂ŁA�����S�����҈Ђ�U����Ă���13���I�̃`�x�b�g������ƂȂ��Ă��܂��B���n�ł͖��@�����̂��Ƃ��u���N�V���[�V�[�v�ƌĂ�ł���A�~����i���N�V���[�V�[�j���J��グ���卑�i�����S���j�֗����������Ă����n���ɂȂ��������u�w���J�E���}�v�̒Z�����Z�����U��Ԃ��Ă����B
�@���̘b�̎�l���ɓ�����w���J�����A�ӊO�Ȃ��Ƃɐ��`���͂��܂苭���Ȃ��ĕ��i�̐����ԓx���ӑāA���͗ǂ����Ǘ�߂�����ŒB�ς��Ă��郄���E�E�F�����[�^�̎q�ł��B����m��Ȃ����l�̂��߂ɖ���q���Ȃ�Đ^���͓���ł��Ȃ����A�e�F�ł���u�h���}�v����蔲�����߂Ȃ�ǂ�ȋ]�����Ă��\��Ȃ��A�Ƃ����o��ŗ������i���N�V���[�V�[�j�ɂȂ��Ă����B�h���}���w���J�̂��Ƃ��Ȑe�F�Ƒz���A�S�̎コ�����삢�Ă��̊���������ɂ͂����Ȃ��B�h���}�̐S�������Ȃ����߂ɍŌ�܂Łu���N�V���[�V�[�v�Ƃ��ĐU�镑�����Ƃ�����ς��ꂸ�A����ڑO�ɂ��ĔN�����̎コ�����炯�o���Ă��܂��w���J�����̎p�ɓ����̃v���[���[�͔]���܂��ꂽ���̂ł����B�u����Ȃ̂��ĂȂ���A����܂肾��v�Ȍ����Ƀs�b�N�A�b�v�K�`�����l�����o�B�u�V�i���I�ʼn���v��n�ōs���悤�ȓ��e�ł���A����u���̃Q�[������Ă���N���A��ɕK���Ńw���J�����̃K�`���Ă������������ȁc�c�v�Ƒz�����ă]�b�Ƃ��Ăق����B�{�҂̃L�������o�ė��邯�ǁA�����܂Ńw���J�ƃh���}�A�ӂ���̊W�ɍi�����X�g�[���[�Ȃ̂ł܂ǃ}�M�̊�{�m���i���@�����Ɩ����̊W�j�����m���Ă���}�M���R�m�����Ȃ��Ă����v�ł��B�ǂݏI�������ɂӂ���̕��a�ȓ����`�����n�삪�~�����Ȃ邱�Ɛ��������B
�ETV�A�j���u�������̌� �������[�X�^�@���C�g�v�S�b�������J�A5���܂�YouTube���i�R�~�b�N�i�^���[�j
�@Youtube�Ŗ����z�M���Ă��A�}�v���Ƃ��Ŋς�邾�낤���c�c���Ē��ׂ��獡�A�}�v���Ŕz�M���Ă�̂�2.5�����ł����ŃA�j���̕��̓T�u�`�����l���_�Ȃ��Ɗς�Ȃ��̂��B�Ȃ�I�X�X�����Ă������B�w�������̌� �������[�X�^�@���C�g�x�́u����v�\�\�u�����v��u�~���[�W�J���v���e�[�}�ɂ������f�B�A�~�b�N�X���ŁA�A�j���ł�2018�N�ɕ�������܂����B��ˉ��y�w�Z�����f���ɂ����Ƃ��ڂ����u���ĉ��y�w���v�ŁA���䏭���������u�g�b�v�X�^�@�v�̍���ڎw���Č������M�����B�n�������āu�I�[�f�B�V�����v�Ƃ������̌����ɑł������A�����I�Ɏ����͂ݎ��I�@�����̂��ėx���ĒD�������܂��傤�B�w�A�C�J�c�x�݂����ȃA�j�����Ǝv���Ċς���w�����v���E�e�i�x�݂����ȃm���Łw���ʃ��C�_�[���R�x���݂��o�g�����C�������n�܂����A�ƕ��������Ɏ����҂����̓x�̂�����i�ł��B���Ă͎O�N���ŁA�A�j���͎�l����������N�ɐi�����������肩��n�܂邽�ߐl�ԊW�͂قڏo���オ���Ă���A�����Ȃ�ς�Ə�������ɂ����������邩������܂���B�R�~�J���C�Y�́w�I�[�o�[�`���A�x�i���͂Ƃ����Ӗ��j�����w���ĊԂ��Ȃ����A��l�������̈�N�����`���Ă��邩���ɂ�������ǂ�ł����Ɨ������₷���Ȃ�ł��傤�B�����I�[�o�[�`���A�̎��_�ł̓I�[�f�B�V�������n�܂��Ă��炸�A�����܂Łu�l�ԊW���������₷���Ȃ�v�����ł����āA�ʂɔ���Ă��X�g�[���[��ǂ������Ŏx��͂���܂���B�P���ɃR�~�J���C�Y�̏o�����C�C����A�j���ƕ����ēǂ�ŗ~�����ł����ǂˁB
�@�͂����茾���čŏ��̂����́u�킯�킩��Ȃ��A�j���v���Ċ��z�ɂȂ�Ǝv���܂��B�����Ȃ�u�A�^�V�Đ��Y�I�v�Ƌ���āu�Ȃ�قǁv���ĂȂ�l�̕������Ȃ��ł���B�����u���o���Â��Ă�ȁ`�v���炢�̊��o�ŊςĂ��āA�͂��߂̕��͂���ȂɈ������܂�Ȃ������i�uThis is �V���^��v�Ƃ����L���[���t�����ʂɏ����j���A��5�b�u�L���߂��̂��肩�v�Łu����H�@���̃A�j���Ђ���Ƃ��ĕ������ʔ�����Ȃ��H�v�ƋC�Â��p���𐳂����B�����A���g�i���ĉ��y�w�����\������̂����������[�X�^�@���C�g�Ń��C���ɂȂ�9���j�ɂ����鎄�̐����́u�I��܂Ђ�v�ł��B�C�̎セ���ȏ��̎q�Ȃ�ł����ǁA�����̂ł���u���̖����v�͏�O�����Ղ�Ńh���h�����Ă��čō��B�u�˂��@�����������ĂĂ�@�ق�@�����Ȍ��Ȃ�ā@�^���ɂȂ�Ώ����Ă��܂��v�@�܂Ђ邿������Ƃ����b���Ă��Ă��������̏����i��l���j�Ɂu�_�y�Ђ���v�Ƃ����c����݂������Ă����̂Łu���i���̎q�j�Ȃ�Đ^���i���j�����������Ă��v�Ɛ錾���Ă�킯�ł���B�Ƃɂ����������[�X�^�@���C�g�͏�O�̘U�������̎���Z���t�������āu���t����H�v�Ȑl�Ԃɂ͂��܂�Ȃ��B���N�o���Q�[���ł̋ȁuStar Darling�v�ɂ��u���Ȃ��ɂȂ�Ȃ��@�����炠�Ȃ�����������v�Ȃ�ĉ̎��������āu���H�����炱��Ȃ̏o�͂����v�Ɛk���܂����B
�@�������[�X�^�@���C�g�͍ŏ�����o�g�����C�����Ƃ��č\�z���ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�����Ă��ƃl�E���C�I�Ȃǂ�������N���Ă�����̃G�~�l�[�Ɛ키�u��������v�߂����v�������������������B���̖��c���A����łł̓R���X�i�Q�O�j�Ƃ�����̃G�l�~�[���o�ꂷ��B�������A1�N�[����9�l���̃��C���L�������J���ƂȂ�Ɛ�����m�͎ڂ����������߁A�������m���Ԃ��荇���o�g�����C�����`���ɗ����������B���ɃA�j���ł͕���łɂ������R���X�⋳�t�������ł��A�u���䏭��vs���䏭���v�Ƃ����\�}�ɐ�O����B���������Ɓu�A�j���ł͎E���Ƃ��Ă���ȁv�Ɗ����邩������܂��ނ���t�ŁA���݂��ɑS�͂Ŋ�����Ԃ��������炱�������F�߂違�Ƃ��ɍ��ߍ������Ƃ��ł�����e�ɂȂ��Ă���A���t�����̂��ƂŁu�����v���ӎ����Đ키����ł̕����ǂ��炩�ƌ����s���s�����Ă���B�C�M���X�������Ă����A���q���́u�_�y�Ђ���v�ɑ��u�ȃ@�X�J���Ă�ȁv�Ƃ��ڂ��u�Γ��o�t�v��A�u�܂����C�����ŃL���L����ɂ��Ă��鈤�邳��ɂ͂킩��Ȃ��ł��傤�ˁv�ƌ����������u�V���^��v�A�u�r�͐��ɎN�����́\�\�E�`�ɔs�k�̓��͂��܂ւ�v�ƚ����u�Ԗ����q�v�ȂǁA�A�j���ł���͑z�����ɂ����V�[��������B����ł͌��\�h�^�o�^���Ă��đ�����������M�X�M�X���������܂ŋC�ɂȂ�Ȃ����A����ł��x�[�X�ɂ����R�~�J���C�Y�w���� �������̌� �������[�X�^�@���C�g �\The LIVE�\ SHOW MUST GO ON�x�̓X���b�v�X�e�B�b�N�v�f���Ă��邹���ł��Ȃ茕�ۂȕ��͋C������Ă���B����łɂ���A�j���łɂ��냌�����[�X�^�@���C�g�ɒʒꂵ�Ă���̂́u�z���̋��������t�̋����Ƃ��Ĕ��f�����v�Ƃ������W�b�N�ł���A�ׂ��������͂��Ă����āu���t�̋����v�ɒ��ڂ��Ď�������Ƙb��ۂݍ��݂₷���Ȃ�܂��B�܂𗬂��Ċ����Ă��鑊��Ɂu�����Ȃ��Łv�ƌ�������u�����ȁI�v�Ɩ��߂�����ق��ăn���J�`�������o�����肷��̂ł͂Ȃ��u������������ł���v���Ĕ��݂�����A����͋����B�u���O�͋����炪�����ƖJ�߂��Ă߂��߂�����������悤�ȃ^�}����Ȃ�����H�v�Ɛ��邱�Ƃŋ�����ނ悤�����u����͂���Ƃ��Ė{���ɋ�����������ł���i�͂��Ɓj�v�ƌ������Ă���B���܂�ɂ��n�C�R���e�N�X�g������Z���t�ōD���ł��B
�@�����TV�V���[�Y�̓��e���܂Ƃ߂����W�҂�����ő�1�e�w�����h�E�����h�E�����h�x�ł���A�������̑������㉉���銮�S�V��̌���ő�2�e���w����� �������̌� �������[�X�^�@���C�g�x�i�ʏ́u���X�v�j�ł��BTV�V���[�Y���ς�����Ȃ烍�����͔���Ă����Ȃ茀�X�ɍs���Ă��\��Ȃ���������܂���B���X�Ŏ�l�������͎O�N���ɂȂ�A���悢��u����v�ɂ��Đ^���ɍl���Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ȃ�B���䏭���́u���Ɓv�Ɓu�i�H�v��`���A�A�j���ł̊����҂ɑ�������X�g�[���[�ł��B��x�ς������ł͙���Ȃ��قǂ̏��ʂ������Ă��郀�[�r�[�ł���A����BD�͂قƂ�ǔ���Ȃ��Ȃ������ł����킸�ɂ͂����Ȃ��Ȃ�o���ł����B���N��CS�Q�[���Ƃ��āw�������̌� �������[�X�^�@���C�g ����t���� ꡂ��Ȃ�G���h���h�x����������Ă��܂��B�܂��������[�X�^�@���C�g�̓W�J�͊��S�ɏI�������킯�ł͂���܂��A�҂����������A�v���i�X�^�����j�����N�T�[�r�X�I���ɂȂ������A�������Ƃ�2.5�������ʂœ�����������x�ŁA���炭����A�j���̐V�삪���삳��邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�Ƃ������A���ꂾ����������e�̃A�j���Ō���ł�2�{����ꂽ�̂͊�Ղ������ȁB����̖����z�M�ŃA�j���Ƀn�}�����l�͂��낢�뒲�ׂ��w���������� �I�[���X�^�@���C�g�x�Ƃ����A�v�����Ŕz�M����Ă����~�j�A�j���̏��ɍs��������������Ȃ����A�Ԃ����Ⴏ�A���͂���ȂɃI�X�X���ł��Ȃ��ł��B�T�v�Ƃ��Ă̓K���p�s�R�n�̂�����炯�V���[�g�A�j���Ȃ���A�L�����̉𑜓x���Ⴗ���Čl�I�ɕs����ł����B����ς��������Łu�s�R���Ĉꌩ���`���N�`������Ă�悤�ł��āA�L�������߂��Ă������ׂ�����͂����Ǝ���Ă����ȁv�ƋC�Â����Ƃ��ł����_�̂ݎ��n�B���������A�v������ĂȂ��Ƃ킩��Ȃ��L��������Ȃ̂ɁA�̐S�̃A�v���͂����T�I���Ă܂�����c�c�B
�@����A���������������ȁc�c�T�I���鍠�ɂ͂�������ĂȂ��������ǁA�X�^�����̓T�[�r�X�J�n���炵�炭�̓v���[���Ă���ł���ˁB�u���̐l���ꏏ������v�Ƃ������R���w�T��I�y�� �~���L�B�z�[���Y�x�Ƃ̃R���{���������Ƃ��Ȃ��ɑ��������R�ȃQ�[���ł����B�R���{�C�x���g�͂��낢�날�������ǁA�V���t�H�M�A�����u���C�u�T���V���C��������͂Ƃ������A�V���^�Q�R���{�͍��U��Ԃ��Ă��u�Ȃ�������H�v���Ď���X���Ă��܂��B�X�^�����͊�{�I�ɒj�L�����̏o�Ă��Ȃ��Q�[���Ȃ�ł����A�I�J���������͗�O�ł����Ɨ����G����������ł���ˁB�o���h���R���{�ʼn̂����J�o�[���u�C�j�V�����v�͍������Ă��J�b�R�����B�o���h���Ƃ͉��x���R���{���Ă��āA�|�s�p�ȊO��RAISE A SUILEN�Ƃ̃R���{����������ł���B�z���ق�5���̂���2����RAS�Ɛ��D����Ă�Ƃ������̐l�l�^��������ł����ǂ��B
�@�Ō�ɁA�u�������Ȃ������ɂȂ��đS�b�����z�M�Ȃ�ăL�����y�[���ł��Ă�낤�H�v�ƕs�v�c�Ɋ����Ē��ׂ���A�ǂ����������[�X�^�@���C�g���X���b�g������݂����ŁA����ɍ��킹�Ă̎{��݂����ł��ˁB�X�����Ɂu�͂��Ȃ��āA�܂Ԃ����v�ƍĉ��i�lj������j���d�˂���u�V���W�L���E�[���I�v�Ƌ��肷�镑��n���Ȃ̐��k�����Ă��܂��̂��c�c�⑫�������܂��ƁA���ĉ��y�w���ɂ͔o�D��ڎw��A�g�i�A�N�^�[�A�A�N�g���X��A�A�������̂́u�o�D�琬�ȁv�j�Ƒ哹��E������E�Ɩ��E���o�E�r�{�ȂǗ����d�����w��B�g�i�u����n���ȁv��B�j�A�ӂ��̃R�[�X������A����Ń������[�X�^�@���C�g�̊ϋq�́uB�g�̐��k�v�Ƃ���A�g�̖ʁX��������Ă���A�Ƃ����ݒ�ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ̂ŃL���X�g���q�ȂɌ������āuB�g�݂̂Ȃ���I�v�ƌĂт�����V�[�������܂ɂ���B�u����n���ȁ��������[�X�^�@���C�g�̃t�@���v�Ƃ����킯���B�T�I�����X�^�������A�����́u����n���Ȃ̐��k�Ƃ��ĕ��䏭�������ɐڂ���v�Ƃ����`���ɂȂ��Ă��܂����B�K���p�Ńv���[���[�̕��g���u���C�u�n�E�X�̐V�l�X�^�b�t�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă�̂Ǝ����悤�Ȋ����ł����A�����̉����w�Z���o�Ă���W�������Ă��̐ݒ�͊��Ƃ����L�떳��ɂȂ�܂����B���̂ւ�̕�������������Ɓu�w�Z�ɂ��s���Ȃ��ŃX���b�g�ł��Ă�B�g�̐��k�����v�Ƃ����C���ȊG�ʂ��z�N����Ă��܂����A���ł��ꂱ�̃X���b�g����q�b�g������A�j���̐V�삪�o����\�����[���ł͂���܂��ʁB�X���b�^�[����L���߂��Ƃ������̃V���W�L����D���ăA�j���Đ��Y�ł��邩���A�Ǝv���Ƌ����A�c���Ȃ�ȁB
�E���背�X�B
�@�����ł����Q.E.D. �}�W�b�N&�}�W�b�N������Ȃ��D���Ȃ�
�@�o���ĂȂ�����ǂݕԂ��܂������ǁA�ӎ��̖ӓ_���Ղ����e�Ŗʔ��������B�wQ.E.D�x�͐l�̎��ȂȂ��b�ł�����オ�肪����̂��C�C�ł��ˁB���͏����G�s�\�[�h�́u���R�u�̊K�i�v���D���ł��B�l�����ʓz���Ɠ��c���i���̂���u���Ă��S�Ɓv�̓^�C�g�����܂߂Ċ����x�����B
>>back�@�@�@